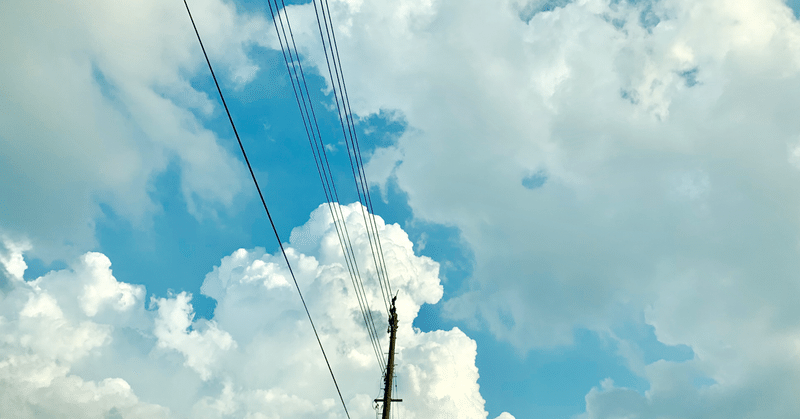
大学受験数学の勉強法について
〜軽く自己紹介〜
2022年に某国立大理学部から某私立医学部へ再受験して入学しました.2022共通テストは全体で91%(2021年度のセンター試験は89%でした).浪人時は今年の私立の2次試験では面接を含め正規合格を自学自習で勝ち取ることができました.理学部時代は家庭教師,塾講師をしていました.(4年間で担当した生徒さんの進学先は京大工学部,筑波大医学部,順大医学部,東邦大医学部,慶大法学部,日本女子大家政学部)
→詳しい自己紹介はこちら(※後日記載)
今回は数学の勉強法について書きたいと思います.数学の成績が伸びやなんでいたり,数学への取り組み方がわからない方向けに書いています.
読んでもらいたい層は中堅私立・地方国公立〜難関大(医学部を含む)までを目指す方です.
1,はじめに
まずはじめに,大学受験の数学は実はそれほど難しいものではありません.確かに覚える量は少なくないかもしれませんし,本番どの分野のなんの問題が出るかは試験本番になってみないとわかりません.が,大学受験の数学の範囲は限られています.大学の高等教育とは違い無限に広がる世界の中から答えを探すものではありません.大学受験数学は非常に限定されたものであり,今まで勉強したものの中から試験では出題されます.
教科書でも,チャートでも,4stepでも,駿台のテキストでもなんでも,一度は見たことがある問題から出題されます.そして本番の試験でこういった問題を取りこぼさなければ基本的に大学は受かります.もちろん大学受験には時間制限がありますので,知っている問題でも時間がかかりすぎてしまう問題は飛ばして他の問題を解かないといけません→受験力(試験・受験本番の取り組み方は後日まとめます).試験で点数を取るには数学力以外にも受験力が必要です.
まずは受験数学の世界を浅く広く俯瞰できるようになる.つまりこの問題はどの分野の何の知識を使うのかが判る(わかる)ようになってほしいです.(全体像を掴む)
わかって解けるようになったら進研模試で偏差値65,全統模試58,駿台全国55)くらいの力になります.
そこから先の得点力(進研模試で66〜)は問題のパターン化をしたり,解法の暗記,計算力,答案力(記述力),分野ごとに特化した力(整数問題が得意),落ち着いて解ける,受験力,慣れ,前日よく眠れたか,体調,会場のコンディション(隣の人が騒がしい),etc…
などあります.
ということでつまりはまずは浅く広く俯瞰できるようになる(森を歩いて今何の木が目の前に立っていて,その木はどういう性質なのかを分かるようになってほしいと思います)→数学の基礎力
★ 数学の得点力= 数学力 + 受験力
2,基礎力をつける
基礎力をつけるには手を動かして問題を解いたり,動画を見て解法を覚えたりしないといけません.私の高校時代は教科書・参考書等で自学するか,学校や予備校(駿台に通ってました)で学ぶのが主流でしたが,今はyoutubeが充実しています.自分のレベルにあった動画コンテンツを探して問題を解いて,解説をみて解き直すという勉強スタイルは賢いかもしれません.しかし有名ではあるが本質ではない,偽の動画も多く,それぞれのリテラシーに委ねられています.大学受験では必要のない知識や,オーバースペックな解法など半ばパフォーマンス臭がする『上手な』解き方を紹介するチャンネルが見受けられますが,まあ自分が納得できるチャンネルを探してみてください.そして本人のレベルによって合うチャンネル合わないもの,理解度が進みにつれ分かってくることが出てくると思うのでその都度,臨機応変に対応してください.
ということで話を戻しますが,基礎力をつけるには,全分野を網羅してある参考書を一冊仕上げてください.青チャート(いきなりは難易度高いかも),旺文社基礎・標準問題精講(基礎からやるのがおすすめ),4stepは計算練習用,1対1大学への数学(無難),月刊大学への数学(毎月やるのをお薦めするが数学で稼ぐ人向け),河合プラチカ(東北など旧帝大や医学部志望向け),z会数学基礎問題集(おすすめ)
を仕上げましょう.この基礎力があれば大学受験は十分戦えますし,基礎力があるからこの先成績は伸びます.確実に.
数学だけではありませんが勉強は積み重ねです.土台づくりへの時間は惜しまないでください.
3.基礎力がついたか確認する
2.で参考書一冊仕上げて,と言いましたが何十週もやれと言っているわけではありません.ボロボロにしろといっているわけでもありません.結果的に書き込み等をしていたらボロボロになるだけです.(メルカリで売ろうとしないで徹底的に書き込みしてください).で,定着度を確認するためには模試(全統模試・駿台全国判定模試・駿台ベネッセ記述模試)を受けたり,高校生や予備校生なら先生に毎日数問を問題集の中からpick upしてもらって最後まで解き切ったり,大学数学のYouTuber(楽しい数学の世界へ)などをみて問題を解いてください.自分は楽しい数学さんにお世話になりました.自分としても今後問題をup loadしていきたいと思います.
4.基礎力定着の後
一定の学力がついたなと思ったら,過去問演習をしてください.過去問は夏以降でいいとおっしゃる先生もいますが,私としては学力がつき始めたなと思った時から始めてもいいと思います.なぜなら自分の戦う相手を知ること,相手と自分の距離を測ること,測れることが受験において大事だと考えるからです.それに過去問を持って解くだけでもモチベーションが上がるからです.もちろん傾向が変わることもあるので過去問研究はそこまで必要ではないと思います(東大京大志望者は25ヵ年の過去問集を徹底的にやるのがいいと思います).結局試験本番は自分の力が出るだけなので,それまでにたくさん問題を解いて考え,まとめ上げることが重要だと思います.そうしたら『結局どこも似通った問題だなあ』と気がつくと思います.そして出題者の意図や,問題の作成の巧みさに感動するようになります(なるかもです).
5.だけどね
ずらずらと書いてきましたが結局は『勉強は楽しんだもの勝ち』です.野球を嫌々やっている人がプロ野球選手になれないと思いますし,このことは勉強でも言えることだと思います.勉強(今回は数学)が好き,楽しいと思えたら成績は伸びます.あとはやり方と演習.頭を使うことを楽しみましょう! やり方はそれぞれなので自分に合った勉強スタイルを見つけましょう.
おすすめの参考書はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
