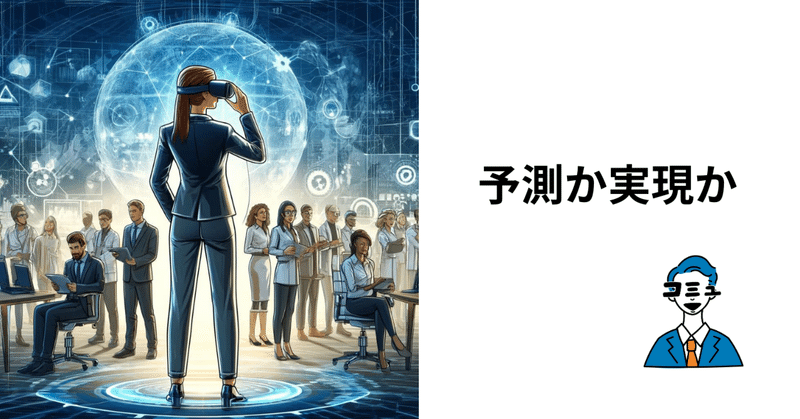
【未来予測】未来を予測する「最善」の方法
数学者、科学者、技術者の3人がキャンプに行きました。
すると、突然テントが火事になりました。
数学者は火を消すために必要な水の量を計算し、それを用いて火を消します。彼は最も効率的な方法で問題を解決し、数式で完璧な解答を出します。
次に科学者は、火の化学的性質を考慮に入れ、消火剤の最適な組み合わせを実験し、そして実際に火を消します。彼は実験と観察を通じて問題にアプローチします。
最後に技術者は、すぐに何かを組み立て、大量の水を火に投げつけて消火します。彼は実用的で直接的な解決策を好み、時にはそれが大掛かりなものであったとしても、より効果的な方法を選びます。
この話は、STEM(科学、技術、工学、数学)の分野に関わる人々にとってはよく知られているジョークだそうで、3人共に実に完璧な仕事をこなしていることがわかります。
このジョークには色々なバリエーションがあるらしく、私が聞いた中で特にユーモラスだなと感じた次のような話もあります。
数学者は「火を消す方法は存在する」とだけ言い放ち、どこかへ行った。
「おい!数学的理論はいいから火を消せ!」と言いたくなりますよね。しかもこの場合、理論すら言っていないという。
次に科学者は即座に計算を行い、必要な分だけ消火器を使用し火を消した。
彼については「お見事!」と言いたい気持ちをいったん堪えてみると、「火事の規模がテントだから上手くいった」というツッコミが存在するそうで、それが大規模だと通用しないという、なかなか手厳しいものです。
最後に技術者。彼は火に驚き周章狼狽しながらあたり一面に消火器を噴霧、火は消えたが余計な被害も引き起こした。
なんと言えばいいやら。勤務先の原子力発言所でしょっちゅう原発事故を引き起こしながら、それを解決するパパシンプソン=ホーマーが活躍(?)する、アメリカのアニメ『ザ・シンプソンズ』をイメージしちゃいませんか?とにかく解決したから「めでたし、めでたし」と。
なぜ、わざわざ同じジョークを全く異なる二つの視点で述べたかというと、このジョークは、専門職ごとのアプローチを比較する一種の教育的な側面も持ち合わせているため、異なる専門分野がどのように異なる視点や方法論を持っているかを示す例として使われることがあるからであり、本記事で取り上げる「最善」の方法を取るために必要なのが「視点」を変えることだと考えたからです。
さて、それでは下の絵を見てください。 ほとんどの人が、「ああ、iPadね。で?」と思うでしょう。これが一方の目線です。

では続いて次の絵を見てもらいましょう。

どうでしょう。多くの人は、「あれ?なんかちょっと違うなあ。なんだこれは」と思ったのではないでしょうか?これが他方の目線です。
種明かしをすれば、この2つの絵は、「コンピューターの父」とも呼ばれるサイエンティストのアラン・ケイが、1972年に著した彼の論文『A Personal Computer for Children of All Ages』の中で、ダイナブックというコンセプトを説明するために用いたものです。そう、今から半世紀近く前のことです。
この種明かしをされて、「すごい!40年以上も前に未来を予測してたんだ!」と思ったのだとすれば、その解釈は完全に間違っています。
これはアラン・ケイ自身も言っていることですが、彼は未来を予測してこれを描いたわけではありません。彼がやったのは、「こういうものがあったらいいな」と考えて、そのコンセプトを絵にして、それが実際に生み出されるように粘り強く運動したということです。
ここに、「予測」と「実現」の逆転が見られます。
逆転とはどういうことか?まずは「予測の悲惨さ」を物語る一つの例を挙げます。
1982年、当時全米最大の電話会社だったAT&Tは、コンサルティング会社のマッキンゼー&カンパニーに対して、「2000年時点での携帯電話の市場規模を予測してほしい」と依頼しました。この依頼に対してマッキンゼーが最終的に示した回答は「90万台」というものでした。では実際にはどうだったかというと、市場規模は軽く「1億台」を突破し、3日ごとに100万台が売れる状況となっていました。
この悲惨なアドバイスに基づき、1984年、当時AT&Tの社長だったブラウンCEOは携帯電話事業を売却するという致命的な経営判断を行い、以後AT&Tはモバイル化の流れに乗り遅れて経営的に行き詰まり、最終的には自ら切り離したかつてのグループ企業であるSBCに買収され、消滅するという皮肉な最後を迎えます。
膨大な調査費用をかけ、超一流のリサーチャーを使って行われた予測だったはずですが、文字通りケタ外れのスケールで「予測」を外しているわけです。

次に「予測」と「実現」の逆転について見てみましょう。
2000年代初頭、ノキアは世界の携帯電話市場で最大のシェアを持っており、その地位は揺るぎないものと見られていました。彼らは自社が持つその優れた製造能力、強固なブランド力、広範な販売ネットワークを基盤に、これからも市場を支配し続けると「予測」していました。
ノキアの会長リスト・シラスマは自著の中で「ノキアの携帯を持つ消費者にアンケートをとると、95%はタッチパネルのデバイスを使いたくないと答え、数字キーボードやQWERTYキーボードが圧倒的な支持を集めた」と述べています。彼らは顧客の声に耳を傾け、それに従い続けていました。
ノキアは初期のスマートフォンが登場し少しづつ市場が形成されていく中においても、これまで市場を支配してきた実績と、新たに生み出した独自のオペレーティングシステムである「Symbian」があれば、スマートフォン市場でもリードしていけると「予測」していました。
そこにやってきたのが?ええ、AppleのiPhoneですね。彼らはスマートフォン市場を根本から変えました。圧倒的な使いやすさ、アプリケーションのエコシステム、マルチメディア機能において、ノキアの「Symbian」ベースのスマートフォンを遥かに凌駕していました。
シラスマは「そもそも消費者である顧客は通信会社のものなので、われわれのものではないと考えていた。アップルが「アップルID」でユーザーを囲い込んだように、われわれも「クラブ・ノキア」という仕組みを作ろうとしたが、通信会社からは反対された」と、人のせい?とも読めることを述べてはいますが、そんな自分たちの失敗については、はっきりと認めています。
顧客の声、通信会社の声に従い続けて実績を積んできたノキアの「予測」は、Appleが「実現」したiPhoneによってノックアウトされてしまったのです。まさに「予測」と「実現」の逆転が起きました。この凄さが伝わるでしょうか?
Apple は iPhone という全く新しい製品の「実現」から始めたので、通信会社のことを気にする必要はありません。彼らはこの「実現」によって「我々のシステムを受け入れないならiPhoneを売らせない」という姿勢でビジネスができるようになりました。こうなるとノキアとは話が真逆。エンドユーザーがiPhoneを求める以上、通信会社の方がAppleを扱わざるを得ない。
ノキアの堅固な要塞を鮮やかに迂回し、革新の旗を高く掲げたAppleは見事な「主客転倒劇」を見せました。私自身は「上下論」を嫌いますが、この場合は、Appleがエンドユーザー、通信会社、そしてもちろんノキアよりも上に立ったのです。このように新参者が「予測」ではなく「実現」することで、ルールそのものを変えてしまう現象が、いまどんな業界でも起きているのです。

さて、スティーブ・ジョブズの起こした世界を魅了する一大革命劇に魅了され、つい本記事の主役がアラン・ケイであることを忘れてしまった方も多いことでしょう。ここからはぜひ「色々と視点を変えながら」読んでいただきたいのですが、ここで冒頭に述べたジョークに話を戻したいと思います。
ここでは
数学者=アーティスト=ビジョンやコンセプトを描く人
科学者=サイエンティスト=既存の知識から新しい知見を探す人
技術者=エンジニア=数学者と科学者の構想を具現化する人
であると仮置きして考えてみたいと思います。
アラン・ケイはこの三者のうちの誰に該当するかと言えば、もちろん彼は計算機器科学者なのでサイエンティストです。それと同時にダイナブックというコンセプトを描いたわけですから、優れたアーティストであるとも言えるでしょう。しかし技術者ではない。もちろんこれは字義通りの意味ではなく、あくまで思考実験の一つとして考えてください。
彼が考えたコンセプトであるダイナブックのビジョンは、現代のデバイスにおいてもなお影響を与えたことは言うまでもありません。iPadに限らず各種のAndroidタブレットもまた、ダイナブックのコンセプトと非常に似た形で、多くの機能や用途を提供しています。また、プログラミング学習を目的としたさまざまなアプリケーションや環境が開発されていることも、ダイナブックの精神を反映していると言えるでしょう。
しかし、ケイは物理的な「モノ」としてのダイナブックを作った人でもなければ、そもそも彼の考えるダイナブックはまだ完成していません。
彼が考えるダイナブックを具体的に言えば、ユーザーがプログラムをより簡単に作成し、カスタマイズし、他の人と共有できるような環境を想定しています。これは、ユーザーがコンテンツの消費者からクリエーターへと移行することを促すものです。つまり、ダイナブックの実現プロセスは今日も続いているというわけです。
教育者でもある彼は、アーティストとして自分が描いたダイナブックというコンセプトを、サイエンティストとして既存の知識から新しい知見を探し続けながら、その作り方を教える、一緒に考える、というようなことをしています。したがって「作らせる天才」と言い現すことができると思います。
次に挙げる彼の有名メッセージは、多くのエンジニアの背中を押します。
The best way to predict the future is to invent it.
未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ
そんな彼のメッセ―ジを受けたかどうかはともかく、間違いなく彼に影響を受けたと考えられるのが「作る天才」スティーブ・ジョブズです。
この二人を結ぶ有名な話があります。その舞台はXerox社が設立した研究開発施設であるパロアルト研究所です。この研究所の話は、私の好きな話の一つでもあるのですが、私は「実にアラン・ケイみたいな研究所だな」と思っています。
どういうことかと言うと、パロアルト研究所はグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)、イーサネット、レーザープリンター、オブジェクト指向プログラミングなど、今日の情報技術に不可欠な多くの技術を発明しました。ちょっとカタカナが多いので取り上げるのは二つだけにしますね。
その一つが、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)といって、要するに、ユーザーがコンピューターと対話するための視覚的なインターフェイスです。アイコン、ウィンドウ、ボタンなど、マウスやタッチスクリーンを通じて操作できるものなどがそうです。皆さんもPCやスマホで毎日操作しているはずです。
ジョブズがパロアルト研究所を訪れた際、彼はここで開発されたグラフィカルユーザーインターフェイスに深い印象を受けました。ジョブズはこの技術の潜在的な価値を見抜き、自社の製品に応用することで、Appleのマッキントッシュを成功させました。ジョブズは特に、個人ユーザーをターゲットにすることで、これらの技術を広く普及させることに成功した「作る天才」と言えるのではないでしょうか。「実現の天才」とも言えますね。
二つ目がレーザープリンター、そう、コピー機です。パロアルト研究所は革新的なコンセプトを描き、それを論理実証させたがこれらの革新を商業的成功に結びつけることができませんでした。その理由は、Xerox自体が主にコピー機という特定のビジネスに集中していたため、同研究所が開発した技術の真の価値を理解し、市場に適切に導入することができなかったのです。
私はなにもパロアルト研究所の商業的失敗を論いたいわけではなく、この研究所が「描き、実証する場所」と考えれば、なんとアラン・ケイ的ではないか?と思うわけですね。さらに論を重ねれば、「作らせる天才」と「作る天才」、二人共に「実現の天才ではないか?」とも思えてならないのです。
さて、アラン・ケイ=パロアルト研究所、スティーブ・ジョブズ=Appleというと、なんだか話が大きすぎて、皆さんは自分事にできないと感じるかもしれませんが、何もそんなに大きな話ではなく、私は皆さんに「予測を止めて、やってみよう」ということを訴えているに過ぎないのですね。
しかしながら、なぜ私たちはこんなにも「予測」が止められないのでしょうか?
あるいは、なぜ「実現」させようとしないのか、なぜ「開発」しないのか、なぜ「やってみない」のか、視点は色々あると思いますが、ここに一つの可能性を提示してみたいと思います。
恥の文化
先に挙げたこれらの問題は、文化人類学者のルース・ベネディクトが『菊と刀』で指摘した「恥の文化」という枠組みで説明ができると思います。
ベネディクトは
諸文化の人類学的研究において重要なことは、恥に大きく頼る文化と、罪に大きく頼る文化とを区別することである。道徳の絶対的基準を説き、各人の良心の啓発に頼る社会は、「罪の文化」と定義することができる。
としたうえで、さらに
恥が主要な社会的強制力になっているところでは、たとえ告解僧に対して過ちを公にしたところで、ひとは苦しみの軽減を経験しない。
と指摘しています。
つまり「罪」は救済できるけど「恥」は救済できないということです。
これは考えてみれば恐ろしいことですよね。西洋の「罪の文化」では、告解によって罪は救済されることに、一応はなっています。この「罪の文化」に対して、ベネディクトは、「恥の文化」においては、たとえそれが悪行であっても、世間に知られない限り、心配する必要はない。したがって「恥の文化」では告解という習慣はない、と指摘しています。
「バレなければいいが、バレたら終わり」とも読み取れるわけですが、ベネディクトの指摘のうえにそのまま考察を積み重ねれば、日本人の生活においては「恥」が行動を規定する最大の軸になる。
それはつまり
各人が自分の行動に対する世間の目を気にしている、ということです。
この場合、彼あるいは彼女は、ただ世間の他人が自分の行動をどのように判断するかを「予測」しさえすればよく、その他人の意見の方向に沿って行動するのが賢明であり、さらには優秀であるということになります。
しかし、ここまで読んでくださった皆さんであれば、ここで言う賢明さ、優秀さの先に待ち受けるのが「AT&Tのケタ外れの予測外し」であり「AppleによるiPhoneの開発によってノックアウトされたノキア」である、ということをご理解いただけると思います。
そうです、「予測」することは本質的な意味においての優秀さとは、決してイコールでないということです。世間の目を気にするとは、AT&Tやノキアのようになりかねないということですから。
長くなってきたのでまとめましょう。
もしも皆さんが
何も実現させようとしていない
何も開発しようとしていない
新しいことをやってみない
このような場合、視点を自分自身の思考様式や行動様式、日頃の言動などに向けてみてください。おそらくかなり高い確率でなにかしらのネガティブな「予測」をしているはずです。
そして
数学者=アーティストになって、「火を消す方法は存在する」とだけ言い放ち、どこかへ行ってみてください。つまり、自分がやってみたい、実現してみたい、開発したいものを、どこにでも良いので宣言してみてください。断言しますが、せいぜい笑われるか怒られる程度です。実害なんてその程度。
次にサイエンティストとエンジニアを、とにかくどちらもやってみましょう。自分はサイエンティストとして人を動かすために動くのが得意なのか、エンジニアとしてサイエンティストのアタマの中を具現化するのが得意なのか、やってみなければわかりません。
いまある世界は偶然このように出来上がっているわけではありません。どこかで誰かが行った「意思決定」の集積によって今の世界の風景は描かれているのです。
意思決定をする側に回るか、意思決定に引きずられる側に回るか?
自分の人生の主導権を握られていないか?
まずは視点を変えてみてください。
僕の武器になった哲学/コミュリーマン
ステップ1.現状認識:この世界を「なにかおかしい」「なにか理不尽だ」と感じ、それを変えたいと思っている人へ
キーコンセプト15「未来予測」
もしよろしければ、サポートをお願いいたします^^いただいたサポートは作家の活動費にさせていただき、よりいっそう皆さんが「なりたい自分を見つける」「なりたい自分になる」お手伝いをさせせていただきます♡
