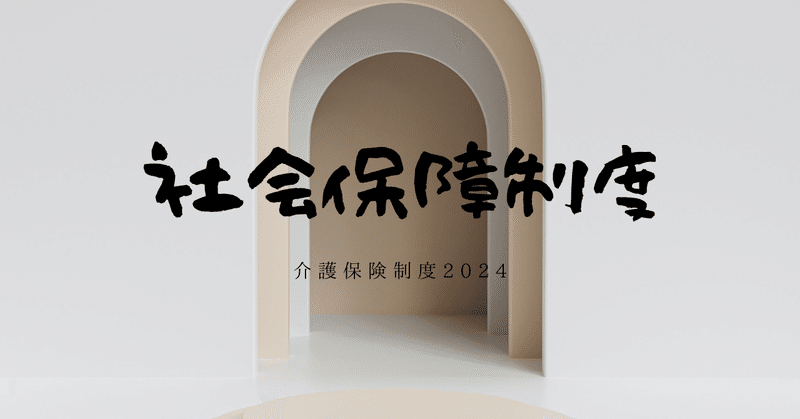
令和6年度介護報酬改定における改定事項について ⑧
おはようございます。fumioです。
今朝も報酬改定の読み込みし、「損しない」をキーワードにお伝えしていきますね。本日は、認知症について、認知症基本法が昨年成立したことで介護保険でも目新しい取組みがありますね。
※上記から認知症関連の改定事項をみていきましょう。
・1.(7)② 訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進(P54)
➤認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、 応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善
(これは、自宅でトイレ動作や更衣などの関わり方(声掛け方や混乱するきっかけの理解など)を分析して、リハビリテーションを行うことで自宅で家族負担が軽減を目的にしています
・1.(7)③ 通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し(P55)
➤当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催しているこ と。(事業所のスタッフが認知症の方の関わり方やその事例、技術的指導を事業所内で行い、事業所を利用する認知症のケアを充実する)
・1.(7)④ (看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化(P56)
➤認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施(認知症のリーダー研修終了者の方がいる事業所で、且つ、対象となる認知症の高齢者が利用場合)
・1.(7)⑤ 認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの 認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進(P57)
➤認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時から の取組を推進する
(認知症の専門的な研修をうけた職員が配置され、介護職員等からなるチームで「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応」)
・1. (7) ⑥介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し(P58)
➤認知症を有する入所者の居宅における生活環境に対応したサービス提供を推進するために、「当該入所者の居宅を訪問し生活環境を把握すること」を評価(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が協働して、自宅での生活を考えたリハビリテーションを実施する)
※認知症にて「自宅での生活にうまく関係がとれない症状」が出ている、今後出るかもしれない高齢者に対して、施設や通所の場面でなく「自宅で家族と環境」に関わり支障が軽減できるように、認知症の研修を受け終了した専門職や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、チームで当たる!
認知症の方と家族・環境から「離す」から家族と環境の中で「暮らす」をチームで支える方法に変わっています。お近くに、事業所でサービス提供を受ける際は、認知症の専門研修等を受けた職員の有無や自宅での困りごとを
訪問して解決できるように「取組んでくれる」かを確認しましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
