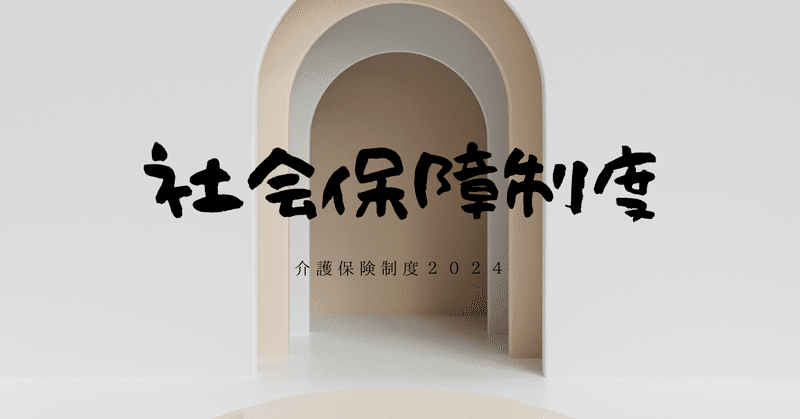
令和6年度介護報酬改定における改定事項について ④
おはようございます。fumioです。
今日は、昨日の続きから、よろしくお願いいたします。
■通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント(P67)

➡【昨日の内容の解説図】で行っている内容です。これを解説した図になります。↑
上記の図のように、解説してくれいたことは私の見てきた限りではなかったと思いますので、「家族の方は、この図をしっかり確認していただくと、
高齢者に提供されているリハビリの意味と参加(時間を使う意味)がかわりすいと思います。
【昨日内容】
・2.(1)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進①(P64)
➡まずリハビリテーションを提供されている高齢者のための「リハビリテーション会議」が「定期的に開催」。次に「LIFE(リハビリテーション等のデータを国に送る」。次に、「栄養・口腔・リハビリテーションの多職種で情報共有」しさらにリハビリ提供すること。この3つのステップを行うと事業所に入るお金が多い、利用者のリハビリテーションマネジメント(しっかり観察して機能低下を防止します)内容です。
・2.(1)⑦ 要介護・要支援のリハビリテーションの評価の差別化(P72)
➡要支援1・2(介護予防)と要介護1・2・3・4・5、で報酬に差が
つく内容です。1回リハビリが、予防が報酬が安くなり、要介護が少し高くなっています。
・2.(1)⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価(P73)
➡リハビリ開始をした「要支援の高齢者」が12カ月後に、報酬が下がるけれど「リハビリテーション会議の実施、国へのリハビリテーションのデータ提出を実施する」ことで報酬を下げずに「リハビリテーションの質」を認めていくことのようです。
家族の方には、「国へのデータ提出」(LIFE)については、高齢者の身体機能の人間ドックのようなものなので、しっかりデータをもらい1年前との
身体機能の結果を確認しましょう!!
・2.(1)⑨ 退院直後の診療未実施減算の免除(P74)
・2.(1)⑩ 診療未実施減算の経過措置の延長等(P75)
➡これまで、退院直後の高齢者の方へのリハビリテーション実施が退院医療機関と退院後のリハビリテーション実施までの間「医師の指示」がもらえず
空白な期間が生まれリハビリテーションが実施できず「退院時の機能が低下」する事態がおったこと。
令和6年の改定からは、入院中の「医師の指示」を「1月程度」継続して
リハビリテーションを実施してください。となったので、報酬が下がらないので退院後のリハビリテーションをどんどんやれますよ!という内容ですね。
・2.(1)⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し①(P76)
・2.(1)⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し②(P77)
➡これまで、リハビリテーションを実施している事業所は、1日の定員もありますが、一定の期間での延べ利用者数で、「通常規模」「大規模Ⅰ」「大規模Ⅱ」と延べ人数が多くなると、利用者の1回のサービス提供で頂く報酬が下がっていした。
令和6年からは、リハビリテーションマネジメント、専門職の配置数により、報酬が下がらないようになりました。
利用する高齢者にとっては、利用者の定員や規模で「あの通所リハビリテーションへいけない」ということは無くなり、利用もしやすくなると思います。
でも、事業所にリハビリスタッフが増えないと難しいかも・・。
・2.(2)② 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)の見直し(P91)
➡「自宅で高齢者が入浴する」に向けて、取組ことを促すことを言っています。自宅で入浴するには、介助者と環境(浴室、脱衣)が中心になってリハビリテーションを展開していく必要があります。
通所リハビリテーションの取組に加えて、以下、ことばでは伝えにくいので資料の画を抜粋します↓

【資料の抜粋:取組みの内容です】
・ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価 を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び 経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴 室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行う ことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用 具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境 整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への 訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握 した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えない ものとする。
・ 当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室 の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリ テーション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の 浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置するこ とにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。
※これは、読む量も大変ですが「家族と協働して実施する」そして、「自宅で入浴する」を考える・・・尊厳と自立につながる一つですが・・・エネルギーがいりますよね。
リハビリテーションは、尊厳と自立を促す大事な役割です。どんどんリハビリテーションを活用してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
