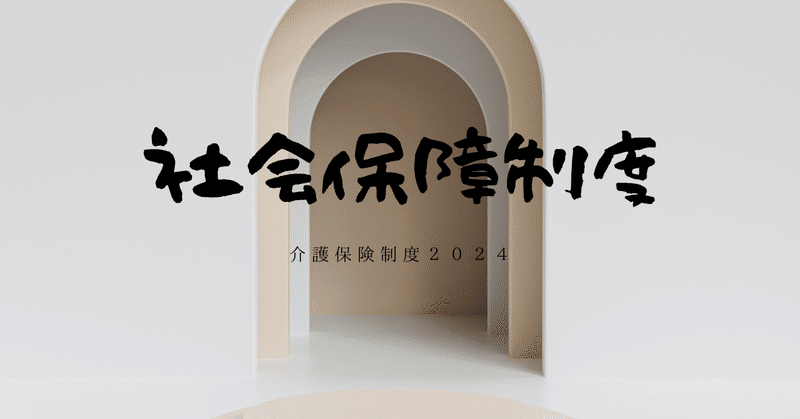
令和6年度介護報酬改定における改定事項について ③
おはようございます。fumioです。
仕事前の時間に、今日も令和6年介護報酬改定について、解釈したいと思います。私のnote発信は、50代前後の親の介護をされている方、医療・介護の相談援助職の方、介護をお仕事にしている方と思っています。
しかし、内容が同業者よりの発信になるのでこの「令和6年介護報酬改定における改定事項について」のシリーズは「親の介護」の方に、「損しない介護」の観点で綴れたと思っています。
■通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション
・1.(3)⑧ 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化(P22)
・1.(3)⑨ 退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進(P23)
・1.(7)② 訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進(P54)
・2.(1)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進①(P64)
・2.(1)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進②(P65)
・2.(1)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進③(P66)
・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント(P67)
・2.(1)⑥ 訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し(P71)
・2.(1)⑦ 要介護・要支援のリハビリテーションの評価の差別化(P72)
・2.(1)⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価(P73)
・2.(1)⑨ 退院直後の診療未実施減算の免除(P74)
・2.(1)⑩ 診療未実施減算の経過措置の延長等(P75)
・2.(1)⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し①(P76)
・2.(1)⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し②(P77)
・2.(2)② 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)の見直し(P91)
以上、改定事項を列挙してみました。「リハビリテーション」でまとめると
介護老人保健施設でのリハビリもあります。リハビリでの事項は多いです。
※それだけ、国は、リハビリに力を入れているということ。さらに、高齢者の状態が増悪して要介護度が上がったり、医療へかかり医療費の負担が大きくならないようにすることを考えています。
■上記の中で、高齢者とその家族が「損しないように」の観点から
次の内容です。ザックリ説明すると
・1.(3)⑧ 医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化(P22)
➡入院中に高齢者がしっかりリハビリをして、退院に向けてリハビリを頑張った効果を「退院後の生活も、リハビリが継続的に必要とする方」には
入院中のリハビリテーションの計画書を退院後にリハビリテーションを提供する事業所(通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション)は計画書を病院から計画書をもらい把握することが義務になった内容です。
・1.(3)⑨ 退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進(P23)
➡病院からの退院前に、病院とリハビリテーションを提供する事業所の
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が一緒に会議に出席するこを評価すること(退院後のリハビ職員が、家族と病院の意向を一緒に考える場ができたので、入院中と退院後でリハビリの目的がずれていかない)
・1.(7)② 訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進(P54)
➡単純に、機能訓練(歩けるなど)の行為に目を向けるのでなく、認知症と自宅の環境や関わり方で、認知機能の賦活して、排泄の一連の動作(トイレに向かう・ズボンを下す・トレイに座る・始末する・衣類を整える・・)ができるリハビリテーションを行うことです。
・2.(1)①訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進①(P64)
➡まずリハビリテーションを提供されている高齢者のための「リハビリテーション会議」が「定期的に開催」。次に「LIFE(リハビリテーション等のデータを国に送る」。次に、「栄養・口腔・リハビリテーションの多職種で情報共有」しさらにリハビリ提供すること。この3つのステップを行うと事業所に入るお金が多い、利用者のリハビリテーションマネジメント(しっかり観察して機能低下を防止します)内容です。
※高齢者と家族には、手厚くサービス提供がなされます。「リハビリテーション会議」とリハビリ事業者から連絡あったら要チェックです。
・・・・・・ここから以降は、次の投稿で解釈します。・・・・
・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント(P67)
・2.(1)⑥ 訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し(P71)
・2.(1)⑦ 要介護・要支援のリハビリテーションの評価の差別化(P72)
・2.(1)⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価(P73)
・2.(1)⑨ 退院直後の診療未実施減算の免除(P74)
・2.(1)⑩ 診療未実施減算の経過措置の延長等(P75)
・2.(1)⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し①(P76)
・2.(1)⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し②(P77)
・2.(2)② 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算(Ⅱ)の見直し(P91)
■注意点
リハビリテーションは、どうしても難しいというイメージがあります。だから、高齢者・家族の方も一歩引いてお任せであったり、介護支援専門員の方も制度が複雑でわからないことが多いです。
しかし、必ず事業所が求められるのが計画書・同意・実施したことの事実(記録)です。(これは、高齢者や家族の方の支払うお金です)
計画書のわかりやすい説明、そのことにより担保される高齢者と家族の恩恵、いつどのくらい会議が開かれ、リハビリは何回提供されて・・・。
高齢者と家族の生活継続ができるか?をしっかり判断してください。
※但し、家族の時間とお金のバランスを考えて「損」と判断しても、その判断の物差しは、個人差があり、安易に効果が見られないように見られるリハビリテーションがどの生活場面で効いているかを見極めていください。
「リハビリの提供時間と家族の使う時間と払うお金」のバランスで考えるのは失敗します。高齢者と家族の方が生活継続する「毎日の活動」の負担と継続から判断して「相談」を関係者としてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
