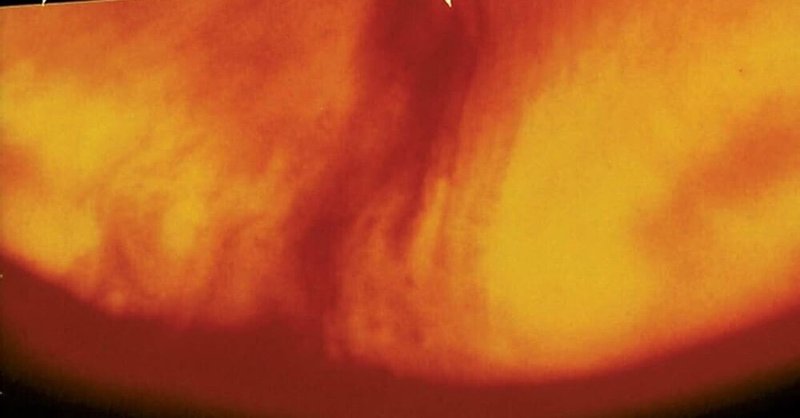
才能のない僕がやるべきこと
先日、「人を尊敬できるかどうかって才能だと思う」とXで投稿した。しかしこの投稿は、少し誤解されてしまった。言葉が足りなかったのだ。もちろん額面通り、「人のことを尊敬して真似ていこうということができる人と、謙虚さのない人がいる」という意味でも通るのだが、僕があの投稿をした際に考えていたのは芸術のことだ。
僕は音楽と文学をやってきて長いが、音楽にはちゃんと師がいて、文学に関しては独学だ。そのため、文学の技術的なことを考える際は、どうしても音楽で勉強してきたことを流用することになる。そしてそんな僕の見解が、「人を尊敬できるかどうかって才能だと思う」ということなのだ。
芸術にはどうしても個人的な好みが出てくる。さまざまな種類の芸術作品に触れるのは大切なことだし、それぞれのジャンルの良い点を認めるのも大事だろう。ただそれでも、「やっぱりいろいろ好きだけど、自分はこの人が好きなんだよなあ」という人がいるかどうか、それが前述の、「人を尊敬できるかどうかって才能だと思う」という投稿になったのだ。
誰かを尊敬するということは、お手本やパクリ元ができるということでもある。たまにパクリに対して猛然と怒る人もいるが、芸術の世界には「天才はいいところからパクる」という言葉もあるくらい、模倣は大事だ。「分析して模倣したら尊敬する人の二番煎じになるんじゃないか」と思う人もいるだろうが、案外、人と同じにはならないものだし、尊敬しているからこそその人の作品を深く理解でき、「ここは模倣して、ここは少し変えてみよう」ということができるようになるのだ。なので、僕は芸術においては「いろいろな作品を半端に摂取するよりは、一種の信仰の方が強い」と確信している。
とにかく、まず自分が好きなものはなんなのか、そして、その好きなもののどこが好きなのか、こういったことを分析しないと、上達はしない。
だがしかし、そんなことを言っている一方で、僕は上記の「いろいろな作品を半端に摂取している人間」だ。本当に、好きな作家や好きなスタイルが多すぎる。初めて小説を書いたときは誰をお手本とも思わずに自然な成り行きで書いていたが、何作か書いている内に「僕が書いている小説の文体は行動描写が主のハードボイルド文体だ」と気づき、それからはアーネスト・ヘミングウェイをかなり意識的に模倣したが、これは尊敬と言うよりはもっと実利的な観点だと思う。実際、ヘミングウェイ作品は好きだが、もっと好きな作家は沢山いる。
例えば僕はF・ドストエフスキー、トーマス・マン、ヘルマン・ヘッセ、J・P・サルトル、大江健三郎が好きだが、一方で志賀直哉や川端康成、それに永井龍男や庄野順三、吉行淳之介が好きだし、今でも東野圭吾や姫野カオルコ、江國香織といったエンタメ作家もよく読む(純文学/エンタメなんて分け方をそもそもしていない)。好みに統一感はない。信条もない。
芸術の世界は結局、幅広さではなく個性の世界だ。心の底から尊敬して影響を公言して憚らない師というものを持たなかった僕は、これから先、より個性を磨くために読むにせよ書くにせよもっともっと意識的になっていく必要がある。
まあ、そんな努力は「好きで読んで好きで書いている」という人には敵わないし、どんな「個性」も「ひたすら面白い」には及ばないんだけれど…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
