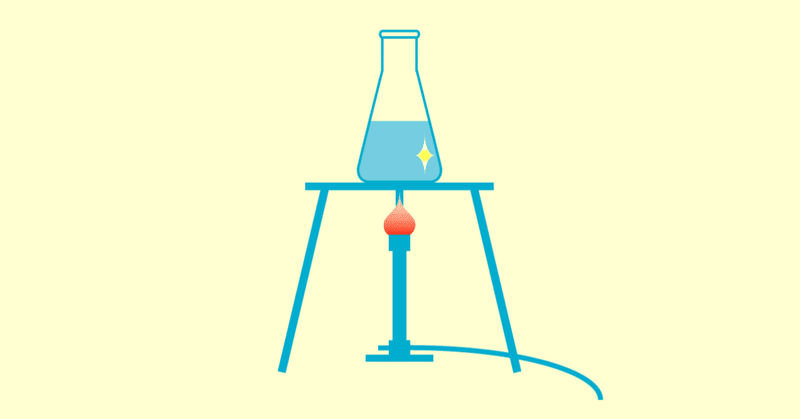
【日常業務にも使える】実験レポートの書き方
お久しぶりです。E研究員です。
IT企業の企画職として研究部門の人たちと仕事をしていると、実験レポートの書き方が人によってまちまちなことに気づきました。
思い返すと、自身がメーカーのものづくり系研究職だった新人時代に上司から教わった「実験レポートの書き方」が他業務にも汎用性が高い気がしたので共有しようと思います。
概要
といっても、伝えたいことは以下の図1枚だけです。
当時の上司に渡された手書きメモを書き起こしたんですが、シンプルですね。
背景と今後の展開、目的と結論、方法と結果、それぞれを対応づけて書くことが肝となります。とはいえ実例がないと理解しにくいためサンプルを示してみます。

実験レポートのサンプル
たとえば、精密機器メーカーで製品の1パーツを開発しており、その素材を選定しているとします。それぞれの項目のサンプルを書いてみます。(プロの方から見たらアラがあるかもですが汗)
「背景」
"20XX年の製品Aの改良版リリースに向け、パーツBにおいて性能Xの5%向上が求められている。"
「目的」
"性能Xの向上を見込めるパーツBの素材を選定する。"
「方法」
"物性Yの値が高いほど性能Xが向上する相関関係がある。"
"候補素材a, b, c, d の1mm厚のシートを1cm角に切り出し、物性Yを装置Zで測定し比較する。"
「結果」
"候補素材a, b, c, d それぞれの物性Yの値は ~~~~ だった。候補素材 c が最も高い値が得られた。"
「結論」
"パーツBの候補素材として c を選定する。"
「今後の展開」
"候補素材 c でパーツBを試作して製品に組み込み、性能Xの向上を評価する。"
実験レポートの解説
<前提条件>
会社の主力製品Aの改良版において、性能Xを5%改善したいようです。そのためにパーツBを改善したいようですね。
レポートを書く人は、パーツBを担当している設計者です。
とはいえパーツBを改善する方針としては形状を変えたり、加工方法を変えたり、素材を変えたり、様々なアプローチがあります。
このレポートでは、まず素材を変えることからアプローチをするようです。
また、いろんな素材でパーツBをつくって製品に組み込んで評価するのは大変なため、有望な素材を1つに絞ることを考えているようですね。
さらにパーツBを製品に組み込んだ時の性能Xと、パーツBの素材の物性Yに相関があるため、素材の物性Yを調べることで、パーツBに適した素材を探そうとしています。
<実験レポート(サンプル)の構成>
そのため、背景では「パーツBにおいて性能Xの向上が求められ」ており、
今後の展開では「実際にパーツBの性能Xが向上するか確かめる」という形に対応づけています。
また、目的では「パーツBの素材を選定」するため、結論では「パーツBの候補素材を c に選定」しています。
方法では「候補素材の物性Yを測定比較」しようとし、結果において「候補素材の物性Yの比較結果」を示しています。
レポート構成のメリット
背景と今後の展開、目的と結論、方法と結果 それぞれを対応づけて書くとなぜ良いのでしょうか?
1. 「会社/組織の方針」と「自分の行動」を整合するため
自分は会社/組織のどんな方針に合わせて行動を考えており(背景)、自分の行動によって会社/組織が次にどんな行動を起こせば良いか(今後の展開)、をレポートで明示する。それにより、周囲の人は自分が適切に行動したことを理解することができます。
2. いま自分がフォーカスしたい課題に注力するため
会社/組織でさまざまな方針があっても、自分が全てを対応できるわけではありません。「製品Aの性能向上」という会社方針に寄与するための「パーツBの候補素材を選ぶ」という個人の課題に落とし込み、個人の課題の範囲内(目的)において答え(結論)を出します。
実は素材の変更ではなく、形状や加工方法を変える必要が出てくるかもしれません。とはいえ、最初から”素材と形状と加工方法を全部変えないといけないかも〜〜”と考えていたら誰も第一歩を動き出せません。
そのため、まず素材から(小さい範囲内で)改善できるか試してみる、というのがこの実験レポートです。
3. 型があると迷いにくいし、読みやすい
実験レポートの型を理解していると、書き方に迷いがなくなり、書くスピードが上がります。また、読む人(上司や周りの部署の人)も何が書いてあるのか、どうアクションを取ればいいのか分かりやすくなります。
おわりに
今日は実験レポートの書き方の型を紹介しました。なぜ紹介しようと思ったかといいますと、実験レポート以外にも業務目的を整理したり、企画書を書く時にも使えると気づいたためです。技術者以外でも利用シーンがありそうですね。
またお役立ちできることが思いついたら投稿しようと思います。それでは!
無料のプログラミングクラブCoderDojoを運営するにあたり寄付を受け付けています。お金は会場費・Wifiの費用・教科書に使用します。
