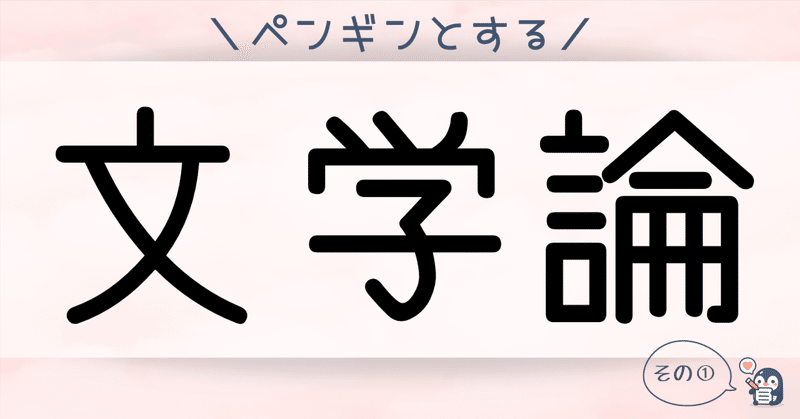
ペンギンとする文学論①ー文学者になろう

ごあいさつ
タンカペンギン(以下P)ーこんにちは。ぼく、タンカペンギンといいます。メルマガやLINEを読まれている方にはおなじみですよね…。実はぼく、はじめて作者がAIでつくったキャラクターらしいんです。はじめてAIでつくったにしては、その出来栄えもいいじゃんと作者が自信を持ってしまい、そのままnoteの公式キャラクターという扱いになったみたいです。今日は作者が一人じゃ嫌だ、ということで、アシスタントとして出演します。みなさんよろしくお願いします。
西巻真(以下N) ーいや、すごいね。とうとう君、記事に出てきたね。でも読者の方はぼくが期待しているほど、きみを「かわいい」と思ってはいないみたいだよ。なんか変なペンギンいるな、っていうくらいの認識なんじゃないの?
Pーえええっ。いきなりそんなひどいこと言わないでくださいよ。出にくいじゃないですか…。
N-いやいや。半分冗談だけど、でももう半分はぼくも自信がない。ぼくの記事への反応はたまに返ってくるけど、きみへの反応を聞いたことがないんだよ。ぼくとしては「かわいいじゃん」と思って登場させてるけど、とりたてて意識されてないのかな…。
Pーいいんですか。そんなにアシスタントにひどいことを言って。だから友だちいないんでしょ。
Nーまあ「友だちがいない」のは事実だから言い返せないけど…。でも実はこういう「架空対談形式」って、なんやかんやで色んな人がやってるんだよね。ぼくを未来短歌会に誘ってくれた大恩人の笹公人さんが、キャラクターをアシスタントにして笹短歌ドットコムやってたじゃん。あのときのペリカンどうなったのかな…。
Pーペリカンですか。そう言えば、アシスタントさんがいたみたいですね。
Nーそうそう。みんな笹さんがいまやスーパースターなのは知ってるけどさ…。あの笹さんのアシスタントが「ペリカン」だったことを覚えてる人いる? ってたまに思う。
俺も「笹さんのことが好きだ」って、多くのファンの方と同じくらいには言えるけどさ、あの「ペリカン」のことが忘れられない、しかも彼は「カッタくん」っていうとパクリだから、「カッタくん」の子供という設定で、「カンタくん」だった、なんてことを覚えてる人はほぼ、いないんじゃないかな。あのマスコットがペリカンだったかかもめだったか、何か鳥が出てたことは覚えてるけど、何の鳥かってすぐ思い出せる人は少ないかも…。でもぼくはそのくらい、笹短歌ドットコムが恋しい、ってことよ。
Pーあ、そういえば笹欄ができたら入るって話はどうなったんですか?
Nーうん。真剣に検討したけどね…。
Pー入らなかったの?
Nーうん。正直いまも前向きには考えてるんだけど、古来から「二君に仕えず」っていうじゃん。先生は簡単には変えられないのよ。だから、ぼくはもう「誰の弟子ともはっきりさせない」ことにしたの。
P―未来にはまだ居るんですね。
Nーそうなの。7月から「ニューアトランティス」欄に復帰です。きちんと歌も出てるはず…。大遅刻したけど。
Pーそれは、良かったです。
「文学」とはなにか?
1.さっそく本題
Pーじゃあさっそく本題に入りますね。なんで「歌人」ではなくて「文学者」になるなんて急に言い出したか、みんな怪しいと思ってると思います。もうちょっと補足してくださいよ。
Nーそうね。ぱっとみ似てるように思うんだけど、大きな違いだよね。「文学」って、西洋の「Literature」まで含めちゃうと、ほんとにいろんなものが対象になるからね。古代ギリシアまで遡らなきゃいけない、っていわれるとびびる。でも、ぼくは日本人で、日本以外で暮らしたことがなくて、日本語で書かれた文章以外きちんと読めたことがないから、この日本語の「文」のみを対象にする日本の「文学者」だって言っとくよ。
P―いきなりよくわからないです。ドストエフスキーとかヘミングウェイとかやらないんですか。
Nーうん。参考に読みはするけど、語れない。翻訳の人たちには大変失礼な言い方になるけど、ぼく日本人で日本語しかできないから、「この翻訳あってるの?」ってそもそも検証できないじゃん。
Pーえっ。さすがに間違ったものが流布しないんじゃないですか?
Nーもちろん「意味」はあってると思う。しかし、じゃあ文脈は? 用法は日本と同じ? 海外では同じ意味で「刀」と使っていたとしても、文化によって、まったく使い方が異なってたりとかしたらどうする?
例えば、ソードは、西洋では「剣」で、日本は「刀」っていうイメージがあるから、うまく訳し分けられてると思うけど、これがもっと「具体性がないもの」だと、だんだん困るんだよ。
「[LOVE]は「愛」と同じ意味?」
「それとも「恋」と同じ意味?」
と、恋する乙女の謎かけみたいに言い出しちゃったらきりがないし、一語一句、日本の文化と海外の文化を参照しながら「置き換えが成功してるか」を検証するのって、大変な作業なので、ぼくみたいに途中で疲れたり飽きたりする人間にはそもそもできない。
Pーうーん、なんかモヤモヤします。じゃあ西巻さんが「文学」というのはどのへんからなんですか。
Nー実はこれ、意外と歴史浅くてさ…。まさに明治時代からなんだよ。
Pーえ。古典は?
Nーそう思うっしょ。古典は大事だって明治からもちろん意識はされてたけど、「古典文学」っていう言い方はなかったの。文学っていうことばは実は以前もあったんだけど、「Literature」の翻訳として「文学」が当てられたのは明治からなんだよ。
P-意外っすね。
Nー実は小説もそうなんだよね。「小説」っていう言葉自体は昔からあるんだよ。江戸時代から…。江戸時代にあの曲亭馬琴が「小説」って自作につけてるのを見てびっくりしたことがあったけど、このまえ青空文庫で幸田露伴の講演録を読んでたら、「馬琴の小説」って確かに書いてあるんだよ。「えええっ…。露伴も認める?」みたいに思って。『南総里見八犬伝』ってあるけど、あれ「おはなし」は「おはなし」だけど、ほんとのジャンルは何なの…。って思う。
P-重要な問題なのかどうでもいい話なのかよくわからないです…。
N-「里見八犬伝」が小説なのかって、「ジャンル」の問題だから結構重要だよ。学術的に言うと「読本(よみほん)」として書かれたものらしいんだけど、「戯作」とはまた違うし…。いまとは違う意味の「伝奇小説」という分類の仕方もある。
P-難しいんですね。
N-そうなの。難しいんだよ。翻訳って業が深くてさ、うちら近代文学ばっかり読んでた人間にとって、「日本ではじめての小説は」?って聞かれたら
「それはもう坪内逍遥の『小説神髄』でしょ!」
って答えちゃうし、「実践編として『当世書生気質』とか、二葉亭四迷の『浮雲』とかあの辺りでしょ」っていう勘が働くんだけど、語源的には間違いなんだよね。
Wikipedia見たら、Wikiですら正確に『小説神髄』は、「初の日本の「近代小説」」って書いてある。「初の小説」なんてどこにも書いてない。つまり、「novel」の翻訳語として「小説」を使ったのが坪内逍遥だったと言うだけでさ、小説っていう言葉はもともとあるんだよ。漢文に。
漢文の本当のニュアンスだと、実は小説があると同じように「大説」があるの。「四書五経」って言うんだけど、孔子の儒教とかは、昔風にいうと「大説」なのよ。なんだかイメージつかない人は、岩波文庫で『論語』が出てるから読むといい。まあ道徳、というとあれだけど、「国を治める人のあるべき姿」を書いた「教え」だよね。現代のぼくらでも知ってる「教え」がでてくる。その対義語としてひとびとの巷(ちまた)の話を「小説」って言ってたらしいんだけどね…。
Pーなんか語源みたいな話ばっかりですね。
Nーいや、これほんと大事な話なの。ぼくらが馬琴の「小説」っていうとき、うちらが使い慣れた現代の小説の「喩え」として馬琴の「読本(よみほん)」を「小説」と言ってるのか、中国の「大説」と同じく本来の意味で「小説」と言っているのか、ごっちゃになるから。
馬琴は確かに、日本ではじめて筆一本で食えた人というか、日本初の職業作家、って現代的に言っても間違いじゃない人だから、「そこだけみたら「現代的に」小説家って言っても間違いはなくない?」
って思ったりするんだけど、「里見八犬伝」は名作だけど、さすがに今の意味の小説ではないよな、って思う。
Pーうーん。
疲れたのでおしゃべり
1.大学の思い出
Nーなんか疲れたからもうおしゃべりにしよう。実は最初、この対談をそのまま時系列に並べて、文学が社会にどう役立つかを明らかにするのがゴールかなと思って書き始めたんだけど、もう疲れたのでおしゃべりにします。
Pーはやっ。いきなり脇道にそれますね。
Nー大変なんだよ。どう書いてもわかりやすくならない。なんでこんなにぼくが語源にこだわってるんだろう、ってのも、そもそも理解されないだろうし。実はすごい「正統な方法」なんだけど、多分全く伝わってないよな。
この「語源で理解する」のがマジで大事だなと痛感したのは、日本語の話じゃなくて、「フランス哲学の話」で気づいてたんだ。ぼくがはじめて知った哲学のトピックが、ジャック・デリダの「脱構築」だったからなんだな。
P―デリダ? 誰ですか?
Nー「デリダって誰だ」ってダジャレがあったね。まあ日本で3人だけ哲学者をあげよ、って言われて、ジャック・デリダっていう人はちょっとは増えてるけど、まだまだメジャーじゃないかも。
ただ、高校卒業したてでほんとの哲学書も読めないのにさ、いきなりその時のゼミの先生に「読め」って言われて買わされた本が、テリー・イーグルトンの文学理論の本、『文学とは何か』だった。そこに確かに「脱構築」批評って書いてあるの。いやーーー。と頭を抱えた。
Pーいきなりゼミがあったんですね。
N-そうそう、実はうちの大学って1年生のときから基礎ゼミを選べるの。それは英文学とか国文学とか仏文学とか関係なく、好きな教授を選べる。高校を出たてで、いきなり少人数で大学の先生と意見交換をするんだよ。
ぼくはまったくなんの訓練も受けてないし、そもそも「大学教授」という人種にも出会ったことがないからさ。そのときの「大学教授」が、話し方からしてカッコよくて、「うわー。これが知識人かあ」と思ってミーハーにも痺れちゃった。
Pーなんか宗教みたいな話ですね。
Nーそう。あれは一種の霊的な体験だったね。話す内容より、話し方から刺激的で「ほんものの知識に飢えてる」ぼくを魅了した。取り憑かれたように「この人は間違いない」と思って、言われるがままにいろいろ本を買ったよ。すべて文学理論の本。あれほど世界が輝いて見えたことはないよ。読めば読むほど面白いんだ。ただ、当時はもうフェミニズムとか、ポストコロニアル批評とか、構造主義とか、だいたい高校上がりでも何を問題にしてるかはわかるし、人にも教えられるよね。
2.文学理論?
Pーええっ、ほんと? それって、ペンギンでもわかります?
Nーうん。フェミニズムが一番いまも流行しててわかりやすいけど、男と女。ポストコロニアル批評(コロニーって植民地だから)は白人と黒人。どっちが歴史的に「優位だったか」って話だよね。もちろんそれぞれ内側にいろんな問題があって、ジェンダークリティークとか、LGBTとかトランスジェンダーとか混血とか移民とか黄禍論とか、とかくデリケートな話題ばかりなんだけど、説明しやすさで言うと、この2つは具体性があってわかりやすい。
構造主義がちょっと分かりづらいけど、「中心/周縁」って書き方をする。実際、日本の文脈で捉えられた構造主義って、高校生にもわかりやすく「東京/田舎」とか、「日本の中心=東京/日本の周縁=東京以外の地方」で例示してくれるからね。わかりやすいの。
ただ、脱構築だけは説明しにくい。
Pーたしかに…。なんの話なんでしょうね。
Nー脱構築ってまあいろんな捉え方があるけど、構造主義がでたあとの「ポスト構造主義」の中心的なトピックとして出たんだよ。ポストっていうのがまた、訳しにくいんだけど…。郵便ポストと間違わないように、日本語でいい言い方ないかな、と思うんだよね。
Pーさすがに郵便ポストとは間違えないでしょう…。
Nーこれって、ふつうにカタカナの日本語になっちゃってるけど、ポストモダン(post-modern)みたいな言い方は定着してるんだよ。短歌の世界でもポストニューウェーブっていう言い方が流行したけど、あれは単なるパチもんだと思う。英訳してもダサすぎて和製英語っぽいし。
「未来」の歌人なら常識だし、歌人なら知ってるという人多いと思うけど、岡井さんのほうが断然うまくやってるよねやっぱり。
岡井隆に『〈テロリズム〉以後の感想/草の雨』ていう歌集があるのね。絶対わかってやってるじゃん。岡井さん。
Pーええ、なにがわかるんですか?
Nー一瞬戸惑うよね。「感想」って言われると。うちらは読書感想文みたいな言い方でしか、感想って使わないから、なんかダサくねって思うんだけど…。英訳してみたらわかるのよ。挑発なんだよこれ岡井さんの。この「テロリズム以後の感想」は、訳しにくいけど「Post-Terrorism Thoughts」になる。 めっちゃかっこいいタイトル。しっかり韻も踏んでるし。わざとダサく書いて、いくらでも日本語でかっこよく言い直せるのに、わざとぶっきらぼうに言ってるよね。ってわかる。
Pーおお、翻訳するとかっこいいっすね。
Nー単なる名詞のポストだと、ほんと、ただの「役職」とか「柱」って言う意味になるけど、Post-って接頭語になると、「後の」とか「以後」になるから、訳しやすい。岡井隆さんは自らを「龍(ドラゴン)」って言った人だから、歌に一首も触れなくてもタイトルの付け方を見ただけで「痺れるわ」ってなるよ。一見、無骨にみえて、「実は英訳したらカッコよかった」なんて、いくらでもあるし。
Pーめっちゃ新しい解釈ですね。
Nーだからポストモダン=近代以後、みたいな言い方かな。漢字では耳慣れないけど、三国志の時代が「後漢」だったり、「後」鳥羽上皇とか、後北条氏っていう言い方があったりするから、「後ー」って訳すかな。日本語の場合、あくまで時間的な「後」を言い表す言葉だから、以後ってニュアンスはない。だから、ちょっとニュアンスが違うけど。
Pーうーん。いきなり西巻さんが全力過ぎて、多分読者戸惑ってると思います…。
Nーそうか…。俺もなんか意味の話をしてるようで、語源の話しかしてないんだけど、海外の思想を学ぶのに、ぜったい「この訳し方でいいの?腑に落ちるの?」っていう視点はすごい大事だよ。昔は国語辞典を持ってて、それと同時に英和・和英辞典は絶対持ってた。いまインターネットがあって情報収集と調査が簡単だからめっちゃ楽だけどね。「近代」をやる予定の文学部の学生が、国文学だからといって、英語(話せなくてもいいけど)が苦手で意味がとれなかったらまずいよ…。
Pーへええ…。
Nーデリダの脱構築は、dé-constructionの訳語。もともとフランス語で、デリダ自身の造語だからマジで厄介なんだけど、ちょうど今いちばん日本でヒットしてるアニメが「デデデデ~」みたいなタイトルだったよなあ…。
P-あ、この前、りらちゃんとあのちゃんが出て盛り上がりましたね。
Nーそう。あれあれ。「悪りら」とか言って盛り上がってたけど、あの映画、正式なタイトルを書くと大変。『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』らしい。まさにdestructionだよね。日本語の意味は破壊。その対義語がconstraction。これが構築や建築っていう意味。
だから「destruction+constraction」で、「破壊+構築」とか、「破壊+建築」の造語だ、って答えが出たら60点。
P-どっから「脱」がでてきたんでしょうね。
Nーここからが俺も語学が苦手なところなんだけど、フランス語にはフランス語独自の接頭語があるらしいんだよ。dé-っていう接頭語は、このフランス語経由でラテン語から英語に入ってきたらしい。実はdé-strucitonもcon-structionも、「接頭語が違うだけで同じことに対しての動作なんだ」って、気づくとすごい早いよ。
P-ええええ。初めて聞いた。
Nーこんなん日本人はわかんねーよ、と思うけど、実は英語もふくめたラテン語系の言語って、この接頭語や接尾語が同じだから、なんか同じ系統の言葉って言えちゃうところがあるのよ。そもそも構造主義は、「structural-ism」だからね。
P-あれ、なんか似てますよね。
Nーそうなの。structって、構造物だったり構造だったりするの。それを壊すのがde-structで、作り上げるのがcon-struct。de-のなかに「抜く」とか「除去する」という意味があるから、脱‐は、英語では構造を脱するとか抜くとか、そういうニュアンスで理解されているんだと思う。もちろん英語だけでいうのは正確じゃないんだ。フランス語の辞書のほうが本義があるんだよね。
脱構築(dé-construction)って、まさに構造主義以後(post-structuralism)の、「構造主義そのものの取り扱いとか、振る舞い」のことを示してる。そこがわかると80点かな。
だから以前、詩の会で「脱構築という「概念」」ってとうとうと語ってた人がいたけど、あれほんとに意味わかってるのかな。と思う。みんな脱構築って「運動」とか「動作」とか「構造(struct)を、作ったり抜けたり脱したり壊したりし続ける」っていう「動き」のことを言ってるから、概念(concept)って言っても間違いではないけどさ、日本人って翻訳でしか理解しないしできないけど、日本語にすでになっちゃっている「英語」をきちんと参照したり踏まえたりすると、ものすごくかっこよかったりわかりやすかったり腑に落ちたりするよ、ていう話。
Pーわかってたら最初から言ってくださいよ…。
2.短歌を始めた理由
Nーそうだな…。俺、自分の得た知識がどう役に立つかが見えなかったし、すごい言いづらかったんだよね。なんか「短歌に入門する」んだから「今までやってきたことはゼロにしてがんばろう」と思ってて、ほんと「何も知らないふり」をして、短歌に入門したのよ。15年たった。でも、「短歌の世界」も相当やばいよ。って危機感しかなくてさ…。短歌って「情緒とか情感をすごい大事にする」と思ってる人もいるし、「普通でいいんだ」という人もいるし、もうバラバラだしね。俺、自分で「短歌の読み方」よりも「文学の読み方」を以前から死ぬほど叩き込んで来たから、それをちょっと思い出せば、いまの状況なんかも簡単に説明できちゃう。
Pーえええ、なんかずるいっすね。爪を隠してたんですか…。
Nーそうなの。実は俺、歌人にしては「詩」を読んでるほうかな、と思うよ。岡井さんが詩集出したときも驚かなかったし、実は最初ほんとに「小説家」になろうと思ってて、文学部卒業したらなにか「出版関連の仕事」に潜り込みたいと思ってた。だけど、愛読する大江さんがしきりに「いや、小説なんかよりいつも日本語について考えてるのは詩人のほうで、ぼくは詩人になれなかったので仕方なく小説書いてるんです」って真顔で言ってるから、詩は結構意識してたの。大学のときから「戦後詩」もそうだけど「新体詩」は買ったし、詩人としての吉本隆明もめっちゃハマって、それから吉本隆明が書いてる著作も読んでたから、結構「読者」としてはスジは良かったと思う。
でも今小説家になろうと思わないし、小説家で食えるってなっても、ついさっきリアルに成城の街を散歩していた大江健三郎さんみたいに書いて、現 代で評価されるかなって、当時は見通しが立たなかった。
そしたらだんだん不安になってきて、だって俺が勉強すればするほど、巷で売られている小説がつまんないんだよ。あの頃、確か『鉄道員(ぽっぽや)』がベストセラーで、「何が面白いのこれ」って思ったり、小説家が散々口を揃えて「批評家なんていらない。自分たちの役に立たない」って文芸誌で文句言ってて、実際、批評家がどんどん文芸誌からいなくなっていった。
しかも、最初に文芸時評をやめたのって、江藤淳さんなんだけど、どう考えても、俺がものごころついた時はもう亡くなる直前でさ…。とっくに「小説の批評に意味をみいだせなくなった」って言って、小説の批評から撤退しちゃったあとで、その後も、小説家が批評家に文句を言うっていう風潮が続くんだよね。
Pーへええ。
Nーそうなのよ。しかもその頃はまだ柄谷行人が現役バリバリのときで、彼がもう「文芸評論」はやらないよ、って言ったとき、やっぱり小説家にはなれないかなあ、と思った。批評家って、「難しそう」とか「勉強しすぎ」ってイメージもあるでしょう。でも、日本できちんと最先端の思想をわかりやすくくれるのって、ほとんどは文芸評論家だったの。
だから、「もう柄谷さんが見なくなった小説なんて意味ある?」って、はっきり失望しちゃった。 その後、小説が売れなくなっちゃって、批評家が去って、残った小説家たちに誰か名前が知られている人いる?
批評家は、別に「あなたの作品の指導をするためにいるんじゃなくて、あなたの存在を過去と比較して位置づけるのが仕事なんですよ」って言いたいね。
実作者と批評家、それぞれの仕事の違いを全くわからなかった小説家に、俺、誰も知ってる人がいないんだ。実際、きちんとした作家は「文学理論を読んだり」(筒井康隆)「批評家と対談してる」(大江健三郎)のを見てるから、全員がそうじゃないって思うけどね。
Pー難しいっすね。
Nー最後の世代って、
・「戦中派」
・「戦後派」
・「第三の新人」
・「内向の世代」
・(名付けられてないけど)村上春樹さんくらいまで
かな。
俺は古井由吉さんのことがあんまり好きじゃなかったけどさ、古井さんが亡くなったあと、これといって面白い作品に出会わなかったから、文学部をでたあと小説家は目指さずに地元に帰った。で、そのまま「生きる不安」を感じて歌人になったけど、小説は批評を否定したと言うか、さすがに日本の活字芸術の旗艦ジャンルとしての「小説」だから、曲がりなりにも売れてなきゃしょうがないじゃん。
だから、結局売るために「文芸評論(クリティーク)」が、「書評(ブック・レビュー)」に変わったんでしょ。と思ってる…。
小説は残ってるけど、小説はもう長い時間かけて「名付けられる」よりも「売れる」ほうが大事になってたんじゃない?
でも、もともと「売れてない」のがウリの短歌がそうなる必要ってある?
って俺には言えるの。短歌はその分まだ批評が残ってて、間違ってるかもしれないけど、まだ意味付けとか価値づけ、つまりは「~派」みたいな名付けが続いてるんだよ。前衛以後も。
でも、短歌は短歌のなかで閉じちゃってるから、それが短歌以外のジャンルに広まらないし、それが問題になることもそもそもない。実際、最近は木下龍也さんがでてきたりして、すごいいいこと言ってるし、木下さんにはいい印象しかないけど、誰もさ、木下さんに物申す歌人がいない…。
日本の小説の悲惨な結末(ぱっと見て、あ、この人面白そうだ、っていうのがなくなって、ふつうの人は装丁とかで手が出しやすいけど…)もうアニメやラノベのほうが全然面白かったり、海外ではまだフェミニズム批評とか、英文学者がまだ文芸批評って言って海外文学を対象にバリバリやってるのを見ると、「日本の小説は?」ってちょっと思うけどね。
Pーうーん。
Nーまあ、この嘆きはまたね。
枡野さんと木下さんの話は、ペンギンといつかするよ。
Pーはーい。
Nーそれに、だんだん国語がいらない、文系と理系は対立してるみたいな感覚もめっちゃ危険だと思ってる。俺は文学って「自分の意見をなるべく廃して」客観的にものをいう訓練、むしろ「科学だ」って思ってるから、実は文学者はほんとは理系が好きで、科学の進歩をありがたがる立場なんだと思ってるんだ。科学者は、どっかでいつでも文学の力を借りれるように相補的でないと、「文系か理系か」みたいな対決の場になっちゃったら、ほんとそれこそがハルマゲドンというかアポカリプスだからさ。実際、日本の社会は今すごいことになっててさ…。俺、同じ「学問」の仲間であるはずの「医学」に病気と名付けられて、15年だらだら飼い殺しされてたから、このことを「問題」と言わなくて何を問題というのって自分で言えるしね…。
みんなまだ二元論の亡霊に取り憑かれてる。この話もまたするね。とりあえずもう駆け足だけど、きちんと言わないと…と思ったから。ペンギンありがと。
Pーはい。なんというか…大変なおしゃべりでした。ではまた。
(最終更新日時:2024/05/19 20:58)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
