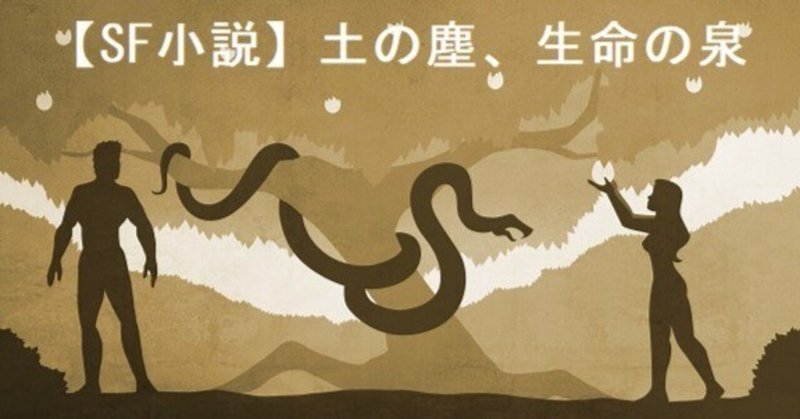
【SF小説】土の塵、生命の泉
(見出し画像はJeff JacobsによるPixabayからの画像)
アダム篇
「神ありて土の塵(アダマ)を集め成し、人を創りたもう。すなわちアダムと名付けり…… 旧約聖書「創世記」
1
――数十年前のことだ。
私はレコーダーに語りかけた。
命の火種が尽きかけているいま、語り残しておくことがあったのだ。
当時、私は国の防衛を担う人材を育成する大学に身を置いていた。
早くに両親を亡くし、兄弟もなく、お金を融通してくれるような近しい身寄りもなかった。
その学校は卒業後の一定期間、軍務に服すことで学費が免除される。平和なこの国では前線に立つこともないだろうし、後方勤務でも良いというのが魅力だった。
どのみち、選択肢はなかったのだ。
学費こそ免除されたが、生活費は両親が残してくれたわずかな蓄えの中から捻出しなければならない。
だから学校の近くの老朽化した寮に、いれてもらうことにした。
ある休日の午後、なにもすることがなく横になって寮の天井を眺めていると、スマホに着信があった。
勧誘などの迷惑電話が多かったので、番号を確認するまでとらない習慣だったのに、そのときは反射的に受けてしまった。
「お金儲けをしないか。君にその気があれば、いい方法を教えてあげるのだが」
受話器の向こうから、相手はいきなりこう切り出してきた。くぐもった男の声だった。
何かの勧誘か、詐欺の類だと考えるのが当然だ。それでなくとも、私はこの時期少々人間不信になっていた。
数日前に、自室に隠していたひと月分の生活費を盗まれたのだ。大騒ぎするような額ではないが、私にとっては大金だった。
このとき私は、何も返事をせずに通話を切るべきだった。
だが誰かに憤懣をぶつけたかったのだろう。「なぜ赤の他人のぼくなんかに? そんな良い方法があるのなら、自分で試したらどうです」と言い返してしまった。
「赤の他人なんかじゃないよ」相手は落ち着いた声で答えた。「幼なじみの誼で、良い情報を教えてあげたいと思うんだ」
嘘をついているのは明白だった。私には今も昔も、特別親しい友人などいなかったのだから。
「君とは子どもの頃、一緒によく遊んだじゃないか。忘れたのかい? 裏手の沢の上流にある隠れ淵で釣りをしていて、綺麗な縞のある魚を釣り上げたこと」
私は驚いた。
忘れかけていたが、田舎で育った子どもの頃、秘密のポイントで色鮮やかな魚を釣り上げたことがあった。だがそのことは、誰にも言わなかったはずだ。
「ぼくが転校してきて友だちになったとき、その秘密の釣り場のことを教えてくれたじゃないか」
会って話したいことがある。彼はそう付け加えた。
それでも私は彼のことを思い出せなかった。
しかし興味を惹かれたので、会うことにした。なにしろその頃の私は、お金はなくとも時間だけはたっぷりとあったのだ。
2
数日後の昼過ぎに、近所のレストランバーで約束の時刻きっかりに現れた電話の男は、ラフなジーンズに紺のシャツ、帽子を目深に被り、髭を蓄えた顔を伏せ気味に、迷わず私のところへ歩いてきた。
意外だったのは連れの若い女性がいたことだ。彼は妹だと紹介した。
白いワンピースの似合う、清楚な女性だ。肩までとどく黒いまっすぐな髪が卵形の顔を被い、その下から黒目がちな瞳がのぞいていた。
彼女は慈母のような温かみがある声で、「はじめまして」と挨拶し、まりあと名乗った。
その声を聞いた途端、あたりに光が満ちたように感じた。そう、ひと目で心を奪われたのだ。
彼はそんな私を興味深そうな顔で眺め、向かいの席にまりあと共に腰掛けた。
「久しぶりだね!」
互いに昔話をたどると、彼は間違いなく私のことを知っていた。
だんだんと、思い出せない自分のほうがおかしいのではないか、という気になってきた。
私たちが話している間、まりあは会話に加わるでもなく壁のほうを見ていたが、退屈している様子でもなかった。
「君に渡すものがあるんだ」
その声が、私の注意を話に引き戻した。
彼は白い封筒を三通取り出し、私に差し出した。見ると宛名のところに今月、来月、そして再来月の異なる日付が書いてある。
「表書きの日時に開いて、中を読んで欲しい」
それだけを告げると、注文していたコーヒーを飲み干し、まりあを伴って席を後にした。
彼女の後ろ姿を、未練を込めて見送る私を残して。
*
私は寮の自室に帰り、夢でも見たような不思議な気分の中で、今日の日付が書いてある封筒を開けた。
中からは変哲のない便箋が現れ、ある銘柄の株を買うこと、と書かれていいる。殴り書きされた文字は、「必ず高騰する」と結ばれていた。
私はがっかりした。やはり詐欺だった。
もちろん指示には従わず、残りの封筒ごと引き出しの中に放り込んだ。
ひと月ほどしてこのことを忘れてかけていた頃に、ひとつのニュースが目に止まった。
再生医療の分野で、画期的な治療法が話題になっているらしい。テレビのキャスターは、その製薬ベンチャーの株価が急騰している、と告げていた。
その企業の名まえに聞き覚えが合った。株を買うよう、先日の男に指示されていた銘柄だったのだ。
半信半疑のまま、しまい込んであった封筒を取り出すと、ふたつめの封筒にはちょうどその日の日付が書いてあった。
中からは、翌日に開催される競馬の重賞レースで、ある馬券を買うようにと書かれた便箋が出てきた。
競馬に詳しくない私でも、そのレースには大本命がいることを知っていたが、書かれていたのは別の馬の名まえだった。
「大穴がくる」前と同じく、殴り書きの文字がそこにあった。
翌日、競馬場で指定された馬券をわずかばかり購入してスタジアムに入ると、そこはすでに大勢の熱気に包まれていた。
最終レースに出走予定の本命馬は、人気が高すぎて配当は小さなものだった。そのため観客の多くは、大金をその馬に賭けていたようだ。
連勝を重ねていた本命馬が、私が買った穴馬に結局鼻ひとつ届かず、熱気と歓声が叫喚とため息に変わったとき、私は元手からすると結構な額の配当を手にしていた。
翌月になって三通目の封筒を開くときは、その中身を疑う気持ちはなくなっていた。どのようなカラクリかはわからなかったが、あの男は特殊な情報に通じているようだ。
その中身に従ってある国の外貨を買ったが、インサイダー取引の片棒を担がされているのかもしれない、とも疑っていた。
結局、男の意図を疑いつつも、私は楽をして大金を手にすることになった。
あの男の目的は何なのだろう? 大学の防衛機密でも狙っているのだろうか。
そこまで考えて、私は苦笑した。学生の身分で、高度な機密情報に接触できるわけもないからだ。
3
数日して、彼から電話があった。
「信じる気になってくれたかい?」
私は再び彼と会う約束をした。
以前と同じレストランバーで待っていると、密かに期待していたとおり、まりあも彼の後ろから姿を現した。
カジュアルなジーンズとピンクのサマーセーターに身を包んだ彼女が腰を下ろすと、そこだけにスポットライトが当たったかのようだった。
心なしか、お店の空気もなごんだような気がした。
電話の男は、私の向かいの席に着くなり口を開いた。
「実は君に頼みたいことがあるんだ」
そら来た。私は身構えた。しかし、後に続いた言葉は意外なものだった。
「まりあと暮らして欲しいんだ」
どきりとして彼女を見ると、ジュースのストローをもてあそびながら、「人身売買だわ。訴えてやる!」
彼女の話し声は先日と変わらず魅力的で、笑みを含んだ口調は心地よかった。
「冗談でしょう? 妹さんを見ず知らずの男と一緒になんて。第一ぼくは寮住まいなんですよ」
「それがふつうの反応よね。私なんてもらい手ないもの」
いや、そんなことは。そこを出ればいい。私と男の声が重なり、相手の男はもういちど、落ち着いた口調で言い直した。
「そこを出ればいい。実はもう適当な借家を選ばせてもらったんだ」
相手の言葉に驚いた。本気なのだろうか?
「そのために資金を稼がせてやったんじゃないか。これからも折を見て運用方法をアドバイスしてあげるから、お金の心配はしなくていい」
ことの成り行きについて行けず、私はとまどっていた。
「それとも、君はまりあが気に入らないのか?」
「ウソ!こんな美少女なのに?」
そんなことは。自分で言うな! また相手と声が重なった。
「そんなことはありませんが……」私は改めて口ごもりながら言った。
*
すぐに浮かんだのはハニー・トラップではないか、ということだった。対立国の拉致や、保険金詐欺などという言葉も頭の中を駆け巡った。
「ハニー・トラップも拉致も保険金も関係ないよ」まるで私の考えを読み取ったかのように、彼が言い足した。
「ぼくらは君と同じで早くに両親を亡くして、頼りになる身寄りもない。そこへもってきて、ぼくはひとりで海外に赴任することになってしまった」だから、と言葉を継いで、「だれか信頼できる人に、妹の面倒を見てもらうよう託したいんだ」
「なぜ彼女を連れて行かないのですか?」
「そうよ、そうよ!」
まりあも不服そうに、口をちょっと尖らせながら言った。
「実はまりあは、記憶を失っていてね」記憶喪失――物語の中ではやたらと目にするこの病気の主を、現実に見るのは初めてだった。「日常生活に支障はないが、個人的な記憶を失っているんだ」
ウソならもっとうまくつけばいいのに!
「ウソみたいでしょう?」
私がまりあをまじまじと見つめると、彼女はとまどったように言った。
「治療のためには、環境をあまり変えない方がいいと思うんだ」
私は内心首を傾げた。他人と暮らし始めるのは、海外に居を移すのと同じくらい大きな環境の変化ではないだろうか。彼の言葉にはやはり何か裏があるようだった。
「ぼくは信頼できないかもしれませんよ?」
彼は初めて笑顔を見せ、「君のことは良くわかっているからね」
「こちらの事情も考えてください。世間体というものがあるでしょう」
「私といっしょだったら、世間体がわるいの?」「彼女もいないくせに」
またしても声が重なる。彼女がいないのは図星だったので、私は憮然とした。
「そのうちまた連絡するよ」
彼はまりあをひとり残して、店を出て行ってしまいました。そのときの私は、本当に呆然としていた。
気まずい。場をなごませるようなトーク術をもっていない。
ぽつんと取り残されたまりあと向かい合うと、なぜ彼女が記憶を失くしたのか、その経緯さえ聞きそびれたことに気づいた。
それに加えて、彼女の戸籍や年齢、悪名高かった住民登録ID番号など、身元の情報をなにひとつ聞いていなかった。
「ああそうだ。これ!」
まりあは突然何かを思い出したかのように、ポーチの中をごそごそ探ると、契約書を差し出した。
賃貸物件を管理する業者の名が書いてある。どうやら彼女の兄が言っていた借家の管理会社のようだ。
「ぼくなんかと一緒に暮らすなんて、不安じゃないの?」
「不安じゃないわ。あなたは変なことをする度胸もなさそうだし」褒めてくれてありがとう。
「行きましょう!」
彼女に急かされてその業者を訪ねると、本当に私名義で家具付き物件の賃貸契約が申し込まれているとのこと。
本契約に必要な謄本の写しやIDのコピーなどを、後日提出するよう言われた。それなしで、仮契約できていたのが不思議だった。
少しばかりの彼女の荷物は、すでに運び込まれているらしい。
担当者が、鍵を渡すときに私とまりあを見て、
「新婚さんですか?」と尋ねたので、面映ゆい思いをした。
4
こうして同居することになった私とまりあだったが、ひとつ屋根の下に暮らすと言っても、当然寝室は別々で彼女の手を握ることもなかった。
彼女が言ったとおり、私は度胸のない小心者なのだ。
「ここが私の部屋!!」
彼女はそう宣言し、日当たりがよく広い間取りの二階の南側に陣取った。
私はまだ彼らの目的を疑っていたし、まりあは明るくふるまっていても、どこか壊れ物のような繊細さがあった。
だから、まりあとは一定の距離を置いていた。
「共同生活を始めるに当たり、まずルールを決めよう」私は彼女を前にこう宣言した。
お互いの部屋へは勝手に立ち入らないこと。
共用部分の掃除は一週間交代で。
まりあは専門学校に通い始めていたが、ときおり塞いだようになって何日も部屋に引きこもることがあった。
心配になって部屋を訪ねると、電池の切れた玩具のように壁を見詰めながらぼんやりとしていたりする。その姿はまるで、アンティークドールのような気品があった。
料理は下手、というより興味がなさそうだったが、ときおり朝食に作ってくれるシナモントーストだけは、私の好みにぴったりだった。
「お兄さんが好きだったの」
彼女の兄は、私と似た嗜好だったようだ。
私は彼女と不思議な運命のつながりを感じた。
それは思ったより居心地がよく、初めて家族らしいものを持てた気がした。
彼女も私のことを、「平凡でカッコイイところが全然ないのがイイ」と褒めてくれた。
それにしても気になるのは、兄と称するあの男の消息だ。彼は連絡先さえ残さずに姿を消してしまった。
そのうち、コワイ人達を引き連れてくるんじゃないか?との疑念が払えずにいた。
まりあにお兄さんのことを訊いても、よく覚えていない、との返事だった。なぜ記憶を失ったのかもわからず、最初の記憶は心配そうにのぞき込む彼の顔だったのだそうだ。
その後病院で精密検査をしても、異常は見つからなかったとのこと。
「彼は本当に、君のお兄さんなの?」
私はこの質問だけは呑み込んだ。
なぜかそんな質問をすると、今の関係が壊れてしまうような予感、彼女が薄もやの中に溶けて消え入ってしまうような予感がしたからだ。
ときおり彼から手紙が届き、約束通りお金の運用方法を指示された。
消印は外国のものだったが住所はなく、妹の様子も気に掛けていないふうなのが不審だった。
しかし指示は的確で、私はお金の心配から解放されることになった。
休日にはふたりで、よく近所のショッピング・モールに買い物に行った。
まりあは頭が良く計算能力は優れていたが、方向感覚が鈍いのかよく迷子になった。
何かに夢中になっているうちに、私ともはぐれてしまう。
インフォメーションに迎えに行くと、歳端も行かない子どもたちに混ざって、半べそで私を待っていたりする。
私は彼女に、GPS機能の付いた携帯を持たせて、同意をもらって必要なら位置情報をトレースできるようにした。
束縛じゃないぞ。と束縛する人間は言う。私もそのひとりかもしれない。
5
まりあがひとりで遠出をすることは滅多になかったのだが、落ち葉の舞い散る季節になったある日、夜になっても帰ってこないことがあった。
スマホの位置情報は、少し離れた場所にある海浜公園を示している。
何度コールしても「ただいま通話できません」と機械的な音声が返ってくるだけだった。
また帰り道がわからなくなったのかもしれない、と思った私は彼女を迎えに行くことにした。
その公園は港の近くにあり、夜はライトアップした帆船が見られるデートスポットとして有名だった。
最終のモノレールで最寄り駅に着いた私は、帰りはタクシーを拾わなければと考えながら、小綺麗なタイル張りの道を急いだ。細かな霧が立ちこめており、ときおり走る車のライトが輝線を描いていた。
冷たい風が頬をなぶり、ジャケットを着てくれば良かったと思った。急ぎ足で公園の正面ゲートに着いた頃には霧は小雨になっており、私は持参したビニール傘を広げた。
敷地は広く、外側を鬱蒼とした木立に囲まれていた。
周囲を遊歩道が巡り、中を通らなくても海側に出ることができる造りだ。
スマホを見てまりあの居場所を再確認し、私は遊歩道を歩いて海の方に向かった。
風に混じる潮の香りが、海に近いことを告げていた。
防風林の役も果たしていた木立を回り込むと視界が開け、黒々とした海から潮風が吹きつけてくる。傘を持つ手に力がこもった。
遊歩道は幅が広くなり、海側にフェンス、公園側に一定間隔でベンチが連なっているデート仕様になっていたが、さすがに今はカップルの姿もまばららだ。
歩道の先にある港にはランドマークの帆船が停泊しており、GPSが示していた場所にあおい人影が浮かんでいた。急いで駆け寄ると、街灯の下のシルエットはふたつが重なり合ったものであるとわかった。
「まりあ?」
そっと呼びかけると、影のひとつが慌てたように離れていった。その後ろ姿に見覚えがあった。
「なにをやってるんだ!」
思わず声を荒らげると、残された方の影はやはりまりあだった。
私は彼女に歩み寄り、肩を揺すって問い詰めた。
いつの間にか私の手からは傘がなくなっていたが、そんなことは気になたなかった。
「今のはお兄さんじゃなかったの?」
そのときのまりあの顔に浮かんでいた悲しみの表情。私には見せたことのないその切ない表情が、私の嫉妬をかき立てた。
「彼は本当に君のお兄さんなのか?」
私は封印していた質問を、ぶつけていた。
公園の中央にある観覧車のゴンドラが、風に大きく揺れている。潮が満ちてきたのか、波がぶつかる音が高くなり、しぶきが歩道の方へ舞い上がっていた。
無言を貫く彼女に、私はもう一度同じ質問を繰り返した。
「だったらどうだって言うの?」まりあは挑むような目で私を見返し、身軽に海側のフェンスに飛び乗ると、こちら向きに腰掛けた。
細身のジーンズに包まれた足先の華奢なミュールが、ぶらぶらと揺れる。
「私の世界に、私と同じ人間は兄さんとあなただけ。両親の記憶もないの。それがどんなに心細いか、わかる?」
私には想像がつかなかった。
答える代わりに、私は彼女を抱きしめながら言葉を掛けていた。
「これからは、ぼくがいるよ」と。
6
卒業を目前に控えた翌年の秋、私は彼女にプロポーズした。
保護者意識や同情などではなく、彼女をひとりの女性として愛していたからだ。まりあも私を受け入れてくれた。
戸籍を回復していなかった彼女とは、入籍はできなかった。しかし私たちは、教会でふたりだけの式を挙げた。
私は大学を卒業すると共に、都心にある防衛技術関連の企業に勤めることになった。
就職後の十年ばかりは、”奇跡の日々”とマスコミが謳ったように世界的にも紛争がほとんどなかった。だから私が軍務に就く機会などなかった。
波風のない平穏で満ち足りた十年余りの日々が、あっと言う間に過ぎていった。
ふたりの間に子どもはできなかったが、私はまりあのことを愛していたし、彼女もそれに応えてくれた。
まりあの兄と自称したあの男について、子どもの頃を過ごした学校に問い合わせるなどして調べてみたが、結局なにもわからずじまいだった。
彼はまるで最初からいなかったかのように、何の痕跡も残していなかったのだ。
それでも私は、いつかあの男が彼女を連れ戻しにくるのではないかと不安だった。その予感は半ば当たっていたのだが……
先走ってしまった。話を戻そう。
私は言葉を切り、ボイスレコーダーのスイッチをオフにした。
水差しからコップに水を注いで、一気に飲み干す。感傷を切り離そうとしても、あの時代を思い出すとどうしてもこうなる。
私は自分を励ますようにレコーダーのスイッチを入れて、ふたたび語り始めた。
防衛関連の技術を扱うと言っても、私が勤めた企業の本社ビルは都心の一角にあり、一般企業となんら変わりなかった。
私たちが扱う”商品”は多岐にわたり、この世の中に軍事転用できない技術などないのだ、ということが実感された。
私は自己進化型ニューロ・コンピュータを母体としたAI開発に、入社以来専従することになった。
ニューロ・コンピュータとは、iPS細胞を神経細胞成長因子で分化誘導してできた擬似神経組織を、シリコン素子で置き換えた演算用プロセッサのことだ。
我々が<エゼキエル>と呼んでいたプライマリ・ニューロ・コンピュータの本体は、地下施設に設置されていた。
<エゼキエル>の脳幹からはニューラル・ネットワークが形成され、進化を繰り返して複雑な分化を遂げていた。
自己進化型のニューロAIはふるまいが生物に似ており、それを解析するのに必要なのはエンジニアではなく、心理学者だった。
やっと主任クラスになれた年には、私の紹介でまりあも同じ企業に職を得ていた。
年齢を重ねても、まりあは一向に対人恐怖症が直る気配がなかった。だからプログラマ同士が高いパーティションで仕切られて、顔を見ることもないその仕事を喜んでいた。
キーボードの上をなめらかに走る彼女の左の薬指には、私と同じ銀色のリングが嵌められていた。
彼女の仕事は、電磁波を遮蔽した地階の無味乾燥な室内で、ときには一日じゅう人と言葉を交わすこともなく、<エゼキエル>の自己学習の進展を確認することだった。
エゼキエルとは、旧約聖書に出てくるバビロニアの預言者であり、当時の私は知るよしもなかったのだが、それはプロジェクトの本質を表していた。
開発に携わって約十年。
やっと<エゼキエル>が幼児程度の自我に目覚め始めたとき、私はプロジェクト・リーダーのヨセフに呼び出された。
*
彼はメールや仮想空間のアバターでしか会話を交わすことのなかった、雲の上の人物だ。
社員が”天上界”と呼んでいる最上階の一画に、役員たちと同じく専用の部屋を持っている。どうやら彼は、単なるリーダー以上の扱いを受けているようだった。
私などに何の用だろう。
最初は半信半疑だったのだが、秘書に案内されて執務室に入ったとき、初めて彼と面会するという実感がわいてきた。
ヨセフとの面会には別の興味もあった。
なぜかアバターを使ってテレビ会議に参加するだけで、人前にその姿や肉声をさらすことがなかった、本人の姿を目にすることができるのだ。
柔らかい照明に照らされた室内で待っていたのは、当時の私より少し年長と思われる、ラフな格好をした背の高い男だった。
コーカソイドと東洋系のハーフのような中間的な顔立ちが、人種を超越した印象を与えていた。
「よろしく」
差し出された手を握ったときに一瞬ながら、まりあとよく似た雰囲気を感じた。
「<エゼキエル>は、ニューロ・コンピュータの弱点である解析速度の問題も克服したようだ。プロジェクトを次の段階に進めるときが近づいている」
「その話のために、ぼくを呼び出したのですか。ぼくなんかにできることがあるのでしょうか?」
ヨセフが語ったのは、ニューロ・コンピュータの実用化に向けての方針でだった。
この分野の先駆けとなった、郭―エクハート効果による同調転移の応用開発。
人間の脳を模したニューロ・コンピュータは演算処理、つまり人で言えば考えていることに応じた微弱な電磁波を発している。
エクハート教授は初期のニューロ・システムを研究中に、このコンピュータが周りの人間の情動に干渉を及ぼすことを見いだした。しかもそれは双方向性を持ち、人間からニューロ・システムに干渉することも可能だった。
また干渉の強さには個人差があった。彼はこの現象を体系立てて理論化した最初の研究者だ。
「エクハートが発見し、郭先生が証明した同調効果を今さら研究するのですか?」
「郭のチームは全てを証明したわけではない。彼らの成果は、部分共鳴とでも言うべきものだ」
この技術に将来性があるのは、誰もが認めるところだった。
事故や病気で身体機能の一部をを失った人が、ニューロ・コンピュータを介してCCDカメラやセンサーを使うことにより、視覚、聴覚をおぎなえる。
また精密な遠隔操作をする代替兵士を、前線に送り出すこともできる可能性があった。
「ニューロ・システムに同調する適性について、一般的な最適解はない。だから社員全員の適性を試してみた」
忘れていたが、そう言えば先月そのテストを受けさせられた。
「ぼくが合格したのですか?」
「いや」彼は首を振った。「君の奥さんだ」
彼が私を呼んだのは、私からまりあに実験への参加を促すよう頼むためだったのだ。
彼はおもむろに英語論文の粗いコピーを机から取り出すと、「郭教授の未発表論文だ」と私の前にかざした。
入手経路は訊かないでくれ、と言われて差し出されたその論文に目を通した私は、驚いた。
『過剰同調時の被験者における特異例』という題でまとめられていたのは、郭教授のグループが行ったとされる、数年前の同調実験の結果だった。
読み進めると、そこには被験者が幻視した未来の光景が、実際の映像である可能性が高いという結論が導かれていた。
到底学会には受け入れられない内容だ。
「研究者の間では、ニューロンのゴーストと呼ばれている現象だ。単なる錯覚かもしれん。あるいは何らかのバグか」
「あなたはこれを否定するのですね」
それが当然だと思った。しかし彼から返ってきたのは、別の言葉だった。
「公的見解としてはね」
含みのある言い回し。
「私自身は、ニューロ・コンピュータとの同調は、質量転移をも可能にすると考えている」
情報だけではなく、質量をもつ物体の時空間転移。そんなことがありうるのだろうか。
「実はこの未発表論文にすら、記載されなかった事実があるんだ」
この実験のとき、過剰同調を起こした被験者側のシステムとニューロ・コンピュータとの間で、不具合が発生したそうだ。
原因は、被験者の脳波モニタリング・システムとニューロ・コンピュータの内部クロックが二・一七秒ずれたことだった、と彼は言った。
「実験開始時にはこのずれはなかった。このとき、被験者は未来のイメージをリアルに想起していたんだ。このタイム・ラグは、被験者とそのシステムが二・一七秒未来にスリップしたことによると私は考えている」
「質量保存則から考えれば、あり得ないことのように思いますが」
「転移した先の時空間で質量が増加する問題だね。それは質量の交換、あるいはエントロピーの増大によって相殺されることで解決される」
「どのようなメカニズムで、この現象が起こると考えているのですか?」
「ニューロ・コンピュータは我々の脳をモデルにしたものだが、動物は潜在能力として危機回避のための予知や特殊能力を持っている。超能力などというと安く聞こえるがね。
この能力は動物では通常抑制されているが、ニューロ・コンピュータは演算能力を増大する過程でそれを顕在化させたのだと思う。だが残念なことに、我々にはそれをコントロールする手段がない。ニューロ・コンピュータとの同調技術は、その解決策となる可能性があるんだ」
「もしそれが真実だとしても」私は慎重に言葉を継いだ。「それでは同調することが可能な、まりあにしか制御できない技術になります。普遍化、つまりどんな人が使っても同じように効果が現れなければ、使える技術にはならないのでは?」
「そのとおりだ」ヨセフは苦笑した。「タイムマシンを創ろうとまでは考えていないからね。確度の高い未来の情報が得られれば、当面、プロジェクトのスポンサー企業は納得してくれるだろう。彼女がそのための巫女として働いてくれるのなら、専用マシンになっても構わない」
エゼキエル=予言の書は、実際に未来を語るシステムになるのだろうか。
「ヨセフ、あなたが郭教授ですね。あなたも適性者なのでしょう? だから、まりあのことも、見ただけでわかったんだ」
「悪いが亡命中の身なのでね」彼は、最初の質問にはそうとしか答えなかった。「私は適性者だった、と言っておこう。成長の過程でその能力を喪ってしまったんだよ」
そして、やや暗い調子で付け加えた。
「私の究極の願いは、人々を楽園に導く存在を創ることにある。しかし私自身がそのような存在になることはできないようだ。
だから私はマルアークを創り出すことにしたんだ。誰も祖国を追われることのない世界をこの地上に築くために……」
7
そのときは、「マルアーク」の意味を知らなかった。
私はその夜、自宅で夕食を摂りながらまりあにヨセフの申し出を説明した。もちろん「いやなら断っていいんだよ」と付け加えながら。
私は彼女が拒否してくれることを、内心願っていた。
しかし彼女が発したのは、「私なら大丈夫、でも、なぜみんな未来を知りたがるのかしら?」
「君だって占いが好きじゃないか」
すると彼女は、屈託のない笑顔を浮かべた。
私にはひとつの疑問があった。
もし事前に未来の出来事を知ったがために行動を変えたら、未来に起こる出来事自体が変わってしまうのではないか? というパラドクスだ。
その場合、存在しないはずの未来を見たことになる。
この疑問をぶつけられたヨセフは、パラドクスの答えを知ることも実験の目的のひとつだ、と答えた。
彼の見解は一般的なもので、未来は多重分化し、<エゼキエル>が見せるのはその時点で蓋然性の高い未来像だということだった。
被験者の候補は他にも何人かいたようだが、適性試験の結果まりあが第一候補になった。
数ヶ月かけて<エゼキエル>の一部を調整し、まりあの神経系に擬したブランチ・システムが立ち上げられ、それは当然のように<マリア>と呼ばれることになった。
しかしマリア・システムと同調を試みた二回の予備実験結果は、芳しいものではなかった。
実験のあと『どんな気分?』と尋ねられたまりあは、『サイアク!』とだけ答えた。
予備実験の結果はヨセフに伝えられ、本実験の予定はしばらく延期になった。
*
導電水が体温と同じ温度に調整されたコクーンの内部は、私とまりあが手をつないで浮いていられる広さがあった。
コクーン上部が閉じられるとき、一瞬パニックになりそうになったが、実験前に投与された精神安定剤が効いているためか、すぐに落ち着きを取り戻した。
口にくわえたマウスピースから聞こえるプシュー、プシューという給気音と交互に、コポコポという排気音が大きく響く。
まりあの右手を握りしめると、彼女も握り返してきた。彼女の指が、ふたりの絆を確認するかのように、私の薬指の指輪の痕をなぞる。
実験の前に金属類は除かれ、虫歯の金属冠も樹脂のそれに替えられていた。
照明のせいで薄く黄色に染まった液体の中、羊水に包まれるように浮かんだ状態で首をひねり、私は彼女の表情を確かめた。
彼女はリラックスしているようで、微笑み返してくれた。
話が飛んだようだ。
二度の予備実験の失敗のあと、ヨセフは私にもまりあと共に実験に参加するよう、促した。
「彼女の同調能力が優れていることは間違いないが、感情が乱れやすく力が安定しない。安定化装置が必要だ」
「安定化装置?」
「君のことだよ」
プロジェクト・リーダーのひと声で、コクーンはふたり用に作り替えられた。
初期の同調実験しか知らなかった私は、パッドを頭頂部に付けるものと思っていたので、この金属製の繭を見て驚いた。
コクーンと呼ぶこの金属カプセルの中に、導電性流体と共に入ることにより、全方位的に脳から発する微弱な電磁波を捕捉できるということらしい。
「何か異常を感じたらスイッチを押すように」
注意を促す声が、イヤフォンを通じて響く。それにしてもこの状態で、何が異常で何が正常なのか、判断がつくものなのか?
体が安定するように胎児姿勢をとると、体温と同じ温度の周りの液体が心地よく感じられ、実験の緊張感も薄れて眠気に誘われる。
導電水は浸透圧も調整されているせいか、皮膚がふやける感じもなく、目を開けても痛くない。
最初はひらひらと揺れる薄手の手術衣が気になっていたが、やがてそれすら忘れ、自分の身体と周りを囲む液体との境目すらあやふやになってくる。
まるで体が、どんどん膨らんでいくようだ。
気泡の進む方向が上だと理性で言い聞かせなければ、上下すらもあいまいになりそうだった。
コクーンの中でホログラフィ映像が焦点を結び、ヨセフが作成した催眠術のような同調プログラムが、映像と音になって現れた。
液体窒素がコクーンの外殻に満たされ、外周に巡らされた超伝導コイルが励起されてまりあの脳波を拾っているのだろう。同時に<マリア>の方も同じように波形調整が行われているはずだ。
トクン、トクン、鼓動の音が耳から伝わってくる。いつの間にか、眠っているとも起きているともつかない状態でゆらゆらと揺れていた。
まりあ、まりあ、大丈夫か? だれかが顔をのぞき込んでいる。
ああ、これはまりあが見ている夢だ。自分の記憶と、彼女の記憶が混ざり合ってきているようだった。
「脈拍が速い。大丈夫か?」
どこか遠くから、声が聞こえてくる。
「危険だ。同調を解除する」
私は緊急スイッチに手を掛けようとするが、体に力が入らず、思うように動かない。
最後に覚えているのは、光が視野にあふれたことだけだった。
8
どれくらいの時間、気を失っていたのだろうか。
気がつくと私とまりあは、どこともつかぬ小高い丘の上にある、牧草地のような所に横たわっていた。
しばらくの間意識がもうろうとし、体にも力が入らなかった。まるで破水したかのように導電水が周りを濡らしていた。
胎内から産み出されたばかりの赤子のように、びしょ濡れの手術衣のまま、私はまりあの手を握って倒れていた。
ここはいったいどこ?
ゆっくりと体を起こすと、徐々に手足に力が戻ってきた。髪も服もびしょ濡れだったが、幸いにも暖かい光が差している。
ヨセフが語った、ニューロ・システムとの同調実験時の、二・一七秒間のタイムスリップ。もしかしたら、私たちは未来へ飛ばされたのかもしれない。
時空間を未来に――
考えに集中しようと思ったが、先ほどから何かしらの違和感がじゃましている。
うめき声がしてまりあが目を覚ました。
慌てて駆け寄り、「まりあ、まりあ、大丈夫か?」顔をのぞき込むと、怯えたような声で、「……だれ?」
初めて会ったときと同じような、記憶喪失状態だった。
ショックによる一時的な症状かと思い、彼女の体をゆっくりと起こすと、先ほどからの違和感の正体に気づいた。
もともとまりあは若く見え、この十年でそれほど歳を取った感じはなかったが、それでも加齢による外見の変化はある。それが、すっかり若返っていた。
私は自分の手をまじまじと見詰め、さらに顔を触ってみた。
その変化は彼女だけでなく、自分にも起きていることがわかった。肌の張り、視力、筋力などが明らかに昨日までとは違っていたのだ。
途方に暮れてあたりに目をやったとき、私は衝撃を受けた。
丘の中腹にある廃墟のような小屋の周りに、壊れた自動車や機械の大型部品が散らばっていたのだ。それらはいずれも錆び付き、動物の死骸のように無残な姿を晒していた。
私は動転した。小説や映画で幾度も見た荒廃した未来像がそこにあったからだ。
文明が滅んだ未来世界にまでタイムスリップしてしまったのではないか。この先どうやって生きていけばいいのだろう。
「あんたたち、こんなとこで何してるんだ?」
そのとき、いつの間にか背後に止まっていた軽トラックの運転席から、しわの奥まで日に焼けたような老人が声を掛けてきた。
「産業廃棄物を捨てに来たんじゃないだろうな」
「産業廃棄物?」
まりあをかばうように背後にやりながら尋ねると、老人は廃墟のような小屋の方をあごで示した。
「違法投棄をするやつが、後を絶たないんだ」
どうやら勘違いしていたようだ。
「川にでも落ちたかね?」
相手は運転席から、気味悪そうに私たちのびしょ濡れの手術衣を見回している。
私は軽トラックの助手席に、見慣れたタブロイド紙が置いてあるのに気づき、彼に懇願した。
「見せてもらえませんか?」
手渡されたゴシップ紙の日付は、実験の日から十年ほど前のものだった。私たちは未来ではなく、過去に飛ばされたのだ。
*
軽トラックの男は、このあたりの土地を持っている地権者だった。
林業を営んでいたが、今は引退したとのこと。この丘は山ひとつ越えると、私が勤めていた市街地が遠望できる場所だったのだ。
意外に親切なその老人は、困った様子の私とまりあを自宅に泊めてくれ、息子が着ていたという乾いた服を私に、亡くなった奥さんの古い服をまりあに貸してくれた。
彼と同じように歳を経た二階のベッドに、まりあとふたり横になって、私はこの日の出来事を考えてみた。
過去への転移は、まりあとマリア・システムとの同調実験の予期せぬ結果によるものとしか思えなかった。
転移を制御する方法が確立されていない以上、未来に転移するのと同じように、過去に飛ばされる可能性もあったということか。
私たちの若返りについても、ヨセフの話がヒントになってひとつの仮説を思いついた。
この時空に私たちが出現することによるエネルギーの増大分を相殺する、エントロピーの増大が起こったとしたら……
人間の身体を構成する六十兆個もの細胞が蓄積した、DNAの加齢情報が失われることにより、質量分のエネルギー増加を打ち消して若返りが起こったのではないか。
遡行年数とほぼ同じ、十数年の若返りが。
天井の木目を見上げながら、このようなことを考えているうちに、私は自分の体が揺らいだように感じた。
目の前の光景が蜃気楼のように揺れ、視界がぼやけて一瞬コクーン内部の映像が浮かんだ。
私の身体は、この時空間では不安定なのかもしれない。
まりあを介して<マリア>と同調していたため、結びつきが希薄で転移が不完全だったのだろう。
だとしたら、私の身体はそのうちに元の時間に戻れる可能性がある。そのことを考えたとき、冷水を浴びたようになった。
まりあは?
隣で寝息を立てている彼女の体には、このような異変は起きていないようだ。
彼女は<マリア>と直接的に同調していたため、時間遡行が完全だった。そのため細胞の若返りだけでなく、記憶という脳内情報も解放することで、この時空間に対して、より大きな対価を支払ったのかもしれない。
このままだと私は未来に、元の時間に引き戻されてしまう。
私が戻るのが実験後の世界だとすれば、そこには私と暮らしたまりあはいいない。
あるいはそこでは過去に戻ったまりあが、別の経験を経て生きているのだろうか? それとも、そこは元の時空間とは異なる、平行世界となっているのだろうか。
なんとか私の体の再転移を止める方法はないか、またまりあを私と同じ未来に送る方法はないかと考えたが、何も思いつかなかった。
ただ、このまま記憶を失ったまりあを残して、自分だけ元の時代に帰ることがあってはならない、と強く思った。
翌日、息子を訪ねるついでにと、市街地まで軽トラックで私たちを運んでくれた親切な老人は、別れ際に「生きてさえいれば、必ずいいことがあるさ」と言って手を振ってくれた。
どうやら心中を謀ったカップルと思われていたようだ。
9
ウイークデーならこの時間、過去の私は学校の授業に出ているはずだ。
記憶を失ったまりあを伴い、昔住んでいた寮の裏口からそっと中に入って自室の風景を見たときは、やはり信じられない思いがした。
狭い一人部屋に差し込む日の光が、見覚えのある情景を照らしている。
黄ばんだ壁紙の枯れたにおい。良い思い出が少しもなかった部屋だが、それでも懐かしい気持ちがこみ上げてきた。
ここに、過去の自分が暮らしているのだ。
そのとき、私は感慨と共に自分殺しのパラドクスを試したい衝動に駆られた。
もしここで過去の自分を殺したなら、この身にいったい何が起きるだろうか? もちろん実際にはそのようなことはしなかったが――
私は過去の自分に手を合わせ、戸棚に隠していたお金を取り出した。
若い頃に、生活費を盗まれたことで人間不信になった時期があったが、盗んだのは自分自身だったわけだ。
そう。私は過去の自分にまりあを託すことにしたのだ。過去に自分がそうされたとおりに。
手に入れたお金でまりあとモーテルに逗留し、思い出せる限りこの時代で起きた出来事をメモした。
あらかじめ起きるイベントを知っていることで、ずいぶんとお金を得る手段があるものだとわかった。
記憶を失ったまりあには私のことを兄と説明し、彼女の名まえや簡単な履歴を教え込んだ。
彼女は個人的な記憶を失ってはいたが、言語や計算能力はすぐに回復した。
そして他方では過去の自分にアドバイスして、まりあを養うための資金を作らせた。過去の自分に宛てた手紙は、筆跡がわからないようにわざと殴り書きにしたり、それなりの苦労が伴った。
いよいよ過去の自分と対面すると、十年前の私はだらしなくまりあに見とれていた。
自分に対して嫉妬を覚えるというのは奇妙なものだが、他の人間に彼女を取られるよりはるかにましだ、と自らに言い聞かせた。
兄と自称した私と、過去の自分がそっくりなことでまりあが混乱しないよう、私は髭を生やして人相を変えた。
彼女がこの私と、過去の自分との関係に気づいたのかどうかはわからない。聡明な彼女は何もかも見通しているような気がしたので、詳しい説明はせず、私は遠くに行かねばならないので他の人のお世話になるのだ、とだけ告げておいた。
過去の私が未来から来た自分に気づくのではないか、とも思ったが、間抜けな私は気づく素振りもなかった。
自分自身の声は、空気振動と骨伝導の合成音なので外部音として聞くと違って聴こえるし、自分が動いている姿を見る機会は一般人の私にはほとんどないのだから無理からぬことだ、とは自己弁護になるだろうか。
もちろん知人に会わないよう身辺には注意を払ったし、お金の運用に関する助言を書いた郵便は、海外から投函したと見せかける必要があった。
ジョーク・グッズを扱うショップで買った、偽の消印スタンプを押して新居のポストに直接配達したりと、工夫を重ねた。
こうして私は過去の自分をコントロールし、まりあを託すことに成功した。
計画がうまくいくと、安堵すると共に寂しさが募る。私の体が揺らぐ時間間隔が狭くなってきていた。未来に戻る日が近づいているのかもしれない。
この世界に長くいられないことだけは、なせかわかっていた。
まりあがいなくなった喪失感は、思っていた以上に私を苦しめた。前の世界には、もはや以前のまりあはいないのだ。
最後の別れを告げるため、私は電話でまりあを呼び出した。
小雨の降る夜、港の見える公園で私は彼女に告げた。
「ぼくはもうすぐ行かなければならない」
まりあの顔を脳裏に焼き付けておこうとその瞳を見つめると、記憶を失っていたはずの彼女に、微かな変化が起こった。
彼女の唇は、涙の味がしました。
「なにをやってるんだ!」
昔の私が上げる嫉妬に駆られた叫び声に苦笑し、まりあの体を離すと私はその場を退散した。彼女がその時浮かべた切ない表情を、忘れることはできないだろう。
*
この時代に帰って以来、ずっと考えていることがある。
それは、まりあの存在についてだ。私にとってかけがえのない女性。未来の自分に託された、彼女自身はいったい何者だったのだろう?
まりあはいったい誰から生まれたのだろうか?
いや、彼女はどのようにしてこの世界に現れ、どこに行くのだろうか?
そのことに気づいたとき、私は呆然とした。
私は、ボイスレコーダーを見つめながら、しばらく言葉を発せずにいた。
私は未来の自分が連れてきたまりあという女性と出会い、恋に落ちた。そして十年余りの結婚生活の後、ニューロ・コンピュータとの同調実験により共に時間を遡行すると、若返った彼女を過去の自分に託し、私自身は未来へ帰った。
まりあはそこで過去の私と共に十年余りを過ごし、また……無限の循環が繰り返されることになる。
ではこの循環を逆にたどったとき、まりあという女性はいったいどこで誕生したのか?
彼女はいつ死ぬのだ?
始まりはいったいどのようになっているのか? この循環が終わることはあるのか?
時の無限ループを抜け出す選択肢はあるのか?
連綿と続く時の循環、存在の環の中で永遠に繰り返される生。
彼女は自分の尻尾を飲み込む輪廻の蛇のように、永遠のループを繰り返すしかないのだろうか?
ああ、頭がおかしくなりそうだ!
人はみな全能の神が土の塵からお創りになり、アダムと名付けた最初の人間の子ども。
塵より生まれ、塵に還る存在。
それが人であるならば、まりあとはいったい何者なのか?
この話の中で、ひとつ気になることがあった。
ヨセフが語った言葉。「だから私はマルアークを創り出すことにした」
”マルアーク”、もしくは”マルアハ”とは、右から左に文字を綴るヘブライ語で”遣わされし者”、人とは起源を異にする者を指す言葉なのだと知った。
これがヨセフの言う、人々を楽園に導く存在なのだろうか。
彼の行為が生み出した、人ならぬ者の存在の可能性に、私は魂が震えるのを感じた。
この十年ほどの間、世界中で奇跡的に紛争の火種が途絶えていた。
メディアはそろって、まるで天使がこの世に現れたかのようだ、と表現した。(了)
(【SF小説】土の塵、生命の泉 イブ篇に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
