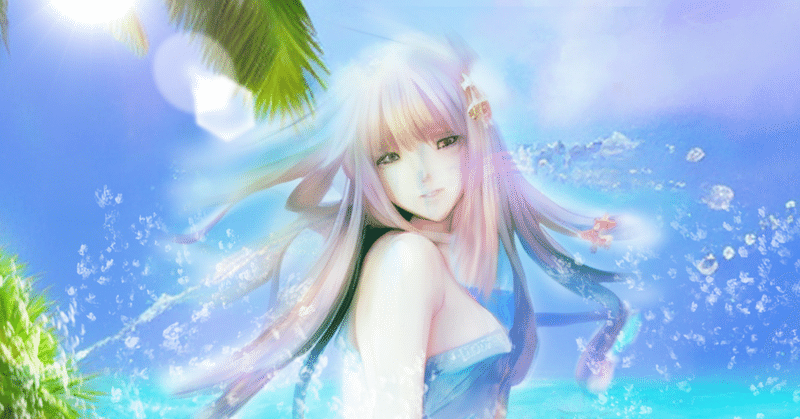
【ミステリ小説】セイレーンの謳う夏(2)
(あらすじ)民宿兼ダイビングショップ『はまゆり』でバイトする「顔のない」ぼくは、お客さんがダイビング中に不思議な生き物?を見た、という話を聞く。
2 人魚の憂鬱
冷房が効いた店内から外に出ると、とたんにムッと焼けた砂の熱気や焼きそばのソースの匂いなどが混ざった夏の欠片が押し寄せてくる。
日の光が眩しく、揺れる海面が白い光を反射していた。
「ほっとけよ!!」
エアをチャージしたボンベを台車で店先に運んでいた、ダイビング・インストラクターの御子柴さんが、ぼくの意図を察して声を掛けてきた。
目鼻の区別がつかないほど真っ黒に焼けた顔で、その強面の風貌はバイト仲間からも一目置かれている。生え際と額の境目があいまいなボーズ頭の彼は、まだ三十過ぎだそうだ。
ぼくは彼の言葉を振り払うかのように、入り口にあった白い日傘を手に鶏君のあとを追った。
騎士(ナイト)という柄ではなかったが、ぼくが守ってやらねば、という気持ちがもくもくと湧きあがってくる。
しかし、わさびソフトクリームの看板を回ったところで、当の鶏君が今にも泣きだしそうな顔つきで引き返してくるのに出くわした。
あー、手遅れだったか! ぼくは頭を抱えそうになる。
「夢愛さん!」日傘を差し掛けながら声をかけると、長い黒髪を揺らして人魚姫が振り向いた。「だめじゃないですか」
「なんのこと?」
日に焼けてはいるものの、龍ケ崎のスタンダードからするとずっと白い顔に、無邪気な表情を浮かべて彼女は答えた。
バイト仲間に言わせれば、その整った顔立ちは坂道にいてもおかしくないらしい。
真っ直ぐな長い黒髪が掛かる、左の頸筋から肩に掛けての薔薇(ローズ)タトゥーが、アンビバレンツな雰囲気。目立つラピスラズリのピアスは熱くないのだろうか?
「さっきのお客さんですよ」
彼女はああ、と言った。
「ラインやらへん、メアド交換せーへん? SNS教えてくれへん? ってうるさいから、『せーへん』って言ったのよ。
したら、ぼくのどこが気にいらへんの? 絶対直すから、だって」楚々とした口調で続ける。「だから、ミサキさんにふられちゃった? 寂しいの? 慰めて欲しいの? って言ってやった」
「お客さんの個人情報をばらしたんですか?」
「まさか!」夢愛さんは驚いたような声を上げる。「そんな個人情報を申告するお客さんはいないでしょう? 単純な推理よ」
ぼくは、昨夜の飲み会、そのあとの花火などの様子を思い出した。
「彼のスマホの裏にプリクラを剥がしたあとがありましたね。長い期間貼っていたためか、四角い痕がくっきりと残っていました。
彼のファンキーなファッションのなかで、キャリーバッグに付いていたゆるキャラの小さなぬいぐるみが異質だった。
おそらく元の彼女からのプレゼントを捨てられずに、彼が引き摺っているため。
それに『東の崎』、『岬』などの言葉に対して、びくっとするときがありましたね。ただ……」ぼくは残る疑問をぶつけた。「それだけでは、元カノの名前は、『サキ』『ミサキ』『サキコ』『サキエ』などの候補から絞ることができません」
夢愛さんは、悪戯っぽい笑い声を上げた。
「可能性の高い、『サキ』『ミサキ』の、どちらともとれる曖昧な発音で言ってやった」
悪魔や。それを知ってて粗塩を擦り込んだんかいな。と思考回路が関西仕様になる。ホームズみたいな演出は、最近みた映画の影響か。
「いまホームズみたいって思ったでしょ。言っとくけどアタシ、デュパン派だから」
量産型のGMに対する、プロトタイプのガンダムみたいなものか。彼女なりのこだわりがあるらしい。彼女のは推理というよりカンだが、鋭いことは間違いない。
「ああ、私のオーギュスト。コナン君が大人になるまで、推しを続けるから」
コナン君は大人にならへんやろ? いや、ごまかされるところだった。話を戻す。
「断るにしても言い方ってものがあるでしょう。せっかくリピーターになってくれたかもしれないのに」
お客さんを彼女の毒牙から守れなかった慙愧の念で、ぼくの口調はついグチっぽくなる。
年頃の男の子のハートは硝子のように繊細だ。
がさつな女子の厚底靴で踏みにじられるのは、見るに堪えない。加えてこの不況の中、レジャー費は真っ先に削られる運命にある。
バイトのぼくでさえ、民宿『はまゆり』の先行きを憂えているというのに。
当事者は、天使のような微笑を浮かべてフナムシをいたぶっていた。
「元カノへの想いを忘れるために、ナンパしようって根性がさもしい」
子どものように、海に投げ出した細い脚をぶらぶらと振る。両方の膝がなぜか赤くなっている。
お転婆な姫はどこかにぶつけたのだろうか。
「男ってホント馬鹿!」
そうでしょうとも。
ミスユニバース、ミスインターナショナル、サッカー・ワールドカップにオリンピック。
美しさでもアスリートとしても世界の頂点に立つ女子に比べ、我ら日本男児は、チビ・出歯・眼鏡と悪条件が三拍子揃っている。
そのうえ国技と自称する相撲では、もう何年も頂点は外国人で占められ、もうひとつの国技、柔道も外人勢の勢いやよし。
容姿、体力に自信がない我ら日本男子が唯一の取り柄だった経済力さえ、今や転落の憂き目に。そんなどん底ニッポン男児が、世界を舞台にブイブイ言わせているなでしこ様に、何を申せましょう。
ああ、まぶしすぎる。我らを家畜人ヤプーとお呼びください、ご主人様。
「だいたいなによ、メアド交換せーへん? ”せーへん”ってなに? 私って関西弁を受け付けない人なの」
「大阪維新を敵に回しましたね」
「タコ焼き以外の上方文化に未練はないから、かまわないわ」夢愛さんの舌鋒がヒートアップする。「なんで奴らは平気で方言をくっちゃべるのかしらね。私が東京へ出たときなんか・・・・・・」
ぼくよりひとつ上の彼女は東京で短大を卒業したあと、就職せずに実家で「家事手伝わない」になったらしい。
「『だらぁ』、っていうこの遠州語尾を恥じて、江戸の方たちとはまともに会話することができなかったものよ。
維新軍は、関東民にコンプレックスを持つべきなのよ。それをなに? 関西方言を恥ずかしげもなく」
「確かに耳障りですが」と、ぼくも関西人を敵に回す発言をしてしまう。
彼女がほい、と飲みかけのペットボトルを差し出す。
「肩貸して」
ぼくの肩に手をかけ、よっこらしょと声を出して立ち上がると、右のサンダルを左手に持ち、右手をぼくの肩に掛けた。
足が地面につくたび、ひゃあ熱い、と声を上げる。
ぼくは日傘を差し掛け、反対の手にペットボトルを持って執事の役を果たす。
右足首がやや内側に曲がり、軽い跛行のある彼女に合わせてゆっくりと歩く。
頭に「超」がつく美少女と評判の夢愛さんだが、手足が細く残念な胸嵩なので襟刳りが広いTシャツだと足下まですとんと見えてしまいそうだ。
「すけべ。いま変なこと考えたでしょ」
彼女に憑依しているデュパンが、ぼくの考えていることをチクッたらしい。体にハンデがある分、直感に長けているのかもしれない。
「ダイビング教えてくれない?」初めてバイトに来たとき、ぶっきらぼうにそう言った彼女に、あそこまで泳げたらね。と五百メートルほど先に見える東の崎を指すと、ふん、と鼻を鳴らしたものだ。
水中で呼吸できるのだから、基本的には泳げなくてもスキューバはできる。でもそこそこの泳力がないと、事故になったときに危険だ。
バイト初日で緊張していたせいか、ぼくは彼女の右足が悪いことに気づいていなかった。
足の不調のせいで体育も休みがちだった彼女は、海辺育ちなのに泳ぎがあまり得意ではなかったらしい。悪いことを言ったと思ったけど、後の祭り。取って付けたように謝るのも変なので、そのままになっている。
以来後ろめたさもあって、彼女の理不尽な要求にも逆らえないでいる。夢愛さんの右手首に光るイルカをモチーフにしたブレスレットが、肩に触れて冷たい。
「いっさい気を遣わない無神経さが、あんたのいいトコよ」
ほめられちゃった。
昔から評判の美少女だったのだろう。
痛々しく足を引きずっていたら、回りの男は気を遣ってみせただろうが、当人には逆に苦痛だったのかもしれない。
そう言えば人魚姫も魔女から足を授かったとき、歩くと痛みが走るという条件付きだったな、と脈絡のないことが頭に浮かぶ。
潮風がなぶっている長い黒髪から、バニラとミントがミックスされたような甘い香りがほのかに漂ってきた。
ぼくは、数日前のことを思い出した。
*
その日の朝方、ぼくは宿泊予定のツアー客を店長の秋月さんと一緒に最寄駅まで迎えに行った。
愛車である4WDのハンドルを握っていたのは秋月さんだ。
週末には台風が来るとの予報だったが、その日は好天だった。お客さんには少しでもいい思い出を作ってもらいたいので、晴れるとほっとする。
海岸沿いの十七号線を走る道からは右に富士、左に太平洋に突きだした龍ヶ崎が遠望できた。
龍の崎と書いて「りょうがさき」と読むこの岬は伊豆半島の西に位置し、関東でもっとも人気の高いダイブスポットのひとつだ。全長でも一キロにみたないちっぽけなこの岬を、古人は龍に見立てたらしい。
グーグルアースのない時代、どうやって全景を把握したのだろう、と思うが富士の峰からでも遠望できるのだそうだ。
左手を丸めてCの字を作ると、岬のイメージになる。
人差し指の先には龍神池があり、『民宿はまゆり』が位置するのは指の付け根になる。湾内と外海という二大スポットに近いため、『はまゆり』、『ホウボウ』、『ウミネコ』、『カモメ荘』といったダイブショップ兼業の民宿が、海岸沿いに軒を連ねている。
湾内は風の影響を受けにくく、台風のさなかでもダイビングが可能だ。
一方反対側の外海は野性味あふれる海中の景観があり、バリエーションに富んだダイブを味わえるのが特徴だ。
親指側は海際まで山が迫り、緑に覆われた斜面には蜜柑などの樹木の間に、保養地として利用されるコンドミニアム風の建物が顔を覗かせる。
東側の岸壁には洞窟なども穿たれており、クルーザーが停泊し、マリンジェットが飛沫を上げるセレブ向けの海になっている。
釣り糸を垂れる人の姿も見受けられるが、ここから見ることができる富士山は、「龍ケ富士」と呼ばれて絶景らしい。
泊りがけでダイブツアーに参加するお客さんは宅急便で機材を送ってくるのだが、自ら持参する人も多い。そのため重い機材の積み下ろしを手伝うのが、ぼくが同乗している理由だ。
秋月さんは身長百八十を超えようかという長身、五分刈りで御子柴さんをひとまわりデカくした海坊主だと言われているが、外見に似合わずふたりの娘に「永遠の夢」という名まえを付けたロマンチストでもある。
「いい天気ねー」
いかつい風貌とミスマッチなおネェ言葉でそう言われると、かなり違和感がある。
このひと、本当にあの綺麗な娘たちのDNA提供者なのかしらん。
「あら、ワタシ両刀使いなのよ」
ぼくの疑問を見越したように言った。
夢愛さんのカンのよさも遺伝なのか? オーギュスト・デュパンの霊が憑いてたのだろうか。
彼は奥さんを亡くしてから、己が欲望を解放することにしたらしい。ぼくの処女は大丈夫か? 力づくで寄り切られたら、抵抗できないかもしれない。
「心配しなくとも大丈夫よ。ワタシ面食いなの」
中肉中背平均顔。何かやらかしても、人相風体の特定が難しいから手配されにくくていいよな、と同級生に羨ましがられるこの容姿が役に立ったようだ。
こう見えて秋月さんの水中写真の腕は一流で、写真集も何冊か出している。彼の写真には写っている以上のものを想像させる奥行きがあり、ぼくはそこが好きだった。
海沿いの道は片側一車線で片方は崖が圧迫するようにそそり立ち、反対側は白い波頭を立てる海になっている。シーズンは渋滞するが朝早いのでまだ流れはスムーズだった。
この一瞬を目に焼き付けておこう、とぼくは思った。
水中写真家になりたいなどとは、口が裂けても言えない。就職活動を始めなければいけない来年までが、ぼくの夢の賞味期限だ。
とーちゃんから慰謝料がっぽりふんだくってるから、 あんたは心配しなくていいのよ。
かーちゃんの言葉に甘えて大学にも行かせてもらったが、さすがに額面通りに受け取らない程度の分別はあった。
「大企業すら倒産する時代だから、公務員にでもなるつもり?」
なら、好きなことやっちゃったモン勝ちじゃない?
確かに夢愛さんの親父さんだ。
ぼくの心を見通したような話を振ってきた。そうは言っても我らひ弱な日本男児、小粒な蟻は群れの中に居てこそナンボである。群れを外れる勇気はなかった。
ぼくたちは車をN駅のロータリーにつけて列車の到着を待った。東京から若いペアが一組と、女性二人が同じ列車で着く予定だった。
「少し遅れているみたいね。悪いけど何か冷たい飲み物を買ってきてくれない?」
硬貨を渡され、ぼくは構内の自販機に向かった。
ふと、ロータリーの脇を見ると、ピンクのミニバイクが留めてある。
――あれ、夢愛さんじゃ?
バイクのわきに駐車している赤いツーシーターの助手席に、夢愛さんらしい女性が掛けていた。青梅ナンバーのスポーツタイプだ。
そう言えば今日は朝から顔を見ていないな。
声を掛けようか迷っていると、どうやら運転席のサングラスの男性と言い争っているように見えた。
男は少し年配のようだが、露出した右肩に藍色の幾何学模様のようなタトゥーが施してある。
「私はあきらめないからね」
顔を伏せて側を通ったときにもれ聞こえてきたその声は、少しやばい感じがした。走って駅構内に入り、スポーツドリンクのボトルを持って出てきた時には、当の車もミニバイクもなかった。
痴話ゲンカにしては少々深刻な空気だった。夢愛さんは彼氏がいるようには見えなかったけど、居てもおかしくはないか。
神経質そうな芸術家風の声音の人で、相当年上のような口調だった。あれで夢愛さんの毒舌に耐えられるのかしらん。それともさしもの夢愛さんも、彼の前では違う顔を見せるのだろうか。
そう思いながら、肩を貸している本人のほうに目をやると、
「なにじろじろ見てるのよ」と怒られてしまった。
言い訳を口にしようとしたとき、あら! と救いの女神が現れた。
夢愛さんのみっつ違いの姉である永遠(とわ)さんが、エプロン姿で食堂から出てきたのだ。結婚して東京に出ていたのだが、一年程前に離婚れて今は民宿の賄いを手伝っている。
ふたりは『はまゆり』の美人姉妹と呼ばれ、彼女ら目当てのリピーターもいる。
「水槽を見てくる」
夢愛さんはそれだけ言うと、ひとりでぷいと歩いていった。永遠さんに対する素っ気ない態度はいつものことで、なぜなのかぼくは理由を知らない。
それでも永遠さんは気を悪くした風もなく、
「仲いいわね」
と笑いながら言った。
永遠さんは髪型をショートにしていて健康的に日に焼けている。ダイバーとしても御子柴さんに代わってインストラクターが勤まるほどの腕前だ。
一見対照的なふたりだが、顔立ちは似ていると評判である。永遠さんのほうが性格が良く、優しくて気立てが良くて料理もうまい、のだが。
「夢愛さんは、ぼくなんか目に入ってませんよ」
舞い上がってしまったぼくは、自分でも何を言ってるのか、と思いつつN駅のロータリーで見た出来事を話す。
「そう」
永遠さんの声が曇る。いけない。よけいな心配をさせてしまったか、と反省した。
ぼくは、夢想する。
ロケーションは真っ白なビーチ。白い砂を透明な波が洗う海岸で、ぼくは永遠さんと向かい合っている。
――よかったら、ぼくと付き合ってもらえませんか。
――私はあなたより年上だし、離婚経験もあるのよ。
――そんなこと構いません。今のあなたが好きなのです。
妄想エンジンが加速しかかったところで、まぁちゃんに声を掛けられて我に返った。
いつからそこにいたのか彼女はきらきらと目を輝かせ、頬を紅潮させて「あの……」と切り出した。
ぼくはまぁちゃんからの頂き物であるかぐわしい文(ふみ)を、愛用のウエストバッグに収めて参ったなあ、と呟いた。
『はまゆり』のお客さんだし、無下にもできないしなあ。
空を見上げるとぼくの心を写したかのように、急に湧き出した黒雲が広がっている。ぽつり、と雨滴を頬に感じ、慌てて機材の取り込みのために走り出した。(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
