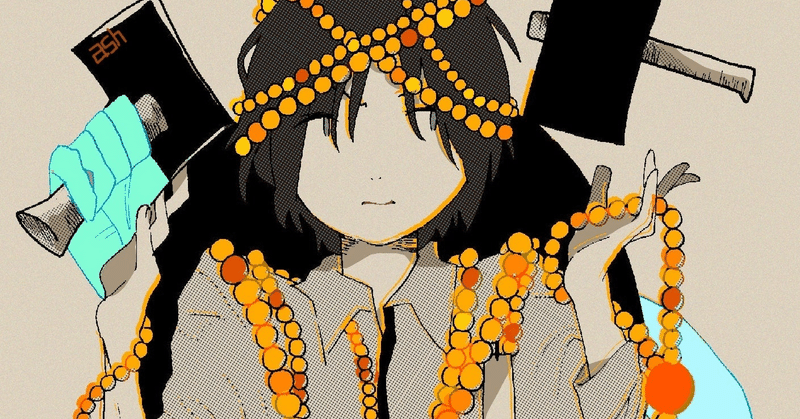
【ファンタジー小説】聖花(2)
2 聖花の谷
むかし天上都市にリーアという娘がいた。
色づく太陽のように美しいとは言えないが、ほのかに白く輝く月のように清楚な娘だった。彼女は早くに両親を亡くし、たった独り小さな畑を守って暮らしていた。
ある年の種蒔祭の日、リーアはひとりの若い旅人と出会った。若者は村人ではなかったが、リーアは彼こそが求める人だと気づいた。
――ぼくは君をしあわせにできないよ。
――構わないわ。あなたと一緒にいることが、私のしあわせなの。
――ぼくは君を養うことができないよ。
――構わないわ。私があなたを養ってあげる。
天上都市の古老たちは反対したが、リーアは若者と添い遂げた。
ふたりは小さな畑を耕し、つつましい収穫を分け合った。貧しくとも、リーアはしあわせだった。
しかし、幸福な日々は長く続かなかった。若者は冬の訪れとともに弱っていき、リーアの手を握りながら静かに息を引き取った。まるでひと夏の命しか赦されていない花のように。
リーアは嘆き悲しみ、その瞳からは止めどなく涙がこぼれ落ちた。ほどなくして、彼女も若者のあとを追うかのように黄泉の国へ旅立った。
次の春、リーアの涙が落ちた場所からひとつの花が咲き、それは紅い花をつけて香りを放った。
天上都市の人々はふたりを悼み、真紅の花を大切に育てた。人々はその花をこう呼んだ。
リーアの涙(ラ・ク・リーア)―― 「ラクリヤ」と。
「ラクールの聖花伝説ですね」
ナスカは、古びた灰色のレリーフに刻まれた印刻文字を追いながら、寄宿舎の時代を思い出していた。幼いころに貴族としての教育を受けた彼は、文字を読むことも筆記することもできる。
ラクール市へ旅立つ少し前、帝都テーベでのことである。
彼の学問の師であり、”王の耳”、”王の目”、を束ねる者でもあるサイラス・オルクウム師は、ゴボゴボと奇妙な音を立てて笑った。
オルクウム師の部屋は、かび臭く日当たりも悪い大学の一角にあり、用途のわからない自動機械の部品や、天球儀、呪術用の装身具、時代を経た羊皮紙、何がはいっているか誰も知らない褐色の薬瓶、いまやその製法が太古の闇に包まれている、プラスチクスなどが無秩序に積み上げられている。
<大忘却>以前の科学士が作り出したといわれるこの素材は、製法が失われたため今や溶かして変形させる以外になく、溶かすたびに不純物が混ざりこんで色褪せるために、純白のプラスチクスは同じ体積の黄金と同等の価値で取引されている。
オルクウムの部屋には、その貴重な混じりけのない白色のプラスチクスが、床の上に無造作に放置されていた。
当のオルクウム本人は、窓際のアルコウブの中にちんまりと収まって皓々と眼球を光らせていた。
ナスカは腰を降ろすことのできる場所を目の端で探しながら、部屋の主のようすを観察した。趺座したままミイラと化したその身体の中には、数本の透明なチューブが差し込まれ、色の付いた液体や透明な気体が送り込まれている。乾いたその表情からはわからないが、声音から判断するとご機嫌はいいらしい。
「見てのとおりだ。そこに刻まれている聖花ラクリヤの起源説話は、現実のラクリヤの姿をよく映している。
すなわち赤い花をつけることや、特異なにおいを持つこと。だが実際ラクリヤを特徴づける独特なにおいは、花芯からではなく、葉の先端から放たれることが、数少ない報告からわかっている。ラクール市の誕生と聖花伝説は、分かちがたく結びついている」そして世間話の気安さで付け加えた。「おまえにはラクール市に行ってもらう」
「ラクール市?」
ナスカはこわれた自動機械の上に座りながら、反芻した。名のみ知るものの全くなじみのないその都市に、よもや自分が赴くことになろうとは思ってもみなかった。
「彼の地に、なにか”王の耳”の興味を引くものがあるとでも?」
「エレドニア山系の中央に位置するラクールは、わずかばかりの貴鉱石、薬草、岩塩などを帝国相手に商うだけの辺地だ。我が帝国が版図の中で飛び島のような彼の自由市の存在を許しているのは、それが征服に値しないからじゃ」
「征服に値しない辺地を探れとは、なにか脅威の芽が生まれつつあるということでしょうか」
「確かにラクールの女市長ルクレツィアは油断がならぬ。ルクレツィアとは、西方魔法士の女系が代々引き継ぐ名だが、当代のルクレツィアは、過去の英名をもっとも濃く受け継いでその名に恥じないと聞く」
ナスカの肩に止まったネヴァ・モアが、会話に割り込んだ。
「邪教に染まって、帝国を放逐された一派だったな」
「おお、黒き賢者。闇よりの使い」
夜の闇に覚醒したネヴァ・モアは、オルクウムがこの世界で一目置く唯一の相手だった。
「そのとおり。ラクール市民の祖は中央での政争に破れ、落ち延びていったルールドの魔法士一派の裔という説がある。言葉も山岳民族よりむしろ帝国に近い。
元はリンボスと呼ばれていたラクールは、長く不毛の地だった。リンボスとは現地の言葉で”黄泉の台地”という程度の意味じゃ。なにより大気がうすく精素が少ないため、ふつうの生物は活きていく事さえ適わない」
ネヴァ・モアが乾いた笑い声を上げた。「不毛の地ラクール!」
オルクウム師のミイラの指にはめられた指輪のルビーから、一条の赤い光が伸びて、部屋の隅にある鉢植えを照らした。そこに植わっているのは、観葉植物としては素っ気ない、幅広の葉を四方に放っているだけの植物。
「その鉢を水槽の中に沈めてみるがよい」
部屋の中央に硝子張りの大きな水槽があり、水が張ってあった。ナスカは命じられるがまま、その植物を鉢ごと水槽に沈めた。すると水の中できらきらと光を反射させながら、無数の気泡が葉の表面から舞い上がった。
「多気孔植物ペディティウム・ドラスクス。帝国領内に生育する植物、半植物のなかでは、もっともラクリヤに近い品種と言われておるものじゃ。
この植物は、月の光を受けると大気の成分のひとつ排素を別の成分である精素に変える力がある。精素は物が燃えるのに必要な元素(エレメント)じゃ。
我々の体も静かに燃えているが故に、この精素を必要とする」
もっとも…… オルクウムの体から伸びるチューブのひとつが、ゴボゴボと音を立てた。どうやら笑ったらしい。「わしのような枯れた体は、ほとんど精素を必要とせんがな」
オルクウムを師と仰ぐナスカですら、その前半生を全く知らない。
半ばミイラと化した体で、いったいどれほどの歳月を生きているのだろう。ミイラと化す以前は、どのような人物だったのだろう。
彼は帝国の勃興期を、ほぼ体験してきているとすら言われていた。
「動物は呼吸とともに精素を吸い、排素を吐き出す。植物は光と排素と水から精素を作り出す。世界はこのようにして循環しておるのだ。
精素は大地と深い縁のある元素で、高さが高くなるにつれ薄くなる性質がある。人が高山に住まうことができないのは、そのためだ。
ラクール市のように、この世界で飛びぬけて高い山の頂にはほとんど精素がないため、人は生きていくことができない。
ラクールに入植した、というよりは流刑に処された魔法士の一団は、奇抜な方法でこの薄い大気の問題を解決し、この地を住処とすることに成功した」
「それがラクリヤ、ですか?」
「そのとおり。聖花―ラクリヤは、光と水と排素からペディティウム・ドラスクスと比べてもはるかに多くの精素を吐き出す。
ラクール市民の祖は、居住不可能な高山にラクリヤを多数栽培することで、この地に入植することを可能とした。
<大忘却>以前の科学士は、思いのままに新しい動物や植物の品種を作ることができたと言う。この植物もまた科学士たちが人為的に作り出したもの、という説があるが」師は再度笑った。「もちろん科学士どもが、己が力を過大に喧伝するために広めたたわごとじゃ」
科学士と魔法士は軍を別にすると帝国を二分する勢力だが、オルクウムはそのどちらにも属さない独自の勢力基盤を持っていた。
「このように、現実的な用途によってラクリヤを広めていったラクール市民たちだが、その後ラクリヤを聖なる花として崇める信仰へと急速に傾斜していった」
「その聖花崇拝がよくない、と?」
「いや聖花崇拝は邪教だが、わざわざ弾圧するほどのものではない」
オルクウムは一端言葉を切った。
「このラクリヤだが、不思議なことにラクール以外の土地では根付くことかなわぬ。その栽培法は累代続くラクールの栽培官のみが伝承し、門外不出の秘事となっている。
聖花ラクリヤを栽培するのは難事じゃ。
しかし”二なき人”は、この花を望んでおられる」
「二なき人が? なぜ、そうまでしてその花を求めるのです?」
「帝国の領地内には、未開拓の山岳部も多い。このラクリヤをもって入植すれば領土が広がる、と進言した魔法士がおる」
苦々しい口調は、皇帝側近に対するオルクウムの心象を写しているかのようだ。枯れた体となっても、世俗から完全に無縁とはなれないらしい。
「その進言に、二なき人も心を動かされたのですか」
「ラクリヤの葉から得られる成分には、魔法士の能力を拡張する作用があるといううわさがある。魔法士がラクリヤを得るよう進言した真の狙いは、存外そこにあるのかもしれん」
「ラクリヤの株を手に入れることは、さほどの難事と思えませんが」
「もちろんそれを手に入れること自体は、難しくない。
ラクールへの道々には、自生のラクリヤも多数生えておる。それらを密かに採取して栽培を試みたが、ひと間月ももたずして全て枯れてしまったそうじゃ。
ラクリヤ栽培を託された皇立の科学士どもは、彼の地から土、水をすべて取り寄せ、同じ環境を作ってみたがそれでも栽培はできなかった。
ここに至って科学士どもは音を上げおった。
この植物はラクールという土地が生み出す精気がなければ育たない、とのこじつけを言う者まで現れる始末」
「そこで、我々の出番ですか?」
「<大忘却>ののちの混沌を最初の二なき人が治め、帝国の礎を築かれたことは知っていよう。
その時代より今日まで、我々”王の守護者”は二なき人の耳目となって働いてきた。理由の如何にかかわらず、我らは命に応じて答えを探さねばならない」
「ラクールの栽培官が秘匿する、聖花の栽培法を探るのですね!」
「そのとおり」オルクウムは声音を変え、動かぬ体の居住まいを正したかのような口調で、「”王の耳”ナスカ・ソーンに命を下す。ラクールへ赴き、ラクリヤ栽培の秘事をつきとめよ。二なき人のために。帝国の礎が永遠ならんことを!」
ナスカはひざまずき、厳粛な面持ちで拝命した。しばらくするとオルクウムの目の光が失せるとともに、ただのミイラに戻った。
ネヴァ・モアの鳴き声が、部屋の中にこだました。
赤い夕陽の残光が鮮血のようにあたりを照らす谷間には、よどんだ香りが満ちていた。
「これが、聖花の谷か!」
かたわらに立つロアは、その禿頭に血の染みをつけているが、大きな怪我ではないらしい。
谷は花崗岩、カンラン岩、黒曜石などから成り、黒い岩肌を割ってラクリヤの葉球が顔をのぞかせていて、まるで無数の緑の頭に取り囲まれたようだ。あたりは瘴気が漂い、ラクリヤの葉陰からちろちろと回りを伺うげっ歯類が、キキッと甲高い鳴声を上げた。
ネヴァ・モアがいずこからか舞い降りると、ナスカの肩に止まった。
ロアがナスカに目で合図を送り、谷の中の一点を指差した。
「リーア?」ナスカは思わず、伝説の娘の名を口にしていた。
赤く染まるうすい霧の中に、ひとりの娘が立っている。そのまわりだけはラクリヤの魔力も及ばないとでもいうかのように、凛冽な空気を身にまとった姿は、伝説の娘を思い起こさせた。
娘は長い漆黒の髪をなびかせ、一心に崖のほうを見上げていた。
その横顔は、交易市で高い値がつく象牙細工のように滑らかに白く、伝説よりも美しいと思わせる。娘が見上げる視線を追ったナスカは、ひとつの人影に気づいた。
崖の中腹に、ステージのように突き出した岩場がある。
まるで帝国の歌劇を見るかのように、舞台の壇上に人影が踊り出た。”王の耳”が見守るうち、人影は岩場の端に達すると途方に暮れたように背後を振り返った。その途端、背後から数人の新たな登場人物が現れ、槍のようなもので最初の人物を激しく突いた。
娘が小さく叫びを上げた!
つかの間抗うような仕草をしたものの、槍で突かれた人物は抵抗できずに崖から落下した。
まるで悪夢のような、一瞬の光景だった。
人影は長い悲鳴を引きずりながら崖を墜落し、鈍い音を立ててラクリヤの谷間に消えた。
その瞬間、ナスカはラクリヤが歓喜する声を聞いたように思った。
「花刑法廷……」
肩に止まったネヴァ・モアが言った。西の方、日が没しつつあり、あたりを急速に闇が席巻している。鳥類の習として闇夜の視力を失う代わりに、ネヴァ・モアの瞳に知性の灯が宿る。
「ラクール市民が、宗教犯・政治犯を処刑するやり方よ。主に聖花に関する罪をさばく場と聞いている」
ネヴァ・モアの声が静寂の谷に響く。
「山の神の名を汚し、約をたがえた愚か者めが!
こちらが落下する寸前、奴の両眼をつぶしてやった。あの商人が無事に下山できることはあるまい」
花の谷は死の谷でもある。ネヴァ・モアは自分たちを突き落とした商人に、きっちりと代償を払わせたらしい。
ナスカの目には、先に見た処刑に対する言い知れぬ嫌悪の情が浮かんでいた。
ふと目を移すと、いつの間にか娘の姿は消えていた。
ラクリヤの香の中で、伝説の少女の幻を見たかのようだ。しかしそれが幻でない証拠に、彼女が立っていた場所に胸飾りが落ちていた。
拾い上げると銀細工の決して安くはない品で、中央の玉に花を簡略化した意匠が刻んである。ナスカは、飾りを自分の首にかけた。
「行こう」
ロアを促して、六つ足のところへと戻る。青白い月あかりの中、荷物を拾い集めてやっと六つ足の背に納めると、疲れ果てたナスカとロアは天幕の支度も早々に眠りについた。
その夜これまで以上に強いラクリヤの香の中で、ナスカは夢と現実のはざまを行き来した。夢の中で彼は崖から突き落とされ、ラクリヤの群生の中に落ちていくのだ。
翌朝、はねあげられた天幕の入り口から差し込むまぶしい陽の光に、ナスカは目をさました。
見知らぬ男が、槍の先で天幕の入り口をはね上げている。天幕は、いつの間にか数人の男たちに囲まれていた。皆長衣をまとい、槍を携えている。臑当て、肘当てを付けてはいるものの、帝国の正規兵と比べるとはるかに貧相な軍装にはちがいない。
ラクールの兵士のようだ。
ひとりの兵士が、やっと起き上がったナスカに向かって槍を突きつけながら何か言ったが、ナスカには聞き取れなかった。
ナスカは両手を上げて天幕から出ると、兵の前に立った。
「怪しい者ではありません。ラクールへは交易のために参りました」
やはり兵士に槍を突きつけられているロアが、ナスカの言った事を山岳民の言葉に直す。
「私はハイラム・ビンガム」周りを囲む兵士の背後から、彼らの長らしき背の低い男が進み出て、きれいな帝国の発音で名乗った。「交易路からははずれているようだが、ここでなにをしているのですか?」
ナスカは手短に、崖を落ちた経緯を説明した。
「ここは他国の者が入ってよい場所ではありません。私たちについて来てもらいましょう」
ハイラムの口調はていねいだが、逆らうすべはないようだった。(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
