
こういう時だからこそ妄想する「理想の経営像」
※2013年4月頃にブログに書いていた連載記事の再掲載のため情報は古く7年経った今は状況がいろいろ変わってるものもありますが、今でもこの理想像は変わってないのと、新型コロナウィルス後の世界をポジティブに考え始めるために、僕が妄想する「理想の経営」について転載します。
僕は経営者でも何でもないけど、経営の理想像みたいなものがある。
抽象的な表現では、従業員が主体性と当事者性を持ち、出来る限りボトムアップで経営されるビジネスユニット。今騒がれているブラック企業のような、会社の利益のために社員をパーツ(消耗品)として扱うことも厭わない会社とは対極的なもの。
1. ポートランドのフードカート

僕がポートランドに行って驚いたことの一つに、フードカートの文化がある。
フードカートとは、車を改造して屋台風にしたもの。
ポートランドでは街中の車の駐車スペースがどんどん屋台村みたいになっていっている。今はもっとあると思うけど、僕がいた頃でポートランド都市圏内に800以上のフードカートがあったらしい。
アメリカ全土を探しても、こんなに街中がフードカートだらけの都市はない。ポートランドの食文化は、アメリカの中では異端と言えるほど豊か。味の世界一周が出来ると言われるほど様多様で質が高い。
ファーストフード店などのチェーン店とフードカートのような無数の零細起業家が競合出来るってのがかなり驚きだった。一軒一軒のフードカートは、いろんな面でマクドナルドには勝てないかもしれない。だけど、それぞれのオーナーは自由に想像力を発揮させ、多様でユニークな料理とサービスを提供出来る。
無数のカートが集まれば、全体としての価値はマクドナルド一辺倒よりずっと高くなるに違いない。つまり、零細起業家の事業の方が、事業主も従業員も、自主性や当事者性を最も発揮出来やすいということ。
そして、無数の零細起業家がアライアンスを組めば、巨人のようなチェーンビジネスよりも、豊かで質の高いモノやサービスが提供可能ということ。
2. バンドマン社長・河野 章宏さん率いる「残響」
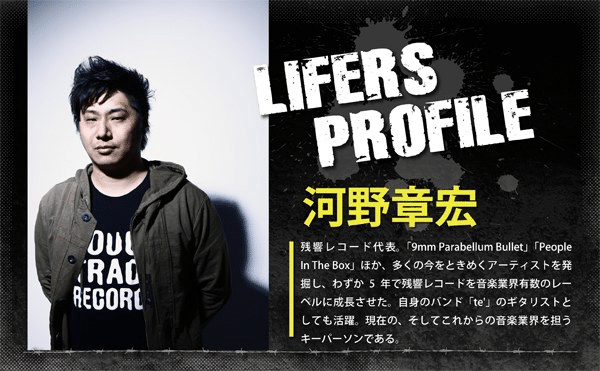
今回は、バンドマン社長・河野 章宏さん率いる「残響」の例。
河野さんは、2004年立ち上げた自主レーベル「残響レコード」を、10万円の資金からのスタートにも関わらず、2010年の決算ではグループ年商5億を売り上げるまでになったそうです。6年ほどでここまで売り上げを伸ばせたのなら、かなり成功していると言えるでしょう。
「右肩上がり」や「前年比」は眼中になし
この残響の経営方針として特徴的なのは、「右肩上がり」や「前年比」が眼中にないということ。どうして「前年比」を超えないといけないんですか?という日経ビジネスオンラインの記事を読んで、「なるほど」と思いました。
普通の会社は、売上など利益面での「前年比超え」を経営目標に置くものですよね。どんな手を使ってもいいなら、前年比を超える手段はいくらでもあると思うんです。社員や関係者に無理をさせたり、悪いことをさせたりすれば…
例えば、河野さんは以下のように例示しています。
アーティストの肉体、精神的な疲弊、現場のスタッフのやる気に目をつぶれば、「数千万円の売上を積み増せ?任せとけよ!」です。いくらでもできます。
具体的には、ライブハウス規模での興行を10本よけいに打てば、それだけで1000万円の売上が立つ。利益も500万円近く出ます。これを何組かの所属アーティストに、やらせればいいだけの話です。
皆さんご存じの「年度末になぜか大量のCDリリース」はその実例です。業界の「決算書」を見栄えよくするための都合で、アーティストが犠牲になっているのです。
でも、こういうように従業員の待遇より、会社の「前年比超え」という方針を重視するなら、いつかはその右肩上がりの結果は破たんすることになるでしょう。「前年比」を目標にしなくても、従業員の待遇を良くし、成長をサポートすることによって、長い目で見て着実に売り上げを伸ばしていけるということは、この残響が結果で示せていると思います。
給料は「自己申告制」
残響が従業員に提供する待遇やサポートでユニークな点が、給料は「自己申告制」ということ。(詳しくは、「前年比」は、経営者にとって魔法の言葉なんです。を参照)
河野さんは言います。
給料を上げたければ、「今年はこれだけのことをやろうと思っていて、これだけ稼ぐのに予算がこれだけ要ります。儲けがこの額になりますから、その中からこれだけ自分の給料をください」というのが基本です。
仕事内容や給料は社員自身が決めるんです。僕から押しつけられるノルマを待っている社員は1人もいません。
一人ひとりがアイデアを振り絞って挑戦し続ければ、業績は自ずと前年を超える。数字の上での「前年比超え」に血道を上げる必要なんて、ありません。
これなら、従業員は、会社に対する帰属意識も高まるし、モチベーションを維持しやすく、更には経営の面でも主体性を持てやすいと思います。
このように、従業員の主体性やモチベーションを高め、成長を促すことによって、おのずと売り上げが伸びていくことを狙う経営方針もあり得ると思います。
それは、この「残響」が証明していると思うし、これからも証明し続けていけるのか、残響の動向を見守っていきたいです。
3-1. 家入一真さんのLivertyのようなケース

今回は家入一真さんのLivertyのようなケースです。
家入さんのことは良く知っているわけではないんですが、彼の展開するLivertyという実験にとても共感しました。
その実験の概要について、Livertyのサイトから引用させていただきます。
こんにちは家入です。この度、僕らは新しい実験をします。 普段は別の仕事を持っているメンバーが集まって、新しいビジネスやウェブサービスを立ち上げまくるモノづくり集団、「Liverty」を立ち上げました。 「もっと自由に働きたい」この思いを持って、フリーランス、経営者、学生、サラリーマン、フリーター、などなど色んな職業の人たちが集まりました。 退社後の時間や土日を使い、僕らは色んなサービスやビジネスを、ものすごいスピードで立ち上げていきます。 そのサービスから産まれた評価や利益は、メンバーで山分けしていく。そこで得たものが、次の働き方、生き方につながる。 独立してもいい。起業してもいい。海外移住してもいい。引きこもってもいい。アーティストになってもいい。 色んな働き方が可能になり、色んな生き方を選択できる。僕らは解放され、自由に生きる事が出来る。 そこで「自由」「解放」を意味する「Liberty」に、「生き方」である「Live」を組み合わせて 「Liverty」という造語を考えました。 僕らもこの働き方を実践しながら、この考え方を広げていく事が出来ればいいなあと思っています。 そう、僕らはもっと身軽でいい。
具体的に立ち上がっているビジネスやサービスの内容は、Livertyのサイトで確認できます。とてもユニークで創造豊かなものが次々と立ち上がっていることが分かります。Livertyが無ければ日の目を見ることが無かったものばかりだと思います。
僕が注目しているのは、そういった無数のマイクロ事業を、「眠っている労働力」を駆使して生み出している点です。
「労働力」といっても、一人1日8時間など、まとまった時間は必ずしも必要ありません。「空いている時間に何かビジネスやサービスを立ち上げたい」と思っている人が複数人いれば成り立つ可能性があります。そういった意味では、正社員化とは全く逆の流れですね。
でも、企業の正社員になることによって台無しになってしまう労働力もたくさんあるはずです。このLivertyは、そういったお零れ的な労働力を総動員して、メンバーのモチベーションとソーシャル・キャピタルを高めることにより、追加で新たな価値を生み出しまくる橋渡し役なんだと思います。もしかしたら、この実験を進めていけば、正社員を多数抱える大企業なんかとは違った面白い価値を生み出せるのではないでしょうか。
まぁ、このケースでは「経営」っていうほどではないのかもしれないけど、こういった「眠っている労働力」の価値に目を向けることは、どの経営者にも必要だと思います。
3−2. 眠っている労働力を生かす(既存企業からのアプローチ)
昨日アップした家入一真さんのLivertyのようなケースの補足です。
「眠っている労働力を生かす」ことについて、既存企業からのアプローチの例を書きたいと思います。
以前、日経ビジネスOnlineでなぜOLは3000円を払って弁当を開発するのかという記事が投稿されました。これは、首都圏にあるコンビニエンスストア「ナチュラルローソン」の、一般のOLにただで弁当の商品開発に参加してもらう取り組み。
さらに、同ウェブサイトのタダで企業に貢献する人たちという記事で、「グランサンク」というレストランの「ママシェフ大募集!」と、ホテル日航アリビラの「読谷を味わう料理レシピコンテスト」というプロジェクトが紹介されていました。このプロジェクトも、一般の人が企業にただでレシピのアイデアを提供し、自らロイヤリティの高い顧客になり、さらに宣伝して人まで呼んで企業に貢献する。
この場合、企業側のメリットは分かりやすい。
・ただでモチベーションの高い労働力が確保できる
・商品開発のコストが浮く
・宣伝のコストが浮く
「そんなにうまい話が本当にあるのか!?」ってにわかに信じられませんよね。でも、中には、以下のような理由で無償で喜んで企業に貢献する人もいるようです。
・有名企業から商品開発への参加の機会が与えられる
・表彰されたり、自分の商品が発売されることによる名誉やステータスの向上
・やりがいがもてる
企業側と消費者側でこういうwin-winな関係が持てるなら、企業側はやらない手はないですよね。企業側がこういった機会を提供するだけで、眠っている労働力を呼び覚ますことが出来ます。逆に、こういった機会がないばかりにせっかくの労働力を台無しにしているのが現状ともいえるのかもしれません。
この記事で紹介してきたのはあくまで既存企業側からのアプローチです。画期的ではあるかもしれないけど、あくまで補助的な活動に過ぎません。
逆に、家入一真さんのLivertyは企業という形ではなく、こういった眠っている労働力を生かすことを本業としている団体なんだと思います。
4-1. 生意気ながら、サトマン氏の経営理論への批評を書きます
先日、平塚の青年会議所が開催したサトマンこと佐藤満氏の講演を聞きに行きました。

勉強不足で佐藤氏のことは良く知らなかったのですが、ホンダカーズタイランドやフォルクスワーゲン、日本ゼネラルモーターズなどで社長を歴任してグローバルに活躍し、「伝説の男」と称される人物なんですね。ビジネスの具体的な事例や先人たちの言葉など、部分的にはとても参考になりました。
ただ、根本的な部分で、ものすごく批判的に講演を聴いていました。いろいろ質問してみたかったんですが、質疑応答の時間がなくて残念でした。
1時間ほどの講演で、佐藤氏も言い足りないことは多々あったと思います。でも、その講演のほぼすべてを「お客を増やす」「売り上げ・利益を増やす」といったことに費やすのは如何なのでしょうか?あたかも、それらが「企業経営の目的」になってしまっているような講演でした。
企業の存続と拡大のために「お客や利益を増やす」というのは、かなり低次元の目的感だと思うんです。僕は、会社を経営した経験もないし、隠し立てする気もなく「負け組」の人間です。普通の人は僕の話より佐藤氏の話を聞くでしょう。それをどうにかする気は僕にはありませんので、ただ自分の感じたことを率直に書いてみようと思いました。
早速、率直に言ってみると、佐藤氏の経営理論は化石のように古く感じました。もちろん、新しければ良いという訳では無いんですが、今の時代、「利益追求」でゴリ押しする経営理論は通用しないと感じます。
それは、ここ近年のMBA(経営管理大学院)の動向に現れています。僕が行っていたポートランド州立大学(PSU)のMBAプログラムは、2009年のことですが、ノースウェストでナンバー1、世界で25位に選ばれました。(2009-2010 edition of Beyond Grey Pinstripes magazineで)
http://www.pdx.edu/news/portland-state-s-mba-program-named-1-in-the-northwest-25th-in-the-world
このプログラムが評価された背景に、social(社会の), environmental(環境の) and ethical(倫理の) issues(関連事)をいち早くMBAプログラムに取り入れた点だったそうです。恐らく、マイクロクレジットでビジネスとしても成功したグラミン銀行なんかのことも、立派なビジネスのあり方として教えているのでしょう。
PSUに在籍していた時、ビジネス専攻の学生たちと一緒に学んだクラスがありました。そのクラスは、近隣のことを、通りや公園、ビジネスや住宅の特徴などを多角的に学ぶクラスでした。ビジネス専攻の学生にとっては選択科目なんですが、「近隣に配慮する」というごく当たり前のことを、学生にしっかり意識させようという意思を感じました。
従来の(日本では現在も!?)MBAプログラムでは、こういった分野をすっとばして、とにかく「利益を上げる」ことに主眼を置いていると思います。ちょうど、佐藤氏の講演内容のように…
もし「売り上げを伸ばす」「お客を増やす」ことが目的になると、例えばこういうことが起こりえます。統合失調症(7)活力を奪うだけの治療でも書いた通り、世界の精神科病床の2割を日本が抱えるという現状があります。日本の精神医療は、精神障がい者が増え、回復しないことによってお客が増え、利益が伸びているという見方も出来ます。
もし、利益を伸ばす為にお客をもっと増やしたいなら、回復しないような治療を施し、精神障がいを抱えやすい社会構造をそのまま放置すればいいだけです。恐らく、こういったことは、様々な場面で様々な形で今この瞬間にも起こっていると思います。
また、佐藤氏は、自動車関連会社で世界を股にかけて実績を上げていますが、必ずしも自動車を売りまくることが人や社会、環境に良い影響を与えるとは限りません。当然、自動車が増えれば、そこに生活する人にとって危険が増えます。また、エコ仕様の車が増えたとはいえ、環境にも具体的に悪影響を与えます。そして何より、自動車が存続することによって、街は広がったままにならざるを得ないのです。
都市計画のモデルは「歩いて暮らせる」がキーワードですが、自動車を売りまくるということは、都市計画の目的との間に具体的に摩擦を起こします。もっと言ってしまえば、社会や環境に責任を度外視している限り、いくら利益を上げても企業の持続可能性は保証されません。自分の企業だけ一人勝ちしても、社会や環境が不安定になれば、結局は存続さえも危うくなるからです。
企業経営をする上で、「利益を伸ばす」ということは言うまでもなく重要ですが、こういった環境や社会への「使命や責任」は同じくらい重要だと思うんです。売りまくればいいという訳ではなく、「必要な人に適量を売る」ということがその使命であり責任であるはずです。
多くの企業のマーケティングが「必要でもない人にいかに売るか?」になってしまっている感がありますが、これは本来の企業の使命からは外れてしまっているのではないでしょうか?その前提で、商品やサービスを苦心しながら捻り出すというのが企業の本来の姿であるはずです。
一私企業でありながらノーベル平和賞受賞経験もあるバングラデシュのグラミン銀行は、社会貢献事業自体をビジネスとしてほぼ完璧に成り立たせたモデル的な企業だと思います。(グラミン銀行については別記事で詳しく書く予定です)
当然、佐藤氏がそういう部分まで考慮していない訳はないと思いますが、彼の講演の中でそういう部分にほとんど触れなかったのが僕にとって驚きでした。
講演の中で、僕が佐藤氏に質問したかった内容は以下のようなものです。
* 企業の社会的責任についてどう考えるか?
* 佐藤氏のこれまでの経歴の中で、具体的にどのように社会的使命と責任を果たしてきたと考えているか?
* 企業経営の根本的な使命と目的をどう考えるか?
何の実績も残せていない僕がこんな批評を出来る立場ではないんですが、僕自身がもっと理解を深めたいという想いから批評させて頂きました。
いろいろご意見を頂けると助かります。
4-2. 「社会貢献」をビジネスにする
前回の「理想の経営(4)生意気ながら、サトマン氏の経営理論への批評を書きます」の続きです。
前回の記事で、サトマン氏の「お客を増やす」「収益を増やす」ということが大部分を占めていた講演内容について、生意気ながら批評をさせて頂きました。その上であまりにも忘れ去られていた点が「社会貢献」という視点だということも指摘させて頂きました。
そこで、企業の活動で収益を上げながらどこまで社会貢献が出来るかを「グラミン銀行」の例で見て行きたいと思います。

グラミン銀行は、マイクロ・クレジットという手法で、微小なローンを貧しい人(特に女性)に貸すことにより、国内の貧困削減に貢献してきた。
ビジネスのターゲットは、従来の銀行からは相手にもされなかった貧しい人たち。微小なローンを元手にそれぞれで極小の起業を促し、あらゆる点から支援し、ビジネスを成功させることによって高い返済率を維持している。そして、結果的に企業としての収益が上がり、経営的な面でもビジネスが成り立っている。
こういった取り組みが評価され、創設者のムハマド・ユヌスさんとグラミン銀行が2006年にノーベル平和賞が授与された。
以下は、Web GOETHEの滝川クリステルさんとグラミン銀行総裁のムハマド・ユヌスさんの対談で紹介されていたグラミン銀行の取り組みについての紹介文。
慈善事業ではない、真の貧困からの脱却を目指したもの。特筆すべきは現在、800万人の顧客を有し、その97%は女性で、彼女たちが銀行の株主でもあるこ と。また、融資を受けた人々の子供たちの識字率はなんと99%に及ぶ。弱い立場にある女性の自立と生活向上を可能にしたシステムの根底にあるもの、それは “信頼関係に基づいた、徹底した決意の共有”だ。グラミン銀行から融資を受けるためには5人組を作り、メンバーはお金を借りる前にグラミン銀行の規則や考 え方を学ぶ。その後も、グループリーダーが活動報告や行員との交流を定期的に行う。この共同体としての原動力が、システム成功の重要なカギといえる。
一人一人の立ち上げるビジネスは小さいかもしれないけど、今や、バングラデシュでは、考えられないほど多様な職種が存在し、バングラデシュの社会を支えてる。道端でただ物乞いをすることしか出来なかった人々が、バングラデシュ社会の再建の役割をしっかり担っている。
ここで重要になってくるのは、グラミン銀行は慈善団体ではなく、あくまでビジネスを行っているという点。それも、とても儲かっている。
最近は、BOP(bottom of the pyramid)ビジネスなんて言葉が出回っていて、「ビジネスターゲットとしての最貧困層」という可能性が考えられるけど、こういった見方は以前はほとんど存在しなかった。
例えば、現存する多くの銀行は、未だにターゲットのスコープが、所得や住居などの「ある一定の信用のある層」に限られている。つまり、ビジネス的に「堅い」ところしか相手にしないということ。そういった従来型の企業の傾向性から、行政では手が届かず、企業からは相手にされずに手付かずの領域が、社会の中で拡大していってしまった。NPO(非営利団体)はそのギャップの中に埋もれたニーズに対応するために生まれたが、「非営利」という縛りが存続を難しくさせている面があった。
そこで注目され始めたのが、グラミン銀行のような社会起業家たち。
社会起業家も、一般企業と同じ土俵に立ち、同様の競争原理にさらされる。一般企業との違いは、手付かずの社会的なニーズを満たすことで収益を上げようとする点。その上でいくらでも利益を追求出来る。
本来の企業の存在意義は、まさにこの「社会的企業」の姿のはず。なのにこういった新たな言葉が生まれる背景には、現存する多くの企業の正しい使命感の喪失があるのだと思う。
以前紹介したサトマン氏の講演でも痛いほどそれを感じた。彼の講演内容からは、「手付かずの社会的ニーズを充たす」という部分の強調があまりにも貧弱過ぎた。現行の多くの企業の「CSR(企業の社会的責任)」も、取って付けただけのおまけ的なものでしかない。
グラミン銀行は、最貧困層をターゲットにして誰の眼中にもなかった社会的ニーズを充たし、ビジネスを成功させた。そして、「BOPビジネス」という概念が広まり始めた昨今、いよいよ、社会的起業の可能性や意義が高まってきている。
そういった中で、尚も、「社会貢献」の意識が薄くただ利益を追求するだけの企業は淘汰されていくべきだし、何より、僕たち消費者が賢くなり、企業を選ぶ目を養わなければいけないと思う。
5−1. 「自分主導」より「メンバー主導」で、「思い通り」以上の「想定外の成果」を狙う

経営に携わったことのない筆者が語る、あんまり説得力のない「理想の経営」シリーズ。
突然ですが、みなさんは経営者などリーダーに欠かせない資質とは何だと思いますか?
「リーダーシップ力」
「カリスマ性」
「決断力がある」
「顔が広い」
「先見性」
…
いろいろあると思います。
個人的には、ある資質があれば、ここに挙げたものはすべて必要ない(人並みでいいという意味)と思ってます。
それは、「メンバーの可能性を拓く能力」です。
それさえ出来れば、リーダーは無能でもだらしなくても、意外と組織はうまく回ったりするんじゃないかと思います。むしろ、リーダーが万能でないほうが、メンバーは力を発揮やすいかもしれません。
関連するトピックに「ファシリテーション」と「フォロワーシップ」というものがあります。この2つに共通するのは、「自分主導」ではなく「メンバー主導」だということ。
経営者が「自分主導」で経営を行う場合、想定するのは自分の「思い通り」の結果なんだと思います。でも、果たして「思い通り」というのはベストな結果でしょうか?
一ついえることは、この場合の「思い通り」は、たかがリーダー個人の想像力の範囲内のベストのことですよね。それに対して「メンバー主導」というのは、リスクがある反面、想定外の成果が得られる場合もあります。つまり、リーダーの「思い通り」以上の結果になる可能性が期待できるということです。
経営者がこの点をどう考えるかで、組織は大きく変わってくると思います。
次の記事では、この2つについて詳しく書いていきたいと思います。
5−2. ファシリテーション・フォロワーシップによる経営革新
経営に携わったことのない筆者が語る、あんまり説得力のない「理想の経営」シリーズ。今回で最終回になる予定です。
前回の記事では、経営者などリーダーに最も必要な資質は「メンバーの可能性を拓く能力」だと書きました。関連するトピックに「ファシリテーション」と「フォロワーシップ」というものがあります。
この2つに共通するのは、「自分主導」ではなく「メンバー主導」だということ。「メンバー主導」で、「思い通り」以上の「想定外の成果」を狙うということです。
自分の思い通りに事が進まないのは脅威でもありますが、同時に「思い通り」以上の結果をもたらすこともあります。なので、あえて「自分主導」を捨て、「メンバー主導」に切り替え、「メンバーの可能性を拓く」のに専念することで、想定外の良い結果を狙う経営者がいてもおかしくありません。
ファシリテーション
近年、「ファシリテーター」という立場の人が増えてきているように感じます。議論の場において、ファシリテーターは、議長のように特別な権限を持っている訳でなく、会議への参加者それぞれのいいところを引き出し、交流を促進することによって、本人が予想もしなかったような成果を導こうとする人。
ファシリテーター自身に、突出したリーダーシップ力やアイデア力が求められる訳ではありません。むしろ、おっちょこちょいで未成熟な「普通の人」がいいらしいです。
つまり、ファシリテーターは、初めから、議論の主導権を握ろうとも、思い通りにことを進めようとも思ってません。とにかく、会議への参加者それぞれの一番いいところを引き出し、議論を深めるために、あらゆる手を尽くす人。
こういったファシリテーションの手法を企業経営などに応用させたら面白いのではないかと思います。
フォロワーシップ
「フォロワーシップ」とは、自分がグイグイと引っ張っていくのではなく、部下(選手たち)に自ら考えさせ、意見させ、行動させて組織を活性化していくマネジメント手法。
このフォロワーシップの実践家として有名なのは、サッカー岡田武史氏とラグビー中竹竜二氏です。
岡田さんは、2010年W杯でベスト16という成績を残した日本人監督しては名将中の名将。中竹さんも、早稲田大学ラグビー部を2年連続で優勝に導いている凄腕監督です。
この二人に共通しているのは、選手たちに自ら考え行動させる余地を与えることに主眼を置いていること。それをするのに、カリスマ性やほとばしるオーラなどはむしろ邪魔になる。選手たちの可能性を出来る限り拓くために、自身の「未成熟さ」さえも利用する。精神的支柱であるべき監督が「監督に期待するな」と選手に言い放つ。
Presidentのサイトに掲載された「日本一」早稲田ラグビーは フォロワーシップの勝利であるという記事を読んですごいと思ったのが、中竹監督は、チームのキャプテンにさえも未成熟さや理不尽さを利用させるそう。
キャプテンは自ら「チョ~他力本願」という姿勢で、初めから仲間たちに依存しまくる前提でいる。そんなリーダーシップ力のないキャプテンを尻目に、メンバーは一人立ちするようになる。現に、本当の意味でリーダーシップを取っているのは、キャプテン以外の選手たちだそうです。
リーダーシップを取るべき人は、普通であればキャプテンの一人だけのはずですよね。でも、中竹監督のチームでは、実質的にリーダーシップを取っているのはキャプテン以外のメンバー数人なんです。しかも、監督もリーダーシップを取る気がない。笑
「フォロワーシップ」と呼ばれるこの型破りなチーム運営は、確かに早稲田大学ラグビー部を2年連続優勝に導きました。もちろん、強力なリーダーシップ力を持ったトップがワンマンで残した実績の方が圧倒的に多いはずです。ただ、このフォロワーシップに対して何よりも希望を感じさせるのが、仕掛け人である監督や経営者が特別な能力を持っている必要がないということ。
このフォロワーシップの哲学を身につければ、カリスマ性やオーラがない僕にもあなたにもきっと出来る!
こうやってあらゆるグループや組織の経営方法が変わっていけば、生産性も飛躍的に向上すると思うし、何より、想像もしなかった新たなイノベーションが各地で次々と生み出されるようになるんじゃないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
