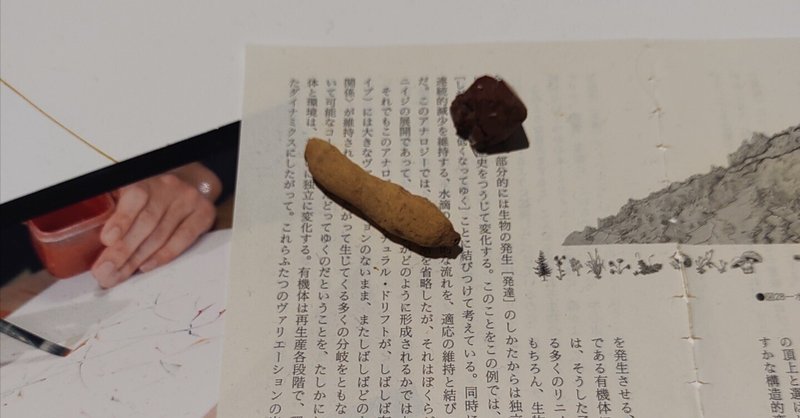
展示『記憶 リメンブラス』からの脱線的メモの束
⬜ 村山悟郎の作品について
「熟練した棋士は、ある戦況を「形」として、二次元的な直感で把握するという。」
「一枚一枚を単一のアルゴリズムで生成するAIとは違い、制作プロセスには創発と段階的なパターンの発展が刻まれ、絵から自然言語へと発達するような道筋が現れている。」
Takuro Someya Contemporary で開催中の村山悟郎の個展『データのバロック』のステートメントにあるこの2つの句は少し離れて配置されており、直接強引に関連付けようとはしていないのがエレガントだと思った。
AI で何かやるなら、AI にどんな教育を施してやるか、または、学習成果を記録して、何か気になる変化をもたらした時に、遡って何を学習させたのが原因でその変化がもたらされたのか、この2つが気になる。何故なら、特徴を抽出し応用可能にする「畳み込み層」及び「プーリング層」でどのようなことが行われているのか、既に人間の認識のレベルではわからない複雑さを持っているからだ。ここで何がどのように行われているのかを人間に説明するような操作が可能であれば、それは興味深い。
しかし『データのバロック』は、サングラスをかけた甥っ子に風船ガムで風船を作る方法を教育する過程を作品化した、マイケル・ポランニーの暗黙知的なものと要素還元主義的なものとの狭間を扱った、あの展示を思い出させる。
AI は、うっかりペトリ皿に青カビを落とすことが出来るだろうか? その行為が故障と呼ばれてもいい。
あとは、何を学習させたら村山悟郎本人のペイントに並ぶか勝るかの絵画を作れるのか? インプットの段階からエフェクトをかけて、認識や理解といった段階にもエフェクトをかけて、詰まり、アウトプットの段階にだけエフェクトがかかるのではなく? 疲労のし方にもエフェクトをかけるのか? 身体が必要なら、ロボットの体長はどれ位が適当なのだろうか? 分岐して、2つが発展して作られて行くので、製作過程で、絵画と作者の間では、カインとアベルのような物語も含まれるはずでは?と推察するが、つまり、禁断の果実を食べた後の、生まれたり死んだりもする、嫉妬も怒りも喜びも悲しみも、驚きか?驚きこそは感動の最上級であると誰かが言った、ゲーテか小林秀雄か? そういうことや、邑田仁の日本テンナンショウについての研究記録などを学習させてみたら、どーなるか?気になる。邑田さんの本は欲しいけど、高額。。因みに、テンナンショウは性転換する植物だそうです。
他にも、村山悟郎本人が未だ読んでいない文献を学習させたAI と、その本を読んでない村山悟郎の作品を比較し、その後その本を読んだ村山悟郎の作品と列べて比較してみたい。まあ、こういうリクエストは宮廷画家に注文を出す貴族気取りか?と嫌がられるだろうけど、否、既にそういった類いの記録がこの展示にも現れているのかもしれない?
因みに、カインとアベルの物語は、出来の良い弟と出来の悪い兄という物語ではなく、神がエコヒイキした物語でもなく、アダムとイヴが禁断の果実を食べた故に、既にカインとアベルも人間になっていた、という所にこそ注目したい。また、カインは神に怒りをぶつけることが出来ず、アベルを殺すに至った?旨なども丁寧に精神分析的に整理してみたい。
つまり、絵画の或る一手が或る一手に、もしくは、隣の一手に嫉妬したり、怒ったり、暴力を振るったりするのか?ロボット三原則なども想起させられる、演劇的なプロセスによって描いたら、村山悟郎本人が描くときに意識的にはそのようなやり取りを認識していなかったとしても、無自覚的には、このような演劇的なやり取りが成されているという可能性もあるのか?急がば回れではないが、寄り道のような、取って付けたノイズのように思われることが、もしかしたら?
⬜ そうだ、東京都写真美術館での展示では、機械へ出された指示自体を想像出来るような、詰まり、村山悟郎の筆の動きを抽象化/単純化した? 絵を描かない私にでも想像出来るような、ある点から別の点へと向かう非可逆的なエネルギーの動きを確認出来るような線があり、否、これじゃそもそもの「線」概念の定義と変わらないか、しかしこれは、筆の軌道が面的であるのに対して限りなく線的な軌道であり、絵を描かない私からすると興味深く、絵描きってのは変なことしてんだなぁ、と簡略化され過ぎた情報を見ながら、少し何かがわかった気になり、小さく満足していた。
そして、機械学習についての話題の度に、「教育して叱ってくれ」という椎名林檎の歌詞を思い出している。
⬜ 同、東京都写真美術館での展示には、小田原のどか氏作品もあり、
_________________________________
1. この文章を会場で手に取ったあなたは、この紙を持ち帰ることができます。その手ざわりを確かめ、折りたたむことができます。誰かに手渡すことができます。
_________________________________
↑ これは、会場に設置された小田原のどか氏の文章です。私は美術展会場で長文を読めない性格で、しかしこの2行(実際の文章でここまでが2行)を読んで、「何か許可を与えるというのは、同時に、それを許さない力を持つと宣言しているようなものだ」旨の小泉義之の句を思い出した。
公民権運動や女性参政権を思い浮かべて想像すれば、明らかなことです。この作品も、これから脱線に脱線を繰り返して遠く逸れたようにも思えるこのメモと、何処かで深く繋がっているいるような気もしていて、だから、今回は遠慮なく脱線します、そんな気分なのです。
普段の生活でも「許可」には敏感だったのですが、小泉義之の言葉によって、許可に対して警戒していたことの意味を知りました。人権についての言及も多い小田原氏のこの作品は、このような権力について考察しているものだと解釈しました。
私は、会場に設置された文章を手に取り、折りたたむことはできなくて、丸めて筒状にして、一緒にいた友人も筒にしていたので、数十年振りに、この筒でチャンバラをすることになった、ちょっと楽しい。その後は、筒をリュックに刺して持ち帰った。
⬜ 本当に自由であるというのは、相手が指し示した選択肢を選ぶ自由もあるはずだと精神科医の神田橋條治が言っていた。詰まり、折りたたむという選択肢を選ぶことも出来るような状態が自由なのだ、と。
精神的に追い詰められた相手が最悪の選択肢を考慮に入れて悩んでいる場合でも、こーしたらあーなっちゃうよ?またあーなってもいいの?というのは、脅しているのだ、と。こーすると取り返しがつかないことになるよ?というのは忠告するのも有効かもしれないけど、アドバイスという体裁すら取らず、可能であれば、選択肢は3つ以上用意して、どれを選んでもどれも選ばなくても大丈夫という風に、選択肢をテーブルの上に列べるような提案のしかたが良い、と。しかし3つ以上というのは難しいね。
既に直接的には関係の無い話題ですが、精神医学に例えるなら、なるべく早い社会復帰と再発防止を天秤にかけている状態があったとします、2つの選択肢ですね。これに対して、同じような性質の選択肢を増やしてもダメなわけです。まず、この2つの選択肢は、根本的な治療というよりは、症状を消したり抑えたりする対症療法ですよね。例えば、大/小のような二択(二項対立)に対して「中」のような項目を増やしても、脱構築 (根本的な治療) には繋がらないでしょう。因みに、対症療法は必要です、しかしそれが対症療法であることを忘れてはいけないということです。
⬜ 精神科医の中井久夫は言いました、精神の病というのは、他の病と違って、元通りにすることが治療なのではない、と。元通りというのは、またいつでも病める危うい状態に戻るだけだ、見栄えは悪くても、その人のなりに合った生き方ができるよに (実際の言葉とはニュアンスが少し違うかもしれません。)、と。
しかし、どーすればいいのか?
もう、ここから更に完全に脱線します。精神分析は説得でしかない、と言った人がいるようですが、余りに重篤な患者に対して精神分析が有効だとは考えられない、想像できない。それでも藤山直樹の『精神分析という営み』は、ここまで切ないほどにやるならあるいは、と思わせる記述だ。この書を「ほとんどフロイトを超えている」と土居健郎 (どい・たけお) が評したのは、フロイト自身が自分の研究と密接な関係があることを認識しながら、キルケゴール及びニーチェの文献を読むこと意図的に避けていたことをユングが批判していたが、藤山直樹はそういったエッセンスも踏まえているからなのか? 例えば、患者に対して「嫌な感じがするな、不遜な態度というか、人を見下している?」といった印象を抱いたとすれば、それは、目の前の患者の中に過去の自分を見ている、誰かに対して嫌な感じだった、不遜だった、人を見下していた、自分を見ているのだ、逆転移が起こっているのだ、と。どんなに語りかけてもまったく反応がない、しかしちゃんと通って来る、、、突然、否、着々と? 中断された治療たったが、何年もして手紙が届き、先生の言った通りでした、などと書いてあった、それに対して?どう思ったかの告白などなど切ない、凄い。。
とはいえ、日本では、精神分析は余り一般的では無いようですし、高額な費用がかかって、多くの人にとって、余り現実的なアプローチではないかもしれない?
⬜ 治療的トラウマを処方した、ミルトン・エリクソンという人もいたが、その技を習得できる人が地球上に何人いるのか、とても限られたアプローチだ。しかし、何らかの属性や集団に対してのアプローチとしては有効かもしれないので、また、別の折に注目したい。
⬜ もしかしたら、オープンダイアローグなどは、ミルトン・エリクソン的なエッセンスを現実的に実施するのに適当なアプローチなのかもしれない、この2つには、似た要素が幾つかかある。
⬜ さて、これも中々身につけるのは難しい、というよりは、今も技術を開発/研磨し続けているのが「生活臨床」というアプローチです。
「生活臨床」を実践する伊勢田尭 (いせだ・たかし) さんは、現在、『生活臨床の家族史療法~数世代の家族史の文脈からもたらされた人生の行き詰まり解消を目指す「作戦会議」』という著書を執筆中で、楽しみです。
伊勢田さんは、治療の研磨と開発、患者さんの行き詰まりを解消することを目指すのに集中しているから、そのことが、医者とその他の看護師など様々な医療関係者や患者自身や患者の家族の間に生まれがちな、弊害にしか成らないヒエラルキーを解体している。
患者と一緒にいる時間が一番長いのは、患者の家族や看護師なわけで、スローガンだけではなく、重要な情報を持っている方々から本当に話を聞くには、その為の態度がなければならないはずで、それが治療の態度でもあるのだろう。
勿論、弊害にしか成らないヒエラルキーを解体することと、責任の放棄とは、まったく別のことだ。そんな批判があったなら、見当違いも甚だしい。しかしだからこそ、弊害にしか成らないヒエラルキーを解体するのも、大変なことだ。
さて、看護師道というか、生きざまで看護するような凄い方もいて、その方は、新人研修のためにオリジナルで、新人は3分間五点拘束されて放置される体験を考案して実施していたそうだ、素晴らしい。
例えば、緊急入院した患者の場合は、最初に、医者は、「ここは病院です、私は医者です」と説明することが大切であり、これをやらないと、後で患者は、白服の怪しい組織に監禁されている?などの想像力に支配され恐い思いをするケースが少なくないそうだ。
だから、看護する側が看護される側のことを想像するのは、とても大切なのだ。
次々に脱線が脱線を呼び、モノローグは展示鑑賞から遠いところに、最近の、普段の興味関心領域に戻ってきてしまいましたが、「生活臨床」ナイス!という報告でした。
⬜ ↓ 生活臨床についての糸川昌成さん(統合失調症多発家系に対するビタミンB6大量摂取療法を発見した神経科医かつ精神科医であるひと)による紹介文がナイス!!なので、URL を貼ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
