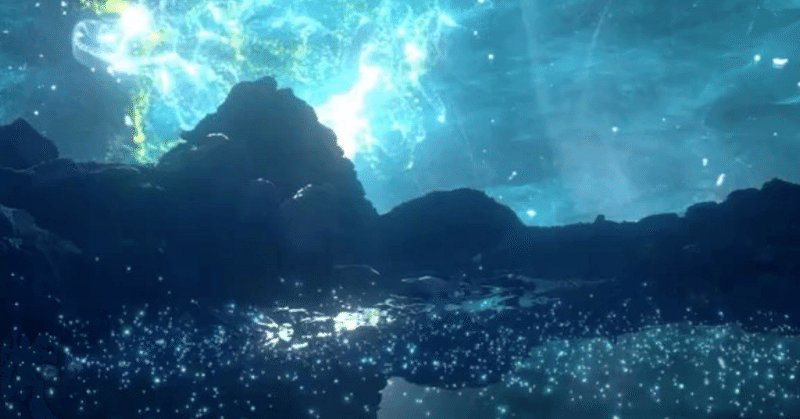
〔178〕石原莞爾が知りたかった明石元二郎の戦争観とは「國體意思」のこと
〔178〕石原莞爾が知りたかった明石元二郎の戦争観
「周蔵手記」昭和十二年七月条をよく読めば石原莞爾の真意が判ってきますから、その部分を再掲します。
甘粕に誘われて君と会ったあの時、明石閣下の話を君から聞いていれば良かった、と今は思っている。明石閣下の策士たる姿勢を君ほどに話す人を他に知らない。故に明石閣下の真実を聞いて、今参考になっている。
△「戦争は長引かしてはいかん」と君に大弁舌をされたという、あの内容を聞いていれば自分は松岡を逃さなかった、と言わる。
周蔵が石原莞爾に初めて会ったのは昭和五(1930)年です。大杉事件の下獄から恩赦され、陸軍の計らいでフランスに留学した甘粕を訪ねて、周蔵は昭和三(1928)年一月に渡仏します。
表向きは絵画修行で滞仏中の佐伯祐三の陣中見舞いですが、実際は上原勇作元帥の命令で、ハプスブルク家が上原に与えた金塊を日本に運ぶ秘密工作のためです。
工作が成功して帰朝した周蔵は、フランスに滞在を続けていた甘粕が昭和五(1930)年、甘粕が満洲に移ったことを聞き、甘粕に会うため二か月の予定で満洲に渡ります。
今後の甘粕が建国工作のために、膨大な資金を必要とすることを察する周蔵は預金をすべて下ろし、金塊輸送成功の褒美として上原がくれた金塊の一部も加えて満洲へ携行します。
張作霖爆死の直後で満洲にいた日本軍人は動揺していましたが、甘粕正彦は平然としていて石原なる軍人と秘かに策を練っているようでした。
甘粕に招かれた支那料理の席で周蔵は石原莞爾を紹介されますが、石原が私服姿のため階級が判りません。実は昭和三(1928)年八月に陸軍中佐に進級した石原は、満洲に渡って関東軍作戦主任参謀に就いていたのです。
石原莞爾と甘粕正彦に同席して両名の話を聞いていた周蔵は、「その遠大なる構想は驚くばかりである。30年計画の日本を描いていて、正に着実にそれに向けているのであるから、この両名の思想には驚く。やはり張作霖をやったことは誤りのようである」と、「周蔵手記」に記しています。
張作霖の死により、対抗的存在であった蒋介石が大きく浮上する、という「誤り」が生じた、と「周蔵手記〕は記していますが、これは石原・甘粕両名の対話を聴いていた周蔵の見解です。
続けて「角力でも東西の横綱があってうまくいく。蒋介石だけになり、それしか人物おらずでは敵の思う壺となる、ということか」との感想を、周蔵が述べています。
WWⅠ後、北洋軍閥の北京政権、蒋介石の国民党政権、張作霖の奉天政権に三分されていた支那世界は、ソ連共産主義の浸透と蒋介石の北伐進行により様相が変化してきました。
「安直戦争」と「奉直戦争」の両度の内戦の結果、生き残った張作霖と蒋介石が周蔵のいうように東西両横綱の並立を成していた、とみても誤りではありません。
両横綱の勢力均衡は日本にとってやり易い状況だったのですが、張作霖がつぶれて蒋介石一人だけとなっては、日本と支那の協同を破壊せんとする敵(西側すなわちトロツキスト)の思う壺となる、とみた周蔵の見識には驚かされます。
周蔵が危惧した通り、「敵」は蒋介石を篭絡して日本に立ち向かわせる作戦に出たのです。石原莞爾の念願した日支共同の計が成らぬうちに、東条らによる蒙古作戦が始まり、これに反対した石原が結局下野することになりますが、ここで最も不思議なのは甘粕正彦のその後の動きです。
結局、二股を張っていた甘粕の動きについては後で述べることとし、その前に石原莞爾と甘粕正彦の関係について観ていくこととします。
ここから先は
¥ 500
いただいたサポートはクリエイター活動の励みになります。
