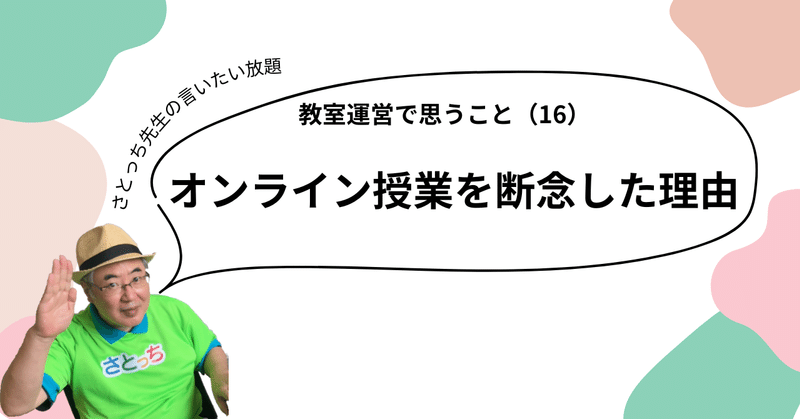
教室運営で思うこと(16)オンライン授業を断念した理由
私が経営する教室ではオンライン授業を導入していません。COVID-19の影響で一時的に授業を中断せざるを得ない時期がありました。感染予防対策とオンライン授業の可能性を模索するために、生徒に声をかけてオンライン授業の実験を行いましたが、その後取りやめることにしました。ここでは、その判断の理由について述べたいと思います。
※この記事では教室運営について思うところを書いています。
オンライン授業への挑戦と限界
私の実験に協力してくれた生徒たちの環境は、授業映像の表示とプログラミングを1台のデバイスで行うパターンと、プログラミング用のパソコンと授業映像を表示するための別のデバイス(タブレットまたはスマートフォン)を用意するパターンの2つでした。当時、小学校でもオンライン授業の導入が検討され、その準備として生徒たちにZoomの使い方を教えていました。そのため、私の実験でもZoomを利用しました。数回のオンライン授業の試みの後、オンライン授業を断念することにしました。その理由は以下の通りです。
適切な教材の不足:
オンライン授業を実施するためには、適切なカリキュラムと教材が必要です。例えば、ロボット組み立てのような実習では、生徒が間違ったブロックを取り付けた場合に、保護者の介入が必要となるケースがありました。また、プログラミングの授業において生徒がプログラムとロボットの関係性を理解するためには、完成したものを提示し、パラメータを変化させながらその影響を確認する方法が適していると感じました。使用した教材はオンライン授業に適した形に改善する必要がありました。受講環境の問題:
オンライン授業を受講するためには、生徒が複数の画面を利用する必要がありました。しかし、生徒の受講環境において2画面を使用することが難しく、画面サイズの制約やデバイスの不足が問題となりました。このため、オンライン授業の受講環境の標準化が困難でした。生徒の理解度の把握の難しさ:
オンライン授業では、生徒の理解度を把握することが難しく、適切なサポートを提供しにくい状況でした。対面授業では生徒の様子をリアルタイムで把握しやすいため、適切なサポートを提供することが容易ですが、オンライン授業では生徒の理解度や進捗を正確に把握することが難しいという問題がありました。Zoomの接続先サーバー問題:
当時、Zoomの接続先サーバーが中国にあることがセキュリティや信頼性の問題となりました。企業からは国内のサーバーに接続するとのアナウンスがありましたが、一時的なものであり、後に香港のサーバーに接続されることがありました。このような予期せぬ接続先の変更は不信感を招きました。これらの理由から、オンライン授業を実施する際の信頼性とセキュリティの問題が明確になり、別の選択肢を模索することになりました。
オンライン授業における教材と教育効果
オンライン授業におけるカリキュラムと教材は、生徒が試行錯誤しながら学習し、個々の状況に合わせたサポートを受けることを前提としています。
ロボットプログラミングの場合、センサーから得られる数値情報は生徒の環境によって異なるため、数値の差異に対する理解を深め、その上でセンサーの数値をどのように判断して活用するかを理解させます。
この過程は小学5年生や6年生の生徒にとっては理解できるかもしれませんが、小学3年生や4年生にとっては難しい場合があります。対面式の授業では、すぐそばにいる先生からのサポートを受けながら取り組むことができますが、オンライン授業では画面の向こうにいるため、自分の状況をうまく説明できないことがあります。このような状況下では、生徒が自ら積極的に取り組むよりも、指示通りに行動することが主体になり、自主性を感じにくいかもしれません。
小学生の生徒は脳が成長の過程にあり、大人向けの論理的な会話による理解は難しいと考えられます。したがって、オンライン授業においては、生徒の認知レベルを考慮し、より分かりやすい言葉や手法で教育を行う必要があります。
オンライン授業には、その特性を理解した上で、効果的なプログラミング教育を行うためのティーチング手法や教材が必要です。授業で使用する教材や手法は、オンライン環境を考慮して設計されるべきであり、生徒が見たり触れたりするものも含めて、オンライン授業の特性に即したものでなければなりません。
オンライン授業への挑戦と学び
オンライン授業の可能性を模索した経験から得た重要な教訓は以下の通りです。
まず、適切な教材の不足が大きな障害でした。オンライン環境では、生徒が自律的に学習するための適切な教材が不可欠です。特に実習やプログラミングなどの実践的な科目では、明確な指導資料が必要です。
次に、受講環境の問題が浮き彫りになりました。生徒が複数の画面を利用することが求められますが、生徒の環境には制約があります。そのため、受講環境の標準化が重要だと感じました。
また、生徒の理解度を把握することも困難でした。オンライン環境では、生徒の反応や理解度をリアルタイムで把握することが難しく、適切なサポートを提供するのが難しいという課題がありました。
さらに、Zoomの接続先サーバーの問題もセキュリティや信頼性の観点から懸念されました。接続先の変更が予期せず行われ、それが不信感を招く結果となりました。
これらの経験から、オンライン授業を導入する際には、生徒のニーズや制約を十分に理解し、それに合わせた教育手法や教材を用意することが重要だということを学びました。生徒が自律的に学び、成長するためには、オンライン環境に最適化された教育アプローチが不可欠です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
