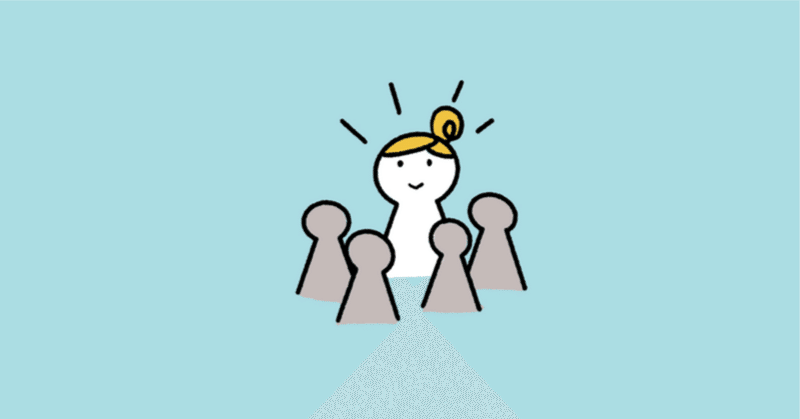
自分の居場所の造り方
「ここは自分の居場所じゃない。本当の居場所は別にあるはず。」と、高校の3年間ずっと思い続けていた。
勉強はできない。飲食店、工場、引っ越し屋などのバイトも3ヶ月続かない。友達も彼女もできない。今でいうスクールカースト最下層の存在。
そんな自分が社会に出て働いている姿が、想像できず常に不安だった。
19歳の時に、認知症の祖母が入院した。死期が近く、家族で交代しながら付き添い。付き添う前に病院の売店で何気なくに手に取った一冊の本。
その本は、マザーテレサの活動を取材したものだった。路上で生まれ、路上で死んでいく人々を、最後は人間らしい死を迎えるための施設の話。読んだ私は強い興味を持った。祖母の命とマザーテレサの活動に、生きること、死ぬことを考えさせられた。
祖母が亡くなった3ヶ月後、インド行きの飛行機に乗っていた。初めての飛行機。初めての海外。飛行機の中、すでに不安で頭の中真っ白。空港に着くと、日本人はいなくなり、インド人で埋め尽くされた。
夜行列車を乗り継ぎ何とか目的地のマザーテレサの施設に着き、ボランティアを志願した。ボランティア内容は食事の準備や食器を洗ったり、洗濯したりと様々だった。
そんな中、うつろな目をして酸素投与されながら亡くなりそうな方がいた。シスターに呼ばれ、その人の手を握るように促される。シスターは「寄り添うことに意味があるの」と言う。その細い手を握ってみたものの、それからどうしていいか分からず時間だけが流れた。自分は何も理解できていないことだけは分かった。
日本に戻った私は、地元の老人ホームで介護職員として初めて就職した。入所している人は介護が必要な人ばかり。寝たきりや重度の認知症。食事、入浴、排泄の介助、空いた時間はレクリエーション。思っていたよりずいぶんと慌ただしい。
ある日、何度も同じ話をする認知症のあばあちゃんの話をずっときいていると、ベテラン介護士のおばちゃんに呼び出された。
「お金もらってるんやから、もっと働きな。」
その一言にショックを受け、トイレに駆け込むとすぐに涙がこぼれ、声を殺しながら泣いた。もう辞めようか、いや、悔しい。まだ何者にもなっていない。そう思うと辞める訳にはいかなかった。
利用者の介護や介助をしていると「ありがとう。」と言ってもらえることがある。この一言は、自分がここに存在してもいいと思える言葉だ。その言葉をもらうために頑張れる自分がいた。
少しずつ介護の仕事が楽しくなり、居心地の良い場所になっていった。職場で友達ができ、初めて彼女ができたりもした。
その一方で、もっと違う仕事も経験してみたいと思うようにもなっていた。職場の看護師の先輩に相談すると「あんたも看護師になったらいいやん」と言われた。始めは自分が看護師なんてと思ったが、介護の経験を活かせる仕事に思えた。
24歳の時に、思い切って看護学校に入り看護師になった。就職先は病院勤務。学校で覚えた知識と、現場で覚えなければいけない知識とのギャップが大きく上手く動けなかった。
指導を受け続ける毎日。自分の不甲斐なさにうんざりし、3ヶ月目にもう辞めようかと本気で考えた。ただ、本当にその日分の全力を出せているだろうか。やるだけやって、どうしてもできない時は先輩に助けを求めよう。分からないことは少しずつ覚えていこう。それでも無理なら辞めよう。
そう切り替え仕事に向かうと、勝手に感じていた重圧が少し軽くなった。
少しずつだか仕事を覚えていくと、少しずつ職場が居心地の良い場所になり、周りのスタッフとも上手く関係を築けるようになっていった。
気がつけば現在、看護師歴10年を超えた。
自分の居場所なんて最初から用意されていない。自分で少しずつ作っていくしかないようだ。そんな分かりきったことに気付くのにすいぶんと時間が掛かった。
この文章は 2023年の日本勤労青少年団体協議会 第36回「働くってなんだろう」エッセイ入賞作品です。2022年から色んなコンテストに月に一回は出すようになり、初めて入賞したものです。自分の文章が誰かに認められた気がしてとても嬉しかったことを覚えています。
読んで頂きありがとうございました。スキやフォローして頂くと励みになりのでよろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
