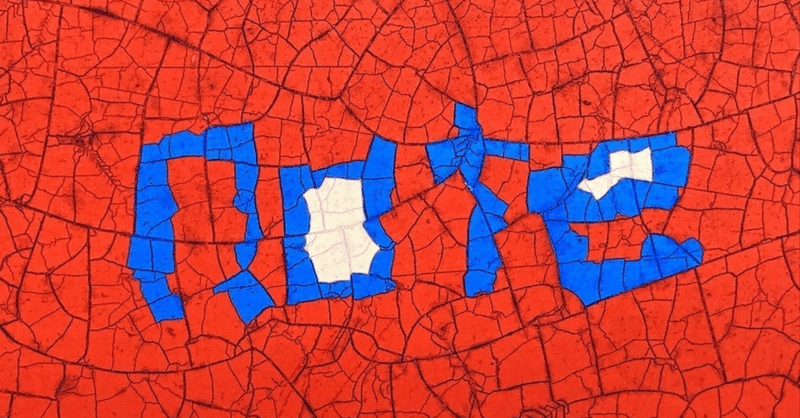
30日間チャレday6、スパイダーマン映画における「蜘蛛の糸」(日記11)
渋谷のHUMAXで『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』観てきた。この映画館は外観も内装もロケットというかステーションというか、とにかく宇宙っぽくて異質だ。宇宙系のSFを観るのに最適。かつて友人と一度来たことがあった気がする。何を観たかは覚えていない。
(以下、大したネタバレはないので気楽に読んでください)
さて、「スパイダーマン」および「蜘蛛の糸」は、そもそも映画映えする主題である。個人的には、映画のために生まれたと言っても過言ではないくらい映画的なキャラだと思っている。アメコミ原作を知らないから迂闊なことは言えないものの。スパイダーマン映画以前と以後では、人々の映像に対する認識が根底から変わったのではないだろうか?
少し前の日記で、アクション映画は「地形+人物+小道具」だという話をした。これは正確に言えば「地形+人物+カメラワーク」の三つ巴(+小道具)と捉えたほうが分かりやすいかもしれない。とある場所(=地形)に主人公と敵(=人物)が配置され、そこでの彼らの動きをカメラが縦横無尽に追う(=カメラワーク)。このときに必須ではないものの、重要な役割を果たすのが武器や装備などの「小道具」である。
スパイダーマンが用いる「蜘蛛の糸」は、ビルなどの建築物にくっつき、彼がスイングによって移動することでカメラが大幅に動く。カメラ自体があまり動かない場合でも、スパイダーマンは画面を立体的に移動する。単純に空を飛ぶのとは異なり、地形によって戦略が大きく変わる。これは『進撃の巨人』における「立体起動装置」とかなり似ている(たぶん発想のレベルでスパイダーマンの影響はあるはず)。蜘蛛の糸と立体起動装置に共通するのは伸縮性とその速度である。同じことは『ワンピース』におけるゴムの腕や、『ハンターハンター』におけるバンジーガムにも言える。この性質によって、人物の移動・カメラの移動はよりダイナミックになる。技の威力が増す。映画という大画面のメディアにおいて、アクション好きがもっとも体感したいのは、画面と人物たちの動きのダイナミックさ・激しさに他ならない(異論は認めます)。
こうした映像的効果の観点からのみならず、そもそも「蜘蛛の糸」には様々な機能がある。戦闘や移動はもとより、敵を捕捉する機能、物を奪う・移動させる機能、仲間を助けるセーフティネットとしての機能など、スーパーヒーローに相応しいギミックがこれでもかと揃っている。なのに、元はただ伸びてくっつくだけの糸だから、シンプルで過剰な感じがしない。それでいて、スパイダーマンの頭脳によって幾通りもの戦い方ができる。だからこそ、スパイダーマンというキャラは極めて映画的な存在なのである。
私は今回新作スパイダーバースを観て、もちろん作り込みに感動はしたのだが、過剰さに気おされてしまった。蜘蛛の糸とマルチバースの相性の良さは言わずもがなである。しかし、こうも何体もスパイダーマンが出てきてしまうと、単純な戦略勝負ではなくなってくる。これまでの実写スパイダーマンは最小限のつくりになっていたからこそ、「蜘蛛の糸」という装置の応用力にフォーカスできたのかもしれない。と逆に気づかされることになった。もちろん、スパイダーバースにもそういった見せ場は少なくないが。
スパイダーバースにおいて注視すべきなのは、戦闘というよりはむしろ、間テクスト性や間メディア性なのかもしれない。「蜘蛛の巣」のメタファーによって、様々に描かれたスパイダーマンのコミックがこの映画で繋がる。各コミックにおけるタッチも多様である。『アクロス・ザ・スパイダーバース』においては実写の映像すらもクロスオーバーする。漫画・アニメ・実写といったメディア間の自由な横断を可能にした映像表現こそ、本シリーズにおける真の意義だと私は信じている。アニメ表現の可能性はほとんど無際限に拡張されてしまったのである。この辺の議論についてはまたいずれ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
