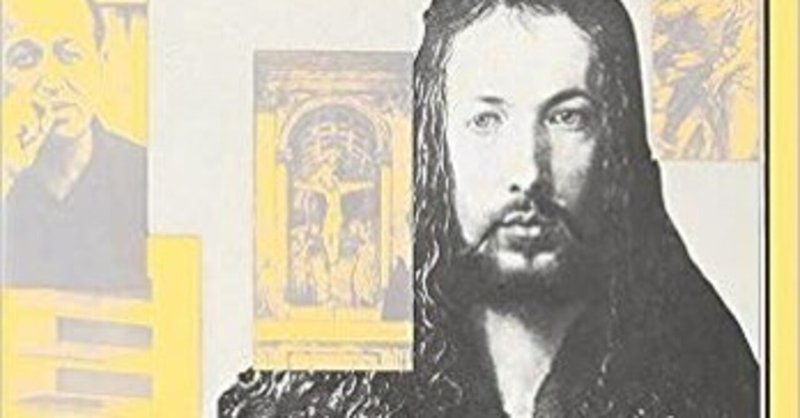
30日間チャレンジday3、『芸術学ハンドブック』と救済芸術論?(日記8)
三日目だ、えらい!
寝坊して10時くらいに起きた。したがってできるノルマは減少してしまった。しかし今日はそれなりに進んだと言えるのではないか。まず『芸術学ハンドブック』を少し読み、次に30日間チャレンジを進め、そして単語カード作りと瞬間英作文を交互にこなした。
『芸術学ハンドブック』を読んだ理由としては、今日が返却期限だったからである。借りてきた本は返却期限にならないと読めないことが多い。これはいつも締切に追われ、締切という動機づけがないと何もできなくなってしまった、ゴミ人間の習性といえるだろう(自虐ばっかですんません)。本当の締切に追われるのではなく、自ら締切を作り出して着々とこなしていける人間が大成するのである。この本を借りてきた理由はもはや思い出せない。確か、後輩の卒論(イメージ論)を読んで、「芸術学」とは何か考えたくなったから、だった気がする。
もう返却期限なので当然読み込めていないが、冒頭を読むだけでもかなりしっかりした概説になっているのがわかる。全体をパラパラと読んでみてもわかる。古いけど、主要なトピックがちゃんと取り上げられている。ただ「芸術学ハンドブック」というよりは、「美術史学ハンドブック」といった方が適切な気がする。正直寄稿者の名前をあまり存じ上げないが(不勉強)、我らが岡田温司先生が「壁画」の項目を寄稿していた。
それはそれとして「第1部 美術史の歴史と方法」のなかの、「2 美学と芸術学」(村田 誠一、10-21頁)の最後の方の記述が面白かった。簡単に引用してみる。
(前略)芸術は科学や道徳に対する批判であるだけではない。マックス・ウェーバー流に言えば、かつて宗教が果たしていた救済の機能を、近代では芸術が代わって引き受けていると言うことができる。すなわち、「現世内的救済」としての芸術であり、それゆえ、近代美学は、世俗化された神学ともみることができる。(中略)現代美術のそうした否定的傾向も、美学が結局人間の救いにかかわることまで否定しているわけではない。
神林 恒道(他)編『芸術学ハンドブック』1989年、勁草書房(太字はあもてゃによる)
マックス・ウェーバーは芸術一般を救済として捉えていたのか。これはチェックする必要があるかもしれない。なぜなら、私は芸術によって救済されたいからである。私が美術史を志した理由の一つとして、自己嫌悪とぺシミズムの超克がある。芸術には救済の力がある。それは直観的にわかっていたが、言語化できるものとは思っていなかった。しかも、救済の手段として考えるのがなんだか悪いことのような気がしていた。ちゃんと研究している人に失礼だなあと、どこか引け目を感じていた。ウェーバーが突破口になるかもしれない。少なくとも、救済としての芸術についての論、すなわち「救済芸術論」(?)の正当化には使えそうだ。(造語作るのって難しいね)
もっといろいろ書きたいところだが、おなかがすいて力が出なくなってきた。これ以上は勘弁してください。。
(ヘッダー画像は上記URLから引用)
関連文献:芸術の自律性について - 同志社大学学術リポジトリ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
