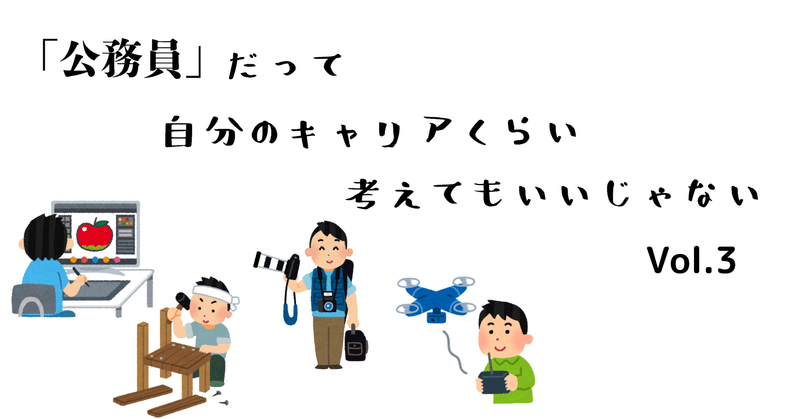
公務員だって自分のキャリアくらい考えてもいいじゃない(Vol.3)
今日は公務員個人が持つスキルと副業などについて。
これまで「個々の公務員がもっと自分のスキル・能力、志向に応じて、(自治体も越えた)キャリアを柔軟に選択できるようにならないか」ということを書いてきました。
そのために、職員個人と人事(最終人事権を持つ上層部も含め)双方で「公務員だって中途採用や転職があっても良いかもしれない」という意識を持つことのほか、役所における人事制度の刷新やvol.2で紹介した地方公務員のレンタル移籍制度といった自治体外の仕組みも必要になってくると思います。
それらは直接的に公務員としてのスキルに関わる話がメインですが、今日はサブスキルというか、職員個人が主に公務外で得たスキルを活用することをどう考えるか、について。
「あ、それくらいなら、自分できます」
実例から書きましょう。
僕は、伝統行事であり地域最大の観光イベントでもある「相馬野馬追」の公式SNSを運用するいわゆる"公式中の人"の1人として、Twitterの更新や発信を行なっています。
このnoteもそうですが、情報発信というのは難しいもので、文字だけでバーっと書き連ねても、情報で溢れる現代デジタル社会の中では誰の目にも留まらないということが常です。
隅から隅まで精読されることが前提の学術論文ならともかく、大多数に向けたお知らせやプロモーションなどでは、いかに「目に留まるか」「読み続けてもらうか」に労力の多くを注ぎ込む必要があります。
(最近だとアナリティクスとかで、数字として明確に「見てもらえたかどうか」が分かっちゃうので尚更)
そのため、投稿する情報の中でも色々写真を編集したり、ラフ絵を描いたり、デザインについて考えることも出てきます。
例えば今僕は、10月に始めるSNSキャンペーンのバナー画像デザイン中で、下の画像のような感じにしようかなーとか考えています。

これはただ要素を配置しただけのラフで、中学校の時美術の成績が2だった僕ではこれ以上のことはできません。
しかし、ウチの職場には幸運なことに、デザインスキルを持った同僚がいるため、お菓子などを渡しながら「これ、いつもみたいによろしく!」とか「できるよね?ニッコリ」などと頼むと、こういったラフをキチッとデザインし直して、SNSという全世界に発信できるものに変えてくれます。

スキルに見合った正当な対価は?
こういった作業は、花岡が頭を抱えてGoogle先生に聞きながらチマチマと進めても時間をかければできるのかもしれませんが、如何せん他の仕事の手が止まります。
デザインスキルを持った職員にお願いすることで、「個人的なスキルを仕事に活かしてもらっている」と言えば聞こえはいいのですが、ここで1つ懸念が生じます。
それは「個人的なスキルに依存した業務に対して、正当な対価や報酬が支払われているのだろうか」ということ。

今回の例でいえば、僕は同僚に対して大量のお菓子(個人で買ったヤツね)を提供することでこの作業をやってもらったりしているのですが、そもそも同僚が役所から支払われる給料ではそれらのスキルを考慮した金額になっている訳ではありません。
いや、金額自体は知りませんけど。そもそもそういった制度がないのでね。
既にこの懸念は現実のものになりつつあって、他課や他部からも「デザインできるんだって?ちょっとこういったチラシ作りたいんだけどお願いしてもいい?」といったような依頼があったりします。
日常の業務協力や人間関係の中で処理できる範囲内なら問題ないかもしれませんし、公務員の給与体系は条例その他で明確に定められていて、個人個人のスキルを適切に反映する仕組み自体がないので、いきなり「このスキルあるんだから給料を上げろ」という訳ではありません。
ただ、「同一労働同一賃金」ではないですが、日常同じ課の職員と同じように業務をし、加えて個人のスキルを活かした業務まで行なっているのであれば、そこには当然それに見合った対価が生じるハズなのになぁ。。というモヤモヤしたものを感じている、ということです。
また、話が広がるのでこの例だけにしますが、行政が「デザイン」というものの価値を正しく認識できていないのではないか、という問題にも問題にも繋がると思っています。(掘り下げれば「個人スキル=デザイン」だけではないのですが)
以前、自治体が1年任期のデザイナーを無報酬で募集したことで、業界の方々からエラい批判を浴びたというニュースがありましたが、まさに象徴的な出来事ではないでしょうか。
まとめると、
・職員個人が持つ特殊技能に対する正当な評価がされる仕組みを考えないといけないのではないか
・こと、「デザイン」というスキルに対して、行政職員は正当に評価できる目というか物差しを持っていないのではないか
ということが僕の課題感です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
