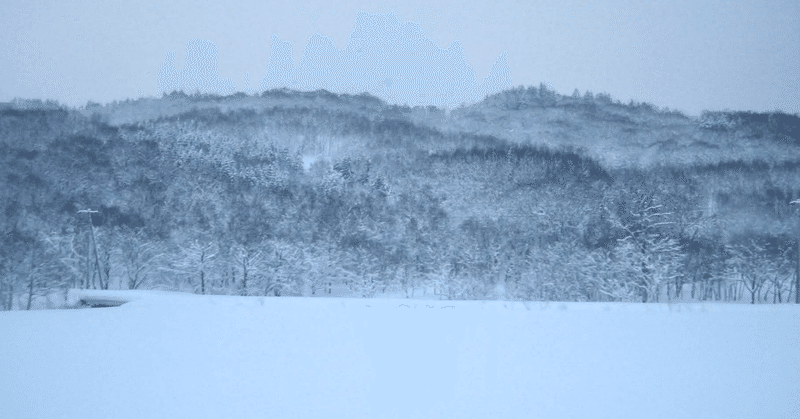
静謐な芸術文化を伝える、という仕事
西に下る東海道新幹線に揺られつつ、この文章を書いている年の瀬です。雪化粧をした富士の山頂だけが、雲から覗いていた大晦日。
今年はそれなりに風呂敷をばあっと広げて、いろんなことをやってみた結果、自分にとっての向き不向きがしっかりわかった1年でした。
表に出せた新しい試みは、3月に始めたYouTube。月に1回出せればええかな……という低空飛行でまだ8本しか出せていないけれど、文章とは違った伝える面白さがあり、また海外の視聴者の方々と出会える嬉しさもあり、これからもライフワーク的に続けていけそう。息抜き的に気軽にやるぞい、と思っていたのに、思いの外編集に時間をかけてしまっておりますが……。
足掻いていたけどちっとも表に出せなかったのは、論考を書くということ。文芸誌や個人的な仕事の中で、「エッセイ」ではなく「論」を書く機会が与えられてはいたのですが……てんでさっぱり駄目でした。論理的に、批評的に……と注意して文章を組み立てようとしても、主観的な感情がそこに混ざり込んでしまう。
思い返せば、私は卒論のときから「これは卒論やなくて、卒論風エッセイやね」と指導教官に笑われていたような。いやその前に、大学入試の小論文でも、入試の最中においおいと泣きながら情緒的なエッセイを書き殴っていた記憶が……。
私はどうやら、情緒を切り離した文章を書くことは逆立ちしても出来ない性質のようです。いやでも、情緒だけで文章を描いていきたいという訳でもなくて……知性を縦の糸に、情緒を横の糸にして織っていく反物のような文章を書いていく、というのが今の理想です。知性と感性のどちらかに偏らせるのではなく、両方を混ぜ込んでいきたい。「とにかくその種の混合がなければ知性ばかりが支配的になり、心の他の能力は硬化して不毛になるのですから。」というヴァージニア・ウルフの言葉を支えにして。
──
そして今年は、あらためて芸術のことを沢山考えた1年でもありました。考えたというか、感じて、そして頼らせてもらった……というほうが適切でしょうか。そうしているうちに、好きな美術について話させてもらう機会が増えたり、サントリーホールさんからお誘いいただいてHanakoで小さな連載を持つようになったり。
振り返ってみればもう15年以上も前から芸術を伝える仕事を志して、たくさんの形で実践してきたけれど、その長い長い年月の中で縁遠くなっていくものもあれば、より親密な関係になるものもありました。その親密なものの内側には、絵画や彫刻、音楽や文芸──さまざまなものがまざってしまっているけれど、ひとつ共通項を見出すのであれば、そのどれもが静謐な空気の中で存在しているということ。
物書きの仕事でいえば、「音楽」「アート」「文芸」「映画」「工芸」といったジャンルで専門を分けることが一般的だし、それに音楽メディア、アートメディア、文芸メディア、etc……というものはもちろん、各々存在します。そのどこにも「専門です」と言えるほどに所属していない自分は中途半端な人間だな……とずっと自虐的にとらえていたけれど、ここ最近は、感性を軸に発信する人間がいてもいいんじゃなかろうか、と思うようになってきました。分野や洋の東西を問わず、静謐な芸術文化を理解し、噛み締め、伝えられる人になりたいのです。
静謐な文化は、大きな声でその魅力を伝えることはむずかしいものです。過剰な宣伝をしてしまうと、その生態系までも壊してしまうかもしれないし、静かな魅力を掻き消してしまうかもしれない。ただ、それを大切に守っているだけでは、出会うべき相手にも出会えない。だからそこに深く潜りながらも、言葉にして、伝えていくことが出来たならば……それはきっと、生涯をかけて探求していけるほど、やり甲斐のある役割であるように思います。
──
そして現在進行中なのが、
ここから先は
新刊『小さな声の向こうに』を文藝春秋から4月9日に上梓します。noteには載せていない書き下ろしも沢山ありますので、ご興味があれば読んでいただけると、とても嬉しいです。

