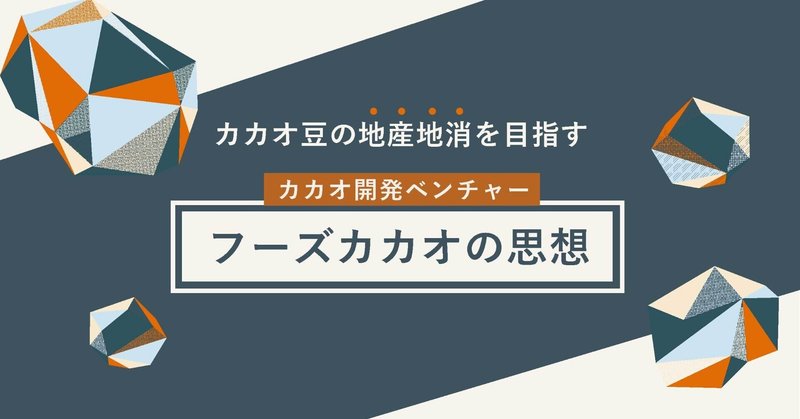
カカオ豆の地産地消を目指す。カカオ開発ベンチャー、フーズカカオの思想
Bean to Barをはじめ、質の良いカカオを適正価格で流通させる動きが注目集めています。そうした取り組みを行う会社の中でも、カカオ農園にひたすら向き合う熱い思いを持つ人がいます。
カカオ開発ベンチャー、フーズカカオの福村瑛(ふくむら・あきら)さんです。フーズカカオはインドネシアやタイなどの東南アジア地域で、現地の企業や生産者と連携をし、カカオ農園とカカオ原料の開発や輸入、卸売事業、商品開発をしています。
私たちCIALは「思想・哲学が力になる世の中へ」というビジョンを掲げ、そのためにデザインという手段を用いています。フーズカカオさんとは、カカオのお菓子ブランド「CROKKA(クロッカ)」の開発を一緒に行いました。
これまでのフーズカカオさんの取り組みを振り返りつつ、情熱に後押しされた事業を絶やさないために福村さんが何を考えているのかを伺いました。
起業のきっかけは、チョコレートのカカオ含有率への違和感

(フーズカカオ代表、福村さん。取材はオンラインで行いました)
——フーズカカオさんとCIALはもう2年以上の付き合いですね。元々、福村さんはどんな思いがあって、会社を立ち上げられたのでしょうか。
僕、チョコが大好きなんですよ。昔、親が兄と自分へ一箱ずつ、ロイズのチョコレートをお土産で買ってきてくれた時に、それを兄にバレる前に一箱食べてしまうくらい好きでした(笑)
——めちゃくちゃ好きですね(笑)
そんなチョコ好きが高じて、その原材料の割合に興味をもったことが起業のきっかけでした。コンビニなどで売られているチョコ菓子に含まれるカカオの割合って、原材料表示の五番目とか六番目の量なんです。
——意外と少ないんですね。
そうなんです。どうして、カカオの成分が少ないんだろうと疑問を持ちました。もしかしたら原材料が高いのかもしれないと思って、実際に現地に行ってみたんです。そこで知ったのは、そもそも農園が良いものを作れる環境ではなかった、ということ。
カカオ豆には風味の優れた「スペシャルティカカオ(ファインカカオ)」とコモディティ商品である「バルク・カカオ」の二つがあります。前者は世界で見ても全カカオ生産量の中の5%程度しか占めません。インドネシアに目を向けると、その生産量はたったの1%。
しかも、農園から消費者の手に渡るまでいくつものバイヤーや加工業者が必要なので、消費者への販売価格に対するカカオ農園の取り分が少ない状態だったんです。
——バリューチェーンの構造が課題だったんですね。
はい。農園の開発から携わり、そもそも美味しいカカオ豆が作れる環境を整えれば、今の仕組みをガラッと変えられるのではないか、と思い起業を決意しました。
作り手の意思を大切に、農園を開発
——農園の開発をするためにどんな取り組みをしてきたのかを教えてください。
コネもツテもないので、まずは現地でつながりを作りながら20くらいの農園を訪問し、最終的に、Enrekang(エンレカン)県の農園と組むことになりました。

——その農園を選んだ決め手はなんだったのでしょうか。
農家さんにプライドがあったんですね。「俺たちのカカオは良いものなんだぜ」って主張してくるくらい自信のある人と組みたかった。そういう人たちはカカオの品質を高めることに積極的だと思ったんです。
実際、クオリティの高いカカオの要件を伝えると「俺たちもやってみよう」と前向きな姿勢だったので、じゃあやってみようかと。
——そもそもつくる側の意志の強さを大切にされていたんですね。スペシャルティカカオをつくるために、具体的にどんな取り組みをされてきたのでしょうか。
これはブランドによって意見が異なりますが、スペシャルティカカオの肝である風味作りで一番大切なのは発酵のプロセスだとフーズカカオは考えています。発酵は白い果肉の部分に含まれる糖分を酵母が発酵させるアルコール発酵と、酢酸菌と乳酸菌による好気性発酵の二段階に分かれています。このプロセスがうまくいくと、格段にカカオの風味の品質が上がります。
発酵のクオリティを担保するために、アルコール発酵時には、アルコールがちゃんと生成されているか、好気性発酵の時にはフルーティーな香りが生まれているか、そして乾燥後にはフルーティーな香りが残っているか、三つの確認プロセスを取り入れています。
最初は僕も現地の農家さんの家に滞在し、データをとって、クオリティ管理を監督していましたが、今では彼らだけで(むしろ彼らのほうが)高品質なカカオ豆を生産できるようになりました。
ブランド作りは、自分たちを見つめ直す行為だった
——農園開発から始めて、カカオ豆の卸をされて、次に手掛けたのがカカオのお菓子「CROKKA」ですね。
そうですね。卸をやっているときに、カカオを豆をどう調理すれば美味しい商品になるのか、わからない方が多いことに気付きました。だったら、自分たちで一つのサンプルとしてお菓子の商品を作ってしまおうと。

(「素材から、カカオの “カタチ”を再発見する。」をコンセプトに掲げたCROKKA。ザクザクとした食感が特徴です。 photography:Yusuke Sano)
——実際にモノがあるだけでもグッと完成形のイメージがつきやすくなりますよね。CROKKAをつくる上で、CIALはコンセプト作りからパッケージ作りまで、3ヶ月ほど伴走させていただきました。コミュニケーションをとる中で、これまで取り組まれてきたことを見つめ直す機会もあったかと思います。CROKKAを作り終えて、福村さんの中でフーズカカオや関係する人たちに対する向き合い方にどんな変化がありましたか。
最初はブランド作りとは何か、その全体像が掴めませんでした。ロゴとブランド名があるんだろうな、という印象で。ただ、CROKKAを形にしていく中で、ブランド作りとは、元々自分たちが持っているものを洗練させていくことなんだと気付きました。
僕らは元々カカオ豆しか持っていなかったけど、それがお菓子になる過程を通じて、自分たちのアイデンティティが整理されていったなと感じています。僕らがやっていることがどうしたらちゃんと伝わるのかを、より一層考えるようになりました。
——多くの人に届くプロダクトだからこそ、自分たちが伝えたいことがより研ぎ澄まされたのかもしれませんね。CROKKAの販売が始まって、一緒に働くメンバーや農園の方々、消費者の方にも変化はありましたか。
Enrekang県の知事の方がとても喜んでくださいました。県知事の部屋にCROKKAが飾ってあるんです。プロダクトという形で自分たちの提供価値が可視化されたことで、作っているカカオに誇りが持てたようで、とてもうれしかったですね。
目指すのは、現地で地産地消が行われる文化づくり
——CROKKAの開発の後は、どんな取り組みをされているのですか?
インドネシアのスラウェシ島にあるハサヌディン大学と連携して、現地でのカカオ豆の生産からチョコレートの製造まで一連の工程における商品開発事業を進めています。

(ハサヌディン大学の方々と)
——分断されていた製造工程をどんどん一つに集約しているんですね。
そうですね。僕らは当初から、インドネシアで一つのプロダクトを作れるようにしたいと思っていました。現地でできることを増やせば、その分農園に利益が配分され、持続可能なビジネスへとつながります。今は日本での流通が主ですが、最終的には生産から消費まで全部現地で完結させたいと思っています。
——大学との連携が、現地で消費文化をつくる一歩目というわけですね。ちなみに日本ではどんな取り組みを予定されているのでしょうか。
自分たちの工房を作ろうと思っています。理由は二つあって、一つはより柔軟に商品の開発を進められるようにするため。これまでは加工パートナーの方に委託をして作っていましたが、どうしてもお客様の声に反応するスピードが遅くなってしまう。マイナーチェンジであれば、すぐに取り組めるような環境の方が、お客様の満足度につながると思いました。
もう一つは、お客様とのコミュニケーションをとりやすくするため。これまではオンラインしか接点がなかったので、伝えられる情報が限られていました。ショールーム的な使い方をすることで、今まで伝え切れていなかったことを届けられたらなと思っています。
——商品の改善サイクルのスピードを早くしつつ、その過程も体験してもらえるような場づくりということですね。
工房は自由に訪問いただくことを可能にしようと思っています。ぜひ、完成したら遊びに来てください。
作ること以上に、続けることに向き合う
——フーズカカオを立ち上げられてから4年が経ちました。振り返ってみて、福村さんの中で事業の向き合い方にどんな変化がありましたか。
ものづくりが継続するためにも、ビジネスとしても成功するかをより考えるようになりました。もともと、農園はそのとき稼げるものをつくるという文化でした。だから、カカオ豆だけでなく、トマトやバナナを育てたりしている。それをなるべくカカオ豆に集中してもらう環境に、僕たちは変えてしまった。もし、カカオ豆が稼げない作物になってしまったらまた一からやり直しです。そういう環境にしてはいけないという思いは強くあります。
——事業に取り組む中で、徐々に「続けること」への意識が強くなっていったのかなと思いますが、特にきっかけとなった出来事はありましたか。
いろいろありますが、2020年でいうと僕らが買おうとしたカカオ豆が買えなかったのが大きい出来事でしたね。僕らはいつも市場やフェアトレードの価格より2倍以上の価格でカカオ豆を仕入れています。その代わりに、事前予約のような形で一定の量を確保してもらっているんです。
ところが、カカオ豆の相場が動いて、僕らが提示していた価格に近くなった瞬間に、確保していた豆が市場に売りに出されたんです。その時に、何よりもまず目の前の生活が担保されていることが大事なんだと改めて気づかされました。

——お互いに稼ぎ続けられる環境が前提にないと、自分たちの思想が実現するのは難しいのだと痛感したんですね。お互いにとって良い関係を構築し、ビジネスを持続させるために、福村さんは何を大切にしているのでしょうか。
とにかく相手に向き合うことです。なるべく対話を避けるようなことをせず、相手が何を本当に求めているのか、耳を傾ける。こっちが何を求めているかも、ちゃんと伝える。
空気を読んで決断する、というのはあまりしませんね。なぁなぁになってしまうことが一番リスクなので。
その上で、自分たちがとっている手段がベストではないかもしれないと常に疑い続けること。続けるためにはどういう手段を取るべきか、前例にとらわれず考え続けたいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
