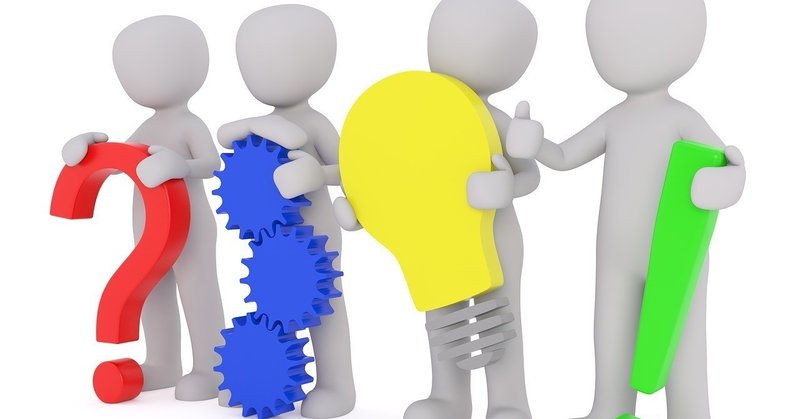
【情報弱者】情報って、みんなが同じだけ得ているわけじゃないんだよね
アメリカの大学に留学したばかりの時、アメリカ手話(ASL:American Sign Language)のクラスを取ったんだよね。
その時の専攻が、Special Education(特別支援教育)だったんで、必須科目だったことがきっかけだったんだけど、アメリカ手話のクラスを通じて私の狭かった世界観がみるみる広がっていったのを今でもはっきり覚えてる。
ドライブスルーが利用できないこと、
音楽は振動で楽しむこと、
「お問い合わせ」方法に電話番号しか書いてなければ問い合わせそのものができない、レストラン等の予約ができないことなどなど、
これらの事は、耳が聞こえない人の立場に立って想像しようと思えば、ある程度は教えてもらわなくても理解できたことかもしれないんだけど、聴覚に障害のある人が「情報弱者」だということは、ASLのクラスで聴覚障害の人の文化について学ぶまで全く知らない世界観だったんだよね。
聴覚に障害のある人だけじゃなく視覚に障害のある人も、情報に「注意を向ける事」で初めて情報を得られる情報弱者。
昨日のnoteにも書いたけど、目や耳に障害のない人は、知覚情報の約80%を視覚から得る情報に頼ってるんだよね。だから、歩いている時や車の運転中に何気なく見ている景色から「あ、ここの空き地だったとこ、スーパーになるんだ」って情報を得たり、行列をみつけたら「あ、あそこのラーメン屋さんおいしいのかも」って思ったり、電車の中吊りやコンビニに並ぶ雑誌の表紙から最近の話題をなんとなく知ったりと、無意識に情報を取り込んでるんだよね。
でも視覚に障害のある人達は、これらの無意識に得られる情報が手に入らないんだよね。
そして聴覚に障害のある人は、周囲の人の話し声や、車の運転中にきくラジオが伝えるニュース、つけっぱなしのテレビから聞こえるCMの情報が得られないんだよね。よくツイッターで登場する「マックで隣の席の女子高生が○○って話をしてた」みたいな情報も得られない。
だから聴覚や視覚に障害のある人は、「情報に意識的に注意を向ける事」で初めて情報を得られるわけで、得られる情報量が絶対的に少ないんだよね。
ここで昨日のnoteの話題でもある「災害時」を想像してみてほしい。
何かいつもと違う事が突然起こったら、視覚や聴覚に障害の無い人は、意識せずとも周りの人の行動や、周りの人が話してる内容からも情報を得られるけれど、目や耳に障害のある人達は「情報を自分から取りに行かない」と得られないから、その場にいる人が口伝えで伝えあう情報や、なんとなく他の人の人波に付いて行ったら出口にたどり着いた、みたいなその人に向けられていない情報からは取り残され、避難が遅れてしまいがち。
だからね、緊急事態を見越した情報提供の方法を普段の情報提供の方法に取りこんでおくって大切だと思うんだよね。
例えばレゴランドだったら、スマホなどのアップを通じて音声や文字での情報を普段からお客さんの障害の有無関係なく提供できてるんだろうけど、
緊急時にもそのアップを通じて情報の提供・行動の指示をしたり、GPSで障害のあるお客さんの位置を確認できたりして、それを入館時に周知すれば、「緊急時を見越して障害のない人の同伴が必要です」っていうルールの必要もなくなり、誰もが楽しめる場所になると思うんだよね。(停電時や災害時のテクノロジーへの影響の事は私はよく分かってないから、ただの思い付き案なんだけど…)
情報は「届けたい人・届けなきゃいけない人」に届いて始めて「情報」の価値がある。届かないと意味がないんだよね。だから「届きにくい人」を見越して情報を届ける工夫をしておくと、「届く情報」「届く人」が増えるはず。
だから昨日のnoteで言ったみたいな、「どんな人にも届く情報」を普段から学校の授業とか、日常のあらゆる場面でも普段から提供できていれば、その延長でそれが緊急時にも活かされると思うんだよね。
普段から複数の知覚(聴覚、視覚、嗅覚、触覚など)を使って情報を伝える心がけ、色んな場面に広がれ~!!!
たくさんの方々に読んでいただいたり、支援方法を参考にしてもらえたらと思い記事を無料公開していますが、 今までもこれからも勉強を続ける私の為に「投げ銭」という形でご支援いただければすごく励みになります。 よろしくお願いします。
