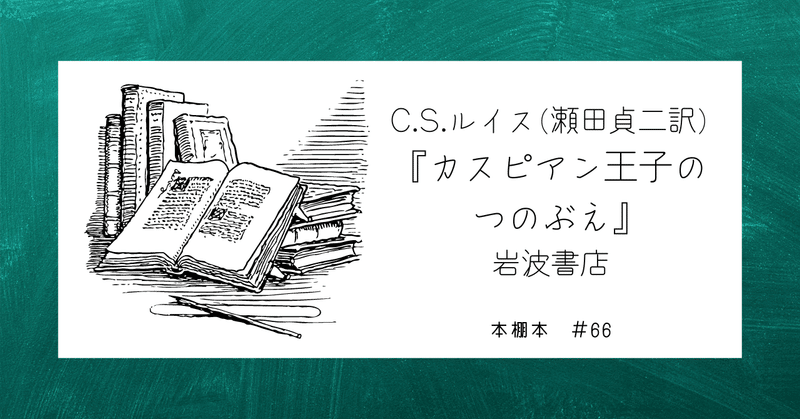
「むかし、ピーター、スーザン、エドマンド、ルーシィの四人の子どもたちが、ふしぎな冒険をしたお話は、『ライオンと魔女』という本に書かれています。」
英国トリビュートが続きます。
初っ端から前作の宣伝とはやりよる、という気持ちになってしまうのは、わたしだけでしょうか。
いままでそんなことを考えたこともなかったのですが、「その辺りの話は、この間発売されたDVDを確認してくれ」という言葉が頭をよぎりました。
ごめんて。
さて、そんなわけで「ナルニア国年代記」2冊目です。

C.S.ルイス著、瀬田貞二訳『カルピア王子のつのぶえ』(岩波書店、1996)
私がも持っている版は1996年のものですが、日本語の初版は1985年ですって。
そして原書が出版されたのが1951年。
ということは、まだジョージ六世の時代…… 出版年が誰の治世だったかを考えると、ものすごくむかしの物語なのだな、と感じます。
この頃は英国は「国王」が当たり前だったのか。
呼び戻された英雄たち
古の英雄が現代に(あるいは物語時点の現代に)呼び出される話は数多くありますし、今やゲームでも当たり前のことです。
わたしは見ていないんですが、「パリピ孔明」とかもそういう感じですよね。
で、この物語で起こるのはそれとは真逆のこと。
ピーターがいうところの、「まるでぼくたち、十字軍か、アングロ・サクソン人か、古代ブリトン人か何かなのに、いまのイギリスに立ち戻ったみたいなもんだな。」(p. 52−53)でした。
四人は、今ではナルニアの伝承にのみ残る、ほとんど伝説上の王と女王で、でも見た目はイギリスにいたときのまま、これから学校に戻る途中の子どもの姿で、そのふしぎさは本人たちよりも、周りの人たち、つまりオチ・カやカスピアンのほうが強く感じているようです。
また翻訳の話してもいい?
いいよ。
わたし、この「オチ・カ」という訳語も大好きなんですよ。
これは「おちいさいかた」という言葉の略で、そもそも小人のトランプキンが、四人がカスピアンの危機を救う力になるとは信じられず(そりゃそうだ)「おちいさいかたがた」と呼んだのが元になっています。
それで四人はそれぞれの能力をトランプキンに示して、彼らがたしかに古の王と女王であることを示したのですが、エドマンドが悪ふざけでトランプキンを「おちいさいかた」と呼んで、しまいには「オチ・カ」と縮めたあだ名にしてしまったのでした。
英語では、“Dear little friends”からの“Dear little friend”で、“DLF”となるのですが、これを「オチ・カ」としたのは、さすが瀬田先生だなあと思います。
何度でもいいますが、わたくし瀬田信者です。
あとは穴熊の松露とりとかね。
すごくいいですね。
松露というのはトリュフのことで、かれの英語の名前はTruffle-hunterですが、やっぱりこれをカタカナで「トラッフルハンター」としては呼びにくいし、ましてや「トリュフハンター」なんてしても間が抜けていると、わたしは思ってしまうわけです。
かれはやっぱり「松露とり」ですよ。
以上、瀬田訳のお話でした。
リーピチープ!!
『カスピアン王子のつのぶえ』と、続く『朝びらき丸東の海へ』で大活躍するのが、ネズミの族長、騎士のリーピチープです。
先日発売の『十二国記ガイドブック』の小野主上インタビューで、「ネズミといえばリーピチープしか思いつかなくて」というようなことをおっしゃっていましたが、それほど印象が強いのがいいですね。
もちろん、リーピチープと楽俊は全く別のタイプのネズミになったわけですが。
リーピチープ、好きなんですよ。
礼儀と礼節を重んじ、騎士の気高き心を持ち、一族のものに慕われ、誰よりもアスランと、ピーターたち古の王を信じ、己の使命をまっとうするその姿は、体の大きさなどまったく関係ありません。
いえ、体が小さいからこそ、周囲に侮られないようにと、より己を律しているのかもしれませんし、尻尾という名誉を尊重しているのです。
アスランへの信頼
わたしはこの物語を読むたびに、自分ははたしてルーシィのように、アスランを信じてついていけるだろうか、と考えてしまいます。
アスランを見たのに、まわりの「常識的な」意見に流されてしまわないだろうかと。
たったひとりで、アスランについて行くことができるだろうかと、思わずにはいられません。
ルーシィとアスランの再会のシーンほど、美しいものはありません。
それが味方か敵かなどと、つゆ考えず、ルーシィは、ライオンのほうにかけよりました。そうしなければ、胸がはりさけそうでした。次の瞬間、ルーシィは、ライオンにキスをして、できるだけしっかりとふかくその首に腕をまわし、美しくゆたかなつやつやしたたてがみに、自分の顔をうずめておりました。
「ああ、アスラン、アスラン、大好きなアスラン。」ルーシィはすすり泣きました。「とうとうお会いできましたね。」(p. 200)
わたしはふわふわでふかふかでつやつやなものが大好きなので、ルーシィのようにアスランに飛びつくことができたら、どんなに幸せかと思います。
このあと、ルーシィはきょうだいたちを連れてくるように言われます。
ピーターもエドマンドもスーザンも、はじめはルーシィの言葉を疑っていて、アスランを見ることができませんでした。
これはとても印象的な出来事です。
そこにかれがいると信じてはじめて、その姿を見、声を聞くことができるのですから。
ルイスは決して、「ナルニア国物語」を信仰書のかわりとして書いたのではありません。
これはかれの中の「大切などこかの国」のひとつであり、物語の中にはギリシャ神話の神々や幻獣たちもたくさん登場します。
英文学者であったルイスらしく、多くの古典の跡が見られます。
それでもなお、この世界の創造主、東の果ての大帝の息子、ナルニアの真の王であるアスランへの信頼と忠誠心とが、物語の根底を流れています。
「ナルニア国年代記」を読むたびに、ああ、アスランに会いたいなあ、という憧憬で胸がいっぱいになります。
わたしは果たして、アスランに会ったときにアスランを見ることができるでしょうか。
その声を聞くことができるでしょうか。
そのあとをついて行くことができるでしょうか。
そうありたいと、心ではいつも思っています。
放っておいても好きなものを紹介しますが、サポートしていただけるともっと喜んで好きなものを推させていただきます。 ぜひわたしのことも推してください!
