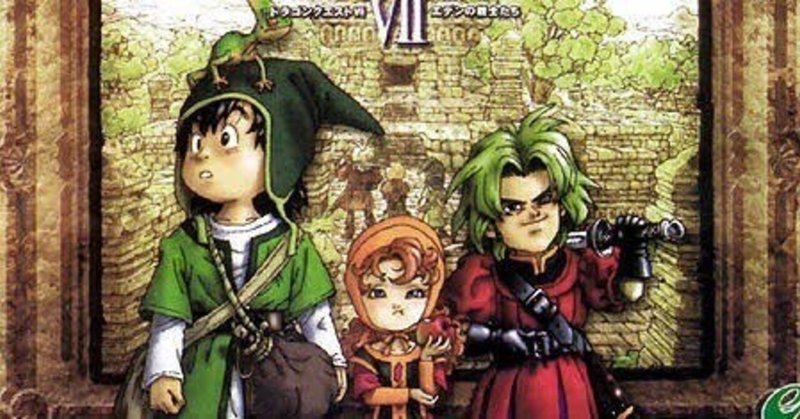
【ドラクエ7】 屈指の名作RPG「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」 について語る 【ひとは、誰かになれる】
希望のかけらを求めて初投稿です。
「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」は、発売から20年経った今でも度々語り草として独り歩きした部分が悪目立ちし、賛否両論と言う評価で落ち着いてはいますが、"否"の部分が誇張されすぎていて過小評価になっている印象です。
キーファ・グラン、彼はその最たる例で、今現在インターネット上で彼の名前を口にした途端謂れのない言葉が飛んできます。
特に「オルゴ・デミーラ説」などという戯言を盲信するがあまり、ただの悪ふざけが今ではあたかも裏設定のように語られているのはドラクエ7のストーリーを真面目に追ってない証拠なんじゃないでしょうか。この論者絶対キーファ好きじゃないの伝わって来るので最悪です。
不当にドラクエ7が貶められる、そんな現状に嘆いてばかりだったので、今日は趣向を変えて如何にドラクエ7のストーリーが素晴らしいのかという題材でとにかくこの作品の良さについてインターネット上にぶちまけたい。オタク語りがしたい。ただそれだけの記事です。もちろんネタバレありで進行します。
・言うほど鬱じゃないストーリー
少年少女が好奇心で始めた冒険は、偽りの平和に揺蕩う楽園を打破し、果てには魔王が秘匿した世界の大いなる真実へと辿り着く。その道中、多種多様な人々の考え方に触れる中で、自分の生きる道を問い、迷い、見つけ…それぞれの目標に向かい歩み続ける…。
ドラクエ7のストーリーと言えば、やれ長いだのやれ鬱だのという意見が飛び交いますが、私はこれに断固として反対したい。
そもそも長くて何が悪いのかが分からないのは置いておいて、確かに他作品と比べれば、魔物による脅威、恐怖を描くドラゴンクエストではないかもしれない。
何故なら魔王オルゴ・デミーラは人間の負の感情を鍵に大陸ごと封印するスマートな手法で世界を手中に収めて来たからだ。
これがシリーズ屈指の有能さで、暴力による統制ではなく、人々の不信感を煽り、対立させ、気力を奪い、負の感情が渦巻くだけでもうオルゴ・デミーラの意のままだ。
その手法により当時無人島だったエスタード島に漂着したコスタールの民を除き全ての大陸を封印したので、実質ほぼ勝ちなのである。(デミーラ説、エスタード島を封印しなかったのは主人公が居たからという主張、時系列めちゃくちゃで草)
なぜ実質かと言うと、それは後述するが神様が人間の可能性を信じ、賭けに勝ったから。
そして、その過去コスタール民の子孫というのが主人公達…という訳。
ちなみに、グランエスタード城に王者の剣があったり、キャラバンハートで竜王にキーファが「ロトの匂いがする」など言われたりと、アレフガルド住民が何らかの手段で異世界転移してきてコスタール民と途中から混ざった説を私は信じています。

3DS版では大幅にカットされている序盤ですが、私はここに時間がかかることに意味があると思っているので勿体ない。
やっとの思いで謎を解いた神殿からいきなり過去の世界に飛ばされ、巻き込まれていく…ただの冒険ごっこから本当の冒険になる瞬間。
真実を暴きたい、知りたいという強い意志が無いと辿り着けないようになっている。
そして、一番最初にたどり着く過去ウッドパルナ。
ここで展開されるエピソードなのだが、「こんな長い謎解きの後に暗い話見せやがって」と辞めてしまうプレイヤーも多かったそうで。
この村は過去に魔物に襲撃にあった際、1人立ち向かった英雄パルナを誰も助けに行ず死なせてしまったのが原因で、恨みを抱いた妹のマチルダが魔王に見初められて魔物と化してしまう。というのが背景だ。
ここで勘違いして欲しくないのだが、村人がパルナを助けに行けなかった事について、単に悪と捉えるのはナンセンス。
見殺しにしてしまったのは事実だが、悪意を持ってパルナを切り捨てた訳では無い。
魔物に立ち向かうのは相当勇気の要ることだし、何より悪いのはこの状況を見てほくそ笑んでいる魔王であろう。(ずしおうまるに農具で渡り合える下ライフコッド村民がヤバいだけ)
そう、「人間の悪意〜」とかそういった類の言い方より「弱さ」と表現するのが正しいのでは無いだろうか。誰もがこんな事態に相対した時、完璧に正しい判断が出来るだろうか?そんな事はないと思う。間違っていると突き放すには少々厳しいのでは無いか。私はそう思う。

そして、そのマチルダの命が封印を解く鍵になっているのだが、ここで手にかけるも退くも自由。ただ、最終的にどの選択をしても彼女は自ら死を選ぶのには変わりがない。人の心が残っている敵、と言うあまりにも特異な例である彼女が、人のまま死ねたのはある意味救いと言うべきか。

悲しい話ではあるが、自らと似た境遇のパトリックを助け、最後に彼の手の元に形見である木の人形が渡るのと、マリベルから貰った花の種が、決して咲くことの無い墓の周りに咲いたのは、本来の優しい人として心の行動が報われた瞬間のようで、これで少しは彼女も浮かばれよう。
最初の村で起こる事件としては些か重いのは事実だが、他のナンバリング作品と違い何の目標もなく始めた彼らの、言ってしまえばお遊びとは違うんだという事実を突き付けるには必要なピースであると私は考えている。
自らの判断で生死を左右する感覚、平和な自分たちの現代の世界とは違う、失われた過去の世界の命運を委ねられた責任感。何もかもが真に迫った事実である事を認識すべく、まずウッドパルナのエピソードが最初にあるのは名采配と言っても過言では無い。
フォロッドやルーメンがトラウマエピソードとして語られているのも首を傾げている。
私はこの2つのエピソードは7の中でもトップクラスに好きで、人ならざるものの愛を感じられる感動寄りのエピソードだと捉えているのだが、世間はそうでは無いみたいだ。

現代フォロッドの王はエリーを分解、解析して技術の発展を図ろうとしていたのも国を考えての事。果てには考えを改めてエリーとゼボットに理解を示し、そっとしておく決断をしたのは粋な判断。フォロッド地方のストーリーは人間の善し悪し両面の描写のバランスが絶妙。
エリーの健気すぎる愛を汲み取ってやれる人間の粋さと、最後にエリーが零した感情に何度見てもボロボロ泣いてしまう。
ここで「死の概念」についてパーティメンバーの意見が聞けるのも良い。哀しくとも優しい、永遠の愛の話である。

過去ルーメンは民がチビィを討伐しようとしたのは町を思っての事だった。結果的にチビィが町を救ったのは事実であるが、何度も滅びの危機が訪れたルーメンにおいて何がトリガーになるか分からない。闇のドラゴン、ヘルバオム襲撃後だからモンスターを恐れるのは人としては真っ当な反応であろう。
何度も救っても別の原因が破滅を導いてしまうこの町で、駆逐しようとしていた人ならざるモノの功績で救われたのは全く不思議な因果である。自らを犠牲にこの町を救ったロッキーやチビィには敬意を評したい。
そして、7と言えばレブレサックがあまりにも悪い意味で有名なので背景は割愛するが、前述の通り人間の「弱さ」をこれでもかと描写している。
正直私はレブレサックのエピソードを完全に否定するのは間違いだと思っている。
過去から現代に至る過程の時代で村の歴史を隠匿しておこうとした判断は、非常に苦しいが仕方ないと思う。戒めとして残しておくにはあまりにも罪深く、事実を受け止めきれなかったのであろう。本当の歴史を記した石版を破壊するシーンも含め、胸糞悪いシーンなのは私もそう思う。
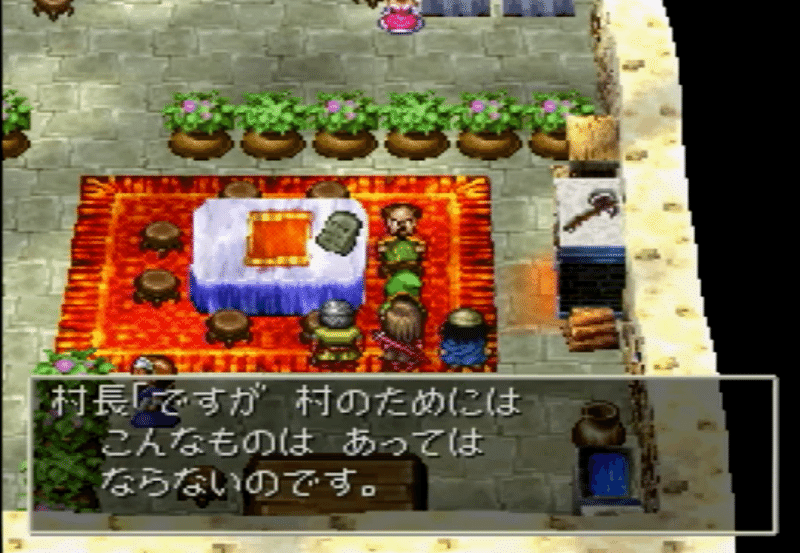
ただ、村のことを思って今更この事実を公表する身にもなってみると恐ろしい。私が仮に村長だったら耐えられないと思う。そういった人としての「弱さ」が現れてしまっている顕著なエピソードだ。

しかし、単純に「人間の本質は悪」で終わるのでは無く、真実を知った子供達が後世に正しい歴史を遺すかもしれない、と言う一筋の希望があるのが素晴らしいのだ。
完全に悪とするならば過去の時点で神父にした仕打ちを反省しないし、現代でも子供たちは本当の歴史を信じなかっただろう。そういった二面性、多様性を併せ持った生物が人間なのだから、人間らしいと言えばそうだし、人間賛歌のテーマを描く上にはレブレサックのような悪い例も欠かせない話だと考えている。
総じて鬱、鬱と騒がれる割にはしっかり希望を持たせた終わり方をするので、胸糞だけで終わる訳では無い事は理解してくれたかと思う。
更に言えば個々のエピソードを繋げてみて全体を通したエンディングも含め全く鬱で終わっていない。なんならドラクエで1番希望に満ちた「平和」「日常」を享受したエンディングである。
・様々な人間の営み、思想、そして側面
ドラクエ7はロト三部作、天空三部作から続くシリーズ7作品目のタイトルであり、今まで以上に新しいドラゴンクエストである事が求められた。
画期的な「石版システム」は、パズルのように散らばった石版を組み合わせると、この世に唯一存在する島と信じられていたエスタード島から過去にタイムワープし、その過去を救うことで魔王に封印された各地が復活し、徐々に本来の形を取り戻していく…というもの。
今までのナンバリングタイトルは凡そ大河形式の地続きで壮大なストーリーを体験することが出来るが、ドラクエ7は違う。
4こそオムニバス形式で各キャラの章を経て、最後にその仲間達が集結していくカタルシスがあるが、7は所謂「1話完結式」だ。
失われた過去の世界を救う事で現代の平和へと繋がる、小さな冒険の積み重ねで構成されている。
だからこそ彼らは1本の大きい筋を辿って冒険している訳では無い。好きな人が出来たらその一族を守るために過去に留まってもいい。親が心配なら実家で一緒に過ごしてやってもいい。それは誰に言われたのでもない彼らが決めた人生であり、ドラゴンクエストなのだから。
その過程で主人公一行は過去と現代を行き来し、各地に赴き、様々な人々と出会い、様々な考え方に触れる。
その中には悲しき女戦士、へんくつな科学者、他人を私欲の為に手にかけるもの、高潔な神父、卑怯な村民に隠匿する村長、etc…普通に過ごしていれば出会わないような人たちばかり。
この人たちが「どう思い、どう生きる(た)のか」を自分たちだけが見届けられる。
人々が織り成す歴史の営みを一瞬の内に自分たちだけが事態を認知し、等身大の少年少女が成長していく。
自分たちが介入した過去の事件がどう伝わっているのかも見ものだ。無かったことになってたり、伝説になってたり、ちょっと細部が違ったり。現代に復活するまでまでも幾回もの世代交代を経る中でも伝わり方は人それぞれ、場所様々。
そう、どんなに卑怯で嫌な人でも、それはまさしく人間の側面である事は紛れもない事実で、また過去を必死に生き抜いた気高い人も同じ人間という種族の一面である事は間違いない。
そんな「弱く醜い」部分と「強く美しい」部分をこの冒険で何度も同時に見ることになる。

更にこの「人間の側面」についてを補強してくれるのが「会話システム」。
私はこれが本当に心から好きで、住民に話しかける都度仲間にも話しかけて会話を楽しむ。時には語り草になるような会話が任意でしか聞けない数テキストで終わる程で、その分量は計り知れない。
その会話文の全てを堀井雄二が担当しているのがまた凄い。8からは分業になってしまうので7までの文化となってしまったのが残念。戦闘中に会話ができるのもドラクエ7が唯一で、これにより仲間の掘り下げがシリーズでも異常なほど行われている。
私は、この堀井雄二の書いたテキストこそがドラクエの世界を深堀りする随一の要素だと捉えていて、主人公が話しかけなければ見過ごしてしまうようなテキストが殆どである。その余分さ、無駄加減が実に素晴らしい。
こう言った自由さが「遊び」を尊ぶ堀井雄二らしい、彼の思想が最も顕著に現れている部分と私は考えている。「人生はロールプレイング」とはまさに言い得て妙。
・「ひとは、誰かになれる」というキャッチコピーとそのエンディング
このキャッチコピー、最も如実にこの作品を体現してるものだと思います。
ドラクエ7は人間賛歌のお話。
神様は人間の持つ無限の可能性を信じ、自らが敗れた時のために最後の楽園になぞの神殿を建てた。いつの日かその楽園から抜け出そうとする自由意思を持った人間が現れると信じて…
神「ここまで来た そなたらなら
すでに知っておろう。
わしは 戦い そして敗れた。
神「いや 正確にいうと
相打ちじゃったのかも知れんかの。
神「わしは 最期の戦いを前に
未来への希望を そなたら
人間たちに たくした。
神「わしが ほろびても
このわしに かわって
世界をとりもどしてくれと…。
神「それが あの神殿じゃったと
いうわけじゃよ。
神「そして そなたらは 見事に
それをやりとげたといって
いいじゃろう。
神「もはや わしの出る幕はない。
そなたらの未来は そなたらが守れ。
それが いちばんじゃよ。
先の通り、主人公たちは冒険の過程で様々な人間の側面の触れた。弱く醜い部分も、強く美しい部分も確かに人間。それを受け止めてかつ前に進む勇気を持つ人間、即ち世界を救う勇者になる。弱い部分をも受け入れるからこそ説得力がある。
しかも、ドラクエ7はゲームシステム的にも唯一「職業:勇者」への転職条件がフラットだ。
勇気ある者、勇者。血統や一族は付随する要素でしかない。大切なのは、どう在りたいかという人の強い意思。


更に言えば人の無限の可能性を問いた今作であるが、勿論必ずしも「勇者」である必要も無い。
最終的に主人公は魔王を倒し世界を救った勇者となるのだが、シャークアイの跡を継いでマール・デ・ドラゴーンの次期総領にもなれた。更にはマーディラスのグレーテ姫とくっついて王になる事も出来た。
だが、主人公が選んだのは、義理の父ボルカノの跡を継ぎ漁師になる事。
これが本当に本当に素晴らしくて、あえて特別な待遇を手放し、自分の手で掴み取ったかけがえのない今まで通りの日常を享受し、噛み締めるること。
何にでもなれるからこそ、あえて漁師になる。世界を救った勇者とは言えど、漁師としての腕はボルカノには及ばない。実父であろうシャークアイや一族を思う気持ちこそあれど、今まで育ててくれた両親やこの村と共に生きたい。それが主人公の生きる道だった。


それはエンディングの最後のイベント。
漁に出た主人公と、それにこっそり着いてくるマリベル。これがオープニングの再現なのは言うまでもないが、漁の最中に網に掛かったのはキーファから主人公に宛てた石版だった。
石版に始まり石版に終わる、エデンの戦士たち3人で始まり3人で終わる。なんともよく出来ている。
その内容なのだが、それはキーファがどれだけ離れていても親友だということ。
そう、主人公はキーファの親友。これ、"誰かの"「誰かになれる」なんです。
「勇者」で、「海賊の息子」で、「水の精霊の一族の末裔」で、「漁師の」の主人公がずっと変わらなかった唯一の存在。"キーファの"「親友」である事。
「ひとは、誰かになれる」は関係性すら孕んだ意味合いを持つ。人間の営みや思いに触れ続け、無限の可能性を問いたドラクエ7だからこそ、「無限の可能性を説き誰もが勇者になれること」と「不特定多数の個人同士の関係性」がゲームシステムとストーリーの上で同時に成り立つ。
よってドラクエ7のエンディングとキャッチコピーはシリーズ最高傑作と言っても差し支えないだろう。
・終わりに
年始早々「スクウェア・エニックスって元は別々の会社だったの!?」という、ジェネギャ感満載のツイートが受け(恐らくショッキング的な意味で)ドラクエやFFが何かと話題になりましたが、私の生まれた年に合併してるんで今年で22年経つんですよね…。
そりゃ知らない世代も出てくる…と言うか、もうそもそもドラクエはおっさんのゲームになっていて完全にコンテンツとしてはなりを潜めています。
ナンバリングタイトルで言えばドラクエ7は最後のエニックス作品になる訳ですが、「ドラクエは7まで」と主張している層の気持ちは正直理解出来ます。同意はしませんが。
やはり合併以前以後で大きく情勢は変わっているので、やはり古参ファンは思うところがあったんでしょう。実際スクエニ有り得ないくらい落ちぶれてますし…やっぱりクロノ・トリガーって凄かったんだな…
— もやぴっぴ(Ⅷプレー中) (@moyashisousaku) December 29, 2023
↑神のイラストだからみんな見て
この記事を読んで少しでもドラクエVIIの素晴らしさもといマリベルちゃんの可愛さが伝わったら幸いです。
今年もよろしくお願いします。
おわり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
