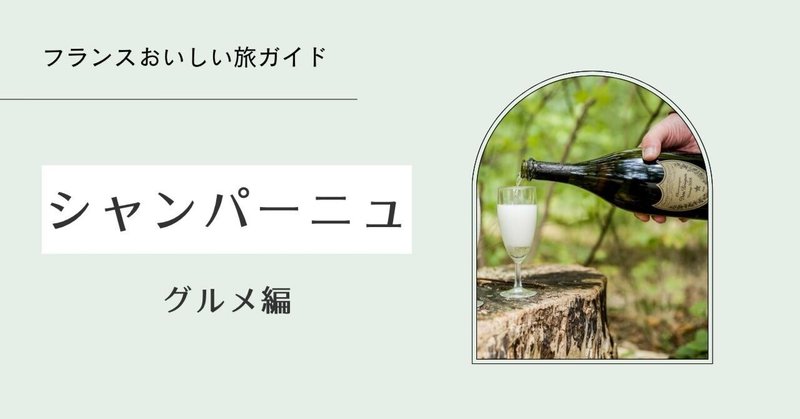
【フランスおいしい旅ガイド】シャンパーニュ=アルデンヌの郷土料理
かつては不毛の地と呼ばれたが、今では土地改良のおかげで地味も肥え、豊かな穀物畑やテンサイの畑がブドウ栽培地の隣に広がる。羊や豚の飼育も盛んで、これらの肉を使った料理は、シャンパーニュ地方のスペシャリテの1つとなっている。この地方で作られるシャンパーニュも、もちろん料理にも使われる。
シャンパーニュを使った料理
○鶏の蒸し焼き シャンパーニュ風味Poulet à la Champenoise
炒めた玉葱とニンニクのみじん切りに、つぶした鶏肝と肉の細かなすり身、さらに少し煮つめたシャンパーニュを加えてよく混ぜてファルス(詰め物)を作る。これを鶏に詰めて大きな鍋に入れ、シャンパーニュを少量加え、焼き色をつけながら蒸し焼きにしたもの。
○鶏の煮込み シャンパーニュ風味Poulet au Champagne
ぶつ切りの鶏をエシャロットとともにバターで黄金色に焼き、小麦粉をふりかける。シャンパーニュをたっぷり注いで調味したのち、マッシュルームを加えて煮込み、卵黄と生クリームでソースをつないだもの。
○カキのシャンパーニュ蒸しHuîtres au Champagne
カキは殻の中の汁とシャンパーニュで火を通し、殻に戻す。煮汁に生クリームとバターを合わせてカキにかけ、サラマンドル(上火だけのふたのないオーヴン)でさっと焼き色をつける。フランス中のレストランで出される豪華な前菜である。
○シャンパーニュ風マトロートMatelote Champenoise
マトロートは1種類または数種類の淡水魚のワイン煮。 Matelot「水夫、水兵」の転用語。この地方ではシャンパーニュをたっぷり使うので、他地方の赤ワインを使うものに比べてまろやかで軽い味に仕上がる。ウナギ、ブロシェ(川カマス)、コイなどの淡水魚を適当な大きさにぶつ切りして、香味野菜と香辛料とともにシャンパーニュの中で、短時間のうちに煮込む。
肉料理
○サント・ムヌー風豚の足のグリエPieds de Porc à la Sainte-Menehould
サント・ムヌーはロレーヌ地方寄りの人口6000人ばかりの町で、シャンパーニュ生みの親といわれるドン・ペリニョンの故郷である。豚の足は下ゆでして臭みをとり、だし汁の中に人参、玉葱などと一緒に入れて火にかける。骨と皮から出るゼラチン質でとろとろになった煮汁が肉にしみ込むまで、弱火でゆっくりと煮込む。水気を切ってから、溶き卵、パン粉をつけて、グリルでこげ目をつけながら香ばしく焼く。マスタードなど香りをきかせたソースがよく合う。1791年6月21日、ルイ16世がヴァレンヌで革命軍に捕らえられたのは、逃亡中に立ち寄ったサント・ムヌーでこの豚の足を食べていて貴重な時間を浪費したからだとのいわくつきの料理。
○シャンパーニュ風ポテPotée Champenoise
塩漬けの豚のもも肉とばら肉、インゲン豆、人参、カブ、キャベツ、ジャガイモなどをたっぷりと入れてゆで煮したもの。この地方ではブドウ収穫期に食べるのが伝統。
○シャンパーニュ風羊の蒸し煮Quartier de Mouton à la Champenoise
羊の肩肉をワインと酢、香味野菜の中に漬けておき、漬け汁ごと蒸し煮したもの。
○タンポポのサラダSalade de Pissenlits au Lard
洗って水気を切ったタンポポに、かりかりに炒めたベーコンとその脂、さらにワインビネガーなどをふりかけた生温かいサラダ。ゆでたジャガイモの薄切りを添えるとよい。
○トロワのアンドゥイエット 玉葱のフライ添えAndouillettes de Troyes aux Oignons Frits
その昔、貧しい人々にただで分け与えられていた豚の内臓、胃を細かく切り、豚の腸に詰めて作るアンドゥイエットは、ソフトで舌触りのよいオーブ県トロワのものが高く評価されている。グリルで焼いて、ぱちぱちとはぜている熱々のうちに玉葱のフライと一緒に食べるのが一般的。
○アルデンヌの生ハムJambon des Ardennes
豚のもも肉とばら肉を丸ごと塩漬けにし、乾燥させてから少し燻製したもの。
○ジュートJoute
キャベツの料理。chou「キュベツ」が語源。キャベツを塩ゆでしてから小さく切り、ベーコン、玉葱とともに煮込む。ソーセージや挽肉団子などのつけ合わせにする。
○トゥイイ・ド・ヴァンディTouillis de Vandy
シャンパーニュ地方ヴァンディの小麦粉入りオムレツ。touiller「木べらで混ぜる」の派生語。
野鳥獣(ジビエ)料理
○アルデンヌ風ツグミの蒸し焼きGrives à l'Ardennaise
ツグミはアルデンヌ地方で特に珍重され、よく食べられている。料理名にアルデンヌ風とつくと、ココットと呼ぶ陶製の鍋を使ったネズの実風味の料理が多い。この料理は、内臓を抜いて豚の背脂を巻いたツグミを、バターで色づけるように炒める。ネズの実、セージの葉を入れ、塩、胡椒して鍋にふたをし、弱火でゆっくりと蒸し焼きする。小さく切った食パンをバターでかりかりに焼いてカナッペにし、上にツグミをのせて出す。ツグミはブドウ収穫期の10月頃が1番おいしい。
○ツグミの蒸し焼き シャンパーニュ風味Grives au Champagne
炒めたツグミに、シャンパーニュとレモン汁、ネズの実で作ったソースをかけてオーヴンで焼いたもの。
○ツグミのロースト クルート盛りGrives Rôties Sauce Périgueux
練りパイ生地で作ったケースの中に、ツグミの肝をベースにして作ったファルス(詰め物)を詰め、上に内臓を抜いてローストしたツグミを盛って、トリュフ入りのソース(ソース・ペリグー)をかけたもの。
○ウズラのブドウ葉包みの灰焼きCailles sous la Cendre
ウズラは、春の訪れとともにアフリカから渡ってきて、秋風が吹き始めると帰ってしまう。「最高の貴族階級に属する野鳥」とたたえられたこともある。この料理は、ウズラの内臓を抜き、フォアグラやトリュフの入った上等なファルスを詰める。1羽ずつブドウの葉、豚の背脂、バターを塗った硫酸紙の順にくるんで、熱い灰の中に埋め込み、30~40分焼く。
○子鹿のもも肉のロースト Cuissot de Cheveuil Rôti
鹿は晩秋から冬にかけてがおいしい。とくに若いうちのもも肉、鞍下肉はやわらかい。もも肉なら骨つきのままローストにする。鞍下肉からとった部分はマリナード(香味野菜と香味料入りのワイン、酢、油を合わせたもの)に、1週間ほど漬けた後、メダル形などに切って焼き、鹿の骨からとっただし汁を煮詰めてミルティーユ(コケモモ)、スグリなどのジャムを加えたソースをかける。いずれも焼き加減は、肉の真ん中部分がまだ生でバラ色になっていることが肝心。
○子イノシシのローストRôti de Marcassin
イノシシで1番おいしいのはマルカサンと呼ばれる子イノシシ。臭みをやわらげるために、香りの強いマリナードに長時間漬けておいてから料理する。鹿とか豚の調理法が多く応用できるほか、鞍下肉や肩肉はローストする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
