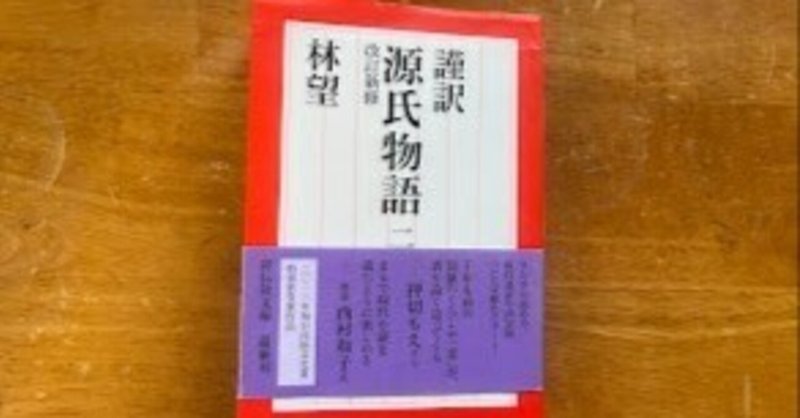
紫式部「謹訳『源氏物語2』」(1008年頃)
2巻では源氏の君の18歳から25歳までを扱う。
この巻では、有名な車争いや、その後葵上が六条御息所に呪い殺されるエピソードなどがある。また、幼女だった紫上が成長し、源氏の妻となる。
また、桐壺院が亡くなり、朝廷の勢力図が変わる。右大臣家が権力を持つようになり、左大臣家側である源氏も抑圧される日々を送る。
源氏の女遊びばかりだった印象の1巻に比べて、きちんと物語が展開しはじめている。
まだまだ先は長いのでこれから変わるかもしれないが、ここまで読み進めてきたところでは、「源氏物語」とは広い意味でのコミュニケーションについての物語なのだという理解に至った。
特徴的なのは、作中人物が互いに歌を贈りあうことで自らの気持ちを伝えるところだ。それも、古い歌の引用であったり、四季折々の風景に気持ちを重ねたりする。その引用のセンスであったり、想いを重ねるアイテム(植物や山など)の選び方によって、人物が評価される。また、どんな紙に歌をしたためて、どのように渡すかという部分も評価対象になる。
こういった世界では本当の自分をさらけだす、などというのはとんでもない話だ。そのため「源氏の君」「葵上」といった名前も本名ではないのも理にかなっている。本作では登場人物がいわばハンドルネームで登場するわけだが、現実の世界はどうだったのだろうか。それも興味のあるところだ。
関係があるかどうかわからないが、アーシュラ・K・ル=グウィンの「ゲド戦記」でも「本当の名前は他人に教えない」というルールがあった。本当の名前を知られると魔法で攻撃されるからだ。一種の言霊思想と言えよう。
六条御息所が葵上の本当の名前を知っていたかどうかは不明だが、憎しみによって他人を呪い殺すというのは「本当の自分」をさらけだしている、とも言える。この物語において数少ない「生身の人間」が描かれているエピソードとも言える。つけくわえるなら、葵上を見舞って生霊の正体を悟った源氏は、六条御息所というペルソナを演じていた女性の真実の姿を目撃したという意味で、他者とのコミュニケーション能力が非常に高いのは間違いないところだろう。
源氏物語に書かれている世界は、SNSの世界にも通ずるものがある。
インフルエンサーと呼ばれる人気者たちは、ユーザーの気分を高揚させ、もっと見たい、もっと知りたいという欲望を刺激する。時代の空気を感じ取り、みんなが欲しいものを理解しやすくて楽しい形で提案する。それは源氏物語で行われていることとなんら変わりはない。現在のレッドオーシャンの争いは、1,000年前から存在していたのだ。
そう考えると源氏物語に農民や村人といった賤しい人々が登場しないのもわかる。彼らはセンスなど持ち合わせていないから最初から競争に参加できないのだった。SNSで言えば、アカウントを持っていないとか、コンテンツを生み出す能力がない、といった人々だ。人気インフルエンサーの争いを描く物語に、アカウントを作れない人のエピソードは不要なのだ。
SNSの話はわかりやすいので取り上げたが、実際の社会も同じだ。
仕事のできる人とできない人の違いを考えてみると理解しやすいと思う。これに関しては墓穴を掘りたくないので細かいことは書かないことにしよう。
それはともかく、源氏物語における、仮面を通じて他者とかかわる社会は、京都という土地のイメージにぴったりで、昔からそういう土地柄だったのかなとも思う。逆に、この物語は京都という土地だったからこそ生まれたのではないか、とも言えるかもしれない。
サポートいただくと、よりよいクリエイティブにつながります!
