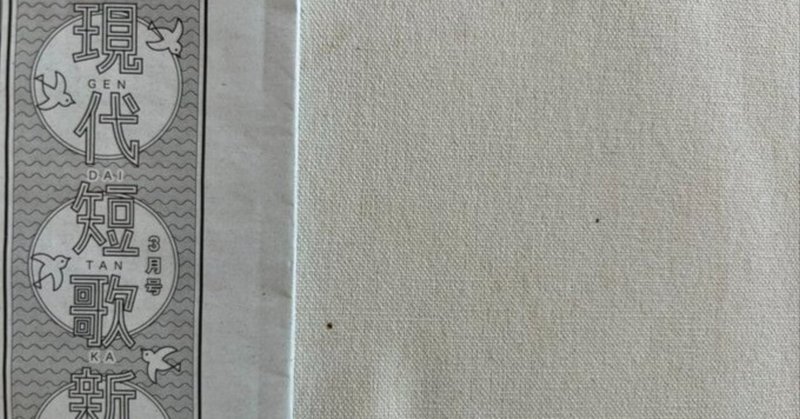
『現代短歌新聞』2024年3月号
①「インタビュー 永田紅氏に聞く」
改めて若山牧水賞おめでとうございます。
〈作者の属性や人生を詠むことを排除する向きがありますが、人生を詠んでいるからつまらないということは決してなくて。そもそもこの二分法が私は嫌いで。境涯派でも言葉派でも、いい歌はいいし、つまらないものはつまらない。〉
ほぼ同意。ただこの境涯派(人生派)と言葉派という用語は、用語だけが一人歩きしているようにも感じている。この言葉が論に使われているのはあまり見たことがない。
②「永田紅」
〈一首の屹立性は大事だし、一首で人の心に刺さるというのは短歌という詩型の本来の形として大事なんだけども、言葉だけでアクロバティックな目立つ表現を求める風潮はよくないと思っています。ゆったりと幅の広さ、厚みで見るべきだなって。歌集単位での厚みというものを私は最近、大切に思っているところです。〉
これもほぼ同意。一首屹立の歌の良さはもちろんあるが、その一首が連作の中の一首の方が私は好きだ。連作単位で歌を捉えたい。最終的には永田の言うように歌集での厚みということになるのだろうな。
③臘梅の花咲く枝をくるしめる雪という理不尽を払いぬ 齋藤芳生 自然の営みは何の意図も無くても、三句の感じ方のように、人間には理不尽に見えてしまう。自然災害などはその最たるものだろう。梅の枝に積もる雪ならばそっと払うこともできるのだが。
④まがなしきいのち生(む)まるる春にして笑ふこどもの顔のかがやき 本田一弘 命が生まれる春という季節。命がもう一度芽吹いて育とうとしている。その春に笑う子供の顔は、かがやきという表現にふさわしい。それによって失われた命により強く思いを馳せる。
⑤永井正子「恐怖を共有して」
〈手付かずの自然が残る原風景として能登は2011年に日本初の世界農業遺産に認定された。裏を返せば、山や斜面に点在する集落と田畑。崖を穿ち、木々を伐採して通した半島を巡る一本きりの国道。〉
昔旅行した時の風景を思い出す。
〈能登から一度も出たことのなり高齢者が県外の施設や避難所に運ばれて行く。(…)心身ともに弱り果てている被災者がどうして自分でなかったと言い切れようか。今回のような地震は、日本列島のどこにでも起こり得るという。〉
頻発する地震に募る不安。共感しながら読んだ。
⑥佐藤文香「現代俳句採集」
〈干されてあまり日の経過しない若布を都会で食べる贅沢もある。この句集(中西夕紀『くれなゐ』)には「海賊も廓もむかし若布干す」という句もあり、干若布の歴史も思われた。〉
著者の海藻愛が楽しい文章。引かれた句から絵が浮かぶ。
⑦小塩卓哉「短歌文法道場 サ変動詞の使い方」
〈文語のサ変動詞「す」を見てみましょう。活用は、「せ(未然形)・し(連用形)・す(終止形)・する(連体形)・すれ(已然形)・せよ(命令形)」となります。〉
〈口語では、「し/せ/さ(未然形)・し(連用形)・する(終止形)・すれ(仮定形)・しろ/せよ(命令形)」と活用します。〉
口語の方が文法だけ取り出すと難しい印象だ。
⑧「集いの場 『キマイラ文語』を読む会」
〈著者の川本氏は「近代の歌人も現代歌人も文語助動詞をを正確には使えず、モダリティとして使っているのではないか」と新たに指摘した。〉
ここ取り上げられてうれしい。これについてはどこかで論じたいと思っている。


2024.4.1.~3. Twitterより編集再掲
