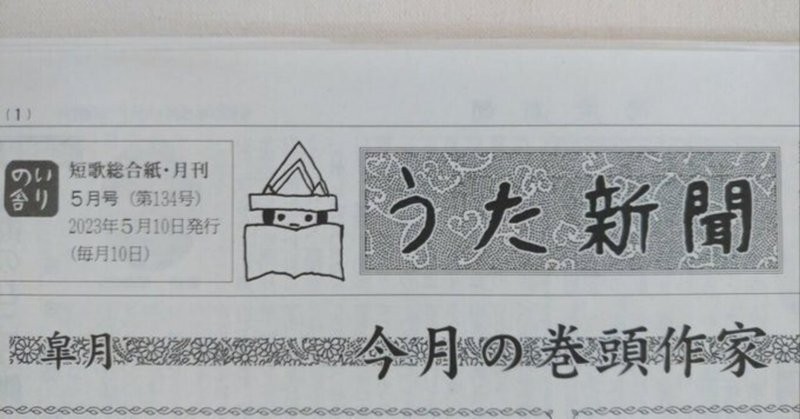
『うた新聞』2023年5月号
①命あるものが鏡にうつるという鏡の奥に昼はあかるく 奥田亡羊 おそらく生物と無生物という分類ではないのだろう。無生物であっても命を持つものが鏡にうつる。上句のように思う人物の発話を受けての歌と取った。「うつる」という語の奥深さも感じさせる歌だ。
②安田純生「青風短歌の山と川ー安田青風没後四十年」
脊に遠き海鳴りの音少年はいつもひとりのとき山に対く 安田青風
「白珠」創刊者の安田青風についての論。青風の歌とその背景となった風景が詳しく述べられている。
ふるさとの揖保の川原ぞおもほゆる青き蓬を摘みて来しかば 安田青風
ゆったりとした自然を背景に詠われる歌に心が和む。抽象的に詠われている風景にも実景が反映していることを安田純生の読みは教えてくれる。この論の最後のプリンの話もほのぼのする。
③松澤俊二「短歌(ほぼ)一〇〇年前『短歌三六五日』」
〈彼(石川啄木)は、一人一人の「いのちの一秒」こそが歌の資であること、その時間を表し得たときにこそ歌はメディアとしての特異な存在感を発揮しうるということを明瞭に意識していた。〉
〈今回取り上げる『短歌三六五日』は、そのように、「時」を記しとどめる記録媒体としての短歌の機能を前面に押し出し、形象化したもの(…)〉
一日に十首ずつの歌が並んでいる本だ。これを見ればその季節に詠われている自然や風物を味わうことができる。1930年発行ということだ。その当時の人々のものの感じ方も知ることができるだろう。自分の誕生日にどんな十首が並んでいるか、見てみたい気がする。
2023.5.14. Twitterより編集再掲
