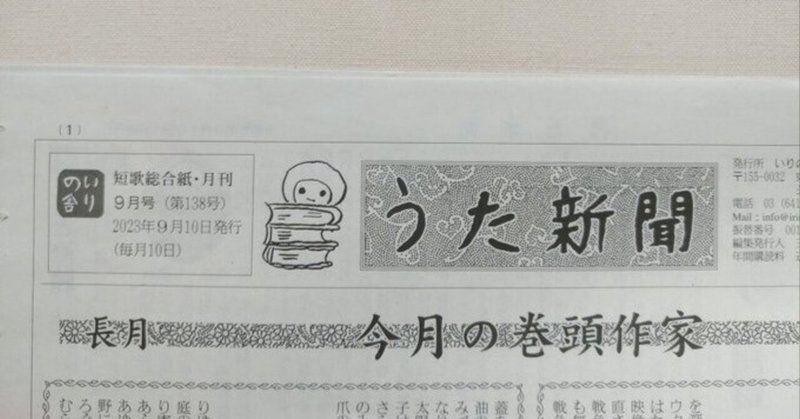
『うた新聞』2023年9月号
①山本登志枝「木俣修・没後四十年」
起ちても濤(なみ)かがみても濤どうしやうもなくて見てゐる高志(こし)の冬濤 木俣修
〈現実の冬波のうねりを感じさせる調べが(…)人生を生きる人間の心のうねりのようなもの、叫びのようなものとなり迫ってくる。〉
この歌、何だか現代的な感じがする。『呼べば谺』(1954)の歌だから、今から70年近く前の歌だが、初句六音、三句六音、三句から四句への句跨り、句跨り部分の口語体、三回繰り返される「濤」の語、などから今っぽい感じを受けるのだろう。この時代としてはどう取られたんだろう。
「破調」、かな。この論に挙げられている、木俣の他の歌とはかなり違う感じ。初句二句の対句仕立てから、この「どうしやうもなくて」に入るところがかなり大胆。1954年当時は何か批評があったのだろうか。富山の冬の荒波の前に呆然と立ち尽くす主体の姿が浮かぶ。
②松澤俊二「短歌(ほぼ)一〇〇年前」
〈今回は同書(『趣味大観』)より(C)「現代代表令嬢総覧」の記述を確認する。この(C)では、総計二九五人の「令嬢」の趣味、プロフィールが写真つきで紹介されている。〉
現代だったら絶対アウトなやつ。
ここ20年ぐらいで個人情報の観念は相当変わった。たかだか20年前でも相当緩かった。だから100年前は今からはびっくりするような個人情報が公然と開示されていたとしても、そんなに驚いてはいけないのかもしれないが。逆にこの落差が面白いと言えば面白い。
③松澤俊二
〈要するに、女芸として歌を学ぶことは、一つは良き配偶者を得るため、さらにその後の家庭生活の質を向上させるためにも重要なのだ。〉
「和歌」を「趣味」の一つとすることは、花嫁修業(←死語)の一つとして大切だったのだ。現代と比べて驚いたりあきれたりする話ではなくて、これはもはや研究の領域だ。松澤のテーマに対する着眼点が、他の評論の書き手と全然違う。この連載は毎回刺激的だ。
2023.9.25.~26 Twitterより編集再掲
