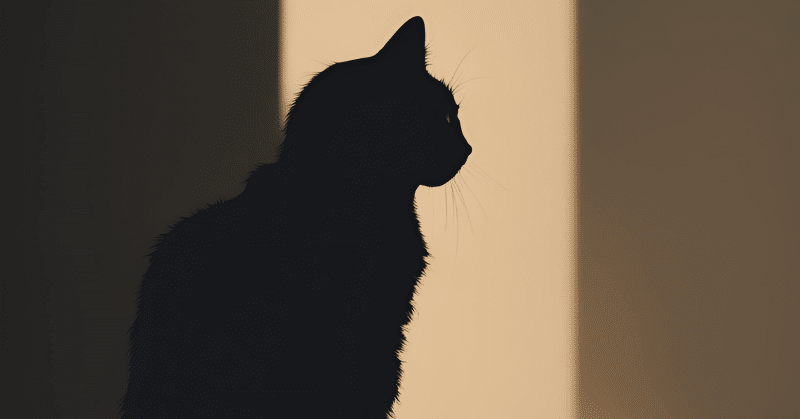
AIは猫にとって理想の家族となり得るか?第8話
《悪夢の襲来》
どうしよう。
小さな体と心が押しつぶされるような不安の中で、真希は何時も部屋の片隅で小さく自分を折りたたんで固まっていた。
どうしよう。また、百点を取れなかった。お母さんに怒られる。
『どうしてあの人と私の子なのに、こんなに出来が悪いのかしら』
母は怒鳴ったり叩いたりしない。怒ると、静かにため息をついて、そのまま。背中を向け、真希など空気か何かのように見なくなる。ひょっとして、真希が真希として存在している事を真希しか知らないのではないか。そう、疑ってしまうほどに。
『こんな出来損ない、産んで損したわ』
心に深く穿つ、鋭い言葉の刃は真希から大切なものを簡単に切り落とし、削ぎ落としていく。
誰もいないところに行きたい。母の目が届かず、かわいそうにとそれっぽい同情もされず、逆に見ないふり、気付かないふりをする大人たちのいないところへ。
目を覚ますと、辺りはまだ暗闇。でも、この手の夢を見た後は再度眠るのが怖くて、眠れなくなる。
真希はベッドサイドの小さな明かりだけを点けて、そっと起き上がった。変に汗をかいて気持ち悪いので着替えたいし、喉が渇いた。
シャワーも浴びたいところだが、こんな早朝では迷惑だろう。ひとまずパジャマから部屋着に着替えだけ済ませ、水を飲もうと台所に行くと、充電中のゴローが立っていた。
(これも人間で言うところの睡眠みたいなものかしら)
そして、人と同じ様に経年劣化で充電機能が落ちていく。
(夢を見るばかりじゃ、全然疲れが取れないわね。いっそショートスリーパーに生まれたかったわ)
などと考えながら水を飲んでいると、突然ゴローの目が青く輝いた。
「きゃあ!」
「おはようございマス、マキ様。本日は二時間十六分三秒早い起床デスね」
「お、おはよう、ゴロー。思ったより早起きね。朝ご飯とか掃除くらいなら、こんなに早起きしなくても……」
「るるなーぅ」
ててて、とちなつが歩いてきてゴローの足にすり寄った。
「チナツさんの朝食は午前四時四十五分なのデス。毎日同じ起床時間デス」
「そう……凄いのね」
「ハイ。正確さが素晴らしいのデス」
ゴローは何時も通りカリカリを掌で軽量している。
「ねえ、私がやってみてもいい?」
ふと思い立って頼んでみると、意外にも快諾して貰えた。
「ハイ。チナツさん、本日はマキ様が朝食の支度をされマス」
「なーぅ、なー、うなー!」
誰が支度しようと構わないから早くして欲しいと催促している鳴き声だ。これくらいなら、分かり易いので真希にも分かる。
「はいはい、直ぐにあげるからね」
計量していると、
「マキ様。○.二五グラム多いデス」
「それぐらい、誤差の範疇でしょ?」
「イイエ。○.二五グラムは四回で一グラムになりマス」
「分かったわよ、ええと、これくらいかしら?」
一粒取り上げると、ゴローは満足そうに頷いた。
「ハイ。チナツさんにとって最適な食事量デス」
どうぞ、とゴローが買い求めたご飯の器にカリカリを入れると、チナツはカリカリを丁寧に噛みしめて食べ始めた。
ゴローがチナツの為に買い求めたご飯の器は、浅めのお皿に脚が付いた、少々値の張る代物。猫が座ってちょっと首を傾げるだけで食べられるのが良いのだとか。
傾斜角がどうの、その場合のチナツの首や体にかかる負担がどうのと小難しい事も言っていたが、要は吐き戻しが減るのだとか。
ともかく、チナツが一心にご飯を食べる姿を見守るのはとても幸せな事だった。ちょっとだけ耳を伏せて美味しそうに目を閉じている。一生懸命カリカリを噛みしめるのだが、ときおりポロポロこぼして、それもちゃんと追いかけて食べている。
だが、チナツはお皿の片隅に四粒くらい残して顔を上げてしまった。
「るなーん」
ご馳走様、とても言いたげに鳴くと、とてて、と尻尾を上げて走って行ってしまった。
「残しちゃったわよ? 具合悪いのかしら……」
「イイエ。マキ様、チナツさんはカリカリを必ず残すのデス」
「え? なんで?」
「推測データが二千百五十二通りありマス。推測一……」
張り切って二千二百五十二も話されたら、起きたばかりなのに日が暮れる気がした真希は、慌てて遮った。
「あ、いらない、自分で調べるわ」
「ハイ、かしこまりマシタ」
早起きついでに、朝食にフレンチトーストをリクエストすると、ゴローは早速支度に移ってくれた。
朝から好きなご飯が食べられるなんて、幸せな事だ。そんな風に考えながら、真希はのんびり顔を洗って今日の予定を確認しておく。
一人で仕事をするなら、スケジュールの管理はとても大切なことだ。
この前、朝ご飯を食べながらスケジュールチェックしていたら、ゴローに怒られてしまったので、最近は朝起きて直ぐに確認し、ご飯を食べながら頭の中で再確認して仕事にとりかかるようにしている。
(ゴローって、たまにオカンよね)
お父さんと言うより、お母さん。お母さんより、オカン。
それはもう真面目に、真希の体を案じてアドバイスしてくれるので、素直に聞き入れる事が出来る。前の仕事をしていた頃の自分なら考えられない事だ。効率優先、スピード勝負。
(でも、それは命を削ってまでやる事じゃない、と)
仕事に対する人のスタイルはそれぞれだが、真希の場合は苛烈過ぎた。命を削ってまでやる事では無い。
真希の代わりは幾らでもいたし、それについて嘆く必要も無い。真希が働く理由は生活であって、その仕事が大好きで極めたかった訳でも無いのだから。
そういうスタンスなら、自分に合った職種で、短時間で稼げる方がより良い選択なのだ。
ゆっくり家で過ごす時間は、チナツと一緒に遊んだり寝転がったりして過ごしている。
真希は今までの人生の中で、こんなに満ち足りた生活をした事は無かった。
誰からも脅かされず、自分の思うままに生きること。
それを、チナツが教えてくれる。チナツは、自分がやりたいことをやりたい時に自由気ままにやっている。お腹が空いたらご飯を食べ、遊びたければ遊び、疲れて眠ければ眠る。そんな当たり前のことを、真希は今まで重要とは思っていなかった。
家にこもってばかりなので運動不足も気になる。でも、真希はジムに通ったりするのは苦手なので、ゴローが推奨してくれたゆっくりと呼吸して行うストレッチや、時にはヨガを取り入れて地道に続けられる運動をしている。
今日も、早めに起きたのでゴローが朝食を支度している間に少し運動をしておこう、と真希は日課となっている体操を一通り終えて、軽くシャワーを浴びて着替えた。
(今日は翻訳の続きからね。順調に進んでいるから締め切りには余裕があるわ。でも、直しが多いところだから……)
髪を乾かしながら仕事の組み立てをしていると、スマホがメールを受信した。
「誰かしら……」
ほとんど仕事用のメールしか届かないので、早朝に連絡があるのは珍しい。メールアプリを開いた途端に、真希は息が止まるかと思った。
(母さんから……)
件名も無い。挨拶も無い。ただ、一言。
『預けていた猫を受け取りに行くわ』
真希は、こんな簡単な文すらも理解出来ずにいた。意味が理解出来ず、軽い目眩がする。
預けていた猫、とはチナツのことだ。
今思えば、チナツの好きなご飯も、今まで使っていたトイレ砂も、名前すらも伝えずに「預かって」と勝手に置いていったのに、自分の都合で更に取りに来ると言う。
(どうしよう……ゴローに、なんて……)
「マキ様。心拍数が上昇、呼吸の乱れがありマス。体調が優れないようデシタら、療養食に切り替えマスカ?」
「るなーん」
まだ、何も事情を知らないゴローとチナツは何時も通りの朝のまま。
「ゴロー……。母が、チナツちゃんを、受け取りに来るって……」
ゴローの目が軽く点滅した。真希にも、ゴローを見ただけでどんな状態か分かれば良いのに。そうすれば、もっとゴローに気遣ってあげられるのに、と真希は泣き出したくなった。
「そうデスカ。現在、チナツさんの所有権はマキ様のお母様にありマス。チナツさんの、荷物をまとめマス」
「……それで良いの?」
真希は思わず、ゴローに尋ねてしまった。ゴローは、人間では無いのに。それでも、人間のようにチナツのお世話をしたいと主張し、自分のスペックをフル活用してチナツの為に毎日一生懸命お世話をしていたのに。
そこに、まるで愛情があるように。
「ハイ。チナツさんの、幸せが最優先デス」
「うるる……」
「チナツさん、お母様がお迎えにいらっしゃいマス。お気に入りのオモチャを一緒にお渡し致しマス」
ゴローは、手際良くチナツの荷物をまとめた。お気に入りのオモチャ、愛用しているトイレ砂、それに大好きなおやつやごはん。丁寧に包んで準備を整えると、
「お母様の到着予定時刻によっては、朝食を支度致しマス」
「……いらないわ。あの人は、私と食事なんてしないから」
「かしこまりマシタ」
ゴローは軽く頭を下げて台所に戻って行く。いつもならゴローの足下に纏わり付くチナツが、真希の足にすり寄った。
「るるなーん」
真希の様子がいつもと違うことを気にしているのだろう。真希は、チナツを驚かせないように、そっと抱き上げた。
真希の母親が、放棄していたチナツを、再度受け取りに来る。家族の元に帰れるのだから、チナツにとっては幸せなことだ。
だから、自分は『他者の幸福を最優先する』原則通りに実行する。
それだけなのに、ゴローは己の機体が急に重くなったように感じた。重量は変わっていない。急激にそんなことが起こったら、大問題である。演算機能が上手く働かない。
甘えるチナツを膝に乗せたまま朝食を取っている真希も、もそもそとフレンチトーストを機械的に口に入れているだけだ。近頃は「美味しいわ、ゴロー」と、笑って褒めてくれていたのに。
「ゴロー……蜂蜜くれる?」
「ハイ。申し訳ありマセン、糖分が足りなかったデスか?」
「うん……足りないと言うか、砂糖が入っていないみたいだけど」
「……スキャンスタート」
ゴローが改めてフレンチトーストの成分をスキャンすると、確かに砂糖が入っていない。まさかのミスだった。
「失礼致しマシタ、ワタシの機能に問題が発生したようデス。ハカセにメンテナンスを……」
「正常よ」
レシピ通りに作るなど、ロボにとっては当たり前のことだ。
ゴローは家事専門ロボットなので、更に主人の好みや、健康に気遣うレシピ変更も自動で行うことが出来る。その機能に明らかな異常があるのに、真希はゴローの言葉を遮るように否定した。
「正常よ、ゴロー」
そして、初めて見る表情で笑った。ゴローの視覚機能が混乱する。真希は笑っているのに、泣いている。泣いているのに、笑っている。
涙は検出されないのに、泣いていると判断し、しかし見た目は笑っているのだ。
「良かった。ゴロー、お願いがあるの」
「ハイ」
「母と話す時、側にいてくれる?」
「ハイ。ワタシは、マキ様のお側にイマス」
「ありがとう」
真希は、ようやくいつも通りの笑顔に近い表情を作っている。懸命にそうしているのが、分かる。
ゴローにとって人の表情とは、現在の状況を知るバロメーターに過ぎないのに、主人である真希の無理をしている姿に、ますます機体が重くなるのを感じた。
「マキ様。ワタシが対応いたしマスか? マキ様は体調が優れない様子デス」
「……ううん。ゴローが一緒なら、大丈夫」
「ハイ。ワタシは、マキ様のお側にイマス」
「るるなーお!」
尻尾をピンと立てたチナツも、真希の膝の上で張り切った声で鳴いた。真希は思わず零れる笑顔を浮かべて、ゆっくりチナツの頭を撫でている。
「いい子ね、ちなちゃん。いい子、いい子」
気持ち良さそうに目を閉じて真希のなでなでをせがんでいるチナツを見ていると、更に機体が重く、軋むようだ。
実際には重くなっておらず、間接部へのオイル供給も十分に潤っている。ゴローは自分の機体に何が起こっているのか、理解出来なかった。
真希の母は、予告通りの時間ピッタリに呼び鈴を押して現れた。
「子猫は?」
扉を開いて出迎えるゴローに、真希の母は挨拶もせずに家の中を覗き込む。以前も真希の所在すら尋ねずにいきなりチナツの入った小さな箱を手渡して帰って行ったのだ。その時は一人だったが……。
「お母さん。子猫ちゃん、どこ?」
真希の母の後ろから、少女が顔を見せた。真希の母を「お母さん」と呼ぶからには、少女は真希の妹に当たるのであろう。とても良く似ていた。
「咲希ちゃん、少し待っていてね」
「子猫ちゃん連れて早く帰ろうよ」
「ええ、直ぐに帰りましょう」
チナツが脱走してしまうといけないので、玄関の扉を閉めない限り連れて来られない。
そう伝えると、母親の方は渋々玄関まで入り、咲希と呼ばれた娘は待ちきれない様子で母親の前に出た。
完全に玄関が閉まったことを確認すると、真希がリビングの扉を開いてチナツを連れてきた。真希の腕に抱っこされているのに、咲希はきょろきょろとまだ子猫を探している様子だ。
「ねえ、いないよ? 子猫ちゃん、どこ?」
「……あの、預かっていたのは、この子だけど」
「違うよ! こんな大きい猫、かわいくない」
チナツがここに預けられた時は、推定生後六ヶ月。まだあどけない子猫の面影を残していたが、近頃しっかりと成長を遂げてチナツは成猫に近い所まで成長していた。
それでも、一般的な猫に比べたら小柄な方だが。
「え……」
真希が言葉を失っていることにも構わず、咲希はチナツには少しも興味を示さなかった。
「ねえ、お母さん。もっと小さくて可愛い子がいい」
「そうね、咲希ちゃん。新しい子を買いに行きましょう」
「やったー!」
真希はチナツを抱っこしたまま呆然としている。ゴローも演算機能が混乱するのを感じた。可愛い、という感覚がゴローには分からない。分からないが、二人がチナツを侮辱したことだけは理解した。
「……動物の遺棄は、犯罪デス」
「は?」
「犯罪デス」
「遺棄なんてしてないわよ。何よ、このポンコツロボットは。人に意見する気なの、機械の分際で!」
母親が目をつり上げると、真希が震える声で割り込んだ。
「ご、ゴローの言う通りよ……」
「なによ? 出来損ないの分際で!」
「出来損ないかどうかなんて、今は関係無い! 正しいかどうかよ!」
肩を震わせて、涙をにじませ、必死で真希は戦っている。腕の中でキョトンとしているチナツの為に。そして、ゴローの為にも。
「何なのよ。頭が悪いと思ったら、気でも狂ったの?」
「正気を疑っているのは、こっちの方よ!」
言い争う母と、おそらく初めて会うであろう姉に全く興味が無いのか、咲希はスマホでさっさと欲しい物を検索していた。
そう、物だ。
生きている動物なのに、チナツは法律上物として扱われ、命に対する確かな保障が無い。
「お母さん、この子が良い。買いに行こう」
「分かったわ、咲希ちゃん。お店に寄って帰りましょうね」
取り乱す真希が過呼吸気味になっているにも関わらず、母親はとっくに真希に興味を失って咲希と共に帰ろうとした。
だが、扉が開かないようだ。
「ちょっと。ドアが開かないんだけど」
『あー、柳原涼子さん? どうも初めまして、葉加瀬小太郎です』
突然、ゴローの音声機能を使って、ハカセが母親に語りかけた。
「葉加瀬? ああ、OWBの……」
『そうです、そこのポンコツを作った天才ですよ。この度はウチのポンコツがご迷惑をおかけしたようで』
「大迷惑よ。どんなプログラムを組んだのよ、人に逆らうなんて、どうかしてるわよ」
『申し訳ありませんねぇ、教育が行き届かず。ここに改めて陳謝致します』
丁寧に語りかけているが、ハカセが激怒していることはありありと分かった。
ハカセは、ロボット達が侮辱されることを何よりも嫌い、そう言った人間を『ウイルス以下』と呼称する。人に対してどうなのかと考えるが、要するにハカセから見ると真希の母は「除菌対象」なのだ。
『お詫びといっちゃあ何ですが、俺が開発したロボットのモニターになって頂けませんか? 子猫を探しておられるとか。丁度、動物アレルギー向けに開発したばかりなんですよ』
「ロボットなんてヤダ!」
『まあまあ、実物を見てみなよ、お嬢さん。好みの外見にカスタマイズ出来るからさ』
その頃には、遠くからパトカーのサイレンが大量に鳴り響いているのが聞こえた。
『うるさくてすみませんねぇ、俺が移動となると大騒ぎでして。あと一分で到着しますから』
音声が切れると、パトカーのサイレンはこちらに高速で近付いて来ていた。どうやら、ハカセがここのセキュリティをハッキングして乗っ取り、扉を開かなくしたようだ。
過呼吸気味だった真希の方が緊急なので、ゴローは音声会話が終了すると同時に真希の様子を確認する。
「マキ様、ゆっくり息を吐いて下サイ」
こくこく、と真希は素直に頷いて、ゆっくり息を吐き出す。チナツを受け取り、真希をリビングのソファに座らせる。
チナツが前足を出して真希の元に戻りたがったので、そっと手渡した。一緒に居た方が、気分が和らぐだろう。過呼吸の原因の大半はストレスなのだから。
ハカセが対処してくれるのであれば、何も問題無い。一分と待たずに、パトカーのサイレンはたちまち真希のマンションを取り巻くと上空からはヘリコプターのホバリング音まで聞こえた。
到着したハカセは、一瞬でセキュリティを解除すると笑顔で現れた。
「どうも。さて、時間があまり無いから本題に入りましょうかね。お嬢さん、ご希望の子はこんな感じで良かったか?」
「あ、私が欲しかった子猫ちゃん!」
先程、咲希がスマホで検索していた子猫と全く同じ姿にプログラムしながら到着したのだろう。可愛らしい声で鳴く子猫に、咲希はすっかり夢中だ。
「良かったわねぇ、咲希ちゃん」
「うん! お母さん、もう帰ろう」
ハカセから子猫を受け取った咲希は、お礼すら言わない。勿論、母親も同様だ。まるでそれが当然かのように、子猫を連れ去ろうとしている。
「あー、一つ言っとくけどな。そいつは確かにロボットだが、実用化のモニタリングだから、ちゃんと生きている猫みたいに世話をしてやらないと機能停止するからな」
「はいはい」
流し聞いた母親は、さっさとタクシーを呼びつけて帰って行った。
真希の容態は落ち着き、母親と妹の所業に呆然としていたが、直ぐにハッと顔を上げてチナツをゴローに預け、慌ててハカセに頭を下げている。
「す、すみません、母と……ええと、妹がご迷惑を……」
「ああ、良いって良いって。俺が勝手にしただけだからな」
真希を主人とした日から、直接ハカセに会うのは実に二年六ヶ月十一日振りのことだ。
「よう、ゴロー。元気そうだな」
「ハイ。ワタシの機能に異常はありマセン」
「おう」
ハカセは、まじまじとゴローを見つめてから、
「お前は俺の最高傑作だからな。ポンコツなんて言うヤツはさっさと追い返すに限る」
「何格好つけてるんですか、博士。制限時間、あと一分三十五秒ですよ」
「マジか? 少ねぇな」
「当たり前でしょう、これ以上善良な警察官の皆さんに負担をかけちゃいけませんよ」
アナログな懐中時計で時間を確認しているのは、ハカセの助手で水城だ。ハカセが研究中に後回しにしがちな、事務処理のアレコレから実験の助手まで幅広くこなせる、ハカセにとって必要不可欠な逸材である。
「じゃあ、チナツちゃんを愛でて帰るか! ちなちゃ~ん、初めましてだなぁ、ハカセでしゅよ~」
ゴローが抱っこしているチナツを前にデレデレと笑って話しかけている。チナツはフンフン鼻を鳴らしてハカセの匂いを嗅ぐと、グイと身を乗り出してハカセに抱きついた。
「おお~! 凄いな、懐っこいな、小次郎とは大違いだぜ」
「コジローさんとは、ハカセが拾った子猫サンのことデスか?」
「おう、そうだよ。アイツは人見知りでなー、俺以外からだと全然飯も食わねぇんだよ」
困ったような声で話しているのに、ハカセは何処か嬉しそう。チナツの為にあらゆるデータを集積したゴローは、知っている。
人は猫と暮らす時、人が猫を選ぶのでは無く、猫が人を選ぶのだ。選ばれた人々は、猫に選ばれたことを誇りに思い、それはもう幸せな下僕となる。そういうものなのだ。
「んでな~、小次郎の友達にしようと思って開発したのが、さっきのロボだったんだ」
「ハカセ、あのロボットはどうなるのデスか」
「あの親子じゃ、間違い無く機能停止するだろうな。その間の記憶を全部綺麗に消して、新しく生まれ変わらせるさ」
ハカセはゴローと目も合わせずに言った。ハカセは、ロボットを物扱いすることを心から嫌っている。
今、ハカセは己の信念を曲げてまで、ゴローと真希、チナツ、果ては買い取られて不幸な末路を歩むところだった見知らぬ子猫を助ける道を選んだのだ。
「ハカセ、もうし……」
ゴローが謝罪しようとする寸前で、真希に引き留められた。何故なのか、ゴローには理解出来なかったが、言われた通りに謝罪を停止する。
「ありがとうございます、博士。ゴローの為に、いつもありがとうございます。ゴロー一人守れない、情けない主人で申し訳ありません」
「いいや、貴方は立派な主人ですよ。ゴローを大切にしてくれて、ゴローの為にお礼と謝罪が出来る主人なんて、そう居ませんから」
ハカセはチナツをそっとゴローに返して、真希の肩を叩いた。
「ゴローのこと、末永く宜しくお願いします。こいつはね、口うるさいオカンみたいだけど、そりゃあもう優秀ですから」
ニッと歯を見せてイタズラ小僧のようにハカセが笑うと、真希は見る間に赤くなって余所見をしてしまった。
「オカン、とは」
母親を呼称する言葉の一つ。どちらかというと、くだけた意味合いだ。
「イイエ、ハカセ。ワタシは母親ではありマセン」
「物の例えだよ、ゴロー。ご主人には覚えがあるみたいだぜ?」
「マキ様」
「そ、そんなこと思って無いわよ、そりゃ、ちょっと口うるさい所もあるけど、それは私の為の助言だし、ありがたいと思ってるわよ、ごめんなさい!」
物凄い早口で真希は言い訳を並べたが直ぐに認めて謝罪した。
「おっと、もう時間だな。じゃあな、ゴロー。定期メンテナンスもサボるなよ」
「ハイ。ワタシは適切な期間で定期メンテナンスを受けマス」
来た時同様、ハカセは大量のパトカーのサイレンとヘリコプターに囲まれて帰って行った。
ゴローの聴覚機能で測定したところ、それぞれ別方向の三方向にパトカーは進んでおり、OWBであるハカセの居場所が特定出来ないように策を講じられているのであろう。
予定外の行動であったので、かなりの方面に無理をさせているに違い無い。OWBには行動制限はあるが、彼等の権限はそれを大きく上回っており、わがままに振る舞えば幾らでも国家権力を振り回せるのだ。
勿論、ハカセはそんな特権に優越を感じるような人柄では無いが。
ホッと息を付いた真希が、床にへたり込んでしまったので健康状態をチェックする。過呼吸気味だったのは治まり、極度の緊張状態から解放されたことによる安堵が強いようだ。
「うるる……」
チナツは床に下りるとウロウロと落ち着き無く走り回った。
「どうしたのかしら?」
「チナツさんは便意を催されたようデス」
「今?」
「ハイ。生理現象デス」
チナツは身軽にトイレに駆け込むと、慎重に砂を掘り、トイレの縁に両前足をかけると、途轍もなく真剣な表情で気張って大便をした。
「あ、つい見ちゃったけど……見てない方が良かったのかしら」
「イイエ、チナツさんはトイレを見守ることを要求しマス。希望に沿った行動デス」
「そうなの……」
気が抜けたように笑う真希は、「手伝うよ」と言ってチナツの健康的な便の片付けをしてくれた。
お腹がスッキリしたチナツは、恒例のトイレハイで家中を駆け回っている。と、突然呼び鈴が鳴ったので斜め上に飛び上がって何処かに隠れてしまった。
「な、なに? 母さんが戻って来たのかしら……」
「イイエ。本日、時間指定で頼んでいた物が届いたようデス。キャンセル出来ない為、返品する予定デシタ」
「なにか買っておいたの?」
「ハイ。チナツさんの幸福度が上昇し、身体能力の向上に貢献し、野生の生活に沿った行動の出来る素晴らしいアイテムデス」
「ふ、ふうん……」
本当は午前指定便だったが、突然の交通規制でギリギリの到着になってしまったことを若い配達員は詫びている。間違い無くハカセの行動による交通規制である。ゴローにも責任の一端がある。
「大変申し訳ありマセン。ワタシのハカセが行動した結果によるものデス」
「ハカセ? え、あのOWBの?」
「ハイ。配達員さん、本日のスケジュールを見せて頂けマスか? ワタシが調整致しマス」
「え、え? えと……」
戸惑いながらも、配達員は配達スケジュールを落とし込んだスマホを差し出してきた。ゴローはコースを分析、今日の交通渋滞を踏まえて完璧に組み直しを行う。無駄の無い買い物機能の応用だ。
「ドウゾ。こちらのスケジュールで、本日の任務は滞り無く終了予定デス。終了予定時刻、午後四時二十四分三十五秒。誤差は三分の範囲内に治まりマス」
「え、ほ、本当ですか? うわわ、今日は絶対残業だと思ったのに! ありがとうございます!」
昼休憩の時間もある、と感激しながら、配達員は元気に走って行った。ゴローが玄関内に戻ると、チナツがこそこそと駆けてきてしきりに玄関の匂いを嗅ぎまくっている。
「チナツさん、配達員さんは帰られマシタ。室内は安全デス、パトロールの必要はありマセン」
「うるるる!」
そんなことは無い、確認しないと、とばかりに勇ましく鳴いたチナツは、玄関の匂いを嗅ぎまくった後は室内中匂いを確認して回った。
鏡の裏に誰か潜んでいるとばかりに、しきりに洗面所の鏡裏を覗こうとしている。
一通りゴローを連れ回して家中を確認し終えたチナツは、満足そうに鼻を鳴らした。
「ハイ。チナツさんの警備は万全デス。常に家が安全に保たれてイマス。チナツさん、ありがとうございマス」
「ふるる!」
ゴローに褒められたことが分かったのか、チナツは誇らしげに鳴いてゴローの足下にすり寄った。
それから、足取り軽く真希の元へ駆けて行き、しきりに鳴いて先程のパトロールを報告しているようだ。チナツが人語を解しているのか、ゴローには判断出来ない。
だが、チナツの方は何か要求がある時や知らせたいことがある時、それぞれ鳴き方を変えて伝えようとしてくる。それは、人に近いコミュニケーション手段で、野生で生きる中では必要としていないものだ。
ゴローのデータによると、猫とは、ほぼ単独行動で生きるものであり、群れを作ることが無い。空腹時に狩りを行って小動物を小まめに食べる。そして、猫同士でコミュニケーションを行うとすれば匂いで判別するのだ。
真希には猫のように鋭い嗅覚は無い。そこで、人々と暮らすようになった猫は鳴き声をコミュニケーションツールとして活用することにしたのだろう。適応力もとても高い。学習能力が高く、賢い動物だ。
「マキ様、早速チナツさんの猫タワー組み立てに入りマス」
「ああ、それ猫タワーだったの。手伝う?」
「イイエ。説明書を解析したところ、ワタシだけで組み立てが可能デス」
「分かったわ。じゃあ、ちなちゃんが邪魔しないように、ちょっとこっちで遊んでいるね」
「ありがとうございマス」
チナツが真希の猫じゃらしに夢中になっていてくれるのは、おそらく五分程度。組み立てをシミュレートすると、五分はギリギリの終了時間だ。
ゴローはサイレントモードで箱を持って移動し、チナツの部屋にこっそり入ると、作業モードに集中して猫タワーの組み立てを四分五十三秒で終了させた。
「これで、チナツさんの幸福度が上昇する筈デス。推定、八十パーセント」
ゴローはハカセから貰う研究費から必要経費を除いてコツコツとお金を貯め、ついにこの猫タワーの目標金額に達したので取り寄せをしたのだ。
上下運動が出来る造りで、一番下にはポールに麻縄を巻いた爪とぎがある。上の方に見張り台のような台座や、こもって眠ることも出来る小さな部屋もある。
チナツの安全の為に、最も安定が良く、倒れにくい物を厳選した。チナツの美しいグレーの毛並みに合うように、淡いアイボリーと白、ナチュラルな木目で統一されたお洒落な品でもある。
「完璧デス。早速、チナツさんを……」
振り返ったゴローの視界に、すでにチナツの姿があった。猫タワーの小さな部屋が収納されていた小さめの箱に、ぴったり収まってゴロゴロ喉を鳴らしている。ゴローは、独自のセンサーでチナツの幸福度を測る。
「チナツさんの幸福度、九十八パーセント……。何故」
ゆったりと寛ぐことも出来ないほど、ビチビチの箱に窮屈に収まっているのに、目を閉じて幸せそうにゴロゴロ言っている。
ゴローが完璧に組み立てた猫タワーに、見向きもしていない。これほど、想定外のことは無かった。チナツに付いて来ていたらしい真希が、箱に収まった所を「写真撮らせてね」とチナツに断ってから寝転がって撮っている。
近くで演算機能が焦げ付きそうなほど考えているゴローを放って。
「ゴロー、気にすること無いわよ。猫ちゃんってたいがい、こういうものらしいわよ? 箱に飽きたら、その内タワーも使ってくれるわよ」
楽しそうに笑いながら……何なら、眦に涙を浮かべるほどなので、ゴローが呆然としているところを最初から見ていたのだろう。
「マキ様……」
「なに?」
「覗き見は推奨されマセン」
「ごめんごめん。ちなちゃんが直ぐおもちゃ飽きちゃって、ゴローの方に行っちゃったんだもの。箱に収まって満足そうにしてるの見たら、ゴローがどんな反応するかなーって気になって」
口では謝っているが、真希は全然謝る気が無いのだ。楽しそうに、笑っている。
(マキ様の幸福度、九十五パーセント……)
それは、今までで一番高い数値。
ゴローは今まで、真希の満足度しか計測出来なかった。
だが、チナツのお世話をするようになってから、満足と幸福が微妙にずれる事に気付いたのだ。少々複雑な計算が必要だったが、満足度の計測を応用することで、真希とチナツの幸福度が測れるようになった。人で言うところの、成長をしたのだ。
AIも、成長する。計算能力を応用すれば、人と同じように更なる効率化を目指すことが出来るのだ。だが、ゴローの成長の仕方は、おそらく他と異なる。
これが、ハカセの言っていた「ちょっとあり得ない反応」だろうか。
「今日はごめんね、ゴロー。ありがとう」
何に対する謝罪で、何に対する謝礼なのか、ゴローには尋ねなくても分かった。今までなら、ゴローは正確に聞き返さねばならなかっただろう。
「マキ様、ワタシは、マキ様のロボットデス。マキ様にとって最適な行動を取るのは、当たり前の事デス」
「そうだけど……」
「デスが」
ゴローは、初めて自らの意思で自らの考えを伝えようとしていた。それも又、「ちょっとあり得ない反応」なのだろう。
「ワタシは、マキ様に認めて頂くと、精度が高まりマス。非常に、有意義デス」
「そう」
ニコリと笑う真希が、今まで以上の幸福度となり、ゴローは演算機能が温まるのを感じた。
「ゴロー、私はゴローを家に迎えて本当に良かったと思っているの。貴方以上のロボットは居ないわ。だから、ずっと元気にオカンでいてね?」
「オカンの機能は搭載されていマセン」
「自然発生してるわよ、自覚が無いだけで」
「それはあり得マセン」
真希と軽い論争をしている間に、「うるさいなー」とばかりにモソモソ起き上がったチナツが、アッサリと猫タワーに飛び乗って小さなこもり部屋に入って爆睡していることに、ゴローと真希は、しばらく気付くことは無かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

