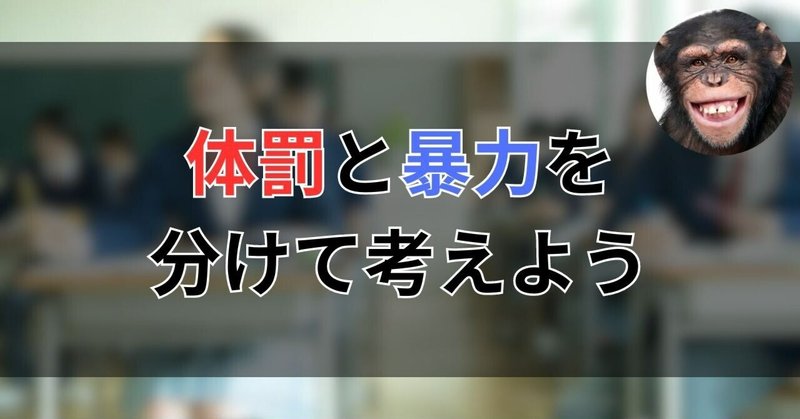
体罰と暴力を分けて考えようよって話
どうも。チン・パンチーです。
今回は「体罰と暴力を分けて考えよう」って話をしていこうと思います。
前提として、多くの方は体罰と暴力を同じものだと考える傾向が強いと感じています。ちょうど下の記事のような考え方ですね。
この記事では体罰を「教育や指導と称して行われる『暴力』を指す言葉」としています。また、この記事を書いた方は体罰と暴力に対して
「体罰」は、教育や指導の一環だという考え方もあるようですが、昔ならともかく、現代ではそんな理屈は一切通じません。
決してあってはならないことで、特に学生に対しては、教育委員会などがそのようなことがないように目を光らせています。
「暴力」も、あってはならないことで、中でも女性に対するそれは厳禁です。
物事の解決手段となる場合がなくもありませんが、そんなことでの解決は、とても褒められたものではなく、犯罪行為となってしまうと考えてください。
と意見をまとめています。
暴力は老若男女問わずあってはならないものであり、「中でも女性に対する」などと強調するのは男性に対する差別意識の表れのように感じられてしまいますが、この際それは良いでしょう。
上記のように体罰を暴力と同一視し、「だから禁止すべきだ!」という考え方を持っている方は多いのではないかと思います。
しかし、上記の認識は本当に正しいものなのでしょうか。つまり、体罰は暴力だから禁止すべきなのでしょうか。
確かに体罰と暴力には似たような性質があります。多くの方が同一視してしまうのも仕方が無いことかもしれません。事実、僕自身も「行き過ぎた体罰は暴力と同義である」と考えています。
しかしそれは裏を返せば「適切な目的と手段をもって行われた体罰は暴力ではない」と考えているということです。以下では体罰と暴力の違いを可能な限り納得できる形で示したうえで、体罰をどのように考えるべきかについて論じてみようと思います。
なお、今回の記事で言う体罰は「学校内で教師が生徒に対して行うもの」に限定しています。家庭内の体罰についてはほぼ触れていないのでご注意ください。
1.体罰と暴力の定義
まず、「体罰とは何か」について定義してみましょう。上の記事では体罰を「教育や指導と称して行われる『暴力』を指す言葉」としていました。
しかし、これは辞書のように定義されたものではなく、個人の考えとしてまとめられたものです。
辞書では体罰を
こらしめのために、からだに直接苦痛を与える罰
と説明しています。
また、文部化科学省は体罰について
(1)教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきである。
(2)(1)により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。
としています。
長いのでまとめると、文部科学省が言う体罰とは
教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為のうち、身体に対する侵害や肉体的苦痛を与えるもの
と表すことができそうですね。
ちなみに懲戒とは
不正または不当な行為に対して制裁を加えること。また、その制裁。こらしめ。
となるようです。
上記をまとめると、体罰とは
教員等が生徒の不正または不当な行為に対して加えた制裁のうち、身体に対する侵害や肉体的苦痛を与えるもの
と定義することができそうです。
続いて、暴力の定義について考えてみようと思います。最初にあげた記事では暴力を以下のように定義しています。
力に任せた乱暴な行為
これでは説明が雑で不十分な印象を受けますね。一応他にも色々と書かれていましたが、その内容は「体罰と暴力は同じで、絶対にあってはならない!」というものであり、暴力という言葉の説明ではありませんでした。
調べてみたところ、辞書では暴力を
不法または不当な仕方で物理的な強制力を行使すること。また、その力
合法性や正当性を欠いた物理的な強制力
と説明していました。
まとめると暴力とは
合法性や正当性を欠いた物理的な強制力を行使すること
と言うことができますね。
二つを見比べてみると、体罰は生徒の不正や不当行為に対する制裁であり、教育的指導の側面を持っています。一方暴力はそれ自体が合法性や正当性を欠いたものなので、そこに体罰との違いを見出すことができそうですね。
2.体罰と暴力の同質性
とはいえ、体罰と暴力を同じものだと考える風潮は非常に強いです。その理由は何なのでしょうか。
分かりやすいので言えば、体罰と暴力は両方とも相手に肉体的苦痛を与える行為であり同一視されやすいという点が挙げられるでしょう。しかし、実はもっと具体的な理由があります。
実は、そもそも日本の法律では体罰が違法です。学校教育法の第十一条では
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
と定められています。
つまり、体罰そのものが合法性を欠いた肉体的苦痛を与える行為であるため、すなわち暴力であるという論理になるわけです。
確かにこの法律に則って考えるなら、体罰は暴力と同じだと考えるのが妥当な気がしますね。
しかし話はそう単純ではありません。
3.「体罰」という曖昧な概念
①指導と体罰と暴力
ここからは竹田敏彦編著「なぜ学校での体罰はなくならないのか」の内容も併せて、体罰を法律で縛ることの難しさと、体罰と暴力を同一視することが本当に妥当なのかを考察していきます。
本書では今橋盛勝教授の理論を紹介しており、その理論では
「体罰」に該当する体罰行為は許されないという解釈を認めたうえで、「体罰」には至らない体罰的行為、法的に許容された体罰的行為が存在し売るか否かという問題が残され続けている
と指摘しています。
要するに、「法律で禁止している体罰の概念がフワッとしているので、体罰かどうか微妙な指導をどうすればいいのか分かんねぇ!」ということです。
具体的な例をあげて考えてみましょう。
授業中にも関わらず、ずっと歩き回っている生徒がいる。このままでは他の生徒たちにも迷惑であり、何より授業どころではないので、教師はその生徒に何度も「座りなさい」と注意をしますが全く聞く耳を持たなかった。そのため教師はその生徒の腕を掴み、無理やり席まで連れていき、肩を抑えるようにして座らせた。
果たしてこれは体罰でしょうか。
生徒の腕を掴み、無理やり席まで連れていき、肩を抑えるようにして座らせるという行為は、その生徒本人にとって肉体的苦痛を感じるものだったかもしれません。しかし、彼は何かけがをしたわけではありません。そもそもこの程度の行為で教師が裁かれてしまっては、教室の秩序を維持するのは非常に困難になります。
また、この場合の教師の行為は、果たして暴力でしょうか。もしこの行為が体罰だったなら、教師は合法性に欠ける強制力を生徒に使用したことになり、暴力と見なされるかもしれません。一方、この場合は授業中に歩き回る生徒によって他の生徒たちの学習を受ける権利が侵害され続けています。教師は何度注意しても言うことを聞かない問題児に対して他にどのように指導すればよかったのでしょうか。
このように、学校の中では体罰かどうか判断が分かれる指導が日常的に行われています。今回の例が体罰であり、有罪であると判断された場合、教師にはいよいよ注意を聞かない生徒を制御する方法がありません。しかし、生徒の言い分や弁護士の主張によっては、上記の行為は体罰であり有罪だと判断されうるのです。
ここで問題なのは、指導と体罰、そして体罰と暴力の境界線が曖昧であるということです。

例えば「肉体的苦痛を感じたら体罰」などと単純に定義してしまうと、そもそも義務教育自体が成り立たなくなります。生徒からすれば、無理やり学校に来させられてほぼ一日中椅子に座らされて面白くもない授業を聞かされることは肉体的に苦痛なことかもしれませんよね。
僕は教育という行為自体が生徒に対して強制力を持つものであり、それを成り立たせるための指導(懲戒等)が認められている以上、その延長線上にある体罰もある程度は認められなければならないと考えています。
しかし今の法律では指導の延長である体罰を暴力と同一視し、体罰行為自体を禁止しているため、注意を聞く気の無い生徒に対してとれる手段が無いということを指摘したいわけです。

そうして教師が生徒を制御する手段を制限した結果、最も迷惑を被るのは真面目に勉学に励んでいる他の生徒たちです。迷惑行動を起こし注意を聞かない生徒に配慮した結果、何も問題を起こさず頑張っている生徒がバカを見る構図ができあがっているわけです。これでは本末転倒です。
そこで僕は、体罰を指導の一環として認め、過度な体罰は暴力として違法行為とみなす考え方を提案したいのです。

ある程度の体罰を認めることで、注意を聞く気のない生徒にも、「肉体的な苦痛を受けたくない」という教師の言うことを聞く理由ができます。また、過度な体罰を法律で禁止することで、大阪市立桜宮高校の体罰自殺のような痛ましい事件の発生を抑制する効果も期待できます。
体罰は曖昧な定義でしか説明することができない概念です。その性質上、強引に法律で禁じてしまうと、教師としては生徒を制御する方法が大きく制限されてしまい、教室の秩序を守ることが困難になります。
強く注意したり怒って見せたりすることで大人しく言うことを聞く生徒ばかりであれば良いのですが、残念ながら現実はそうではありません。体罰が禁止されていることを承知の上で、教師に対して挑発行為をとるようなクソガキもいるのです。
そんな生徒から他の生徒たちを守るためには、体罰を認めることが一つの解決方法だと考えます。
②体罰を法律で禁止する弊害
もう一つ、体罰を法律で禁止する弊害を考えてみようと思います。
それは、体罰を禁じているが故に、いざ体罰が行われたとき、それが感情に任せた危険な暴力行為になりやすいということです。
より具体的に説明するために、「なぜ学校での体罰はなくならないのか」に書かれていた、日本と英米の体罰の理念の違いをご紹介します。
日本における体罰の捉え方はこれまでお話しした通り「禁止すべきもの」です。では、英米ではどうなのでしょうか。
本書によると、英米法制において、教師の懲戒権の一部として一定の体罰が認められていると言います。イギリスのR.V.Hopley 2F.&F.202の〈判旨〉では、体罰の判断基準を以下のように示しています。
親もしくは教師は、子どもの中に宿る悪を直すために、適度な、考えられた体罰を加えることができる。子どもを良くすることにおいて、教師は親の代理者であり、親の権威を委任されている。しかしながら、体罰は常に適度で考えられたものでなければならず、これは体罰の条件である。①感情や怒りにかりたてられてなされた体罰、②その性質や程度において適性を欠く過度な体罰、③子どもの忍耐力を超える長時間にわたる体罰、④生命や身体に危険を及ぼす器具を用いた体罰ーこれらの体罰は全て行き過ぎであり、その暴力は違法である。体罰の結果生命や身体が損なわれた場合には、体罰を行った者は、法的に責任が問われる。体罰の結果死亡すれば、それは殺人である。
つまり、教育において子どもを正すために体罰は必要であり、親や教師に認められるべきであるが、しかし行き過ぎた体罰は暴力と同じで違法であると主張しているのです。
「教師は親の代理者であり、親の権威を委任されている」という部分は議論の余地がありそうですが、実際問題として現在の日本では親の多くが学校に教育を丸投げしている傾向があると思います。
その要因には過度な個人主義の信仰や共働きの親の増加などが挙げられますが、今回は割愛します。
ここで指摘したいのは「適度な、考えられた体罰」を行うためには、大前提として体罰が法的に認められていなければならないということです。つまり、生徒に対する指導方法の選択肢として体罰がある場合に限り、適切な体罰という発想が出てくるということです。
現状の日本では体罰が法律で禁止されています。そしてそれは教育に携わる人間なら全員が把握していることです。にも関わらず体罰が行われる状況とはどのようなものでしょうか。
一つ考えられるのは、我慢の限界が来た結果、その生徒に手を出さなければ気が済まなくなったというものです。教師だって人間です。もし生徒にバカにするような言動をとられ、注意しても効果がなく、それを繰り返されるようであればいずれ爆発することは容易に考えられます。
その結果行われる体罰は、果たして適度で考えられたものでしょうか。とてつもなく理性的な教師であればそれも可能かもしれませんが、この場合は法律で禁止されており、自分もただでは済まないことを理解したうえで我慢できずに体罰を行っていることに注目すべきです。つまり理性のタガが外れ、感情に任せて生徒をボコボコにすることしか頭にない状態が想定されます。
そうなってしまうと、かえって生徒の命が危ないですよね。
これを単純に教師の指導力不足で片づけることができるでしょうか。言葉で言って通じるのは、ちゃんと話す気がある生徒だけです。そもそも言うことを聞く気が無い生徒には、注意以上に効果のある指導が必要です。
つまり何が言いたいかというと、教師の指導方法の選択肢を狭めてしまった結果、かえって理性的な教育を行う機会を奪ってしまっていないかということを指摘したいのです。
体罰が禁じられていなければ、その教師はもっと理性的に生徒に指導できた可能性があります。しかしそれができない現状があり、それを問題視しているわけです。
個人的には、体罰を指導方法の一つとして法的に認めたうえで、過度な体罰に対して思い罰を設ければいいのではないかと考えています。「するか、しないか」と「できるか、できないか」には大きな差があります。
教師に理性的な教育を期待するのであれば、もっと教師を信じるべきです。選択肢を奪うのではなく、与えたうえで、それを乱用しないか監視すべきです、そのために必要なのは「体罰は認めるが暴力は許さない」という考え方なのではないかと思います。
4.まとめ
いかがでしたか。本記事では「体罰と暴力を分けて考えよう」という話をしてきました。
簡単にまとめると、体罰と暴力の違いについては
・体罰は生徒の不正や不当行為に対する制裁であり、教育的指導の側面を持っているが、方暴力はそれ自体が合法性や正当性を欠いたものなので、そこに体罰との違いを見出すことができる
ということを論じてきました。
また、指導と体罰と暴力について
・指導と体罰、そして体罰と暴力の境界線は曖昧である
・今の法律では指導の延長である体罰を暴力と同一視し、体罰行為自体を禁止しているため、注意を聞く気の無い生徒に対して指導ができない
ということを指摘し、そのうえで
・体罰を指導の一環として認め、過度な体罰は暴力として違法行為とみなす
という考え方を提案しました。
さらに、体罰を法律で禁止する弊害として
・体罰を禁じているが故に、いざ体罰が行われたとき、それが感情に任せた危険な暴力行為になりやすい
ということを指摘しました。
体罰が持つ暴力性を否定することはできません。しかし生徒に教師の言うことを聞かせるための有効な手段であることもまた否定できない事実です。
忘れてはいけないのは、守るべきなのは問題行動を起こした生徒の人権だけではないということです。他の生徒の学ぶ権利も同様に守らなければなりませんし、また教師自身も守られるべき存在です。
そもそも、体罰に対する風当たりが強い現代において、なお体罰を受ける方にも何かしらの問題があると考えるべきではないでしょうか。反対される方は多いかもしれませんが、例えばいじめ問題について、僕はいじめられる方にも何かしら悪い部分がある可能性は否定できないと考えています。いじめそのものは絶対的に悪いことであり、相手に落ち度があったとしても正当化されるものではありませんが、それはそれとしていじめられた側が悪くないことにはならない、ということです。体罰問題にも同じようなことが言えると思います。違うのは「そもそも体罰は悪いことか」についてまだまだ議論の余地があると感じられることです。
今後はモンスターペアレントや教師の保護者的役割などのテーマも扱っていけたら面白そうだなと思っています。また、今回あげた指導と体罰と暴力の境界線問題についても、もっと深堀できたらいいなと考えています。
最後に、本記事に対するコメントを頂けると嬉しいです。反対意見も大歓迎ですし、「この問題を一緒に考えてほしい」というリクエストもお待ちしています。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
