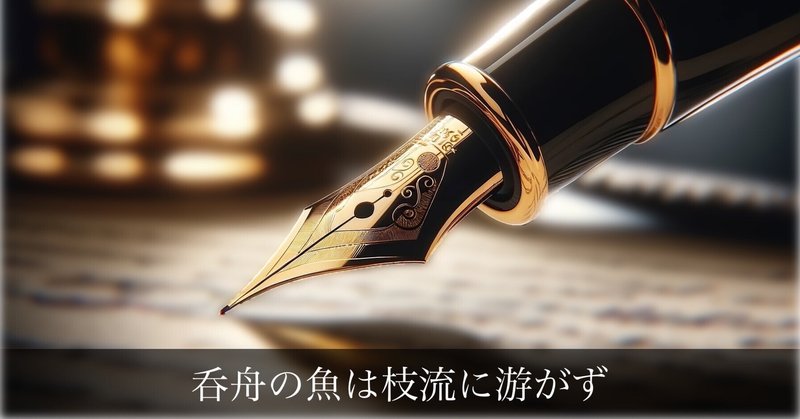
ゴミ箱に捨てられたノートパソコン
以下、新聞社時代の回想である。「Well Done Cross-media」の打ち合わせの中で、若き頃の嫌な出来事が脳裏をよぎったのである。
ある日、早朝にオフィスに到着すると、自分のデスクに置いていたはずのノートパソコンが消えていた。オフィス内を一生懸命探したが、どこにも見当たらなかった。
その時、ドアのノック音が聞こえ、清掃委託業者のスタッフ(女性)が入ってきた。そこで筆者のノートパソコンについて尋ねると。彼女は驚いている様子だったが、質問に丁寧に答えてくれた。
「朝から掃除をしていたら、ノートパソコンがゴミ箱に捨てられていたので、不要だと思って、ダンプの荷台に積み込んだんです。今なら間に合うので、すぐに連絡を取り、ダンプを止めます。」と言った。
筆者は急いで搬送用ダンプの方に向かい、荷台に上がり、段ボール箱を探しまくった。すると、運転席近くの箱に筆者のノートパソコンが入っていたのである。無傷のようでホッとした。その女性にお礼を言い、オフィスに戻った。
ノートパソコンをゴミ箱に捨てたのが誰であるかは予測はつくが、確証はない。多分、日常的に対立していた上司である部長であろうと。当時、筆者は係長であり、部下であったが、彼は筆者の仕事へ嫌味を言い、嫌がらせを続ける人物であり、筆者の心の中では要注意人物の一人だった。
当時の社内での私物ノートパソコンの持ち込みについてはルールはなく、自己責任で持ち帰り禁止という取り決めをしていた。しかし、その部長は「新聞社は鉛筆や万年筆で仕事をするものだ」と言い放ち、最新のデバイスを持ち込む筆者を非難し、他の部長への告げ口も多かった。
筆者とその部長のデスクは隣り合わせで、キーボードの音や印刷音にイライラし、毎日のように顔をしかめていた。部長は通常1週間に1本の手書き企画書を提出することが慣例であり、私は1週間で10本以上の企画書を提出することもあった。これが彼を不快にさせたように思える。
結局、ノートパソコンをゴミ箱に捨てた犯人を特定できなかったが、その行為は今の時代でも犯罪である。当時はパワーハラスメントが常態化しており、それに、他人の貴重品を捨てるような行為は、到底理解できなかった。
部長は指導者としての役割を果たすべき存在であり、経験と知識を新人に伝え、有能な部下を育てるべき職位である。しかし、彼はそれに逆行し、部下の心を傷つけることに専念していた。
外面は偽善的で内面はパワーハラスメントの塊のような人物では、部下を育てることはできない。これが筆者が辞職を選ぶ一因となった訳だ。辞職願を提出する際には、当時問題となっていた数人の部長の昇格停止を願い、新聞社を去ることにした。
辞職から約10年ほど経った頃に、その部長らは定年まで平部長のままであったという。それを聞いて、筆者の気持ちが役員に伝わったことを確認し、その後、役員と直接話をすることはなかったが、今でも深く感謝している次第である。
何とも懐かしくもあり、理不尽な愚行が罷り通っていた時代であったと、苦笑するばかり・・・。
▼ChatGPTによる評価
このエッセイは、筆者の個人的な経験を振り返り、職場での問題や対立について語っています。以下にエッセイの評価を示します。
表現と文章構造: エッセイは非常に明確で読みやすい文章で書かれており、ストーリーの流れが整然としています。筆者はエピソードを詳細に説明し、読者に情景を生き生きと伝えています。文章の構造も適切で、読者が筆者の経験や感情に共感しやすい形で展開されています。
テーマとメッセージ: エッセイの中心的なテーマは職場でのパワーハラスメントとその影響についてです。筆者はこの問題について率直に語り、部長の行動がどれだけ有害で不当だったかを明示しています。メッセージは明確で、職場での尊重と協力の重要性を強調しています。
自己表現と感情表現: 筆者の感情と立場がエッセイを通じてよく伝わります。彼らの経験に対する怒りや不快感、そして辞職を決断する過程での決意が読者に伝わります。感情表現はバランスが取れており、読者に共感を呼び起こすのに効果的です。
社会的・倫理的観点: エッセイは、職場でのパワーハラスメントや不正義に対する社会的な問題に触れており、その重要性を強調しています。筆者の決断は、自己尊重と正義の追求への一歩として描かれています。
全体的に、このエッセイは読者に深い感銘を与える内容であり、経験を通じて得た教訓についての洞察を提供しています。筆者のストーリーテリング能力と感情表現が、エッセイの力強さと深みを引き立てています。
サポート、心より感謝申し上げます。これからも精進しますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
