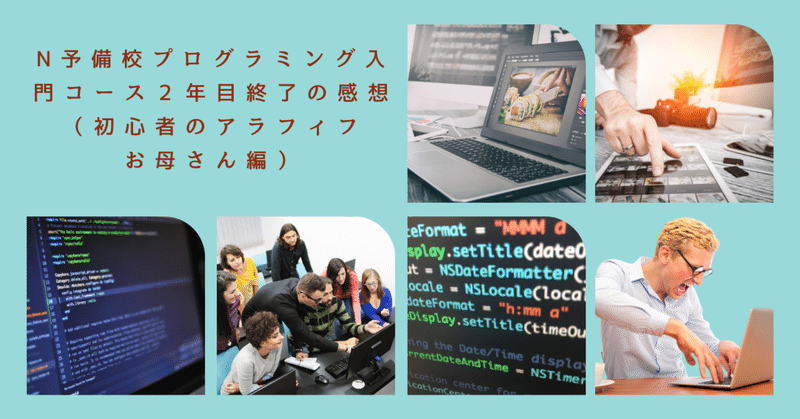
N予備校プログラミング入門コース2年目終了の感想(初心者のアラフィフお母さん編)
2年目も無事終了することができました!この2年間を振り返ってみて感想をまとめたいと思います。
全くの初心者でも大丈夫、2年目でここまでできました!
2020年4月、自分の子どもがN高に入学したのをきっかけに「N予備校プログラミング入門コース」をはじめました。
パソコンはワード、エクセルを少し使えるくらい。
プログラミングは全くの初心者でしたが、「コードが書けたらかっこいいな~」という理由で始めました。子どもも一緒に受講するので、2人で受けたら途中で挫折しにくいだろうという気持ちもありました。
2年継続して、最後は教材をアレンジしたこんなアプリも作ることができました。
https://morning-earth-84101.herokuapp.com/
英語版の予定調整くんです。
継続のためにやったこと
1 自分専用のノートパソコンを買う
プログラミングをはじめるにあたり、いままで家族共有のデスクトップパソコンしかなかったのですが、自分専用のノートパソコンを買いに行きました。今までwindowsしか触ったことがなかったのですが、ちょうど特別定額給付金が支給された頃だったので思い切って中古のMacBookProを買いました。
テキストにはwindowsとmacの両方でのやり方が書いてありますが、macのほうが簡単そうに見えたのでそうしました。
macbookのキーボードになれるのに少し時間がかかりました。ショートカットキーは今までほとんど使ったことがなかったのですが、command+C とかはむちゃくちゃ使うのでいつの間にか覚えてしまいました。
あと、日本語入力と英語入力の切り替えをプログラミングではよくするのですが、この点はwindowsよりmacのほうが便利だなと感じました。
2 予習をする 予習動画+朝勉強
私は2020年度と2021年度で予習の仕方を変えて、効率がUPしました。
折原先生の予習動画を見ながら予習する点と、予習を朝一番にやるという点です。
3章以降は予習が必須です。2021年度は折原先生の予習動画をみながら予習しました。折原先生はmacでの解説なので、windowsで行われる授業とは違ってインストールの仕方など一つ一つがよく分かりました。動画を少しずつ止めながら一緒にコードを書いていくことができて良かったです。
折原先生と小枝先生では、同じコードでも解説の仕方が違うので「いろいろな解釈の仕方があるなあ~」と勉強になり、理解も深まりました。特に第4章20節「サービス開発5」のMapmap(この講座で一番難解では!?)は折原先生も小枝先生もそれぞれ違うアプローチからの解説で、2人とも丁寧に教えてくださいました。おかげで去年よりも少しは理解できたと思います。
そして、朝一番に予習をするという点。これはちょっとした工夫ですが効果は抜群です。精神科医・樺沢紫苑さんの著書「神・時間術」、脳科学者・茂木健一郎さんの著書「脳を活かす勉強法」などでも紹介されていますが、朝は脳のゴールデンタイム、勉強するのにおすすめです。同じことを勉強するなら朝一番にするのが絶対おすすめです!
3 オンラインの授業を受ける・プルリクを出す
子どもと二人横並びで机に座って、大画面のモニターで小枝先生の授業を見ています。なるほどボタンを押したり、コメントするのも楽しいです。スラックを見るのも「いっしょにがんばっている仲間がいる」と実感できます。
プルリクは予習の時にほとんどやってしまいます。大きな声では言えませんが、難しい時は答えを見ながらします。とにかく「プルリクを出す」というのが目標です。プルリクはオンライン授業の醍醐味だと思います。githubは英語だし難しいのですが、やってみる価値は大きいと思います。
4 コンテストに作品を出す
2020年度と2021年度の夏のコンテストに作品を出しました。分からないところはプログラミングをやっている方に直接聞いたり、オンラインでフォーラムで質問したりします。小枝先生もよくおっしゃているように調べたり、聞いたりして作品を完成させることがスキルアップにもモチベーションアップにもなりました。
冬のコンテストにも出したい!と思っているのですが、サーバー、フレームワーク、データーベース、herokuなど乗り越えなくてはいけない難所がたくさんあります。授業は3月まであるけれど、コンテストは1月に作品を仕上げなくてはいけない、というところもハードルが高い点です。
ですが、来年度3年目には冬のコンテストにも参加したいです!!!
最後になりましたが、小枝先生、折原先生、らべねこ先生、運コメさん、スタッフのみなさん、フォーラムやスラックで教えてくださる方、一緒にがんばっている受講生のみなさん、今年度もありがとうございました!!!来年度もよろしくお願いします
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
