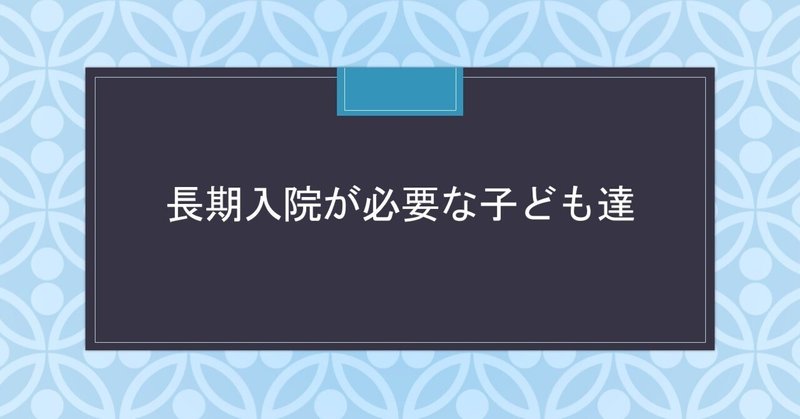
小児の療養環境についての公開講座に参加してみて
先日、某大学の公開講座にZOOMで参加しました。テーマが小児の療養環境ということで関心があったこと、自分が過去にお世話になった支援学校の方のお話も聞けるとのことでとても楽しみにしていました。2時間半ほどの講座でしたがとても充実した内容で時間があっという間に過ぎました。
初めに附属病院における小児の療養環境についてのお話がありました。小児医療センターには「ライフステージに応じた小児慢性疾患患者に生じる課題と支援」をしていくための工夫がされていると感じました。学童のためには緑化空間やプレイエリア、ファミリールームが用意されていて発育支援活動が行われています。院内学級や図書室もあります。
患者本人だけではなく、病気になった子どもの兄弟姉妹への支援もあり、家族で過ごせる施設がありますが、これからはもっと増えていくことを願いたいです。
小児医療センターに入院するAYA世代のために、中高生の集まれる場が提供されていることは自分の経験を思い出してもとてもいい取り組みだなと思いました。
全体の話から「適切な判断と治療に加えて、子どもが病気を克服する勇気と希望を持つことができるように支えていくことが大切」ということを感じました。
続いてシンポジウムに入り「ICTを用いた遠隔授業の取り組み」について様々な立場から3名の方のお話がありました。
高校生の長期療養者に関するお話でしたが、自分の過去と重なる心境が沢山ありました。
病気になると、同年代と同じことができなくなることが精神的にとても負担になります。治療の苦しみもあるけれど、それと同時に学校へ行けないことの焦りと悲しみ(例え少しの間でも子どもにとってはとても大切な時間)、将来への不安でいっぱいになります。まるで自分だけが取り残されてしまったような感じです。薬の副作用による容姿の変化もなかなか受け入れられず、次第に周りとの壁を作ってしまいます。
シンポジウムでは、高校生医教連携コーディネーターという方の存在を初めて知りました。高校生が高校生らしくあり続けるために、そして学校生活の今を共有できるように、病院と高校の架け橋となり活躍されています。
遠隔授業の様子も動画でまとめられていて拝見することができました。
印象に残ったのは、患者本人が前向きになっただけでなく、学校や先生の参画意識の変化や、周りの生徒の成長もあったということです。
最後に、国立成育医療研究センターの理事長より「子どもと家族をbiopsychosocialに捉えて支援する」というテーマでのお話がありました。
現在の日本や世界の具体的な例が出されていました。
小児の難病は医療の発展で寛解状態にまで回復することが多くなりました。でも治療に使う薬の副作用が大人になってから出ることもあります。小児で発症しても多くはその後内科へと移行しなければならず、その後も病気と共に生きていかなければなりません。だからこそ、治療面だけではなく、その時の自分を諦めずに治療を受けられるような精神的な支援が広がっていけばいいなと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
