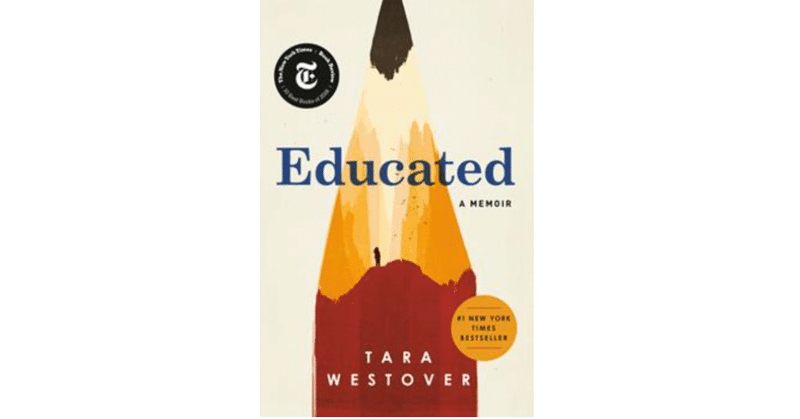
Educated 教育を受けるということ
2021年7月24日
2018年に出版されて以来ずっと気になっていた本。義理の両親の家にあるのを見つけて借りてきました。
読む前は書評などではなく簡単な紹介文しか読んでいなかったので、ホームスクーリングで学校に行かなかった女の子が大学に行き、しかもケンブリッジで博士号を取るというサクセス・ストーリーだと思っていました。
それはそれで間違いではないのですが。。。そんな単純な話ではありませんでした。まず著者のコミュニティーはアイダホ州のモルモン教徒なのですが、その中でも父親は政府を信じない、つまり公教育(得に著者の住む鄙びた地域では私立の学校などありません)を信じていないモルモンの「メイン・ストリーム」とは言えない狂信的な人物です。そのため、兄弟は小学校、中学校には行っておらず、自我が芽生えて学校に行きたい、と高校に行っても、すぐに家の手伝いなどで辞めざるを得ない状況。日本では戸籍に相当する出生証明書さえ著者は持っていませんでした。
信じていないのは政府だけでなく、科学(まあ、実際政府系のお金が流れることが多いといえば多いですが。。。)も信じていませんから、病院に行くこともありません。交通事故や皮膚が溶けてしまうほどの大火傷でも、母親の調合するハーブやオイルでなんとかしようとするのです。著者はこの父親を双極性障害と後に判断するのですが、私には、どこか自殺願望(しかも他人を巻き込むタイプの)があるように思えてなりません。そして、家族はそれに巻き込まれて、何度も危険な目にあうのです。
また、著者は兄が5人、姉が一人いる7人兄弟の末っ子なのですが、兄の一人、ショーンが精神異常と思えるほど暴力的なのです。私から見ると彼は典型的なソシオパス。しかも弱い人にだけ強い、というタイプです。ですから、女性や末っ子の著者などは言葉の暴力だけでなく、身体的な暴力のターゲットとなってしまうのです。
そんな中、タイラーという兄は高校に通い、自力で大学に行き科学の分野で博士号を取ります(後にもうひとりリチャードという兄も博士号を取ります)。家族の中で初めて大学に行った彼が著者に学校に行くように、そして大学に行くように促し、入学に必要な手続きなども手伝ってくれるのです。
こうして著者は狂信的な父親、暴力的な兄が支配する家から出るのですが、そこでめでたし、めでたし、とはなりません。新しい環境に身を置くと誰もが、今まで「普通」と思っていたことがそうではないんだ、と気づくことがあります。しかし彼女の場合、それがとんでもなく極端で痛々しい事件となってしまいます。例えば、「ホームスクーリング」と言いながら、ほとんど教育を受けていない彼女は「ホロコースト」を知らなかったことで教授やクラスメートから眉をひそめられます。
そんな中、色々な人の助けで奨学金を得たり、ケンブリッジへの海外研修の機会も得られます。そこで彼女の才能を認めた教授から正式にケンブリッジで更に勉強できるような特典も得るのです。
けれど、それで彼女の過去が精算されたわけではありません。ショーンの暴力に対して両親と対峙(その後ショーン本人とも)するのですが、その際に自分の味方だと思っていた母親までもが父親と一緒に著者を責め始めます。つまり、ショーンを擁護し、著者の思い出が間違っている、著者がショーンを責めすぎる、というわけです。
大学に入って様々なものの見方を習った著者は、自分の記憶が正しいのか、現実とは何か、と疑い初め精神的に追い詰められます。結局、家族から勘当されてしまうのですが、タイラーだけは味方になってくれます。その後、母方のおばや祖父、いとこ、そのほかの兄弟たちも著者の「家族」となってくれるのです。
私など早くから「その家から逃げて!」「帰っちゃ駄目!」と何度も何度も心の中で叫ぶのですが、彼女は何度も帰って行きます。最終的には著者のことを「悪魔に取り憑かれている」と信じている父親とは音信不通。母親とは会おうと連絡しますが、父親と一緒でないと会わない、と言われ両親とはずっと会っていない、とのこと。
日本でも「毒親」の問題として取り上げられることも増えてきましたが、毒親を持つ子どもが皆通るように著者も親から見放された、あるいは親を見限った、という罪の意識に苛まされるようです。著者はインタビューなどで「親が悪いから私は会わないんじゃない、私にとって会わないほうがいいから会わないんだ」と自分の中で落とし所を見つけたようでした。
読了後、幾つか著者のインタビューを見て、親を決して悪い人だとは言わない彼女に、最初はまだ親をかばってるのか。。。罪悪感のなせる技?などと思っていたのですが、説明を聞くと、納得です。親が自分を愛してくれなかった、と断罪しても何も始まらない、しかも自分が辛くなる。親も親なりにベストを尽くしたけれど私には彼らの世界観を受け入れることは無理だった、と言ったようなことを語っていました。自分で納得のできる答えを見つける、というのがベストなのかもしれません。
一番感銘を受けたのは「強さ」ということ。彼女はショーンから暴力を受けている時、しかもそれを他人が見ている時、時には自分が好意を寄せている人が見ている時には得に笑うのです。それは「これはおふざけですよ。私は惨めに暴力を受けているのではありませんよ。」ということなのです。これには泣けました。そして、それを「強さ」だと思っていたと述懐しています。うーん、強さなのかもしれないけれど、それよりも後にショーンと対峙したり(これはうまくいきませんでしたが)、そういう暴力的な人から離れる、という決断のほうが「強さ」なのだ、と再認識しました。
時に世間は残酷で「実の親なのに」とか「実の兄弟なのに」という理由で暴力的な環境に居続けることを強要してきます。そうした「世間」に抗うことこそが強さかもしれません。それは他人に「強く」見られたい、などという自意識ではない強さです。しかし、そうした「自分を守る」という当たり前の強さを自分の中に見つけること、そしてそれを育てて行くことの難しさをこの本は教えてくれます。(そして、辛くともその方が絶対に良いことも)
最後にこの本を「教育を受けるということ」と題した理由はすごく納得するものです。それこそ「多様性」というものが実は同じような経済的・文化的社会基盤を持った人ばかりが集いがちな大学で推し進められ、教えられているという矛盾をこの本は見せてくれます。そして、それが彼女自身の主張でもあります。教育を受けるということは自分とは違う環境で育った人、世界観を持った人の見方にふれるということ。そういう機会をもっと多くの人に与えるのが教育の本質ということ。教育に携わるものとして反省あり、そして学びの喜びを改めて呼び起こしてくれた本でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
