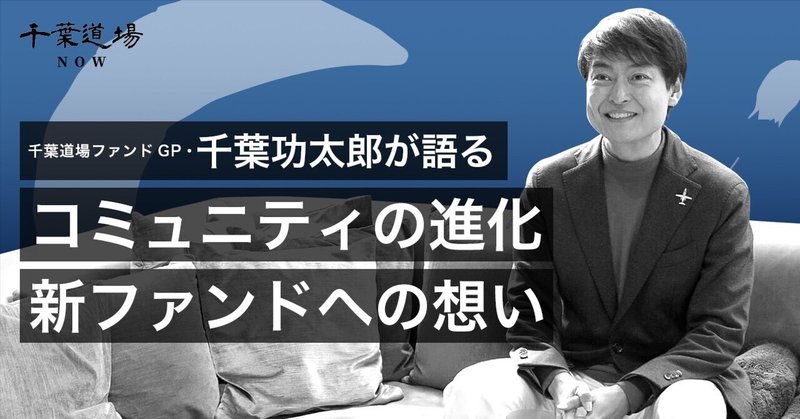
60億円の新ファンド設立!千葉功太郎が語る起業家コミュニティの進化と新ファンド設立の想い
こんにちは、千葉道場ファンドです。
起業家コミュニティ「千葉道場」発のベンチャーキャピタル(VC)・千葉道場ファンドは、この度、3号ファンドを設立しました。引き続きシード・アーリー(プレシリーズA)またはレイターステージのスタートアップに対して手厚い投資を行っていきます。
3号ファンドの総額は2号と同じ最大60億円。ファンドサイズをあえて大きくしない方針です。
あわせて、既存の2号ファンドの投資先に対して3号ファンドで追加投資する、いわゆる「ファンドまたぎ投資」が可能に。単一ファンドの存続期間を越えて投資することで、資金面でも起業家を継続的に支援することができるようになりました。
この異色のファンド設計は長期に渡る起業家支援を考え生まれたものです。
今回は、起業家のためのコミュニティ・千葉道場から生まれた日本唯一のコミュニティVCが考える“起業家支援の理想形”を、千葉道場ファンドGP・千葉功太郎にインタビューしました。
なお、千葉道場とファンド設立の背景については、以下の記事をご覧ください。
千葉道場コミュニティ&ファンド、成長のカギはサスティナビリティ

ーーエンジェル投資家だった千葉さんが起業家コミュニティ「千葉道場」を設立し、そこに集う起業家をより手厚くサポートするためファンド機能を持たせたのが千葉道場ファンドのはじまりです。エンジェル投資家時代と比べ、スタートアップ支援の意思決定方法はどのように変化しましたか?
「ひとりで投資をやっていると、気軽だしフットワークも軽く意思決定できます。ですが、自分の使えるお金が少ないときは、いい起業家と会っても『ごめんなさい』と見送ってしまうこともありますし、『会いたい!』と言っていただいても自分が忙しいときは難しいことが多くありました」。
「そんな状態から、ファンドを設立したことで、理念に共感するメンバーが揃い、チーム戦ができるようになりました。ひとりで好きに投資していたころに比べたら起業家のサポートにも力を入れることができるようになり、個人の忙しさや個人資産の状況に影響されることがなくなりました」。
「ファンドになって、投資先のCEOだけでなく他のボードメンバーと、じっくり話せるようになったのも大きな変化ですね。創業メンバーやそれを支える執行役員クラスがどんな人物かというのは、事業の成否をかなり左右するんです。エンジェル時代は会える人に限界があり、CEOとだけ話して投資を決めることもありました。今は多くのメンバーと話せるようになって、支援をより多角的に検討できるようになったと感じています」。
ーーファンドになると投資金額も多くなりますよね。投資可能額が増えたことで変化はありましたか?
「たしかに、エンジェル投資家としては1,000万から2,000万が限度だったので、投資可能額は10倍以上に増えました。それによってラウンドのリード投資家になれるというのが大きな変化です。もちろん責任も大きくなりますが、起業家にとって、より重要な存在になれるのはうれしいですね」。
「起業家がエンジェル投資家からの投資を受けるのは、資金面のメリットよりも、その投資家が経営面の支援をしてくれることを期待しているという側面があると思います。具体的なアドバイスをもらえたり、悩みを相談できたりっていう」。
「一方、起業家にとってリード投資家の価値は、事業を立ち上げるために5,000万とか1億円規模のお金をワンストップで提供してもらえる点にある。さらに、『あのファンドがリードなら資金を入れよう』と判断するフォロー投資家を呼び込むことも期待される。つまり、求められる役割がエンジェル投資家とは大きく違ってきていますね」。
ーー千葉さん個人としては、エンジェルのころから投資先の経営に積極的には介入せず見守るスタンスだとうかがっています。ファンドになったことによって、投資先との関わり方に変化はありましたか?
「起業家にとって千葉道場ファンドの運営メンバーは話しかけやすいのか、気軽に相談してもらえている印象です。千葉道場に蓄積されているノウハウや知見を、より気軽に聞いてもらえるようになったのはファンド化したことの大きなメリットかもしれません」。
「でも、僕には気軽に相談してはいけないと思われているみたいで……。なぜだかとても遠慮されています(笑)」。
「これを機にちゃんと言っておきますね。『千葉に気軽に相談して大丈夫です! メッセンジャーで連絡をもらえたら、がんばって早く対応します! 遅くなったらごめんなさい』って(笑)」。
人が増えてもオンライン化しても、薄まらないコミュニティをつくる

ーー投資先の起業家が集う千葉道場コミュニティでは、投資先が増えることで必然的にメンバーも増えていきます。コミュニティのあり方にも、変化があったのではないでしょうか?
「この2年半くらいかけて、コミュニティが大きくなっても密度が下がらず、むしろ上がっていくような取り組みを、あの手この手でやってきました。コミュニティが膨らみ始めた時期はコロナ禍とも重なるので必然的にオンラインをフル活用することになりましたが、昔だったらやらなかったことですね」。
「オンラインでの取り組み例を挙げると、これまでは年に2回のリアルな合宿がコミュニティ活動のメインだったのですが、現在はZoomを使った勉強会や飲み会などを月に複数実施するようになりました。ホットトピックスがあれば『次の火曜日の夜20時からZoomでやりましょう』といった感じで気軽に交流できるようになったわけで、これは良いことだと思っています」。
「それとは別に、5〜6人くらいの少人数でリアルの場に集まる試みも行っています。『初めまして』の顔合わせもあれば、特定の悩みを解決するための2時間といったことも。オンボーディングのようなものです」。
ーーコミュニティにはプレIPO段階の起業家もいれば、これからスタートする起業家もいて、多様なメンバーで構成されていますよね。人数が増えると、そういったステージの差からも課題は生まれそうです。
「はい。そこで、実験的に合宿で行うコンテンツをステージごとに分けはじめています。といっても、分けたのはコンテンツだけで、コミュニティそのものはひとつですが」。
「今年の3月に行った合宿では、『白帯』『青帯』『黒帯』とコミュニティの推奨コンテンツを3つに分けて実施しました」。
「シード・アーリー向けが『白帯』。シリーズA〜Cあたりが『青帯』、IPO直前やIPO済みの会社が『黒帯』といった感じですね。また、全体が集まるコンテンツでは視座を下げず、とにかく高みを目指す、すごく視座の高い話をしています。同じ目線で議論する楽しさと、高い視座の話を聞いて影響を受けるという、その両方に意味があるからです」。
「シード・アーリーの会社とレイター以降の数十億円の調達に成功している会社では、悩みの質感が全然違う。例えば『資金調達セッション』『組織マネジメントセッション』を白帯と青帯で行ったとしたら、内容が全然変わってくるわけです。5,000万円の資金調達をするためのイロハを学ぶセッションなのか、10億円を資金調達するためのセッションなのかで内容は大きく変わります。組織もそうですよね。10人以下の組織をどう作っていくか、あるいは最初の経営陣をどうするかみたいな悩みと、すでに100人の社員がいてさらに成長するための悩みというのは別世界ですから」。
ーーむしろ、コミュニティのメンバーが増えても全体で行うコンテンツを残すのは、どんな理由からですか?
「『目線を上げる』とか『マインドを変える』といった、圧倒的な迫力を持つセッションは全体でやったほうがいいと考えています」。
「過去の話でいうと、SmartHRの宮田さんの例がわかりやすい。以前の合宿で、僕が当たり前のように『時価総額1,000億円を超えよう』って話をしていたら、宮田さんは『そうなんだ』って真に受けて。時価総額1,000億円を目指して取り組んだ結果、時価総額が1,731億円の事業になっちゃったっていう(笑)。平たく言うとそういう話です」。
「宮田さんも、当初は時価総額1,000億円なんて考えてもいなかったらしいんです。当時は確か20億円くらいの会社で、それだけでも十分にすごいわけです。目標として100億円超えを掲げて、さらにその先の200億円を達成できれば大成功だと思っていたけど、そんなときに『1,000億円を超えてくださいよ』って言われてハッとしたと」。
「自分で限界を決めてしまっていることってよくあると思うんですが、千葉道場合宿がその天井を破るきっかけを提供できた。こういう気づきを得られる機会って、とても大切だと思っているんですね。だからコミュニティが大きくなっていっても、全員が集まって目線を高くするコンテンツは引き続き行っていきたいですね」。
ーーコミュニティの成長に合わせ、運営サイドも工夫しているわけですね。コミュニティ運営の変化で、起業家同士の関わり方には違いが生まれることはありましたか?
「オンラインで気軽に集まれるようになったことで、最近は部活的なものが自然発生して盛り上がっています」。
「名前を出すのはちょっと恥ずかしいんですが、『ダイエット部』の盛り上がりは異様ですね(笑)。ハードワークになりがちな起業家の体調管理的な意味もあるんでしょうが、目標を達成したいっていう起業家の気質とダイエットって、ドンピシャでハマるのかもしれない(笑)」。
「他にもグルメ部はかなり盛り上がっています。4月にはサウナ部もスタートしましたし、キャンプ部をやりたいという声も挙がっていたり」。
「この『部活』の盛り上がりを見て、資金調達額やステージといった事業自体以外の切り口での集まり方にも価値があるなと思っています。例えばCEOとCXOがクロスオーバーするような機会はなかなか設けられなかったので、このあたりは今後も工夫していきたいですね」。
「起業家のため」を担保する、千葉道場ファンド自体のサスティナビリティ

ーー今回ローンチした3号ファンドには、「ファンドサイズを変えない」「ファンドまたぎ投資の実施」といった特徴があります。この仕組みを取り入れた理由について教えてください。
「千葉道場ファンドは起業家コミュニティに端を発した、日本唯一の『起業家たちの、起業家たちによる、起業家のためのコミュニティファンド』です。コミュニティ内の元起業家がLP投資家となって後輩起業家を支援する、エコシステム的な側面があります。3号ファンドは、その理念を推し進めるための設計にしています」。
「まず、『ファンドのサイズを大きくしない』というコンセプト。一般的なベンチャーキャピタルの経営手法としては、新しいファンドができるごとにサイズを上げていくのが定石です。もともと60億円のファンドがあったとしたら、次は80億円、その次は100億円というかたちですね」。
「もちろん、サイズを大きくしたほうがファンドの運営はダイナミックになる。ですが千葉道場ファンドは2号ファンドの約60億円というサイズを3号ファンドでも続け、未来の4号ファンドでもサイズを変えないことを想定しています。起業家のためのファンドであり続けるためのサスティナビリティを重視しているからです」。
「例えば60億円のファンドを100億円にしようとすると、規模に応じて新たにLP投資家探しが必要になることも多い。すると、ファンドの新規LP投資家の募集に必要なリソースも膨らんでしまいます」。
「千葉道場ファンドは、そこにリソースをかけるよりも、ファンドサイズを固定しつつ既存のLP投資家に引き続き出資をお願いすることで、投資先支援・起業家支援にリソースをかけたいと考えているんです」。
「さらに、ファンドの号ごとにLP投資家の顔ぶれがガラリと変わると、利益相反の問題が出てくるため『ファンドまたぎ投資』がやりにくくなります。しかし我々の仕組みでは、基本的にほとんど同じ顔ぶれのLP投資家が次の号でも出資を行う。だから、利益相反を防止する仕組みさえ整備すればファンドまたぎ投資もしやすいわけです」。
「投資先企業の成長は1年や2年の短期スパンではなく、場合によっては10年かかるケースもあります。成長に必要な期間が長期にわたる場合でも、ファンドまたぎ投資ができれば、シードで出資して、次の号でも投資して、また次の号でも……と長いお付き合いができる。つまりファンドまたぎ投資は、単一のファンドの存続期間を越えて、スタートアップを長く支援するための工夫なんです」。
「ありがたいことに、千葉道場ファンドには、理念に共感して継続して出資いただけるLP投資家が多くいます。さらに『先輩起業家の知見を千葉道場に還元してもらえませんか』とお願いすれば、メンターになっていただけることも多い。出資いただける上にメンターとして知見もくださるという、非常にありがたい存在ですね」。
「もちろん100%顔ぶれが変わらないということはありませんが、言うならば『継ぎ足し続ける伝統のタレ』みたいな仕組みで、スタートアップ支援に必要な資金と知見が引き継がれているわけです(笑)」。
あえて高い目標を掲げる。それが日本のスタートアップを後押しすることになる

ーー起業家のためのファンドとして、投資先企業の成長にフォーカスして設定した目標があるそうですね。
「千葉道場ファンドから、いわゆるユニコーン企業を2025年までに25社、2030年までに100社を出すことを目標に掲げています。さらにその中から、時価総額1兆円越えが2025年までに1社、2030年までに5社出したいと、いつもコミュニティに向けて言っています。この基準で今のところユニコーンが4社が生まれているので、あと21社ですね」。
「すでにイグジットしている会社も含め、これまで投資した企業は74社。ドローン部も別に54社ほどあるんですが、割合から言えば、ずいぶん高い目標ではあります。でも、無理な目標を無理だと思っていたら一生達成しない。無理矢理にでも目標に掲げることで、先に触れたSmartHRのような会社が生まれるはずだと思っています」。
「起業家は、自分の数年間のゴールをどこに置くかによって、経営の意思決定が毎日変化してくる。だから、今は無理な話に聞こえるとしても言い続けるのが大事なんです。実は起業家は、普段はそういうプレッシャーをあまり受けないんです。例え投資家に『時価総額1,000億円を超えてください』って言われても、どこまで本気かわからない。でも『千葉さんが言うなら本気そうだな……』と思ってもらうのが僕の役割でもあるかなと(笑)」。
起業家の夢も、無念さも受け止める千葉道場の想い

ーー千葉道場からユニコーンが生まれる可能性もある反面、起業してもうまくいかないケースは当然出るはずです。「起業家のためのファンド」を掲げる千葉道場ファンドは、そういった起業家にどのように対応するのでしょうか?
「残念ながら、会社を事実上清算したり事業撤退をせざるを得ないケースも千葉道場内で発生しています。ただ、起業家コミュニティとしての千葉道場、それを由来とする千葉道場ファンドの性格を考えたとき、起業家の将来の選択肢を狭めるようなことをしたくないんです」。
「特にコロナ禍になって1年目くらいの合宿では『意志を持って会社を畳む決断をしてもいいんですよ』というメッセージを出しました。いわゆるリビングデッドに陥ってしまって、その起業家の人生を前にも後ろにも進めない状態にするのは日本にとっても損失です。そうなるくらいなら、仁義を切って誠実に撤退する選択肢を提示することで、次のチャレンジを早くできるようにしてあげたいと思っています」。
ーーベンチャーキャピタルとしては、なかなか口に出せない言葉ですね。
「はい。本来は投資家から言いづらい言葉ですが、僕はけっこう口にしています。もちろん損が確定するので金銭的にはマイナスなんですが、起業家にとっては再チャレンジができるようになる。そのほうが、『日本唯一のコミュニティVC』という千葉道場ファンドの性質に沿うことになると思うんです」。
「起業家にとって事業の撤退はすごく難しい問題で、こういうときに本当の人間性が出ると思います。ひと口に『撤退』と言っても、表向きすぐにわかる倒産であることは少なく、ほとんどはフワッと消えていく。そういうときの起業家の立ち振る舞いを、僕はよく観察しています。撤退のときに投資家を含めたステークホルダーとどう向き合っていたかが、次の起業の成否につながったりしますから」。
「起業家はいつもキラキラしているわけではなく、悩んだ末に1周目の起業は失敗したけれど2周目で大成功したっていうケースはよくある。運やタイミングもあります。だから、コミュニティとしては、失敗も許容しています」。
「何度も言っておきたいのですが、我々は『起業家のためのコミュニティ』であり、『起業家のためのファンド』でありたいんですよね。だから、起業家の弱いところ、つらいところを全部受け止めるコミュニティでありたい。成功した人はその情報をギブするし、会社がうまくいっていない人も悩みや迷いをみんなにシェアする。それが千葉道場の精神です」。
「千葉道場の軸はあくまでコミュニティ。単純にファンドとして資金を提供するだけでなく、起業家自身に、そして事業自体に成長していってもらうための精神的なサポートに力を入れているからこその『起業家コミュニティ』です。お金以外に得られる価値があり、それをギブしていくことを惜しみません。この理念に共感いただけるLP投資家と、日本のスタートアップエコシステムの構築を目指して進んでいきます。起業家の皆さんも、ぜひ気軽にご相談いただければと思います」。
ーー最後に、今後どういった企業・起業家に投資していくのか、投資先選びの方向性を教えていただけますか?
「今までと変わらず、夢のある誠実な起業家に投資していきたいと思います。夢というのは『起業家本人の夢』という意味でもあるし、『描いている事業で周りに夢を感じさせられるか』という意味でもあります。さらに市場性という意味でもあるし、そこで勝てそうかという意味もあります。複合して、夢を描けているかということですね」。

「千葉道場ファンドが出資している起業家は、みんな並々ならぬ事業への想いがあります。選んだ分野への想いもあるし、そのプロダクトへの想いもあって、まさに不退転の覚悟で取り組んでいる人ばかりなんですよね。そういう人に出資していきたいと思います」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
