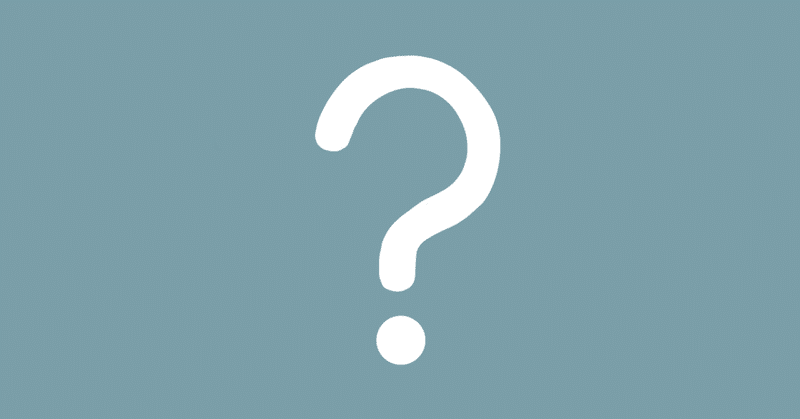
「忘れた」が正解の場合
今日は『十訓抄』にある藤原教通(ふじわらののりみち)さんと随身(ずいじん)の秦近利(はたのちかとし)さんの話。
随身は、皇族や大臣、大将などの偉い人の護衛としてついている近衛府のお役人さん。まあ、SP兼秘書みたいな感じですね。
教通さんが近衛大将だったとき、内裏に出仕したのを、とある女房が見かけて、随身の近利さんを呼んで歌を詠みかけました。近衛大将ってかなりの地位なんですが、逆ナン……ですかね。この女房強い。実際の所は、自分の存在(賢さ・歌ウマ)をアピールしたかったのでしょうか。
本当の初対面ならかなり空気読めない人だった可能性もありますが、もしかすると元カノとか愛人だったのかもしれませんね。予想ですけど。
とにかく、歌を預かった近利さん。教通さんのところに近寄り、
「女房が『申せ』と――」
と主人に声をかけると、教通さんが振り返ります。
そのとき教通さんは、見るからに急いでいる様子。
近利さんは、(わざわざお呼び止めして、歌をお伝えするのはあまりに申し訳ない)と思います。ただでさえ急いでるのを引きとめているのに、返歌まで作ってもらわないといけないですからね。
平安時代のマナーとして、和歌をもらったら返歌をするのが基本。もらってしまったら放置はできないのです。めんどくさいね。
そこで近利さんは……
「あ、忘れました」
と言ったのでした!!!
普通だったら笑い話ですが、この場合は、近利さんの機転が効いた対応として、みんなに口々に褒められたということです。
周りの人に状況をわかってもらったから褒められてますけど、もし返歌が詠めなかったら主人の失態になるところを、和歌を忘れた自分のミスということにして全面的に責任を負っているわけですから、結構覚悟がいることだったと思います。そして、主人に負担をかけまいとする忠誠心もすばらしいですね。
そして、このことを、白河院の随身である下毛野武忠(しもつけのたけただ)という人が聞いて
「すばらしい! 今どきの随身だったら、つぶつぶこまごまと逐一お聞かせしていたに違いない!」
と評価したとか。まあ、伝言をきっちりお伝えするのがマニュアル通りの普通の対応ですね。
ちなみに十訓抄のまとめとしては女房側への「忙しい時は人に和歌を詠みかけちゃダメだよ!」っていう和歌のマナー的なことなのですが(ほんとだよ)、現代的に言い換えるなら近利さんの行動にフォーカスして、
「マニュアル対応よりも、臨機応変に相手のことを考えた対応を!」
とも言えるでしょうか。
平安時代に限らず、「忘れました」「わかりません」という返事は、一見ダメに見えますが、状況によってはまともに答えるよりも効果的なことがあります。例えば、答えたくないことを無理やり答えさせようというような意地悪な質問をされた時や、理不尽な要求をされた時などに敢えてそのように答えることでトラブルを回避できることもあると思います。(あくまで場合によりますが……)
私は昔、大学で話したことのない先輩に授業が始まってから「その席譲ってくれない?」と突然話しかけられた時、「え…?なんでですか…?わかりません…」と、本気で理解できていない風に返事したら、諦めてくれたことがありました。向こうも説明するのが面倒くさいと思ったんでしょうね。ポイントは「はあ?」というニュアンスではなくて、「???」というニュアンスでいうことですかね。
ただ、こちらが侮られる可能性もあるので、繰り返しになりますが、困った時に下手な手を打つよりはわからないふりをした方が効果的な場合があるという感じです。本当に邪悪な人が相手の場合は通用しないので、気をつけてください。
今日の話は、『古典文学紹介』の第15話後半でも紹介しています。
前半は、和歌を即レスできない時の対処法も紹介しているので、気になったらぜひ覗いてみてください。
読んでいただいてありがとうございます! スキ!やコメントなどいただけると励みになります。サポート頂けた分は小説や古典まとめを執筆するための資料を購入する費用に当てさせて頂きたいと思います。
