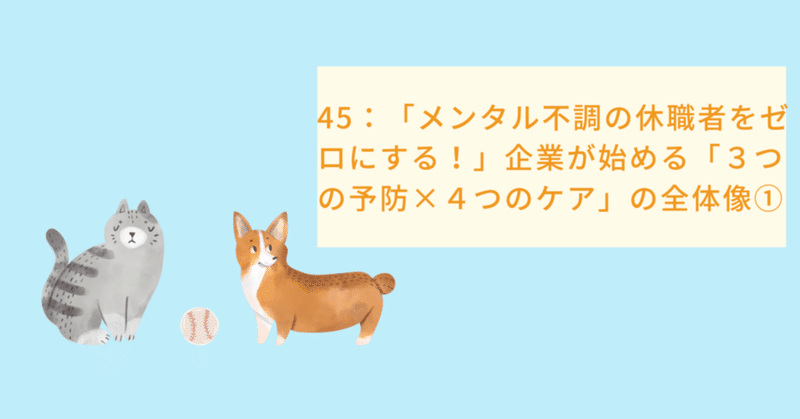
45:メンタル不調の休職者をゼロにする!企業が始める「3つの予防×4つのケア」の全体像①
「3つの予防」と「4つのケア」の掛け合わせで考える
42:組織に「休職する人」が出るのをゼロにしませんか?|森川友晴 (note.com)
こちらの記事から「メンタル不調による休職者をゼロにする!」ということで、記事を書いており、前回は「1次予防×ラインケア」ということで、具体的な対策として「長時間労働」を取り上げました。
次は「ハラスメント」の記事を書き始めていたのですが、ちょっと立ち止まり、この記事では「3つの予防」と「4つのケア」を企業はどのように設計していくと良いかを具体的に書いてみたいと思います。
早速ですが、全体像が下記です。

私が人事部の方と話すときは上記の全体像を前提に話すことが多いです。
詳細に示していきますが、文章の量が多いので、今回はセルフケアと「3つの予防」の掛け合わせについて書いていきます。
セルフケアと「3つの予防」:1次予防
1次予防の目的は「健康の維持」です。そのためストレスに上手に対処できるように育成していくことが企業としては取り組んでいくことになります。
その時に大事なのは下記の4点だと考えます。
①レジリエンス研修の実施
②自己理解・問題解決力の向上を優先する
③認知的な成長は長期的に育てられると良い
④状況によってはメンタルヘルス研修の実施も要件等
レジリエンス研修とメンタルヘルス研修の定義としては
レジリエンス研修:ストレスフルな状況を乗り越える、ストレスがあっても回復しやすい状態になる
メンタルヘルス研修:ストレスとの付き合い方、自分の危険な兆候へ気づきやすくなったり、適切な休み方ができるようになる
レジリエンス研修、メンタルヘルス研修は実際にはどちらも内容が混じりながら実施されますし、名前だけが違う、ということもあります。
企業で実施する際は基礎知識として「メンタルヘルス研修」を実施する、成長するための研修として「レジリエンス研修」を実施する、といった文脈が多いように思います。
私のおすすめとしては研修としてはレジリエンス研修の実施をしながら、内容の中に「弱ったときにどうするか」などの危機管理としてメンタルヘルス研修の要素を入れるとよいのではないかと思います。
なぜそのほうが良いかというと、とても現実的な理由なのですが「その名前のほうが受けが良い」からです。
人事の方が経営陣に実施の許可を取るにしても「成長のため」「パフォーマンスアップのため」という名目が通りやすいですし、受講の対象者の方も「メンタルヘルス」という名称だと「自分は問題ない、大丈夫」といった受け取り方をした方は研修の受講動機が下がってしまいます。
ただ、例えば重篤な出来事があった(自殺者がでた、など)の場合は、その対策としては「レジリエンス」より「メンタルヘルス」を強調すると良いでしょう。レジリエンスは「逆境を乗り越える」といった文脈になりますので、うがった見方をしてしまうと「倒れたのは本人が乗り越える力がなかったからだ」などといった企業側のメッセージになりかねません。
レジリエンス研修を行う際の内容はまた別途記事をあげたいと思います。
レジリエンスの理論は数多くあり、どの理論をベースに研修を実施するのかによって、結果が変わってきます。
私は「自己理解+問題解決力」をレジリエンス研修としては重視しています。
セルフケアと「3つの予防」:2次予防
2次予防の目的は「気づく」です。セルフケアとしては、企業は社員一人一人が自分の状態にきづくこと、そして気づいた時にはすぐに対処にむけて行動できるように教育するとともに、本人が対処にむけて動いたときに適切な対応が準備できていることが大事になります。
その時に大事なのは下記の3点だと考えます。
①軽い悩み、課題でも相談できる状況をつくる
②ストレスチェックの目的を何度も伝え、実施率をあげる
③ストレスチェックの結果(高ストレス者)になったときに対処をすることを推奨する
①軽い悩み、課題でも相談できる状況をつくる
これは1次予防でも重要なのですが、この「軽い悩みでも」相談できる状況をつくることはとても大事です。
1次予防での意味合いと2次予防でも意味合いが変わるのですが、
1次予防では「軽い悩み」から相談できる相手がいることそのものが健康の維持に役立ちます。
人は相談できる相手がいることで安定性が増すからです。
1次予防の観点からすると、相談相手は誰でも良いです。親でも友達でも上司、同僚、人事総務部や社内の保健師、社外のカウンセラーなど。相手がいることが重要です。
しかしながら2次予防を考えると「軽い悩み」から保健師やカウンセラーといった専門家とつながっているのが効果的ではないかと私は考えています。
「軽い悩み」で相談をした方本人や、「軽い相談」で相談をした方の紹介で相談につながりやすいからです。2次予防のように「危ない」と本人が思っているか場合は、前述した上司では荷が重いということもあるからです。
なので「軽い悩み」から専門家に話すことができる環境を整えていくことが大事ではないかと思います。
②ストレスチェックの目的を何度も伝え、実施率をあげる
③ストレスチェックの結果(高ストレス者)になったときに対処することを推奨する
ストレスチェック制度とは厚生労働省によると以下の目的をもっています。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。平成27年12月に施行されました。
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
まとめると
・セルフケアとして本人が自分でストレス状況にきづくこと
・そのことによってメンタル不調のリスクを軽減すること
・検査結果の集団分析により、ラインケアをして職場環境の改善に取り組むこと
になります。
私がストレスチェックを実施している担当者に何人かにお聞きしているところでは、毎回実施のたびに連絡内容に目的を入れているし、管理職にも実施を促すように伝えているところが多いです。
そう考えるとやれることはやっているのかな?とも思うのですが、それでも現場でストレスチェックを大事だと思っている声はあまり聞こえません。
人事の方の発信不足か、管理職の伝達不足か、本人の認識不足か、理由は様々ですが、まだまだ実施状況には改善の余地ありと言えます。
私としてはまずはメールなどの連絡で終わらすのではなく、たとえば簡単で良いので実施のお願いの動画を添付するとか、管理職から口頭で実施の意義・目的を毎回話してもらうなどしつこいくらいに伝えていってほしいと思います。
そしてもう一つの問題が「高ストレス者」になっても産業医面談など必要な対処を行わない、ということです。
ストレスチェックを行った結果に関しての重要性を認識していない、ということが多いのではないかと思います。
これは②ストレスチェックの目的を何度も伝え、実施率をあげるにつながりますが、実施+問題があれば面談など対処を行うことを伝え続けることが大事です。
私は以前、ストレスチェックをしたところ高ストレス者になったから、大丈夫だとは思うけれど・・・と言いながら面接を申し込んだ方と面談をしたときのことです。
実際に話をしてみると睡眠の状態などがあまり良くないことが明らかになり、結局上司の方とすり合わせて仕事量を減らすや担当を変えるなど業務調整をすることで、安定していったことがあります。本人はピンと来ていなくてもカウンセラーと話しながら、だんだんと自己理解が進んできたり、カウンセラーが危険性を判断して管理職や人事の方などに連絡を行うこともできます。
自分では大丈夫だと思っても対処はしてみる、こういった行動を推奨していってほしいと思います。
もし産業医面談へのハードルが高いようであれば、一度カウンセラーと話すことで自分の状態を整理し、産業医面談をするかどうかをカウンセラーと一緒に検討しても良いのではないかと思います。
セルフケアと「3つの予防」:3次予防
3次予防の目的は「復帰と継続」です。
3次予防はメンタルヘルス不調になり休職した方が復職することであり、以前のように働くことでできるようになることを目指すことです。
3次予防の時にセルフケアとして大事なのは下記2点です。
①継続的な専門家との面談
②余裕があれば「認知の変容」に取り組む
復職する、ということは休職していた人にとっても周囲にとっても大変な出来事です。
例えば職場の対人関係のトラブルなどで精神疾患になった方からすると、もし異動などをしていて、同じ職場ではなくても会社の建物を見るだけで、とても緊張が高まるかもしれません。それくらい「怖い」場所になっている可能性もあります。そういった怖い場所にもどる、ということはとても負担ですし、大変な出来事と言えます。
周囲の方にとっても、どのように接するのが良いのか、体調はどうなのか、など気に掛けることが多くあり、負担になることもあります。
このように負担に大きい復職するという行為を自分一人で乗り越える、というのではなく、カウンセラーなど専門家と一緒に話し合いながら進めていくことで少しこころの負担を減らしながら復職を乗り越えていくことが大事です。
それにくわえ、継続的に、ということも大事です。
うつ病などで休職した方が、回復をして復職をし、忙しくなってくると「大丈夫だろう」ということで薬を飲まなくなる、ということも起こります。また病院にも行かなくなる、ということもあります。
こうした人が数年後にまたうつ病になる・・・ということもあることです。
こういったことを防ぐためにも専門家と話しながら自分の状態をチェックすることや専門家と定期的に話すことで医師に無断に薬をやめてしまう、といったこともなくなっていきます。
②余裕があれば「認知の変容」に取り組む
これはある程度安定してきているなら、ということですが、認知(ものごとのとらえ方」を変えていきえるように本人に促すことも効果的です。
「認知の変容」では、たとえば
ある仕事の進め方を注意された!→私は役に立たない存在だ・・・
など
このように「行動」の注意に対して「自分の存在」が否定されていると受け止めてしまうのは、自信を無くさせ、気持ちを落ち込ませる捉え方です。
こういった自分を落ち込ませやすい物事の捉え方を変えていく、ということには効果があります。
ただ私が「余裕があれば」と書いたのは、認知の変容には時間もエネルギーもかかるからです。認知というのは生まれてからここまで育んできたものです。これを変えていく、ということは負荷が高い作業になります。
そのため「余裕があれば」ということが大事なのではないかと思います。
まとめ
今回の記事は「休職する人をゼロにしたい」と書いた記事と連動した内容となっています。
「3つの予防」と「4つのケア」の全体像をまとめました。
その中からセルフケア×「3つの予防」に関して書いています。
次回はラインケア×「3つの予防」について書くつもりです。
この記事を読んで「メンタル不調による休職をゼロにするために何かしたい!」と思った方がいましたらお声がけください。
一緒に考えていきましょう。
チェリッシュグロウ株式会社では研修及びカウンセリングサービスを提供していいます。ご興味がある方はこちらにお問い合わせください。
お問い合わせ - チェリッシュグロウ株式会社 (cherishgrow.jp)
またUdemyにて動画を販売しています。
ご興味があればそちらもご覧いただけると嬉しいです。
逆境に強くなる!レジリエンスを高めるための3つのステップ | Udemy
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
