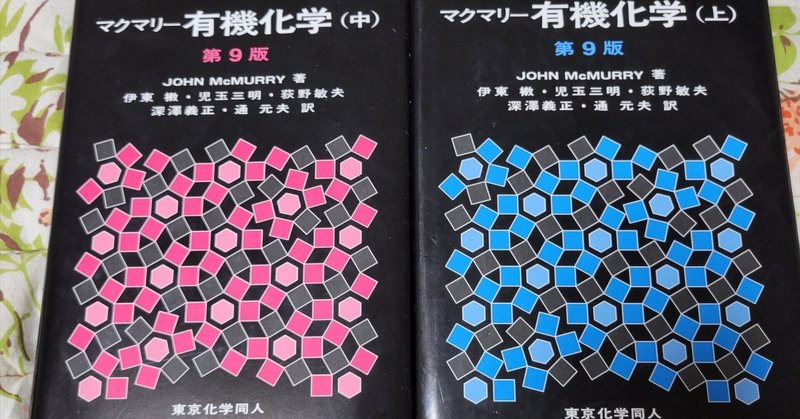
私はなぜ「化学大好き君」になったのか?
化学大好き君です。
今回は、僕にとって化学がどういう存在かについて記します。あまり僕がどのように化学大好き少年になったのか語ってこなかったのですがここで書き記します。
これまで3年間学んできた振り返りでもあります。良かったら読んでいってください!!
(ここから本論です。)
小学校のとき
まず小学生5年生の時2019年だ、まだ世界がコロナ禍になる前のことだ。僕は元素が好きになった。元素周期表が壁に貼ってあってその形を眺めるのが日課となった。だが、そのうち見るものが変わった。その周期表は「1家に1枚周期表」と呼ばれるもので化学好きの方なら分かると思うが、上に日本のノーベル賞(物理、化学、生理医学)授賞者の名前と実績が書いてある。そのあたりを集中的に眺めるようになった。「何やらニュートリノやらカップリングだか訳の分からん言葉が並んどるな~」としか小5の私には分からないものであったが、二つ特に気になるものがあった。一つは鈴木章先生と根岸英一先生のクロスカップリングで、もう一つは福井謙一先生のフロンティア軌道のことだった。おぼろ気ながらこれらが分かるようになりたいと思ってWikipedia を見てみたが当然分かるはずがない。分かりたいと思ってまずは元素の本から読み始めた。その本は大変分かりやすく元素の基本的な性質から応用まで幅広く書いてあった。これを見て改めて元素の奥深さを知った。
そうして私は化学への道を知り志すようになる。今思えば2019年は国際周期表年で色々と周期表が話題になっていた年だった。壁に周期表が貼ってあってのも多分これの影響だろう。まさか国際周期表年の影響が一人の少年を化学好きにされるまで及んでいたとは。玉尾先生、感服致しました。
その後、有機化学の本や物理化学の本、量子化学の本と色々読んだが元素を知っているだけではちんぷんかんぷんであった。唯一分かりそうな本があった。有機化学の本である。なんか6角形きれいだな~あれなんか変な環(今思えばアズレンだった)もあるな~と思い、有機の面白さに触れた。その後早稲田の入試終了後から早稲田中学に入学する前までに斎藤勝裕先生の「ベンゼン環の化学」を読み、将来は有機化学をやろうと決めた。
ちなみに小学校の卒業文集にはノーベル賞をとる!と書いた。恥ずかしい。
中学校のとき
早稲田中学に入った後は化学研究部に(無事?)に入部して化学を深めることになった。化学グランプリのこともそこで知った。最初の一年は高校の化学(未だに意味を見いだせない)と図書館にあった難しそうな有機化学の本ばかりやっていた。図書館にはマクマリーもウォーレンもなかったので古そうな本だった。早く買ってくれよ!今高校の化学はもう6周ぐらいしているけれど、当時は数学の壁がありlogも√もあまり分かっていなかった。化学をやる上での数学の大切さを学んだ。
クリスマスプレゼントにマクマリーの上巻を貰った。だが、挫折してしまいしばらく冬眠させてしまった。後悔。
その後、中2になり「酢酸エステルの匂いと炭素数および分子構造との関係について」というテーマで研究を開始した。とはいえ初めは酢酸エステルだけでなくプロピオン酸エステルや酪酸エステルなども合成、比較検討していた。合成したエステルの数はざっと45に上った。だが、その合成によって有機実験に慣れることが出来て良かったと思う。
同時にもろぴー有機化学チャンネルに出会い、大学有機化学を本格的に始めたのもこの時期だ。中2の時は、Sn2から合成問題まで幅広く動画を視聴していた。見すぎてセリフなどはほぼ暗記していたようにも思う。だがこのチャンネルを見たことにより、冬眠していたマクマリーへの理解度が果てしなく上がり、より上級の本にも取り組めるようになった。今では、もろぴーさんに感謝してもしきれない。sin有機化学さんの動画も見始めた。よく反応機構を抑えようと見ていたようにも思う。
秋頃には、高校化学を体系的に学び直すために化学の新研究を始めた。もともとは化学部の元顧問の先生からのおすすめですが、読んでいくうちに引き込まれていった。やっぱり間違いが多いけど…その元顧問の先生にはその年の秋から来年の春までシュレディンガー方程式に始まり界面活性剤に至るまで様々なことを個人指導していただいた。今も研究についてアドバイスをいただくこともあり、感謝以外の言葉が見当たらない。
その後年が明けて、しばらくしてTwitter(現X)を始めた。ここで私は「化学大好き君」と名乗るようになった。今でこそ私の主要コンテンツであるが、開始したころはネタツイばかりしていたように思う。3月の終わりには #今週の全合成 を出題し始めた。Xで学んだことはたいへん多く、今ではSNSは私の学習ツールとしての面が強い。ツイ廃ではない。(クラスの皆には信じてもらえないが)
まとめ
以上私が化学大好き君になった経緯(そもそも化学好きになったきっかけも含め)について長々と書いてきた。少しでも参考になれば嬉しい。
まとめると、【玉尾先生のお陰で化学が大好きになり、もろぴー先生のお陰で有機化学を大好きになった。と言えるだろう。このお二方が私を「化学大好き君」にしたことについては疑いがない。感謝してもしきれない。】ということに尽きる。次回の記事ではなにかの全合成論文の紹介を書くので、お楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
