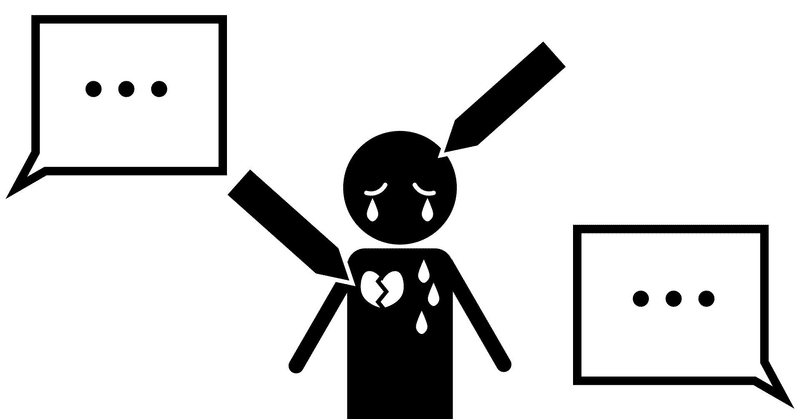
【読書感想文】親だって知っておきたい『いじめっ子・いじめられっ子の保護者支援マニュアル』
いきなり自分の話ではありますが、子どもの頃、私はいじめられっ子でした。
ニュースになりそうな、酷い出来事があったわけではないです。ただちょっと、チョークを投げる的にされたり、買ったばかりのペンを盗まれたり、机を蹴り飛ばされて泣かされたりした程度です。そういう行為の被害者になったときに、ニヤニヤ笑う加害者の顔の、醜さを知っている者です。
大人になった今もそれは忘れませんし、顔も名前もハッキリ覚えています。
別にそいつらが今、どこでどんな風に生きてるかなんてどうでもいいし、幸せだろうが不幸だろうが知ったこっちゃありません。言ってしまえば当時だって、高校に進学すれば離れられるからそれまでの辛抱、と考えることで耐え抜くことはできました。
どちらかというと、ショックだったのはそれに対する大人の対応でして。
昼休みにチョークを投げられ、制服の襟元が真っ白になったので(思えばあいつら、顔を狙ってたんですね)先生に報告に行くと、先生は午後の授業時間、私を別室に隔離しました。その後、話を聞いてはもらいましたが、先生の口から出たのはこんな言葉です。
「あいつらはね、手を出すなと叱ると「手は出してない、足を出したんだ」と言い返すような奴らなんだ」
つまりそれは、あいつらには言ってもムダだから、あなたが我慢するしかないの、ということで。
おかしいですよね。私、何か悪いことをしたわけじゃないのに。母親も、「やられたらやり返せ、やり返さないから舐められるんだ」と私を叱責しました。味方がいないのだと、思い知りました。
大人になった今、私はどんな風に救われればよかったのだろう、と考えます。
今、子どもの教育に関わる大人として、子どもの力になるにはどんな手段を持っておくべきなのかを知っておきたい。そんな思いでこの本を手に取りました。
『いじめっ子・いじめられっ子の保護者支援マニュアル』
マニュアル、とあるように、この本は学校で働く先生向けではあります。ですが、いじめに立ち向かうために先生に必要な心得の中には、保護者に協力してもらうべきこともありました。つまり、保護者だっていじめ解決のために知っておきたいポイントがあるのです。
今回はそんな、いじめと向き合う保護者のためにもなる部分を、ピックアップしながら紹介したいと思います。
1.学校と保護者が噛み合わない理由
学校、いじめ、対応……と聞くと、学校側が不誠実なイメージがなんとなく、浸透していませんか。不誠実な対応をされた、いじめの事実を隠蔽された、なんてニュースを見かけることが多いですよね。そもそも学校は「閉じられた社会」であるために、外部からは見えにくい性質があります。こんなニュースを聞かされると、うちの子は大丈夫だろうかと、心配になるかと思います。
ただ、いじめというものは、完全になくなるということはありません。
子ども同士が集まってコミュニティが生まれる。その中で、力の強い者と弱い者、運動が出来る子と出来ない子、頭の良い子とそうでない子……その善し悪しではなく、違いがあるがために、人は自分と比べて優越感や劣等感を覚えます。優越感から人を見下したり、劣等感から人を攻撃したり、不完全な子どもがそういうことをしてしまうのは、不可抗力とも言えます。
大体、大人だって完璧ではないじゃないですか。
いじめという言葉が使われず、犯罪になるがために一瞬すり替えられたように感じますが、似たようなことを大人もします(する大人がいます)。大人だって完全ではないのに、どうして子どもが自発的に予防したり、あるいは大人の目をすり抜けるのを阻止し、未然に防ぐことができるのでしょうか。「未然に・完全に・いじめをなくす」ことは不可能なのです。残念ながら。
ニュースの話に戻ります。
「○○学校ではこのようないじめ防止策を講じ、未然にいじめを防ぐことに成功しました!」なんてニュースはありえません。だって、起こってもいないことを防ぐことができたかどうかなんて、誰にもわかるはずがないからです。
いじめは大抵、起こって、それが最悪の形になったときにようやく、外部に情報が伝わってきます。つまり、事件になる前のニュースを我々は(当事者でもない限り)知る由もないのです。
我々はこのようなニュースのみで学校というもののイメージするので、大抵、我が身可愛さで子どもをぞんざいに扱う、悪者のような印象が植え付けられています。……と思っているのですが、これはいじめられっ子だった私の、悪いイメージでしかないのでしょうか。
そして学校側も、保護者といじめにまつわる話をするときは大抵、いじめの相談を受けるときです。これが適切な訴えであればいいのですが、こちらも時々「モンスターペアレント」などと称される保護者のイメージから、小さな事で騒ぎたてて、こちらを意のままにしようとする面倒な人、という印象を植え付けられている場合があります。これも、偏見であればいいのですが。
この本には、保護者と学校は互いに協力者でなければ、いじめを解決することはできない、と書いています。対等なパートナーであり、互いに必要な行動を取ったり、連絡を取り合って情報を共有する必要がある。このようなイメージは、お互い「いじめをなんとかしたい」と思っている両者にとってデメリットでしかないのです。
もし、学校へ悪いイメージだけがあって、そのために「こちらがしっかり言ってやらねば」をいう姿勢で話し合いに臨むつもりならば、少しだけ、その態度を変えてみてほしいのです。もちろん、学校がいじめを隠蔽しようとしたりしない、ごく普通の信頼できる先生たちのいる場所であることが前提ですが。
2.先生のとるべき行動マニュアル
この本に書かれている、先生に求められる行動は、大雑把に分けると以下の3つになります。
①保護者に対し、冷静かつ誠実に対応する
②事実を突き止める
③保護者に協力を求める
先に書いたように、いじめを未然に、完全に防ぐことは不可能です。
子どもは不完全ではありますが、先生にバレないよう気をつけていじめをするとか、怒られない程度のイタズラから徐々に悪化していくだとか、家族にバラされないようその場では謝るとか、そういった悪知恵はもっています。それまでの過程を一切知らない状態で、急にいじめが発覚したとすれば、ショックを受けるのは仕方ないですが「学校は一体今まで何をしてたんだ!」と感情的になるのは逆効果です。だって、学校側だけでなんとかできることなら、情報なんて一切届かなかったでしょうから。
先生に冷静であれ、誠実であれと本にはありますが、保護者にだって必要なことでもあります。大事なのは、事実を正確に受け止め、解決に導くことです。
さて、②事実を突き止める、とありますが、これはなかなか至難の業です。
子どもはきっと、自分が悪いことをしたと分かっていても、素直には言いたくないでしょうから嘘をつくかも知れません。かといって、被害者の意見を一方的に鵜呑みにするわけにもいきません。これがまかり通れば、被害者のフリをする子どもが増えるだけです。(加害者のしたことが悪いのは大前提でも)加害者だって、話を聞いてもらう権利くらいはあります。
私の経験から、こんな話を。
体育の時間に、ストレッチが終わった後私は腕を振っていて、それがたまたま隣を歩いてきた女子にぶつかってしまいました。私はとっさに「ごめん」と言ったつもりなのですが、その子には聞こえなかったようで、ぼそぼそと私が「文句を言った」と思い込んだようなのです。そこからこの女子は怒りが収まらず、数日もの間私に酷い態度をとりました。給食を食べている私の机を蹴って食事を散らかしたり、すれ違い様にわざと私にぶつかって「謝れよ」と舌打ちをしたり。
目に余る行動が多かったので、私とその子は先生に呼ばれました。
そして上の状況が発覚したとき、その女子は「聞こえないなら謝ってないのと同じ」と私を非難しました。それは確かにそうなのですが、私としてもそんな嫌がらせを平気でやるような女子相手に、大声を出せるほど肝の据わった子ではなかったので無理な話です。萎縮しながらようやくぼそっと呟けた謝罪でこんな目に遭うのに、大声を出したって「怒鳴ってきた」とか何とか言われるかもしれない……。
そんなチキンな陰キャオタクに馬鹿にされた、という思い込みは、彼女にとって我慢ならなかったのでしょう。見事、典型的な嫌がらせをする悪役・いじめっ子となってしまったワケです。
……どうでしょうか。
ここまでの情報は、先生が話し合いの場を設けて両者の意見を聞いたことで、ようやく見えた事実です。こうした情報は、たとえ我が子がどれだけ正直者でもわからないのです。そのため、事実は学校側に調査をしてもらい、誠実に報告してもらわなければならないのです。
3.いじめられた子の保護者としてできること
いじめが発覚し、我が子が被害者だったと知ったとき、冷静でいられる保護者がどれだけいるでしょうか。それでも敢えて、冷静に、以下の2つを実践してもらいたいのです。
①いじめの相談を学校に行う
保護者として、子どものいじめは早急に解決してもらいたいことです。
そのためにはまず、いじめが発覚した段階ですぐ学校に相談し、協力体制を組むことが理想です。学校がすでに把握していれば、現時点でどのような対応をしているかなどの情報をもらえるでしょうし、あるいはまだ知られていないのであれば、すぐに調査してもらえます。
事実を学校に調査してもらい、事実を把握した上でどのような対応をしてもらえるのか。それを知る権利がありますから、いじめの解決を目指して協力者であってほしいのです。
②子どもに、相談してくれたことはよかったと伝える
子どもの中には、親に知られたくない、というタイプがいます。色々理由はあるかと思いますが、心配をかけたくないとか、お前も悪いところがあるんじゃないかと責められるのではとか、不安を抱えていることがしばしばあります。
いじめの事実に親がショックを受けることすら、子どもにとっては「話すんじゃなかった」と考える要因になりかねません。心配をかけたことを、迷惑をかけたと思い込んでしまうかもしれないからです。
なのでまずは「話してくれてありがとう」と伝えてほしいのです。
いじめられた子に、あなたが悪いのではないと伝えてください。
大人に助けを求めることが、悪いことではないと教えてあげてください。
話して良かった、親は自分の味方なんだと、理解させてあげてください。
少なくともこれで、これからも親に助けを求める、という選択肢が生まれます。
4.いじめた子の保護者としてできること
こちらは保護者にとって、いじめられていた場合よりショックが大きいかも知れません。
誰かをいじめた、という事実が発覚するのは、いじめられた側が被害を訴えたときなど後手に回ることが多いです。本人からいじめてやった、と報告を受けることはほとんどないでしょう。動かぬ証拠を持ってくるまで、嘘を突き通せると考えるかもしれません。保護者にとってこちらも大きなショックを受ける話ですが、そのとき我々にできることは何でしょうか。
①事実を学校と共有する
そして先に書いたように、いじめを解決するには冷静に、誠実に事実を共有することが不可欠です。冷静に、という言い方をするのは「いじめをしてしまったんですね!すぐに頭ひっぱたいて反省させます!」と極端な解決を目指すわけではない、ということです。誠実に、というのも「何か理由があったんじゃないですか?相手にも原因があったのではないですか?」と本質と別のことに意識が向いてしまわないよう、まずは起こったことを受け止めてほしいという意味です。
いじめをするのは家庭に要因がある、と考える人がいます。
全くあり得ない、というわけではありませんが、必ずしも家庭にのみ責任があるわけではないと知っておいてください。ゲームやネット、特にSNSなど、誰かが誰かを傷つけている場面なんていくらでもあります。そういった暴力に全く触れずに生きていくことは不可能です。
どこで何を知ったから、と原因を探ったり、あれこれ禁止にすることに意味はありません。大事なのはこれから、どうやって責任をとるかです。いじめという行動は許されるものではなく、繰り返せば責任は負い続けるものであると、子どもに理解してもらう必要があります。
②いじめをした=処罰、と短絡的に考えない
何か悪いことをしたなら、罰を受けるべき。
法律を破れば逮捕されるように、犯罪(悪いこと)=刑罰の対象、となるのは事実です。では、どうして罰を受けるべきなのか。それは罪を償う必要があるからです。
いじめをした。
そこにどんな事情があれ、誰かを傷つけたことに変わりはない。
事情についてはしっかり耳を傾ける、それは周りの大人がすべきことです。その上で、自分が誰かを傷つけた事実については責任を負わねばならないことを、子どもに学んでもらわなければなりません。
大人がいくら「お前は悪いことをしたのだから、ゲームを取り上げる!」と罰を与えても、子どもが納得していないのなら意味がありません。先に書いた、暴力で不満を訴えた女子のように、子どもには子どもの意見があり、それを訴える手段として間違った「いじめ」を選んだかもしれない。間違った手段であることを知らしめるため、責任を負わねばならないことを教えることが大切です。罰を与えることが目的になってはいけません。大人は子どもに、自分の力で適切な行動を選べるよう、情報やその手段を与えるべきなのです。
また、私の経験ですが。
私がいじめにあったとき、そしてそれが先生に発覚したとき、大抵先生はいじめた側を連れてきて、私に頭を下げさせるという解決方法をとりました。私にチョークを投げた男子たちは複数人いまして、彼らも授業後に私の前に呼びつけられ、謝罪をさせられました。その後、
「これでいい?」と先生が言ったことを、私は忘れません。
何が良かったんですか、先生。
一番チョークをぶつけてゲラゲラ笑っていた、首謀者の男子はそこにいませんでした。おまけみたいにくっついていた男子だけです。首謀者が謝ってもないのに、体よく授業をサボれた腹立つ陰キャに、自分は頭を下げさせられた。彼らにこの事実が残って、何が良かったんでしょうか。帰り際、窓越しに睨みながら中指立ててましたよ彼ら。それを見もせず、何が「これでいい?」だったんでしょう。これで先生が私の味方だなんて、思えるはずもありません。二度と頼るまいと思った出来事です。
私からすれば、チョークを投げようと思った理由なんて知ったこっちゃないですが、こんな一方的な「処罰」で何かいじめが収まるとか、解決するとか思える人はそういないでしょう。私だって謝罪を求めたわけではなくて、二度とそれが起こらなければそれでよかった。それなのに先生の対応は、新たな火種にガソリンを撒かれたような気分です。
謝罪なんてどうでもいいから、どうか、私の知らないところで、彼らの鬱憤が解消されてくれ。大人に求めていたのはそんなことでした。処罰でもなく、学校を誰にとっても等しく安全な場所にしてほしいだけだったんです。
保護者だって先生だって、いじめをする子で居続けてほしくはなかったでしょう。
あのときの彼らの責任の取り方は、正しかったんでしょうか。そうでないなら、どんな解決法があればよかったのでしょうか。少なくともその場でパッと解決する、魔法の話し合いなんてものは存在しません。子ども同士(+その先生)だけで、解決するとも思えません。やっぱり、保護者にも助けてもらう必要があるのです。
5.最後に
本の感想というより、子どもの頃の私の周りにいた、大人への不満をぶつけるような文になってしまいましたが、どのように受け取っていただけたでしょうか。ポイントだけなら目次でまとまっているので、そこだけでもお役に立てましたら幸いです。
私は親という立場になったことはないので、我が子を大切に思う親がこのような状況に陥ったとき、どのように追い詰められるかは想像のしようがありません。私にあるのは、子どもだった経験だけです。特に、いじめられる側で、しかも周りの大人が助けてくれない環境にいた、という経験だけ。
そんな経験を持って大人になった私が、この本を読んだ感想は正直「それって当たり前のことじゃない?」です。子供の頃の私が「だよねぇ?」と相槌します。
学校だって保護者だって、いじめなんてなくなってほしいと願っているに決まっている。それなのに上手くいかないのは、たとえば先生が仕事に忙殺されていて、手が回らないとか。保護者が過敏になりすぎたり、あるいは関心がなさすぎて連携がとれないとか。学生時代の私でも、いくらでも想像はつきます。
でも、本当のところは「面倒事に関わりたくない」と誰しもが思っているからかなあ、と。
子どもは、大人に助けてもらわないとどうすることもできません。
私みたいなのが大人になってしまうと、人に助けを求めるのが極端に苦手になります。未だに上手く出来ません。大人なんだから、しっかりしなきゃいけないのに。
そんな要らない苦労を抱えた大人なので、子どもにはちょっとでも、楽して生きる術を知っていてほしいなあと、思うのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
