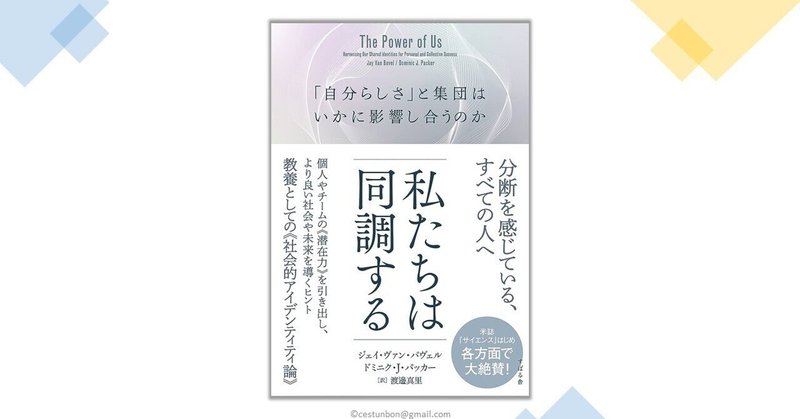
The power of Us 『わたしたち』のパワフルさ。アディダス・カナディアン・Think Different・キング牧師
ひとは何かしらの社会、集団に所属している。
「〇〇会社の✕✕部門の△△です」と自己紹介するとき、わたしは個人ではなく集団のアイデンティティを背負っている。
「じぶんらしさってなんだろう」と考えるとき、日々いっしょに過ごす人たちの存在にじぶんがどれだけ密接に影響を受けているか。人が集まり、同調し、アイデンティティを共有する。その理由やメリットについて、『The Power of Us』から学んだことを紹介したい。(ちなみに「私たちは同調する」がセンターにでかでかと書かれたこの装丁に、わたしは同調しない)
兄弟げんかが街中のけんかに
二人の兄弟げんかが、町をまっぷたつに分けることがある。
ドイツのヘルツォーゲンアウラッハは、世界大手シューズメーカーであるアディダスとプーマの本拠地がある。この2社が、まさに町を分断させた2人の兄弟の対立からうまれた。
兄弟の対立がどうして深まったのかは、諸説あるようだが、同じ街に住む住民たちも総出でこの対立に参加するようになる。
町を歩けば、互いの靴を見下ろして、話している相手が自派の一員であることを確かめた。かくしてヘルツォーゲンアウラッハは「首の曲がった町」として知られることになった。
同じ会社の社員ならまだしも、どうして町の住民たちまでこの争いに足をつっこんだのか。それが本書がつきつめようとしている一番の問題だ。
ひとが同調する3つの理由
仲のいい人が履いてる靴をじぶんも履いたり、同じ本を読んだり、同じお店に行ったり。人は周囲の人になるべく合わせて、協調性を示したり、共通の話題をつくって、さらに仲良くなる。
私たちは周囲に溶け込みたいとき、そしてまた他人を情報源として信頼しているときに、他人に追随する。これに加えて、同調が生じる3つ目の理由は、尊重するアイデンティティを表現するためだ。(略)私たちが属する集団というものには、「ここではこうする」という明確な規範、つまり、その集団の一員であることを証する志向や心構え、行動などのパターンがある。そして集団への同化が強ければ強いほど、その集団の規範を自らの行動によって体現したいと思う傾向は強くなる。
じぶんたちとは別の集団がしているから、じぶんたちはしない、ということを選択することもあるし、別の集団がしないからじぶんたちはする、ということもある。
はたからみるとそこまでしなくても、、と思うことは多い。転職して入った会社に独自な文化(毎日同じ制服を着てたり、無意識に同じ口癖がうつっていたり)があると、ちょっとした宗教性のようなものを感じてしまう。
アイデンティティを共有するメリット
カナダで最も歴史あるビール会社、モルソンの2000年のキャンペーン。
「I am Canadian」というタイトルのとおり、カナダとアメリカを対比することでじぶんたちが何者なのかを強く意識させる内容だ。(ちなみにビールの名前もカナディアン)この1分のCMは成功し、ビールが売れただけでなく、カナダ人の一体感と独自性の2つで多くの人々から共感された。
国や企業やコミュニティ。集団の一員になることは、なんと健康にもいい。
人は他者と関わり、溶け込み、つながりたいという強い欲求がある。この欲求が満たされないと、耐え難い苦痛を感じることがある。他社との有意義な社会的つながりがないという感覚、つまり孤独感は、心だけでなく身体の健康を損なう要因としても知られている。実際、社会学者のロバート・パットナムのよく知られた説に、次のようなものがある。もしある人が1日人はこのタバコを吸い、またどの集団にも属していない場合、どちらを変えても結果はさほど変わらない。すなわち、タバコをやめるか、集団に属するかーその健康への影響は、どちらも同程度だという説だ。
『Think Different』は最強のアイデンティティ
どんな集団の一員になりたいか、と聞かれて、まっさきに思い浮かぶ会社のひとつはAppleだろう。ユニークさを大事にする革新的な会社というイメージは1984年の『Think Different』キャンペーンで強く打ち出された。
アインシュタイン、パブロ・ピカソなど、これまでの常識や社会通念を打ち破ってきた著名人たち。彼らのように「ひととちがうことを考える」ことを大事にするブランドは最強だ。
最も人を引き付ける集団はたいてい、人間のもつ基本的だが相反する2つの動機、すなわち、所属欲求と独自欲求を満たしている集団である。(略)
人には集団に属したいという欲求がある一方で、社会的アイデンティティの力の一部は、集団とは相容れないものー自分が何者であり、何者でないかを明確にしてくれる独自性からうまれるということだ。(略)
私たちはだれかと同じでありたいと思うと同時に、だれかとはちがうと思いたいのである。
iPhoneをもつ=みんなと同じ&みんなと違う。日本人の多くがApple製品を好んでいるのも、協調性をおもんじる国民だからこそ。Apple社員にはなれなくとも、Appleのファンとして支持することはできる。多数派でありながらユニークでもあるなんて、たしかにそんなブランドなかなかない。
道徳的な『目の上のたんこぶ』
「I have a dream. (私には夢がある)」と演説をしたキング牧師。人種差別と闘い、演説をして、その翌年のノーベル平和賞を受賞した直後、彼を好意的に評価する人は多かったことだろう。とおもいきや、そうではない。

1966年に彼を好意的にみていたのはたったの33%。一方で否定的な意見は63%もあった。黒人を支援するためのアクションを継続的に推し進めるキング牧師は、白人からすると脅威であったのはまちがいない。しかしそれだけではなさそうだ。
現代においても、人は「道徳的な反逆者」、つまり、大きな困難に直面しつつも自分の価値観に従って生きる人びとを不快に感じているのが実情だ。(略)
道徳的な反逆者が遠くにいるとき、私たちは彼らを称賛する。だが、「自分は本来、善良で道徳的な人間である」という信念が脅かされたとき、彼らへの見方は変化する。この場合、道徳的な反逆者の存在によって、自分が悪人のように感じられるようになる。また「他者からもそう見えるにちがいない」と感じ、より道徳的な人たちから否定的に見られるのを恐れるようになるからだ
身近ないい人は、目の上のたんこぶ。「わたしたち」とはいえない良い人は、むしろ邪魔で嫌われ者になってしまう。自分ができないことをやってのけてしまう善人は、自分の存在を小さくしてしまいかねない敵なのだ。
わたしたちと、わたしを生きる
みんな自分が素晴らしい存在とまでは言えなくても、平均以上だとは思っていたい。数えきれないほどに人がたくさんいて、自分なんて大した存在じゃないんだってわかっていても、かけがえない唯一無二のじぶんだと、こっそりひっそりとでも思っていたい。
正解がない、確実なものがなにひとつない現代。だからこそ、周囲と手を取り合い、協力しないといけないし、じぶんらしさも必要。
わたしらしく、わたしたちと、わたしを生きる。
「じぶんってなんなんだろう」
「ひとと生きるのってなんでなんだろう」
そんなことを考えることがあるあなたに、おすすめの一冊です。
