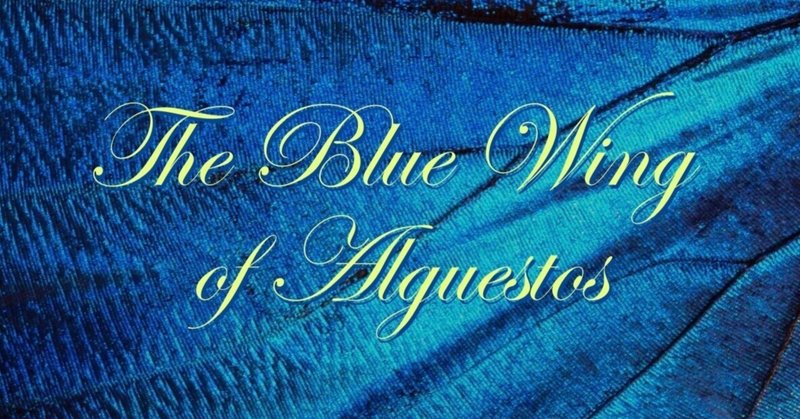
【アルギュストスの青い翅】第2話 満月の運河
黄金色の巨大な月が、建物の角から顔を出した。すり減った石畳が照らし出される。光の道だ。導かれるようにその上を歩く。
運河はまっすぐ目の前。レンガ作りの建物の間を抜ければ、運河と平行して走る道に出る。そこを左へ折れてしばらく行くと小さな船着き場が見えてくる。
運河に張り出したその場所には柵などなく、すとんと切り落とされてすぐに水面だ。俺のお気に入りの場所。いつものように縁に腰を下ろせば、水はまだ、日中の熱を閉じ込めて温かなままだった。
明日から夏休み。だけど学校から解放されたこの夜は、どこにも属さない特別なもののように感じられた。
無神経を装って持ちこたえてきた今日までの俺と、多分自暴自棄になってしまうだろう明日からの俺は、どちらも嘘偽りに塗り固められたもの。そんな自分に失望しながらも、本当の気持ちをさらけ出せずにいた。でもなぜだろう、今だけは今夜だけは、なにものにも囚われず、素直になれるような気がした。
深く長く息を吐き出し、水の中に入れた右手をゆっくりと搔き回す。徐々にスピードを早めれば、柔らかだった波紋がでたらめな軌跡を描き始めた。澄まし顔で水面に並んでいた月も飛んだり跳ねたり。俺はそんな水を、掬ってはこぼし、掬ってはこぼした。
夜の中に、白い包帯を巻いた左手首が浮かび上がる。薄っぺらな布なのに、まるで永遠に外せない手枷のようにずっしりと重い。その手で脇に置いてあったガラス瓶を握れば、少し力を込めただけで突き刺すような痛みが走った。
「……馬鹿みたいに痛えや」
だけどその痛みこそが、俺がこの世界にいることを教えてくれる。捨てたいものでありすがりつきたいもの。たまらない苛立ちと、この場から今すぐ逃げ出したいような気持ちが同時に噴き出し、瓶を握る手に思わず力が籠もる。再び生まれた鋭い痛み。唇を噛み締め、俺はガラス瓶の中で瞬く青い光を見つめた。
青は求める限りいつだって応えてくれる温かい色だ。だけど今、瓶の中のものはあまりにも弱々しく儚げだった。まるで、おまえの夢なんて所詮消えていくものなんだと言われているようで、身を震わせずにはいられない。
「俺は毒か……。そうだな、そうだろうよ。誰からも必要とされない毒だ。忌み嫌われ、決して受け入れてもらえない毒。……でも、だったらなんだよ! 俺だって、俺だって……好きでそうなったわけじゃない……」
肩を寄せ合い、誰かと笑いながら満月を見上げたい。心の中のものを全部掘り起こして、その下敷きになっている自分を引っ張り出したい。心を冷やすばかりの重い仮面を剥ぎ取って、今すぐ運河に投げ込んでしまいたい。
次々と込み上げてくる願いに翻弄される。どれだけ飢えているのか。生暖かい風の中にいるのに、寒くて凍えそうだ。無性に寂しかった。温もりが欲しいと心が叫び続ける。
うまくやっていたはずだ。俺が何であろうと誰であろうと、誰が何を言おうとどんな目で見ようと、ちゃんと笑らえていたはず。だけど本当はそうじゃなかった……。
途端、ぞっとするような孤独が襲ってきた。それは俺の真ん中に深く突き刺さり、少しでも気を抜けば、ばらばらに砕かれてしまいそうだ。俺は傷だらけの心をかばうように身を丸め、ガラス瓶を自分に押しつけた。
「ごめんな、ごめんな……」
本来なら、俺がこの儚げな青を守るべきなのだ。応えてやらなくてはいけない。なのに頼り続けるばかりだ。今だって……。そんな自分が情けなかった。でも、なに一つわからないのだ。どうしていいのか、どうするべきなのか、皆目見当がつかない。俺はただ、ガラス瓶に入った青を抱きしめることしかできなかった。
その時、なにかを感じた。なにかがやってくる。まっすぐ俺に向かって。
はっとして顔を上げれば正面に一隻の小舟が見えた。黒くてしなやかな姿は闇に溶け込まんばかりなのに、その舳先には月光にも負けない輝きがある。
俺はその舟をじっと見つめた。猫一匹通らない深夜の通り、静まり返った運河、そして見知らぬ舟。でもなぜかちっとも怖いと思わなかった。この瞬間がくると、どこかでわかっていたような気さえした。
黒い舟には小柄な人影があった。少し遠くてはっきりしないけれど、うっすらと浮かび上がる顔は少年だろうか。きっちりと襟が詰まった服を着ているように見える。
石畳の縁に腰かけ、足を水に突っこんだまま、俺は視線を外せなかった。やがて、月光に照らし出される中を近づいてきた彼は、小舟二つ半ほど向こうから、実に礼儀正しく声をかけてきた。
「やあ、こんばんは。素敵な夜だね」
少し低めでまろやかで、耳に心地よい声だった。
「ああ。水も温いし、なかなか快適だよ」
まるで昔から知っているかのように、なんのためらいもなく俺も答えた。
「あっ、俺、ジョナシス=アルギュストス・セーゲル・レ・ディカポーネ。みんなはセーゲルって呼ぶ」
聞かれたわけでもないのにそう続ける。
もう一こぎ、舟は俺に近づいて、顔がよく見えるようになった。俺は密かに息を飲んだ。見たこともないほど綺麗な少年だったからだ。年は同じくらいだろうか。髪の色は旧地区の特徴でもある金色よりももっと硬質な輝きをたたえていて、より光を感じさせる白金だ。そしてなによりも、その瞳が凄まじく印象的だった。
一見金色でこの町風。けれどその瞳が俺を真正面から捉えた時、本当の色を教えられた。月の色だ。黄金の様な白銀の様な、それは月光の輝きだった。
はるか頭上に輝く孤高の光。冷たくきらめく神秘。その色は俺の心を一瞬で撃ち抜いた。あまりにも澄み切った輝きに、もしかして彼は月の精なのではないだろうかと思った。馬鹿げた表現かもしれない、けれどそれしか思い浮かばなかったし、それ以上のものはないだろうと思えたのだ。
とにかく、この出会いに心はひどくわなないていた。しかしそれは彼も同じだったようだ。大きな目をさらに見開いて彼は言った。
「ディカポーネ! 薬屋さんのディカポーネ? あぁ、こんなところで会えるなんて……嬉しいよ!」
第3話に続く https://note.com/ccielblue18/n/na992a0cbae6e
第1話に戻る https://note.com/ccielblue18/n/nee437621f2a7
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

