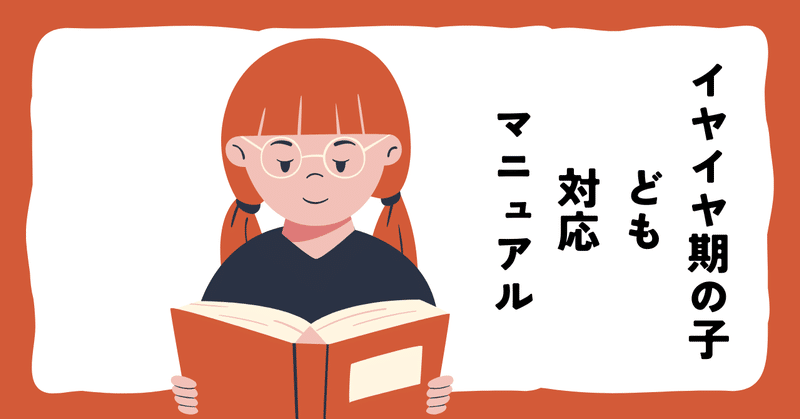
イヤイヤ期への認知行動療法
2才になる我が子は絶賛イヤイヤ期中です。主張が強く、親が何かをしようとすると「イヤイヤ」が止まりません。一体どのように関われば良いか分からなくなることもあります。可愛らしくもミニ怪獣と化した我が子とどのように接すれば良いのか、家族のメンタルヘルスはどのように保てば良いのかについて今回はまとめてみることにしました。
イヤイヤ期とは
イヤイヤ期は医学用語ではありません。イヤイヤ期は子どもの成長過程において自己主張などの自我が芽生えると同時に感情のブレーキとして本来機能する脳の前頭前野が未発達のため、感情や主張がコントロールできない状態になります。ブレーキの効かない自転車に乗っているようなイメージでしょうか。3~4才頃になると前頭前野が成長し自然にブレーキが効き感情がある程度コントロールできるようになります。
イヤイヤ期の子どもと過ごすということ
とはいえ、ただただ成長を待つのも大変です。子どもと外食をしているとすぐに飽きて奇声をあげるなどして自己主張をします。周りの客も次第に苛立ちはじめ文句を言われることもあります。ですが、どれだけ注意したところで落ち着きどころかより強く主張してくるようになります。毎日このような日々が続くと親もヘロヘロになります。家にいても外にいても気が休まらず家族も子ども同様に感情のブレーキが効きづらくなります。
イヤイヤ期への対応
親であり専門家でもある私にできることはないかとさまざまな情報をリサーチしたり対応を模索しました。その結果分かったことは、ある程度は対策できるが万能な方法はないということ。ですが、いくらか対策をとることで負担は軽減するのでイヤイヤ期に悩む同志はぜひご活用ください。
1.イヤイヤ期が発動した時の対応
うちの子は不平不満があると大きな声で主張をします。大きな声で主張をすれば要求が通ってしまうというのも理由の一つです。まず最初にやったことは大きな声を「象さんの声」、小さな声を「アリさんの声」と弁別できるよう普段から子どもに伝えました。次第に「アリさんの声で話してみて」と伝えると小さな声で話してくれるようになりました。次に、大きな声で主張した時には一貫した態度で要求に応えず、その代わりに「アリさんの声」と伝えます。見事に「アリさんの声」で要求を伝えてきた際には速やかに対応することにしました。完璧とまではいきませんが、要求のいくらかは「アリさんの声」でしてくれるようになりました。
2.無理なものは無理
車の運転中に「イヤイヤ期」が発動してもどうすることもできません。どれだけ大きな声を出しても暴れても親は一貫した態度で接することにしました。すると次第に車に乗っている時には暴れることがなくなってきました。この状態になると要求が通らないことが学習されたのかもしれません。
認知行動療法の視点から
いついかなる時も要求を叶えましょうといった対策が書かれていることもありますが場合によっては逆効果になることもあります。
人がある行動を繰り返すのは、その行動をすることによってデメリットを取り除けるかメリットが手に入るといった結果が生じるためです。
欲しいものアリ→「買って」と要求する→親に断られる
欲しいものアリ→大きな声で「買って」と要求する→買ってもらえる
このような経験を繰り返すと何らかの要求をする時に「大きな声」が有効であることを学びます。無条件に要求に応えていてはエスカレートしてしまうこともあるのです。かといってすべてを無視しましょうと言っている訳ではありません。線引きをしっかりと考えておく必要があります。
家族のメンタルヘルスケア
「自分の育て方が悪いのではないか」などと考え思い悩む、普段の育児に疲弊するなど育児には負担がつきものです。育児は長距離走でもありますので無理は続きません。誰よりも親自身のメンタルヘルスを保つことが大切になります。そうはいってもなかなか休みがとれないのが育児でもあります。どうか時には専門家を頼ってみてください。
認知行動療法カウンセリングセンター
認知行動療法カウンセリングセンターは広島、山口、沖縄、大阪、東京にある認知行動療法を専門としたカウンセリングルームです。育児についての相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
認知行動療法カウンセリングセンター | LINE 公式アカウント
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
