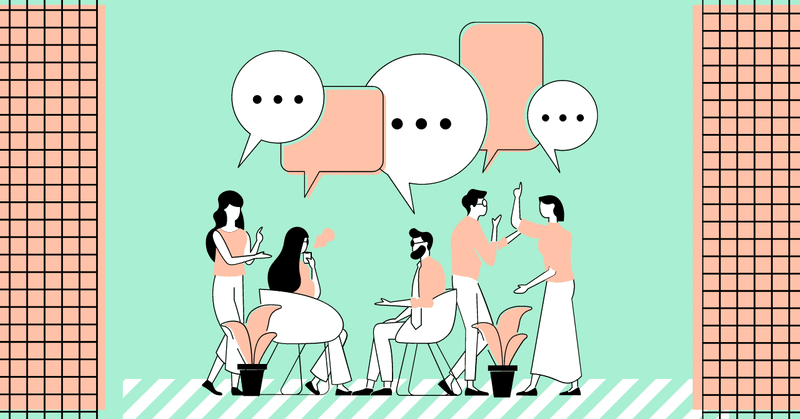
スピーチ恐怖の対処法
大阪のカウンセリング機関「認知行動療法カウンセリングセンター大阪店」の岡村です。今回はスピーチ恐怖の対処法についてまとめてみたいと思います。スピーチ恐怖は日本では人見知りやシャイなど自身の性格のように受け取られますが、生活にさまざまな支障をきたすこころの困りごとです。周囲に理解されないまま苦しまれている方も多いことかと思います。今回の記事がスピーチ恐怖にお困りの方のお役に少しでもたてれば幸いです。
スピーチ恐怖とは
スピーチ恐怖がどのような困りごとかについては上記の記事をご参照ください。今回はより詳細にスピーチ恐怖の改善法について解説していきたいと思います。
スピーチ恐怖の対処法
スピーチ恐怖の対処法として認知行動療法が有用です。今回はスピーチ恐怖に悩むAさんを例にその実際を開設していきたいと思います。なおAさんは架空の事例ですので実際には存在しません。
背景
Aさんは小学生の頃からグループ内で意見をすることが苦手でした。授業中などみんなの前で意見を求められたり黒板に問題の答えを書くことも負担に感じながら我慢して過ごしました。中学進学後にはさらに負担に感じるようになりました。友人が誤った答えをみんなの前で言ったところ、周りの人がそれをからかう様子を目撃してから、恐怖は高まり自分が発表する機会がある時には学校を休むようになりました。高校は通信制を選択し人前での発表機会は減り気持ちも安定していましたが大学進学後、多くの講義において意見を求められる機会が増えゼミにおいて定期的に発表する機会が増えました。その生活に耐えられなくなったAさんは家族に相談したところ、認知行動療法の専門機関を発見し来所することになりました。
カウンセリング初回
カウンセリング初回ではまず質問形式の心理検査を複数行うことになりました。この検査を通して自身がどのような状態なのかを把握していきます。検査結果はあくまで今現在の状態を表したものであり、病院で〇〇症など診断されることとは異なることも説明を受けます。その後、カウンセリングで改善したいことは何かの説明と今現在の様子、これまでの経過などをお話しました。その際、カウンセラーは否定や価値観の押し付けなどはせず親身になって話を聴いてくれました。続いて認知行動療法についての説明を受けました。
認知行動療法の説明
認知行動療法とは、こころのこまりごとをある状況おける自身の考え方や行動がミスマッチを起こしている状態であると捉えます。サバンナという状況において「ライオンは危険な生き物で遭遇すれば大変なことになる。なるべく夜間の外出は避けよう」と考え、夜間はキャンプで過ごすことは自然なことではないでしょうか。しかし、交差点を移動中という状況において「周囲の人は自分を嫌っている。近づくと悪口を言われてしまう」と考え、交差点を避けることを繰り返していては行きたいお店に行けないなど生活に支障をきたします。本当はそれほど警戒しなくても良い状況において必要以上に警戒することで生活に支障が出ているともいえるでしょうか。こころの困りごとは何らかの学習経験により出現することもあれば、ある日突然これまで平気だったことに恐怖や不快感を感じるようになる場合もあります。なので原因が不明なことも多々あります。いずれにしろ現在のパターンを把握し、そのパターンを可能な範囲で調整していきます。その結果、予想していたような事態にはならない、もしくはなったとしても対処可能だと体験的に理解できると次第に安心感を覚えます。危険だと思っていた交差点も安心して歩くことが出来るのです。ただ、それは決して容易なことではありません。頭の中で本当は安全だと分かってはいてもバンジージャンプが怖いのと同様です。ひょっとするとそれ以上のことかもしれません。その点に配慮し無理のないペースで調整する必要があります。何年もかけて歯科調整をするような感じでしょうか。もちろん短期間で調整可能な場合もあります。

自分の場合はどのようなパターンなのかをカウンセラーと一緒に整理していきました。人から注目が集まる状況で、「間違ったらみんなにバカにされて孤立してしまう。突き放されてしまう。ちゃんとしなくちゃ」と考え、事前に何度も練習をしたり台本を用意したり、そもそも休んでしまうといった対応をしていたことが分かってきました。カウンセラーは〈それらの対応もどこかであなたを守ってくれていたのかもしれませんね。だけど、その対応方法だけだど負担が大きくなってしまったのかもしれませんね〉とこれまでの自分について認めてくれたうえで他の対策についても検討していこうと伝えてくれました。初回の最後には次回までのホームワークが出ました。今回話したことが実生活でどのくらい出現するか、実際の状況でも今日話したような考えが浮かぶのか、実際の対処について整理してくるというものでした。

2回目以降のカウンセリング
2回目の最初は、カウンセリング中に話したいテーマをきめていきました。今回はホームワークの振り返りと、スピーチ恐怖の新しい対処法についてお話することになりました。ホームワークを振り返ったところ、前回のカウンセリングで話したようなパターンがあることが明らかになりました。
これまでやってきた対処は一時的には安心感を得れるけど恐怖はずっと続くことも分かってきました。これからは、長い目でみても無理をしなくてすむ対処法について検討していくことになりました。最初にカウンセラーに質問されたことは、〈最初は苦手だったけど繰り返すうちに平気になったことはありますか?〉といったことでした。最初はそんな体験ないと思っていましたが、よくよく考えてみると自転車に乗る時は最初怖かったけど次第に慣れていったことを思い出しました。カウンセリングではそのことを例に、最初はどうしても怖いけど少しずつ転げることに慣れてくることと、予想と実際にどのくらい違いがあるか確かめることが大切であるという話をしました。自分の場合は、スピーチがうまくいかないことが本当にそれほどまでに危険なことか試すことだと思いました。しかし、頭では分かっていてもそれは難しいことをカウンセラーに伝えました。カウンセラーはその発言に理解を示してくれました。〈まずは絶対に安心なことから練習しましょうか。こけても痛くないスポンジの上で自転車に乗るような感じで。スピーチ恐怖では人がそれに当てはまりますかね〉と聞かれました。家族や仲の良い友人の前で事情を話したうえでスピーチをすることがそれに近いことを話したところ、実際にそれをやってみることになりました。帰宅後、家族や友人に事情を説明して実際に5分ほどスピーチをしてみました。事情は伝えているにも関わらず予想以上に緊張し2分ほどで終わってしまいました。カウンセラーからは最初はうまくいかなくても繰り返しの練習が大切だと聞いていたので週3回は練習を繰り返しました。次第に少しずつ慣れていき5分間話しきることができました。
次のカウンセリングではその結果を振り返ることになりました。カウンセラーからは〈しばらく今のペースでもバッチリだと思うし、ステップアップもできるけどあなたはどうしたいですか?〉と質問されました。少し自信もついたこともあり、大学内で分からないことを分からないままに発表してみて質問されても分からないと正直に言ってみることに挑戦したいと伝えました。カウンセリング内で何度か練習を行い実際にやってみるこになりました。実際は想定以上に緊張し挑戦しようにもできませんでした。結果的に、友人の力もかり何とか思いきって挑戦することができました。手足は震え吐き気までしたことを覚えています。実際にやってみると少しガッカリしたのは想像以上に周りが無反応だったことです。笑われることもなければ心配もされませんでした。拍子抜けしたのと同時に負担が少しだけ軽減していきました。その後もカウンセリングでは一進一退はあるもののさまざまなことにチャレンジをいていきました。
認知行動療法を振り返る

認知行動療法にはさまざまな介入法(対処法)が存在します。どの介入法があっているかはしっかりと相談者の情報を整理したうえで選択していく必要があります。その際、カウンセラーが勝手に選択をするのではなく相談者と一緒に何が良さそうか検討していきます。私の場合は、具体的な内容はほぼ相談者自身に決めてもらいます。あれもこれもやれば良いというものではありません。ペースとタイミングが重要なのです。また、介入法を試すも試さないも自由であることが大切です。命に危険がある場合などの例外を除き、認知行動療法は主体的に取り組むことが大切になります。
認知行動療法カウンセリングセンター
認知行動療法カウンセリングセンターではトレーニングを積んだ専門家による認知行動療法を受けることができます。事前無料相談もありますのでまずは一度ご相談ください。対面だけでなくオンラインでのカウンセリングもあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
