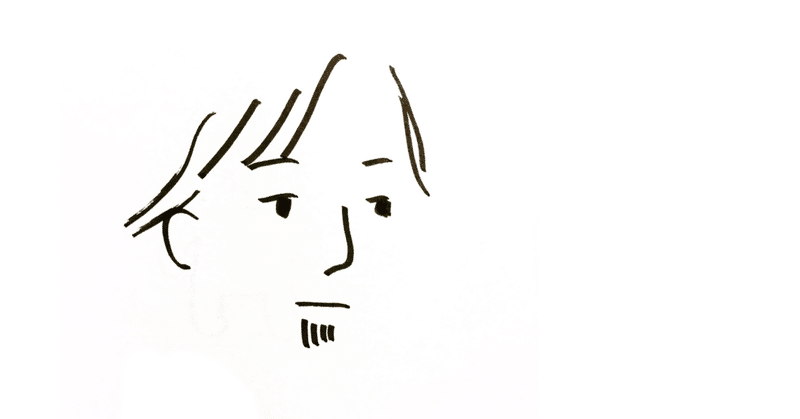
『菓子祭』 吉行淳之介
夏の休日。
冷房の効いた快適な部屋で、たまには吉行淳之介でも、と短編集を手に取った。
*****
「煙突男」
『ヒトラー』というドキュメント映画を観に行く、麻田という男。
彼はヒトラー及びナチスに関心を持っているようだが、その関心は奇妙にねじれて、過去の日本で起きた二つの殺人事件の方により強い興味があるようにうかがわれる。
「水晶の夜」が一九三八年とすると、これは昭和十三年にあたる。・・・「阿部定事件」が起ったのは、同年五月十八日午前五時であるが・・・
一九三五年は、前年に総統兼首相となったヒトラーが、ベルサイユ条約を破り徴兵・再軍備をした年である。
この年、日本では奇怪な殺人事件が起った。
一つは阿部定事件、もう一つは、とある青酸カリ殺人事件だ。
二つの事件については、当時の新聞記事なども交えながら数ページを割いて語られる。
『ヒトラー』を観ながらも、麻田はこの二つの事件で殺された二人を脳裏に浮かべている。この妙な執着は何なのか。
また映画の中の、他の人ならば特に関心を持たないような、地味な風景を映した場面、そこに映った煙突に、彼は注意を引かれる。これも妙である。
これらの謎は、映画を観て帰宅した麻田がベッドの中で思い起こす、16年前の初冬の夜の出来事につながる。
麻田とは別人格の誰かが語っているような、妙に書き手の存在を感じる文章が奇妙で面白い。
不思議な読み心地の作品だ。
下記の言葉に、ぞくっとなった。
血に濡れたことのある手は、暗い官能の匂いを放つ。この受け取り方は危険で、戦争から血と泥と汗と屍体とを抜き去って眺めると、それが壮大なロマンに錯覚されることに似ている。
*****
「菓子祭」
ある中年男性が、中学三年生の娘と、フランス料理のレストランに食事に来ている。
過去の事情により、二人は離れて暮らしており、長く会わない期間もあったために、あまり打ち解け合っていない。
男、娘、給仕するボーイ長の発言と、男の心理がメインのシンプルな構成だが、うんちく臭い男と醒めた娘の食事風景の寒々しさが伝わる。
娘に対し、オードブルはやめておいた方がいい、この料理は少し残した方がいい、と何かと口を出す黒服のボーイ長。
「あとでいいものが用意してありますから」と言うのだが、その態度がどうも粘っこくて気味が悪い。
そうしていよいよ現れる「いいもの」とは、三連のワゴンにてんこ盛りのケーキ類だ。
10代の女の子の前に選び放題のケーキ。歓声が上がっても良さそうなものなのに、娘は父に向かって小声で不気味な皮肉をささやき、いやいや小さなタルト菓子を選ぶだけ。寒々しさが極まる場面だ。
父は、「二人を取り囲み、襲いかかってきそうなこれらの菓子」とまで感じている。
男の眼は釣り上って、黒眼が白眼の中に染滲みこんだようになっている。その表情を見ると、これら夥しい菓子は、男自身の内側の事情と絡まり合っているような気がしてくる。それが何か、想像もできないが。
説明がないだけに異様で恐ろしい、ぞわぞわ感がたまらない作品だ。
ただ、私などは食いしん坊でもあるし、この父親のように後ろ暗いものを持っているわけでは特にないので、ぞわぞわ以上に、食欲を刺激されながら読んだ。そんな楽しみ方ももちろんありだろう。
*****
藤子不二雄Aのブラックな漫画のような怖さのあるもの、エロティックな夢のようなものなど。吉行淳之介の短編はやはり面白い。大人の夏読書にぴったりだった。
