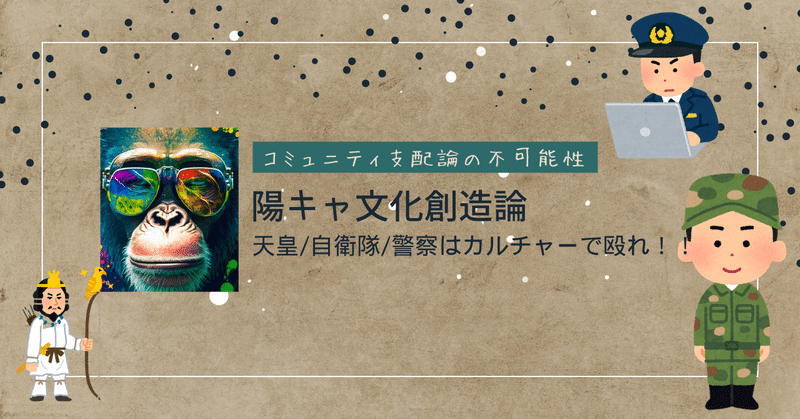
【コミュニティ支配論から文化論へ】なぜ陽キャは自衛隊や天皇を越えたのか?
東京の池袋を舞台としたライトノベル『デュラララ!!』をご存じだろうか。かつてのチーマー文化が存在していた頃の治安の悪い池袋を舞台に、カラーギャングを含めた各団体と登場人物が鎬を削る群像劇である。作中で冴えない高校生である竜ヶ峰帝人が、統率者不明の巨大組織ダラーズを立ち上げ、面白半分で参加するユーザーたちをコントロールして、敵の組織を倒すというシーンがある。これは、本ライトノベルが執筆された2000年代を象徴するようなインターネット文化に対する過大評価だろう。2000年代と言えば、インターネット掲示板2ちゃんねるの匿名たちの連帯感を描いた電車男の映画化や同じく2ちゃんねるの釣り企画を期限に持つボーカロイド重音テトの商業化など、インターネット空間での連帯が世の中にインパクトを与えるという期待感がなんとなく存在していた。匿名のまま、他者と繋がることのできるインターネットは、人類が長らく有してきたコミュニティという概念すら書き換えてしまったように思う。会社、軍隊、自治体など、現在もリアル空間での上意下達は強い組織を構成するための必須要素であることには変わりない。組織において、個々の才能や天才性はマイナスに働くことの方が多い。例えば、有能組織人の代名詞であるところの官僚やテクノクラートは、ある分野のスペシャリストであることよりも、物事や社会の全体性を把握するバランス感覚と、周囲とのコンセンサスを取りながらの業務遂行能力が求められる。強固な組織づくりにおいて、構成員の正常性は物理法則の如く不変である。本記事では、統率者不在の令和型コミュニティが警察権力や学校といった規律を重んじるコミュニティを質で凌駕するにはどのような施策が必要かを考察していきたいと思う。
正常性と異常性
秩序という言葉を聞いて真っ先に思い浮かぶのが警察や軍隊のような国家暴力だろう。社会には無法者が一定数発生してしまう不可避な構造が存在し、それを野放しにしてしまえば、規律を守るものだけが一方的に損をする社会になってしまう。それを防ぐのが暴力による社会の統制である。これは私たちの社会を構成するための前提であり、否定することは難しい。日本の整ったインフラや治安は正常性を担保することによって成り立っている。しかし、功利主義的発想で構築された社会は必ずしも『最大多数の最大幸福』を約束してくれはしない。形而上学では正常性を愛する大衆とそれを嫌う異常者の二項対立で社会を考えてしまいがちである。皆薄々感じていることだと思うが大衆は統計学の作り出した虚構であり、存在しているかどうかは疑問の余地が残る。3人以上の人間が集まれば、中央値と平均値は常に算出されるが、各属性の中央値と平均値がお互いにマジョリティを定義できているかという問題が残る。例えば、30人のクラスの国語の平均点は100点満点中75点である事実と、クラスの平均身長が163㎝である事実の間には関連性がない。この二つの要素を考えれば、国語の点数75点前後で身長が163㎝の生徒が平均的ということになるが、身長が平均的であることは国語の点数の平均性を担保しない。これは『相関関係の誤謬』と呼ばれ、データ分析を行う際の典型的な誤謬として認知されているが、誤謬と分かっていながらも社会は大衆という正常性のイデアを信じることでしか正常に機能しないというジレンマを抱えている。平均点では平均的な人間像を算出することが出来ないとわかりながらも、では何をもって我々の正常性を判断すればいいのかという基準を別に設けることは、相関関係の誤謬を信じ続けるよりも遥かに難易度が高い。『大衆は存在しないが、大衆が存在することにしなければ社会は回らない』という矛盾が多くの個人を苦しめる普通という幻想の正体なのである。近年のグローバルに掲げられている『多様性』というスローガンも、私の耳には違和感として響く。統治や統制という営みは、混沌(カオス)から何らかの社会性を作るために、人を強制するための不自然な行いのはずである。ルソーの言うように、人民を社会という鎖に繋ぐことで人は人であることが出来る。自然人が平和的であるか、闘争的であるかの議論はあるだろうが、原初の我々が多様的であった事実には、ルソーもホッブズも納得せざるを得ないはずだ。多様性をスローガンで啓蒙しなければ実現できないような人間社会を見ていると、サプリメントで栄養を摂取する現代人に、肉や野菜の美味しさを啓蒙しているような歪さを感じる。どこぞの堀江貴文ではないが、『多様性は楽しいからやるの!!多様性が偉いってバカ!!』と叫びたくもなる。私は大学の新卒枠で就職していないこともあり、自己分析ややりたいこと探しのような自己分析とは無縁の人生を送ってきた。個性は探さなければ認識できないような性質のものではなく、常に隣にあるような感覚のものだ。当然、社会からの要請として自身の個性と能力をプレゼンしなければならないシチュエーションに遭遇するが、そのたびに頭を悩ませている。多様性は自己の生き辛さを弱者が主張するためのツールであり、私には不要に思える。
異常性はコミュニティではなく文化
私の弟子的な存在の稲葉恒存が『コミュニティ支配論』という著作を書いた。これについてはYouTubeで批評を行い、問題点と改善点を指摘した。彼の理想は純粋に友達や恋人といった原始的な人間関係を構築して、人生を最適化することである。彼は組織自体がどのように社会変革に関わるかということよりも、ワンピースの麦わら海賊団のルフィのように冒険そのものを楽しむことを切望している。ぼっち系の若者が友達や恋人を作って人生をエンジョイすることは素晴らしいことである。それ自体が実存に対する革命として機能しているし、彼の取り組みが日本中の若者たちに伝播すれば、日本が世界に恥じるべき幸福度ランキングにおける立ち位置の低さも改善されるだろう。社会が若者たちに異常性のレッテルを貼ろうとも、彼ら彼女らが社会を再解釈することで、幸福度や自己肯定感の問題はある程度解決できる。私が話題にしたいテーマはその先にある。異常性を許容する集団が、正常性を前提として秩序を維持している集団をどのように凌駕するかという問題は話し合われなければならないだろう。警察や軍隊のような規律によって全体の統制を担保している集団は、統制力が故に業務遂行能力が高い。アメリカ軍は少数のエリートのみで、市街地全体を占拠する敵対組織のゲリラ兵を数週間、早ければ数時間で制圧することが出来る。正常性による団結は作業効率が高い。フリーランス集団を纏め挙げるStockSun株式会社代表の株本祐己も動画で語っていたが、フリーランスのような個人の戦闘力の寄せ集め集団においても、上位層は大企業出身の人間が多くを占め、組織に馴染めなかった高能力だけが取り柄の非組織的人間は歩兵止まりのポジションに甘んじることになる。正常性と異常性を脱構築したように見えるフリーランス×組織という取り組みにおいても正常性は依然驚異的な能力なのである。
はっきりと言おう。コミュニティ支配論は不可能である。異常性は組織を形成せずゲリラ的に組織を破壊することを得意としている。そもそも役割がまるで逆なのだ。既得権益の治癒力が発動するタイミングで、病原菌のように体内に忍び込むことで幹の部分の構造を変革できる。アメリカ合衆国の成り立ちを考えて欲しい。母国イギリスでの迫害に怯えた清教徒たちによって開拓された大地、それがアメリカ合衆国である。アメリカでは開拓時代以降、常に白人の権力が維持されてきた。そしてアメリカは世界で一番裕福な国でもある。白人、キリスト教(プロテスタント)、銃社会といった表側の絶対法則が存在する中で、心理学、スピリチュアル、陰謀論という独自の文化がアメリカ社会の根底には存在する。日本では60年代安保闘争による左翼革命は失敗に終わり、政治に疲弊した若者たちがオウム真理教とともにオカルトブームの火を付け、ほぼ同時に終止符を打った。これは日本人の『革命観』がフランス革命やロシア革命からアップデートされていないからなのではないか。18世紀のアメリカンドリームが、21世紀のアメリカで今も希望を失っていない理由は、多角的成功への希望が論理と妄想の二軸で幅広い層に伝播しているからなのではないか。イェール大学に入学したのであれば、シリコンバレーで起業するというステップは想像に難くないし、経済的に成功することは想定の範囲内だろう。一方で、陰謀論×多様性は多くの国民の主体性を維持することに一役買っている。ヒップホップはアメリカの低層階級である南部の黒人が成りあがる手段として、さらには黒人たちのプライドやコミュニケーションツールとして発展した。文化として面白味があるため、後続で白人やアジア人も参加することになる。ヒッピーやゴスキッズなども、異端者の仮想敵攻撃から始まった文化であることは共通している。『世の中には生き辛さを作る敵がいる。我々にはそれらを倒す手段があるし可能性も残されている。』この態度が社会をニヒリズムから救うのだ。アメリカではイマイチ流行りきっていない加速主義は、日本で遺伝学、統計学、社会学という客観性三銃士の力を借りて拡大している。だめライフ愛好会や反出生主義が悪いのではない。遺伝ガチャを信じると幸せになるという逆宗教が悪いのだ。統合失調症的世界観を持つしかない。客観性は飽和している。大学や企業やメディアは、あなたを客観的に見ている。もうそれで十分じゃないか。統合失調症的世界観については陽キャ哲学の過去の記事を読んで欲しい。異常性はコミュニティを作るためではなく、文化を作るために存在する。
稲葉君へ
確かに君は、生い立ちや人生から警察や軍隊という強い組織に憧れ、王や天皇のような象徴的存在になろうとしているのかもしれない。しかし、天皇や王は文化の創造には関与できないし、警察や軍隊には思想がない。はっきり言って恐れるに値しない。憲法学者の美濃部達吉『天皇機関説』は正しかったのだ。組織は機関に過ぎない。治安維持や一部の右翼の心の安らぎ程度には機能しているかもしれないが、私たちはさらに上に行く。思想を文化にする。元2ch管理人のひろゆきが『それってあなたの感想ですよね?』を子供たちの流行語にしたように、我々も『〇〇って思想なくない?』というような思想がある方がイケているという文化を作っていこうじゃないか。このノートを書くきっかけになったのは、秋葉原で稲葉君と語った小一時間程度の対談からだ。少ない対話でも創作のチャンスは溢れている。まったく人生とはすばらしいものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
