
「人格」を持った洋服で「文化」を作る。carewillコーポレートアドバイザー藤本幸三氏インタビュー
今回も前回に引き続き、carewillにコーポレートアドバイザー、アーティスティック・ダイレクターとして携わっていただいている、藤本幸三さんがcarewillに携わって感じたことや、carewillが目指すべき未来について、お話を伺いました。
※前回記事をまだお読みいただいていない方は、下記からぜひお読みください。
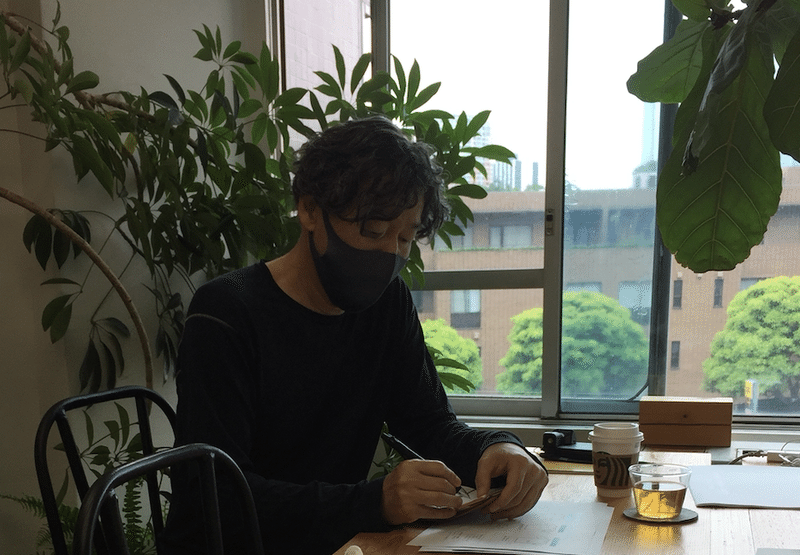
藤本 幸三氏
carewill コーポレート・アドバイザー/アーティスティック・ダイレクター
2001年〜2013年エルメスジャポン株式会社コミュニケーション・CRM担当執行役員 アーティスティック・ダイレクター
2013年〜2016年株式会社アニエス・ベージャパン代表取締役社長
2016〜ジンズ・ホールディングス顧問
carewilの本質は「想い」にある
ーーcarewillとケア衣料と携わり始めたときは、どのような想いで取り組んでいましたか。
藤本さん:最初はただただ、才能豊かなクリエイターと一緒に何かをつくっていくという想いでした。ビジネスとしても成立・発展させなきゃいけないという課題に取り組まなければなりません。
ーー藤本さんがcarewillに携わるようになり、2年ほどが過ぎていますが、2年も経つと変わりますよね。この2年を経て、carewillの本質は何だと考えていらっしゃいますか。
藤本さん:やはりなんと言っても代表の笈沼さんですね。そもそも笈沼さんがこの事業を始めるにあたっての、動機や流れがあって、エモーショナルな部分から始まっているんですけれど。それでいて、適宜いろんな方と接点を持っていくところが「さすがだな」と思いますね。自分たちの内々でできることと、客観性を持たないと知り得ないというところを、広がり感を持って着々とこなしているな、と思います。
ーーやはり、そこなんですね。
藤本さん:想いが市場の中できちっと認識されていくにはどうすればいいか。笈沼さんは、それを常に意識して頭の中に描いていると思います。そこをさらに表現として定着させ、「使命」として形にしていくような流れを作ることが求められます。
「おしゃれをすると、明るくなる」
ーー服のミーティングに参加をされていたり、ケア衣料を必要としている方々にヒアリングした結果を見聞きする中で、発見したことはありますか。
藤本さん:ケア衣料を必要としている方々って、日用着だったり、病院着だったり、外出着だったり、オケージョンと場所によって変わると思うんです。外に出て、思ったようにお洒落ができることが大切。最初につくったドレープのかかったプロトタイプのものとか、結構エレガントにできていると思っていて。
ーーそうですね。エレガントな仕上がりでした。
藤本さん:ファンクション中心に考慮されているけれど、原点として美しさを大切にしていく。そのような姿勢が、ケア衣料を着た方々が胸を張って外に出られるということにつながっていければいいなと思います。
ーーファンクションと美しさを両立させることが大事ですね。
藤本さん:おしゃれをすると明るくなるじゃないですか。ケア衣料をファンクションだけでおさめていくと、ちょっともったいないと思うんです。そういうカテゴリがきちっとあってもいいのかな、と。
ーー今回のプロトタイプは、carewillの重要なアイコンになるかもしれませんね。
藤本さん:一番最初のプロトタイプは、「原点」として、アイコンの一つになるかもしれませんね。「単にファンクションだけではないんだね」という印象は与えたいですし、そこに至ったストーリーも必要だと思います。アーカイブに出発の証として収めたいですねえ。
ーー今後はそういった発信が重要になりますね。
藤本さん:発信は、今後のプランニングで重要です。ただ、モノの本質よりも「ブランドを作る」という、そういうゴールを設けた上で事業展開しようとするのは避けるべきだと思います。本質を誠実にしっかり伝えていったほうがいいでしょうね。
本質を伝えられる、人格を持ったデザイン
ーーcarewillのこれまでの動きを見て、気づいた点はありますか?
藤本さん:これまで僕がやってきたことと、とても近いと思います。洋服が人格を持っているように感じて。単なる「道具」ではないなと思います。
ーー「洋服に人格」ですか。
藤本さん:「carewillはこういう思想でやっているんだね」と本質が伝わるような洋服。「ブランディング」というよりも「自分たちの本質」であるってことが重要だと思います。
ーーcarewillの「本質」をしっかり伝えられるデザインが重要なんですね。
藤本さん:あとは「継続性」が重要ですね。もっというと、事業体そのものがデザインコンシャスであるかどうかということも問われるかもしれません。関わる人々が常にデザインを意識しているかどうか。
ーーcarewilの場合、デザインミーティングでは作り手とデザイナーと、ときには実際に着用する当事者の方が混ざり合って対話をしています。
藤本さん:そういう着想で始まっているところは他にないんじゃないですか。よく知っているわけではないですが、バランスがすごくいいと思います。
ーー良いと思うデザインと、求めるデザインの違いをすり合わせが重要ですよね。
藤本さん:そこは長嶋りかこさんが入ってくれていることで、ブランドの立ち位置がより明確になっていると思います。長嶋さんとは今回、すごくいいご縁ができました。それまで、一緒に仕事をしたことがなかったのですが、ぼくが一緒に何かやりたいとずっと思っていた方なので、お声掛けしたら快く引き受けてくれて、とても嬉しかったです。
ーーどうして長嶋さんと一緒に仕事がしたかったのでしょうか。
藤本さん:長嶋さんの作品は以前から注目していて、長い間「いいデザイナーだ」と思っていました。ただ、なかなか交差することはなかったんです。「他のグラフィックデザイナーとは違う魅力がある」と思って、ずっと"追跡調査"をしていましたよ(笑)。
ーー長嶋さんは、ひとつ情報をお伝えすると、100くらいの緻密な情報がたっぷり返ってくるようなイメージがあります。
藤本さん:長嶋さんは、本当に特別なレベルの方だと思いますね。
carewillはモノではなく、文化をつくる
ーーcarewilは日本はもちろん、世界に羽ばたいていきたいという思いがあります。carewilは、社会に対してどのような役割を果たしていくべきでしょうか。
藤本さん:carewillの事業は、タイムリーだと思います。今は、過去にあった当たり前の価値観とは全然違う概念になってきています。「マイノリティには目を向けない」という人も減ったと思いますし、新たな文化として捉えてもらえるのではないでしょうか。そして、そんな文化をつくる役割があるのではないかと思います。
ーー「新たな文化」ですか。
藤本さん:僕がエルメスにいたころに思ったのは、エルメスは「ものをつくってるんじゃなくて文化を形成している」ということです。僕もいろいろ好きなことをやらせてもらいましたけど、芸術を介して、新たな次の価値感を得るというロジックを説明した時、OKが出た流れがありました。
ーー単にものをつくっているのではなく、「文化」というところまで広げられると、奥行きがあって、いいですね。
藤本さん:プラスアルファをやらないと、僕はあまり魅力を感じないんです。せっかくこういう事業を立ち上げたのだから、もっと広がりのある価値観を表明できたらいいですよね。
ーー「広がりのある価値観」とは、どういったものですか?
藤本さん:例えばエルメスはもともとは馬具のハーネスメーカーですが、今では創業時のマインドはそのままに、顧客の要望に応えて、かなり広がりのある製品をつくっています。ケア衣料のノウハウを通じて、どんなことができるのかというところまで、しっかり見つめられるかどうかが大切だと思います。
ーーなるほど。carewilを通じて、社会に顕在化していない価値観を発見したり問題提起していくということですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。
---------------------------------------------------------------------
藤本幸三さんのお話をうかがい、carewillのケア衣料で「文化をつくる」という意識を強く持つようになりました。洋服をつくって終わりではなく、洋服から何を生むのか。そこをもっと追求していきたいと思います。
carewill参画メンバーのインタビュー企画は続きます。次回もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
