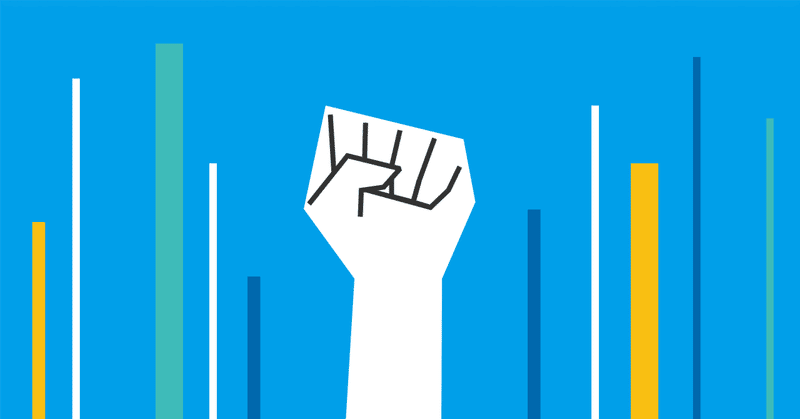
身体と頭、ガッツとヘッド、タフガイの正体は?〜エニアグラム8と6の比較~
はじめに
エニアグラムのタイプ8(以下、8)と性的タイプ6(以下、6sx)が似ることがあるけど、その見分け方ってなんぞや? という話を𝕏でしていたら(2024/5/11)、思いのほか盛り上がったので、このnoteに諸々をまとめておきます。論点をまとめたいのでちょっと引用が多めになります。
私自身はタイプ5ですので、掴めていない部分もあるかと思います。間違っている箇所がありましたら是非ともお知らせください!
1. 8と6sxが似ている点
彼らは並外れてタフで、かなり身体を酷使しても不平をいわずに耐えます。
第十三章 タイプ8・挑戦する人より
まずは8。彼らの身体は非常にタフである、とされています。次に6sx。
通常の段階における性的タイプ6は、安心感を得るため、体力や能力、身体的魅力を発達させます。よりアグレッシヴな性的タイプ6であれば、力やタフな態度を頼りにするため、タイプ8に似ることもあります(「私の邪魔をするな」というように)。
第九章 タイプ6・忠実な人 性的タイプ6より
『「私の邪魔をするな」というように』、とはどういうことでしょうか? 『通常の段階における』と書いてあるので、同じく通常の段階の8の記述から探してみましょう。
通常の段階におけるタイプ8は、自らを「岩」のようにみなしはじめます。強くて動じない人、家族や仕事関係における、他者のための礎。
(中略)
通常の段階のタイプ8は、社会的役割からかかわるのでなければ、人と一緒にいるのが心地よくない気がしてきます。
第十一章 タイプ8・挑戦する人 成長へのチャレンジより
強くて動じない、他者のための礎──という、社会的役割を果たしている私の「邪魔をするな」。この態度が似ると読んでもよさそうです。
また、この「社会的役割」についても突き合わせておきましょう。
強くて動じない人、家族や仕事関係における、他者のための礎(「私はタフだ。誰もが頼りにしないではいられない人間だ」というように)。
第十一章 タイプ8・挑戦する人 成長へのチャレンジより
タイプ6は、自らたゆまず「責任をもつ人」の役割を果たします。エネルギーを注いできた人間関係や仕事や信念がさらにうまくいき、自分を支えてくれるように、長時間働きます。
第九章 タイプ6・忠実な人 成長へのチャレンジより
タイプ8のほうがいくらか抽象的なようですが、つまりは、どちらも「頼りになる責任者」です。とても似ていますね。では、一体何が違うのでしょう?
2. ガッツとヘッド、現在と未来
順を追っていきましょう。8と6はいずれも頼りになる責任者です。責任者は責任範囲にあるモノ・ヒトを守るため、脅威や不安に対処します。
8はガッツ(本能)センター、6はヘッド(思考)センターに属しています。ヘッドセンターの人は未来志向です。未来の不安に対処しようとします。対して、ガッツセンターの人は現在に対処しようとします。(※1)
勿論、ガッツの人も未来の不安について話をします。ただし、その反応はヘッドの人と様子が違います。
私の夫は9w8──調停者と呼ばれる、ガッツセンターに属するタイプですが、未来の不安についての話をしたとき、「まるで今起きているかのように」体が強張り、形のあるものに抵抗しようとしているように見えます。未来の不安を、現在の出来事のように感じなおし、それに対処しようとするかのようです。
一方で、私は5w4、ヘッドセンターに属するタイプです。未来の不安は、未来のままです。未来の不安に形はありません。形のない不安に対処するには、体に力を入れるのではなく、頭を回転させます。
ヘッドタイプが無意識に頭を酷使するのに対し、ガッツタイプは無意識に体を緊張させます。そのため、ガッツタイプは体が凝りやすいようです。私は夫の全身をほぼ毎日マッサージしているのですが、彼の背中は一向にやわらかくなる気配がありません。毎日強張っています。
ここまでを踏まえると、以下のようなことが言えそうです。
・8的な責任者は、主に現在の脅威に対処しようとする。未来の不安については、現在の脅威のように感じ直すことで対処する。
・6的な責任者は、主に未来の不安に対処しようとする。現在の脅威については、予め立てておいた戦略をもとに対処する。
違いを語るにはこれで十分でしょうが、もう少し深く、動機の部分まで考察してみることにしましょう。
3. 8の防衛、6の戦略
父親的存在、母親的存在との関係
原書では、一般的に子どもを守り、導く役割である父親あるいは父親的存在(女性の場合もある)として「保護者(protective-figure)」、愛情を与え、ケアする母親あるいは母親的存在(男性の場合もある)として「養育者(nurturing-figure)」という言葉を使っている。この訳書では、読みやすく、理解しやすいように、「保護者」を「父親的存在」、「養育者」を「母親的存在」と訳している。
第四章 タイプ1・改革する人 訳注2より
8は母親的存在からのケアを求めているとされ、対して、6は父親的存在の導きを求めているとされます。まずは8から。
大半のタイプ8は、幼い頃から「大人」にならざるを得ないと感じたと語っています。
第十一章 タイプ8・挑戦する人 子ども時代のパターンより
この「大人」を、いったん保護者、父親的存在と解釈しましょう。8は防衛のため、幼い頃から父親的な役割を担いました。彼らは自立し、手を尽くして周囲の環境をコントロールしようとします。ですが当然、それには大きなエネルギーが必要ですし、傷も負います。そして、傷を癒やすには母親的存在からのケアが必要になります──それでもやはり、自立を脅かされたくはないでしょうが。
6はどうでしょうか。
ヘッドセンターは二歳〜三歳頃の母子分離期(いわゆる、イヤイヤ期です)に固着があることが多いようです。母子分離のために幼児が取った戦略が、そのままヘッドセンター各タイプの戦略になります(なので、ヘッドセンター各タイプは、あまり母親的存在を求めていないと言えそうです)。
分離期の課題は、「母親的存在から自立したいが、自分は弱い幼児である。どうするか?」です。5は物質的ニーズを減らしてより思い通りになる頭の中に退き、7は母親の代わりになる移行対象を探しました。
一方で6が取った戦略は、父親的存在を頼るというものです。しかし、父親的存在は完璧ではありませんでした。そのため、彼らの中には父親的存在への疑念が残っています。
まとめましょう。ちなみに8も6もニーズのバランスが難しい反応的グループです。
・8は早くから父親的存在を担ったため、母親的存在からのケアを求めているが、それによって自立やコントロールを脅かされたくはない。
・6は母親的存在から自立するために父親的存在を頼ったが、それは決して完璧ではなかったため、疑念が残っている。
母親的存在はケアを提供します。ケアは「現在の脅威から受けたダメージ」を癒すものです。また、父親的存在は導きを提供します。導きは「未来の不安」に対処するものです。8が現在を見ていて、6が未来を見ている、という話にも繋がります。
6が責任者となるまで
さて、8は早いうちから父親的存在、タフな責任者になりました。では、6はどのようにして責任者となるのでしょうか?
6は自分の弱さを認識しており、権威を頼りとして自立を目指しています。
ここで個人的な見解をお話しておきます。よく言う、「6が権威に盲目である」というのは誤解を孕んでいるように思います。6は己の弱さを知っていますが、必ずしも、「弱く支配されやすい人々」ではありません。
権威とは、6にとって、安全を確保するための杖、道具のようなものです。6が権威に盲目になっているというのは、たとえば金槌を持てば何でも打ちたくなるような、「道具に使われている」状態のことです。権威が6を使うのではなく、6が権威を使うのです。生存戦略として。
まだ踏まえておかなければいけないことがあります。各センターの真ん中である3-6-9は社会からの要請に影響を受けやすいといわれます。社会とは「大きな権威」であり──6はその要請によって大きく在り方を変えるということ、そして、その要請には性役割も含まれるということです(あらかじめ、政治的な意図はないことを断っておきます)。
そういうわけで、女性の6は女性らしく、男性の6は男性らしくあろうとする傾向がありそうです。少し戻って、「保護者」が「父親的存在」、「養育者」が「母親的存在」と訳されたのも、この性役割と関わりがあるでしょう。女性の6は母親的存在を、男性の6は父親的存在を目指していくことになります。そして、彼らは「大きな権威」たる社会の要請、役目、役割、規範に沿って、責任を負います。
かくして、社会的な手続きを踏みながら、6は責任者になりました。
4. タフガイの正体
ここまでを踏まえて、「力やタフな態度を頼りにする、よりアグレッシヴな性的タイプ6」からは、父親的存在を目指している男性的な6sx、といった人物像が伺えます。表面的には8と似ていますが、この6sxが戦っているのは、現在の脅威というよりは未来の不安、ひいては自分の不安です。また、求めているものも、傷を癒やす母親的存在からのケアではなく、不安をはらってくれる父親的存在の導きです。
今回の話題は、ガッツセンターの方々(※2)が6sx的なタフガイを理解したい……というところが始まりだと認識しています。そのため、ガッツセンターの方々の視点をお借りすると、上記のような人物像は、「タフな態度を取っているのに、傷の癒やしを求めていない」という点で、「見返りを求めない人」のようにうつるかもしれません。また、「不安を払うために力を示す」ことは、「むやみに弱者を不安にさせかねない、許しがたい行為」とうつることもあるかもしれません。
8的なタフガイは、傷の癒やしを求め、退行時には自分を守るために力をためこみ(5)、統合時には愛情をもって人を守ります(2)。
6sx的なタフガイは、傷よりも形のない不安に苛まれていて、そのため、癒やしよりも導きを求めています。退行時には不安をはらうために力を誇示し(3)、統合時には不安から自由になり、リラックスした状態になります(9)。
参考文献
オラッ! 参考!
新版 エニアグラム【基礎編】 自分を知る9つのタイプ (角川書店単行本)
エニアグラム【実践編】 人生を変える9つのタイプ活用法 (角川書店単行本)
「性格のタイプ」も読んでみたいんですが、入手できてません……。
※1: 基礎編 第四章 三つの要素の最後にある表をご参照ください。
※2: 2024/5/11時点でガッツセンターを自認している方々
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
