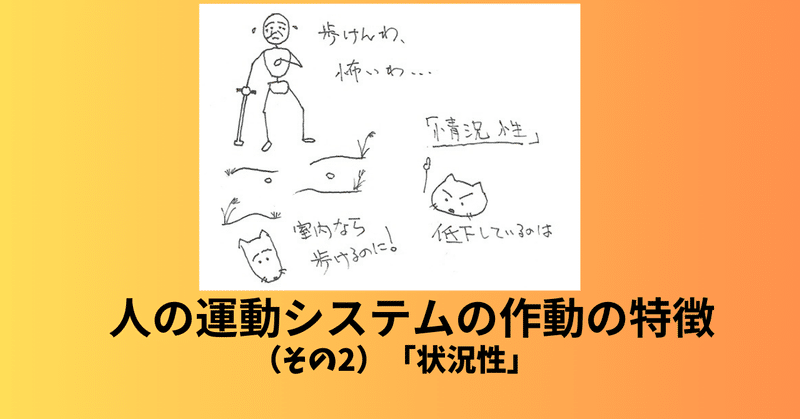
人の運動システムの作動の特徴(その2)「状況性」
今回から人の運動システムの作動の特徴について考えてみます。
これはどうやったら理解できるかというと、普段から自分や周りの人達の運動変化を見ていくことで理解できます。たとえば自分の歩行とその変化を観察してみます。
歳をとってから気がついたのですが、僕は朝起きてトイレに行こうと歩き始めると、足底が床の上を擦るように引きずって歩きます。夜寝ている間に体が硬くなっているのが原因だろうと思います。体幹の重心移動が小さくなり、足の振り出しが小さくなっているのです。しばらく歩いたり動いたりしていると引きずることなく普通に足を持ち上げて振り出すようになります。
おそらくこれがお年寄りの早朝転倒の一つの理由かも知れません。一晩寝ているだけで体が硬くなってしまうわけです。体が硬いと一本の棒の様になって、バランスが崩れやすくなるし股・膝関節の柔軟性も低下して脚が上がらず、引っかかりやすくなるのだと思います。
朝起きたら、ベッド上で体幹や下肢のストレッチをしたり歩き出す前に足踏みをしたりすると良いのかもしれません。今のところ実行していませんけど(^^)
他に家具と壁で作られた狭い通路に入ると何を考えるでもなく自然に横歩きになります。大きな荷物を両手で抱えて階段を降りるときは、足下を見ようと自然に体を斜めにして一段一段脚を揃えながら降ります。安全のために適切な歩き方が自然に生まれてきます。
夜トイレに起きて、暗闇を進みます。「ここに低い家具があるはず・・・」と片脚を伸ばして左右に振って家具を探します。見つけると今度は片手を伸ばして壁のスイッチを探します。気がつくと歩隔を広くとっています。安定を得やすくするためでしょう・・・・
こんな要領で他人の歩行も観察していきます。
近所のおばあちゃんが水田に入って田植えの準備をしています。脚を大きく開いて立ち、片脚に大きく重心移動して反対の脚を「よいしょっ!」と高く引き抜きます。脚を引き抜くときは泥の抵抗を小さくするために足関節を底屈してまっすぐにしています。そして少し前方へよいしょと下ろします。相撲取りが上品に小さく四股をふんでいるようです。
近くでは若いお孫さんが肩幅くらいに脚を開いて立っています。やはりつま先をのばしたままスッと片脚を抜いて膝を高く挙げ、また前方にバチャンと下ろして進みます。下垂足で膝を高く挙げる「鶏歩」と呼ばれる歩行に見えます。
低学年と思われる小学生が二人、ランドセルを背負って帰宅途中です。お互いに何かを言っては二人で大笑いしながら歩いています。楽しそうで、弾むように歩いています。やがて分かれ道で二人は別れます。片方の子は一人になると下を向いて歩きます。なんだかランドセルが急に重くなったようです。小走りで少し進みますが、ランドセルの動きが体と協調しないので走るのが難しくなったようで、また歩きに戻ってしまいます・・・・・
つまり、観察を続けると状況変化がある度に歩行はその見た目の形を変えていくし、その変化は心身の状況を反映しているとも言えます。あるいはいずれもその時その場所で達成するべき課題に向けて、心身と環境の関係性などから歩き方が変化していることがわかります。どうもこれが健常者の歩行あるいは運動の基本となる作動の特徴だと思われます。
人はオモチャのロボットのように、環境が変わっても単に同じ運動を繰り返しているわけではありません。状況変化に応じて歩き方を変えては、その状況での歩くという課題を達成しようとしているわけです。
CAMRではこのような状況変化に応じて適切に達成方法を変える作動の特徴に「状況性」という名前をつけています。
臨床の現場に目を向けると、室内では何とか自立して歩いている片麻痺患者さんが、起伏の大きいアスファルト道路に出ると「怖い」と仰たり、バランスを崩したり、歩くことをやめたりされることがあります。
つまり健常者に見られる「状況性」という作動の特徴が弱まっているわけです。ちょっとした状況変化に対応できないことがあるのです。
健常者の運動を目標にするなら、単純に若者の歩き方の形をまねるのではなく、この「状況性」という特徴を強めることをまずは目標にするべきかもしれませんね。状況が変化しても歩行を維持する頑丈さが必要です。
次回はこの「状況性」という作動の特徴を支えるメカニズムについて考えてみましょう。そうすると自然にリハビリで何をやるべきかがわかってきます。(その3に続く)
※毎週火曜日にはCAMRのフェースブックページに別のエッセイを投稿しています。
最新作は「運動リソースを増やして、運動スキルを多彩に生み出す
(その2)-生活課題達成力の改善について」
以下のURLから
https://www.facebook.com/Contextualapproach
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
