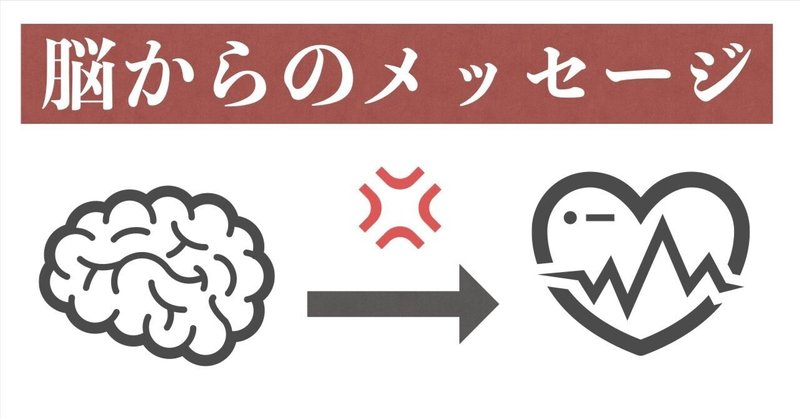
イライラしやすい不登校脳〜情緒脳と理性脳〜
イライラは脳から発せられるメッセージです。
しかし、そもそも発達特性があると、脳機能に支障をきたすため、このイライラのメッセージも発生しやすくなります。
そのために脳機能の原始的とされる身体的「情緒」機能、高度な言語的「理性」機能からストレスに対応していくことが大切です。

【情緒機能の脳アプローチとは?】(リラクゼーション)
情緒へのアプローチでは、リラクゼーションが鍵となります。
特に言語発達が遅れている子には情緒面のアプローチから初めると良いです。
無意識にイラッとするのは理性的に考えているのではなく脳の中心部になる身体情緒の脳が影響しているからです。
情緒脳のための「神経伝達物質」
情緒の脳は神経伝達物質とつながっています。
人間のメンタルに影響する神経伝達物質ははセロトニン(心身健康)、オキシトシン(人間関係)、ドーパミン(興味関心)に起因します。
セロトニンは食事・睡眠・お風呂・運動などの生活習慣が基盤となります。
発達障害があると自分をメタ認知しずらく、自分が疲れているかどうかも分かりません。
そのためにイライラしやくすく休み方を教えることが必要となります。
オキシトシンは友達・家族・恋人などの愛着形成が基盤となります。
相手との関係性作りを教えます。人間関係において普段から嫌なことについて話し合える関係性を構築しておきましょう。
相性を考慮し、合わない人から離れることを教えることが大切です。
ドーパミンは好きなこと・趣味・遊び・運動が基盤となります。上手く使えば成長欲求にもつながります。遊び感覚で訓練しましょう。
難易度調整をして本人のワーキングメモリを考慮しましょう。ワーキングメモリの負荷が上がるとコルチゾールが上昇します。
そのためにスモールステップで苦手なことを把握します。一つずつメモするなど本人にあった支援をすることが大切です。

情緒脳のための「自律神経」
赤ちゃんは自律神経が整っていないので、すぐに泣きます。
同じように発達障害があると自律神経が乱れがちです。
自律神経の発達は世の中への肯定、安心感に繋がります。
そのため感覚遊びを通して自律神経を発達させていきます。
自律神経が整うとドキドキソワソワが減り気分がスッキリします。
自律神経のために平衡感覚と触覚の発達が大切です。
平衡感覚が不足すると情緒不安定になります。自閉症は平衡感覚過敏で運動を嫌がります。
ブランコ・滑り台・鉄棒・高い手押し車などで平衡感覚を鍛えましょう。
触覚には二つの機能があります。
触った感覚を判断する力と快不快を感じる力です。
触覚経験が不足すると自分が安全だと思えることも減ります。自律神経も育ちません。
自閉症は触覚過敏によるスキンシップ不足で感情不安定になりやすいです。そうならないため触覚遊びを増やしましょう。
砂遊び、水遊び、粘土遊び、じゃんけん列車、ボールプールなどで触覚を鍛えます。

【理性機能の脳アプローチとは?】(認知行動療法)
理性で考えるのは脳の外側です。大脳によって理性を言葉で抑えられます。
使える感情言語を増やすと理性が発動しやすくなります。
無意識へのイライラにも理性で抑えられます。
理性脳のための言語指導
暴言を吐く子は言葉の使い分けができていません。
何でもかんでも死ねという子は言葉に感情が引っ張られているだけです。
だから適切なマイナス言葉を教えます。
語彙力が増えるのは体験が伴ったときです。そのため嫌な出来事があったら、そばで声をかけ続けます。
「死ね」ではなく「残念だったね。悔しかったね」という表現を教えます。
嫌な体験があったら言葉を使うことで感情コントロールができるようになります。
アウトプットをたくさんすれば自分の感情を客観的に把握できます。
普段から自分の意思を表出する練習をします。
作文や日記、意見を言うなどが有益です。日記では、自閉症の場合、嫌な記憶が残りやすいため、よかったことも記録していきます。

理性脳のためのSST訓練(Social Skills Training)
見通しを持つことや怒りの代替行動を決めておくことが重要です。
見通しのために、先に選択肢を提示して選ばせます。
お題を出して、自由に意見をさせることで言語が深化していきます。
個々にありそうなケースを考え、その子の生活に近づけるよう努めます。
切り替え言葉「なんとかなるさ、まあいいか」など、自分の感情を切り替える言葉を用意します。楽しく負けられるゲームを普段から行います。
モヤモヤを引きずらないためのハッキリワードを示します。「できることをやろう・ここは学校です・それは先生が決めること・タイムアップ」などをルール化します。

以上、情緒面、理性面からの脳へのアプローチをみてきました。
これらのアプローチは柔軟性を持ち、子供たちの発達特性に合わせた個別化が求められます。
また、繰り返し行うことで、子供たちは感情の表現やストレスへの対処法を身につけ、健やかな成長を遂げることが期待されます。
総合的なサポートと理解ある環境が、彼らの未来をより輝かせる鍵となるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
